
いよいよ、来週、旧暦新年がやってきます。
(今年は2月1日)
やり残したことのブラッシュアップの時!
なのに、ダウンしてしまった先週です。
今日、やっと復活しました。
本日は、前置きを書いたのちに
新年に向けてのテーマを綴ります。
先週、風邪対策をアップしたばかりだったのに、
実は、自分自身が発熱してしまった一週間でした。
発端は、子どもの発熱。
日曜日、部活の試合で、寒い中、汗をかき、
風邪をひいても仕方ないかなと、思いつつ。
やはり、コロナが心配。。。
用心しながら、看病していたけれど
3日後には、私が発熱。
あ〜、まさかの感染!?
頭痛に喉の痛みに熱。
息苦しさは、ひどくはなかったものの、
やや胸が苦しいような。。。。
発熱後3日して、病院へ。
PCR検査は、完全に院外で行われました。
予約制で、病院の窓から、
先生が手を出して行うというもの。
はたから見たら、かなり、滑稽かもしれません。
寒かったです。
とにかく、風の冷たい日でした。
結果は、「陰性」。
ほっ。それが分かると、中に入れてもらえました。
それまでは、車中か外、
コンビニ等で検査結果を待つように指示されました。
まぁ、陽性でなくてホッとしたものの。
症状がオミクロン株に似ていたので、本当にビビりました。
「ウィルス性の風邪は、
他にもいくらでもあるからね。」
と解熱剤を出す主治医。
夜の最後の診療で、ギリギリで
診てくださったのには、感謝です。
かかりつけ医のいる有り難さ。
まぁ、そんなことで、二十四節気「大寒」に
「陰を極めた」この冬です。
ここからは、もう「陽に転じる」しかないと
信じたいですね。
本題です。
春節時には毎年、個人的な目標やテーマを綴ってきました。
令和元年、神社デビュー、神道を学び、
令和二年、お寺デビュー、仏教を学び、
令和三年、陰陽道、五行説を意識し、
令和四年、は、「縄文の世界観」です。
暮らしや生活をデザインする立場から、
令和になって、日本的なものをもう一度見直そう
学び直そうと、心がけてきました。
図らずも、コロナ禍で、日本の良さ、
日本人の暮らしのあり方に社会の関心も高まる中、
実に、昨年から「縄文時代の凄さ」
に触れる機会が増えています。
以前から、関心はありました。
土器の文様の美しさなど、デザイン面では。
(写真集も持っています)
しかし、暮らしの実態などは、竪穴式住居や
狩猟生活だった。くらいしか、
義務教育で学んだことは覚えていませんでした。
国産木材の活用を手探る中、知ったのが、
古代からの杉の植林です。
杉と共に暮らしていたことが分かっているのです。
これまでも、日本人は、自然と共生してきた歴史と、
循環型の生活、、、それがどうも、縄文時代にあるらしい
というのは、漠然と情報が入ってきてはいたのですが。。。
具体的に、どうなのか?
それを現代の暮らしにどう活かせるのか?
と、興味が今、どんどん膨らんでいます。
妊娠すると急に街中で妊婦に出会う
(意識しているものは、目に入るの意味)
というように、
「縄文」が立て続けに
西暦新春に目に入ってきたので、現在、勉強中です。
女性誌の巻頭に載るエッセイの一コマ。
「私たちに生きる縄文の遺伝子、縄文論理空間」とあります。

新聞での特集。小林達雄氏のお名前が、
立て続けに、、、目に入ってきました。
1月4日の読売新聞
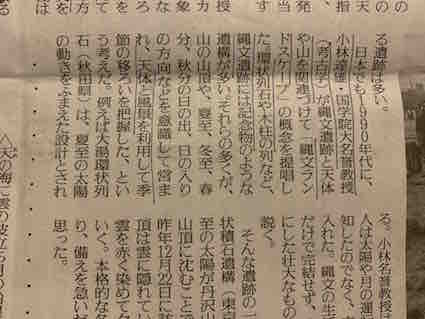
そこで、「縄文ランドスケープ」
(1990年代に提唱されていたとは!)
を、拝読してます。(topの写真)
建築系の人は著者にはいませんが、
方位学的な、考古学者の分析が面白いのです。
こうしてみますと、「季節感のある暮らし」を、
縄文人も、積極的に行っていたことが分かります。
環状列石の方角から、
夏至、冬至、春分、秋分の「二至二分」を
とても大切にしてきたこと。
住まいだけではなく、モニュメント的なものを建造し、
お腹を満たすだけではなく、
心を潤す暮らしを、集団でしていたに違いないなど。
一番、私が知りたいのは、
平和な暮らしをどう運営していたのか?
ということです。
三内丸山遺跡の6本巨木柱も何の目的で作られたのか
今でも、はっきりとは分かっていません。
ただ、格差もなく共同で作業したであろうと推察されています。
建造物と、暮らしと、ランドスケープデザインと、、
長く続いた定住の地。
徳川の世が400年も続いて、その長さが
世界の歴史的にも稀であることは
よく言われます。循環型の暮らしがあったことも。
比べて、縄文はさらに非常に時空のスケールが大きく
1500~1700年の定住ということが
青森であったとは、昨年学んだこと。
あぁ、縄文人がいかに、豊かで知恵があり、
共同的生活を平和に営んできたのか!
感覚としては、なんとなく分かります。
遺跡発掘から、考古学的な様々な情報が
これからも明らかになってくるでしょう。
イギリスのストーンサークルに、憧れていましたが
環状列石が、日本全国で、広範囲で発見されているとは!
吉野ヶ里遺跡は、月の観測地だったとの新説。
天体の動き、暮らしに取り入れながら
どのような暮らしが展開していたのか、想像するとワクワクします。
これからも、素敵な縄文時代に
今の暮らしに必要な循環させて、自然と生き物と共に生きる
暮らしのあり方、住まいのあり方を模索したい令和四年です。
最後に、知人の現代の縄文人、雨宮棟梁(元々大工さん)の
丸木舟旅のクラウドファウンティングはこちら。
彼も、平和と自然共生を考えるに従って、
縄文的な暮らしにたどり着いたのだとか、極端ですけど。
思想の根っこは、似ているので、応援しています。
ちなみに、NHKで、当時のやり方で
対馬海流を渡った壮大なプロジェクトの丸木舟は、
彼が作ったものです。
発掘されたものを参考に
縄文時代の道具を手作りし、
機械に頼らず、手作業の同じ方法で、
丸太を切り出し刳り抜いて作った船で、
渡りきりました!。素晴らしい!
宇宙旅行元年とも言われる、令和ですが
「縄文」も、これから、大いに注目される予感です。
空と地とでもゆうべきか、陰陽ではありませんが、
相反するものが、深堀する時代に突入した、
そんな感覚で学んでいます。
最先端技術も、古代の発掘も、両方最先端!?
だと、私は思います。
こうして、一年一年、発見や驚きが増え
人間としての視点が増えることも、幸せへの一歩なのかなと
感じています。
皆様は、どんな年に?










