向日町競輪場で3日制のGⅢとして実施された国際自転車トラック競技支援競輪の決勝。並びは村上‐安部の東日本,稲毛‐西岡の和歌山,窓場‐沢田の近畿,才迫‐星島の山陽で西川は単騎。
沢田がスタートを取って窓場の前受け。3番手に村上,5番手に才迫,7番手に西川,8番手に稲毛の周回に。残り3周のバックで稲毛が上昇。ここに才迫が続きました。才迫はホームでさらに外から上昇して稲毛の前に。これを村上がバックの入口で叩き,西川が続いて打鐘。村上の3番手に西川,4番手に才迫,6番手に稲毛,8番手に窓場の一列棒状に。稲毛は後ろの窓場を気にし過ぎて動けず。窓場はホームから発進していきましたが,これを見た才迫が先捲りを打つ形に。安部は才迫は止められず,番手の星島の位置を奪いにいきましたが,内に潜った西川に前に出られました。才迫は村上を捲りきると直線でも後ろとの差を広げていくような快勝に。スイッチした西川が2車身差の2着。安部が1車身差で3着。
優勝した広島の才迫開選手はこれがS級での初優勝。11日に全日本選抜が開幕する関係で,GⅢとはいってもそこまで強力なメンバーではありませんでした。ですがFⅠでも優勝経験がなかったわけで,番狂わせといってもいいかもしれません。101期の23歳ですからまだまだこれから力をつけていく筈の選手であり,すぐにというわけにはいかないと思いますが,ゆくゆくは記念競輪やビッグでの活躍を期待してもいいだけの素質はもっている選手だと思います。
書簡三十九と書簡四十からいくつかのことが理解できます。
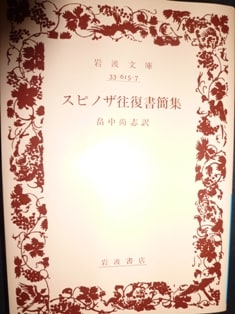
第一にスピノザが光線屈折学について高度な理論的知識を有していたことです。僕には内容の正否は分からないのですが,知識が高度であったということに関しては多言を要さないでしょう。
第二に,スピノザが有していたその知識は,人間がものを視るという場合よりも,望遠鏡のレンズの製作により多く関連付けられていたということです。他面からいえばスピノザにとっての光線屈折学というのは,医学的な意味での人体の解明という見地から重要であったというよりも,天体観測や顕微鏡観察といった光学的な見地から重要であったということです。これはもしかしたら一般に光線屈折学という学問がそういう性質のものであったのかもしれませんが,スピノザの場合にこれが妥当するということについても詳しい説明は不要でしょう。
第三に,実際に望遠鏡を製作するにあたって,その光線屈折学の理論をどのように応用すればよいのかという知識もスピノザにはあったということです。いい換えれば望遠鏡を製作するための理論とそれを実践するときの注意点をスピノザはよく理解していたということです。この点はたぶん重要なのです。理論的知識があったとしても,それを適用すれば高性能の望遠鏡が製作できるというわけではありません。むしろこの理論を製作という実践に使用する場合には,理論の中の何を重視しなければならず,何を無視してもよいのかということを合わせて知っておく必要があります。つまりたとえば望遠鏡を製作するという行為は,単に光線屈折学を適用する行為というよりは,それを応用するような行為であるといえます。このいい方をそのまま用いるとするなら,スピノザは理論について高度な知識を有していて,その理論を応用する方法論についても同じ程度の高度な知識を有していたということになります。
これらはいずれも望遠鏡のレンズに特化して書かれてはいます。しかしここから,カメラ・オブスキュラのレンズの理論と応用についても,スピノザは程度の高い知識を有していたと結論しても,さほど無理があるということはできないでしょう。
沢田がスタートを取って窓場の前受け。3番手に村上,5番手に才迫,7番手に西川,8番手に稲毛の周回に。残り3周のバックで稲毛が上昇。ここに才迫が続きました。才迫はホームでさらに外から上昇して稲毛の前に。これを村上がバックの入口で叩き,西川が続いて打鐘。村上の3番手に西川,4番手に才迫,6番手に稲毛,8番手に窓場の一列棒状に。稲毛は後ろの窓場を気にし過ぎて動けず。窓場はホームから発進していきましたが,これを見た才迫が先捲りを打つ形に。安部は才迫は止められず,番手の星島の位置を奪いにいきましたが,内に潜った西川に前に出られました。才迫は村上を捲りきると直線でも後ろとの差を広げていくような快勝に。スイッチした西川が2車身差の2着。安部が1車身差で3着。
優勝した広島の才迫開選手はこれがS級での初優勝。11日に全日本選抜が開幕する関係で,GⅢとはいってもそこまで強力なメンバーではありませんでした。ですがFⅠでも優勝経験がなかったわけで,番狂わせといってもいいかもしれません。101期の23歳ですからまだまだこれから力をつけていく筈の選手であり,すぐにというわけにはいかないと思いますが,ゆくゆくは記念競輪やビッグでの活躍を期待してもいいだけの素質はもっている選手だと思います。
書簡三十九と書簡四十からいくつかのことが理解できます。
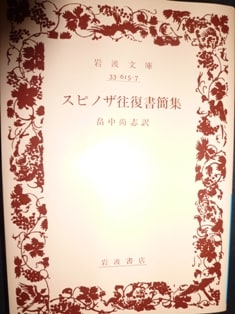
第一にスピノザが光線屈折学について高度な理論的知識を有していたことです。僕には内容の正否は分からないのですが,知識が高度であったということに関しては多言を要さないでしょう。
第二に,スピノザが有していたその知識は,人間がものを視るという場合よりも,望遠鏡のレンズの製作により多く関連付けられていたということです。他面からいえばスピノザにとっての光線屈折学というのは,医学的な意味での人体の解明という見地から重要であったというよりも,天体観測や顕微鏡観察といった光学的な見地から重要であったということです。これはもしかしたら一般に光線屈折学という学問がそういう性質のものであったのかもしれませんが,スピノザの場合にこれが妥当するということについても詳しい説明は不要でしょう。
第三に,実際に望遠鏡を製作するにあたって,その光線屈折学の理論をどのように応用すればよいのかという知識もスピノザにはあったということです。いい換えれば望遠鏡を製作するための理論とそれを実践するときの注意点をスピノザはよく理解していたということです。この点はたぶん重要なのです。理論的知識があったとしても,それを適用すれば高性能の望遠鏡が製作できるというわけではありません。むしろこの理論を製作という実践に使用する場合には,理論の中の何を重視しなければならず,何を無視してもよいのかということを合わせて知っておく必要があります。つまりたとえば望遠鏡を製作するという行為は,単に光線屈折学を適用する行為というよりは,それを応用するような行為であるといえます。このいい方をそのまま用いるとするなら,スピノザは理論について高度な知識を有していて,その理論を応用する方法論についても同じ程度の高度な知識を有していたということになります。
これらはいずれも望遠鏡のレンズに特化して書かれてはいます。しかしここから,カメラ・オブスキュラのレンズの理論と応用についても,スピノザは程度の高い知識を有していたと結論しても,さほど無理があるということはできないでしょう。















