書簡十三は書簡十一への返信です。当然ながらこちらはオルデンブルクHeinrich Ordenburgからスピノザに宛てられたもの。1663年4月3日付で遺稿集Opera Posthumaに掲載されました。
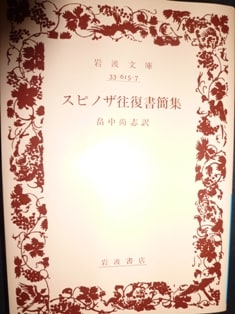
手紙の前半部分,というかこれは中心部分ですが,この部分はロバート・ボイルRobert Boyleからスピノザへの返事になっています。スピノザがオルデンブルクに宛てた書簡六の中で,スピノザはボイルに対して数々の疑問を投げ掛けていたのですが,それに対するボイルからの返信ということです。ただ,スピノザとボイルの間では,哲学的な立ち位置が異なりますので,この返信がスピノザを納得させられるものであったかどうかは疑問です。いくらボイルが自身の硝石に関する実験の正当性を主張したとしても,スピノザの中心的な関心はそこにあったわけではなかったと思われるのです。
このことに関連してはこの部分の冒頭で,ボイルは硝石に関する哲学的な分析を試みることにあったわけではなく,スコラ学派で受け入れられている通俗的な学説が薄弱な基礎の上に立っているということと,諸物の間にある種差は部分の大きさ,運動motusと静止quies,位置に帰せられることを示すためであったといわれています。つまり,何か正しい哲学的分析の結論を出すということを意図しているわけではなく,単に現に受け入れられている哲学的基盤は,実際には基盤として怪しいということを示す意図であったということです。たぶん現に受け入れられている基盤が怪しいということはスピノザも同意すると思いますが,では実際の基盤が何かということはスピノザには明らかだと思えていたので,それを導こうとしないことには不満を抱いたのではないでしょうか。
後半はオルデンブルクからスピノザに対する質問ですが,これはスピノザの著作が完成したかどうかを問うものにすぎません。この著作は『短論文Korte Verhandeling van God / de Mensch en deszelfs Welstand』か『知性改善論Tractatus de Intellectus Emendatione』ですが,畠中はその両方を示しているという主旨の訳注を付しています。
ホッブズThomas Hobbesがいう自然法lex naturalisは,社会契約という形で現実化されることになっています。この点に関しても,ホッブズがそれを理念的に考えていたのか,それとも人類の歴史が現にそういうものであったと解していたかは分かりません。僕はそもそもホッブズがいう自然状態status naturalisというのが人類の歴史の中で存在したと考えないので,これは理念的にしか解することができません。自然法はあるいは社会契約は,人間が自然状態を脱却するために現実化されるものですから,脱却するべき自然状態が存在しなかったのなら,そこから脱却するために社会契約を締結する必要性もなかったということになるからです。ただホッブズの政治理論では,あるいは国家論では,人びとは自らの意志voluntasで自然権を放棄して,共通の権力を設立するための契約pactumを結ぶということに,事実としてなっています。
僕がそれをどのように解しているのかということから分かるように,たとえこれを理論的なものとだけ解するにしても,大きな難点を抱えています。この難点を國分は別の角度から説明しています。ホッブズがいう自然権が,どんなことでも行うことができる自由libertasであるというなら,この自然権は個々の人間に与えられている力potentiaそのものと解するほかありません。一方で自然法が教えているのは,この自然権を放棄することとなっています。ここで放棄するというのは,たとえば手にしている武器を捨てて使えないようにするという意味です。しかし,たとえば武器を捨てるのと同じように,自然権を捨てることができるのかといえば,そんなことができるわけがありません。武器と違って自然権は個々の人間に属する力のことだからです。武器は捨てることができますが,力は捨てることができません。できるとすれば,力を使用しないということ,すなわち自制するということだけです。
ここから分かるように,ホッブズは実際には捨てることができないものを捨てるように自然法が命じているといっているのです。他面からいえば,力を自制するということを力を放棄するといっているのです。つまり自制と放棄を同じ意味で使用しているという点で,この論理には不徹底なところが残っています。
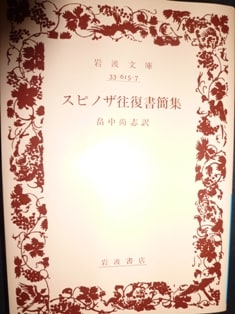
手紙の前半部分,というかこれは中心部分ですが,この部分はロバート・ボイルRobert Boyleからスピノザへの返事になっています。スピノザがオルデンブルクに宛てた書簡六の中で,スピノザはボイルに対して数々の疑問を投げ掛けていたのですが,それに対するボイルからの返信ということです。ただ,スピノザとボイルの間では,哲学的な立ち位置が異なりますので,この返信がスピノザを納得させられるものであったかどうかは疑問です。いくらボイルが自身の硝石に関する実験の正当性を主張したとしても,スピノザの中心的な関心はそこにあったわけではなかったと思われるのです。
このことに関連してはこの部分の冒頭で,ボイルは硝石に関する哲学的な分析を試みることにあったわけではなく,スコラ学派で受け入れられている通俗的な学説が薄弱な基礎の上に立っているということと,諸物の間にある種差は部分の大きさ,運動motusと静止quies,位置に帰せられることを示すためであったといわれています。つまり,何か正しい哲学的分析の結論を出すということを意図しているわけではなく,単に現に受け入れられている哲学的基盤は,実際には基盤として怪しいということを示す意図であったということです。たぶん現に受け入れられている基盤が怪しいということはスピノザも同意すると思いますが,では実際の基盤が何かということはスピノザには明らかだと思えていたので,それを導こうとしないことには不満を抱いたのではないでしょうか。
後半はオルデンブルクからスピノザに対する質問ですが,これはスピノザの著作が完成したかどうかを問うものにすぎません。この著作は『短論文Korte Verhandeling van God / de Mensch en deszelfs Welstand』か『知性改善論Tractatus de Intellectus Emendatione』ですが,畠中はその両方を示しているという主旨の訳注を付しています。
ホッブズThomas Hobbesがいう自然法lex naturalisは,社会契約という形で現実化されることになっています。この点に関しても,ホッブズがそれを理念的に考えていたのか,それとも人類の歴史が現にそういうものであったと解していたかは分かりません。僕はそもそもホッブズがいう自然状態status naturalisというのが人類の歴史の中で存在したと考えないので,これは理念的にしか解することができません。自然法はあるいは社会契約は,人間が自然状態を脱却するために現実化されるものですから,脱却するべき自然状態が存在しなかったのなら,そこから脱却するために社会契約を締結する必要性もなかったということになるからです。ただホッブズの政治理論では,あるいは国家論では,人びとは自らの意志voluntasで自然権を放棄して,共通の権力を設立するための契約pactumを結ぶということに,事実としてなっています。
僕がそれをどのように解しているのかということから分かるように,たとえこれを理論的なものとだけ解するにしても,大きな難点を抱えています。この難点を國分は別の角度から説明しています。ホッブズがいう自然権が,どんなことでも行うことができる自由libertasであるというなら,この自然権は個々の人間に与えられている力potentiaそのものと解するほかありません。一方で自然法が教えているのは,この自然権を放棄することとなっています。ここで放棄するというのは,たとえば手にしている武器を捨てて使えないようにするという意味です。しかし,たとえば武器を捨てるのと同じように,自然権を捨てることができるのかといえば,そんなことができるわけがありません。武器と違って自然権は個々の人間に属する力のことだからです。武器は捨てることができますが,力は捨てることができません。できるとすれば,力を使用しないということ,すなわち自制するということだけです。
ここから分かるように,ホッブズは実際には捨てることができないものを捨てるように自然法が命じているといっているのです。他面からいえば,力を自制するということを力を放棄するといっているのです。つまり自制と放棄を同じ意味で使用しているという点で,この論理には不徹底なところが残っています。













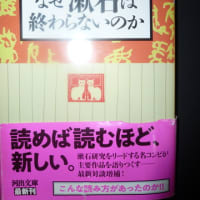








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます