
鉄道模型自体にはかなり早くから馴染みはあったのですが、それでいて当時唯一の専門誌だったTMSに手を出すのはかなり後のことでした。
理由としては「模型と工作」別冊で「高級趣味誌」と書かれていたので子供心に敷居の高さを感じた事もあったのですが、それ以上に田舎だった私の故郷ではTMS自体が地元の書店に並ばなかった事と言うのが大きかったのです。
当然TMSの別冊の存在も殆ど知りませんでした。
そんな折家族と共に東京へ出かける機会があってその際に当時は秋葉原だった「交通博物館」を見学する機会を得ました。
昭和50年頃の事です。
当時鉄道模型の「レイアウト」自体に触れる機会が殆どなかった私にとってはここのレイアウトが実質的な初体験(と言っても見ているだけですが)となりました。
広大なスペースとそこを縦横に走り回る列車の数々、更に照明効果によって一日の流れを表現する様は正に「小宇宙」の魅力を持って私を酔わせたものでした。
そんなイメージに酔ったまま帰りがけに館内の売店に立ち寄ったのですがそこの書籍コーナーにあったのがこの「レイアウトモデリング」でした。
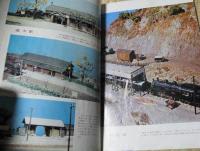
その時は内容も良く分からずに買ってもらいました。
これも良く覚えているのですが、帰宅の当日はダイヤの乱れもあって列車に乗るのに3時間待たされ乗った後も食堂車は営業休止、車内販売も殆どなく途中の駅では売店も営業終了していた悪夢のような夜汽車旅だったのですがその車内で買ったばかりの本書をひたすら読みふけり交通博物館のレイアウトとは全く異質の驚きに打たれました。
それまでレイアウトと言えば引き回された線路に駅を中心とした鉄道施設が付いているイメージが大きかったのですがここで取り上げられていたレイアウトにはそれだけではなく線路の沿線風景、それも一般の農家だったり観光地の城だったりするのですが、それらが列車の走る線路と良くマッチしてとても生き生きしているのが分かったからです。
帰宅後しばらくはこの本に酔っ払い自分なりのレイアウトプランを落書きする日々が続きました。
曲がりなりにもレイアウトを作り出すには30年近く掛かったのですが(習作はこの数年後にひとつ試しています)…
この本は今読み返しても非常に面白く、特に摂津鉄道や八里九里観光鉄道、初代の雲竜寺鉄道には強くリスペクトされました。一方で私鉄駅のシーナリィセクションなどもコンセプトは後の私のレイアウト製作に影響を与えています。
今では新刊として店頭で見ることが出来なくなっている本ですが本書を持っている他の方も触れていますが、今再販しても読み物としても充分に楽しめる内容ではないかと思います。
そんな訳で私の中では「レイアウトモデリング」と「交通博物館」はつながってイメージされています。









