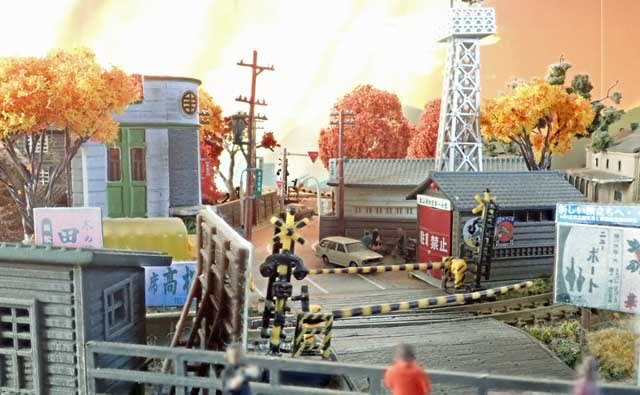久しぶりの新車の入線ネタから。

ステンレス電機の嚆矢となったEF30は最初にTOMIXが製品化し、当時としてはよく出来ていたモデルだった事もあって、わたしも趣味の再開直後くらいに入線させています(とはいえ「レールクリーニングカーの牽引機」としてでしたが)
その後、対抗機種も出ないまま暫くTOMIXの天下が続いていたのですが、割合最近にKATOも満を持して新作のEF30を投入。
TOMIX以来のインターバルの長さに見合うだけの、バージョンアップ感溢れるモデルでファンを驚かせたのは記憶に新しいところです。
わたし自身、KATOのEF30は兼ねて心の隅に引っかかるモデルではあったのですが、なかなか物を手にする事が出来ず、先日ようやく出物を抑える事ができました。

KATO製EF30のアドバンテージは何と言っても「ステンレス車体の質感」
TOMIXのそれも造形面で不満を感じることはないのですが、何せ30年近く前のモデルだけに今となっては「単なる銀色」にしか見えないカラーの質感に旧さを感じ始めていたのも確かです。
今回のモデルはプラ製でありながら微妙に「ステンレス臭い質感の塗装」になっているところがとても魅力的です。
エンドウの様な宇宙刑事じみたピカピカではなく、かといってTOMIXの様に地味でもない、この釣り合いはとても微妙なものと思いますが、KATOは本当によくやってくれました。

屋根上機器、特に配線の別パーツ化とか手すり類の細密感も、30年間のブランクを埋めて余りあるものがあります。
とまあ、今回のEF30は期待に違わぬ出来に、ぞっこん惚れ込んでしまう程のインパクトを感じました。
ステンレスの電機そのものはわたしには馴染みのないものではありますが、これだけの物だったら模型として十分に魅力的に映ります。
走行性は「いつものKATO電機」
スローや惰行もほど良く効いてKATOらしい「ぬるぬるした走り(個人的な感触、ですが)」を堪能できます。

ステンレス電機の嚆矢となったEF30は最初にTOMIXが製品化し、当時としてはよく出来ていたモデルだった事もあって、わたしも趣味の再開直後くらいに入線させています(とはいえ「レールクリーニングカーの牽引機」としてでしたが)
その後、対抗機種も出ないまま暫くTOMIXの天下が続いていたのですが、割合最近にKATOも満を持して新作のEF30を投入。
TOMIX以来のインターバルの長さに見合うだけの、バージョンアップ感溢れるモデルでファンを驚かせたのは記憶に新しいところです。
わたし自身、KATOのEF30は兼ねて心の隅に引っかかるモデルではあったのですが、なかなか物を手にする事が出来ず、先日ようやく出物を抑える事ができました。

KATO製EF30のアドバンテージは何と言っても「ステンレス車体の質感」
TOMIXのそれも造形面で不満を感じることはないのですが、何せ30年近く前のモデルだけに今となっては「単なる銀色」にしか見えないカラーの質感に旧さを感じ始めていたのも確かです。
今回のモデルはプラ製でありながら微妙に「ステンレス臭い質感の塗装」になっているところがとても魅力的です。
エンドウの様な宇宙刑事じみたピカピカではなく、かといってTOMIXの様に地味でもない、この釣り合いはとても微妙なものと思いますが、KATOは本当によくやってくれました。

屋根上機器、特に配線の別パーツ化とか手すり類の細密感も、30年間のブランクを埋めて余りあるものがあります。
とまあ、今回のEF30は期待に違わぬ出来に、ぞっこん惚れ込んでしまう程のインパクトを感じました。
ステンレスの電機そのものはわたしには馴染みのないものではありますが、これだけの物だったら模型として十分に魅力的に映ります。
走行性は「いつものKATO電機」
スローや惰行もほど良く効いてKATOらしい「ぬるぬるした走り(個人的な感触、ですが)」を堪能できます。