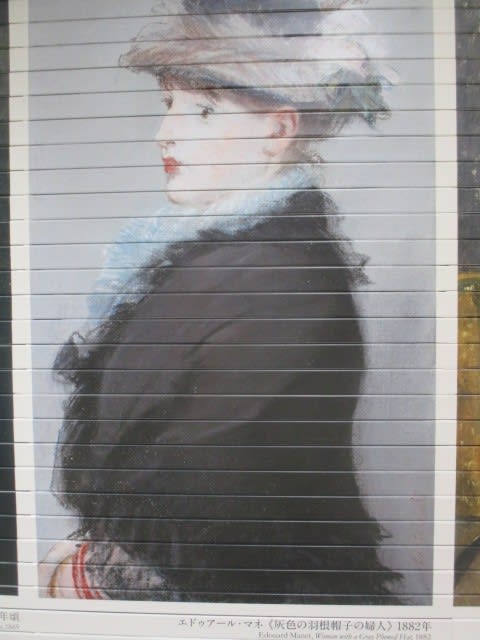昭和の時代の経営者は、売上高と経常利益に着目していれば大丈夫でした。
でも、2年前に東京証券取引所がPBR改善の要請を出しました。
PBRとは、株価純資産倍率のこと、時価総額を純資産で割ったものです。
PBRが1割れになると、時価総額が解散価値を下回るという事態になります。
日本企業で1倍割れの会社は34%、米国の22%、欧州の18%に比べて多いです。

今週の日経ビジネス誌2024.7.29号の特集記事は「逆襲のPBR経営 効率よく稼ぐ会社への変身」
PBRを高めるために努力する企業を取り上げています。
ニチガス、グンゼ、四国化成、メルコHDなどの事例が紹介されています。
Contents
Part1 優等生ニチガス 投資家から知恵を学ぶ
Part2 中堅・地方企業 PBRが促す目覚め
Part3 変われぬ経営 投資家とすれ違い

PBRは、時価総額を純資産で割ったもの。
ROEとPERを掛けた数字でもあります。
つまり、純資産を減少させるか、純利益または時価総額を増加させることによって数字が改善されます。
現代の経営者には、効率よく稼ぐ会社へ変身させ、PBRを改善することが求められています。
MBA(経営大学院)のコアとなる科目は、まさにこのファイナンス。
財務会計は現在、今を、ファイナンスは未来の数字を扱う学問です。
夏休みは、財務・ファイナンス本を再読したいと考えています。