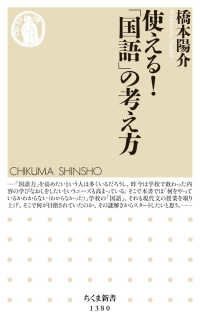今、指摘されているのは、国語の授業で文学を学ぶ意義があるのかという点です。
しかし、文学を学ぶことを否定し、論理的な思考法のみに注力すべきとの声は偏った意見です。
文学や論理といった枠にとらわれず、別角度からの国語聞養育の方法があってしかるべきです。
文章の作り手が用いる表現の仕組みや原理等、技術的な面を学ぶことです。
名作と呼ばれる小説や話題になる作品には、いくつかの法則があります。
この構造を学ぶことで、文章力・読解力をさらに育むことができると考えます。
作品、作者が置かれた時代や環境など、前提となる知識を学ぶことが重要です。
言葉に隠された背景を押さえることで、理解が深まり、その作品の魅力に気付く新たな発見があるはずです。
内容説明
国語の授業はとかく批判されがちである。
つまらない、役に立たない、小説を読む意味はない、といった声が聞こえてくる。
そのため、論理力をつけるための内容に変えるべきだという意見も強まっている。
でも、それで本当に国語の力はつくのだろうか?
そこで、文学、論理といった枠にとらわれないで、読む力・書く力を身につけるための新しい考え方を提案する。これまでなかった国語の授業がここにお披露目される。
教壇に立つ著者は、何度も「わかりやすく」と強調した。
自らの授業と伝える言葉が、生徒に理解されなければ意味ががないと言うのである。
目次
第1章 現代文の授業から何を学んだのか?
第2章 小説を読むことの意味を問う
第3章 教科書にのる名作にツッコミをいれる
第4章 「論理的」にもいろいろある
第5章 理解されやすい文章のセオリー
第6章 情報を整理し、ストーリーをつくる
第7章 論理ではなく、論拠を探せ!
第8章 すべての事実は物語られる
著者等紹介
橋本陽介[ハシモトヨウスケ]
1982年、埼玉県生まれ。慶應義塾志木高等学校卒、慶應義塾大学大学院文学研究科中国文学専攻博士課程修了。博士(文学)。慶應義塾志木高等学校講師(国語科)等を経て、お茶の水女子大学基幹研究院助教。専門は中国語を中心とした文体論、比較詩学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
出版社内容情報
小説と評論、どっちも学ばなきゃいけないの? 国語にまつわる疑問を解きあかし、そのイメージを一新させ、読む書く力を身につける。読む書く力は必要だけど、授業で身につくの? 小説と評論、どっちも学ばなきゃいけないの? 国語にまつわる疑問を解きあかし、そのイメージを一新させる。