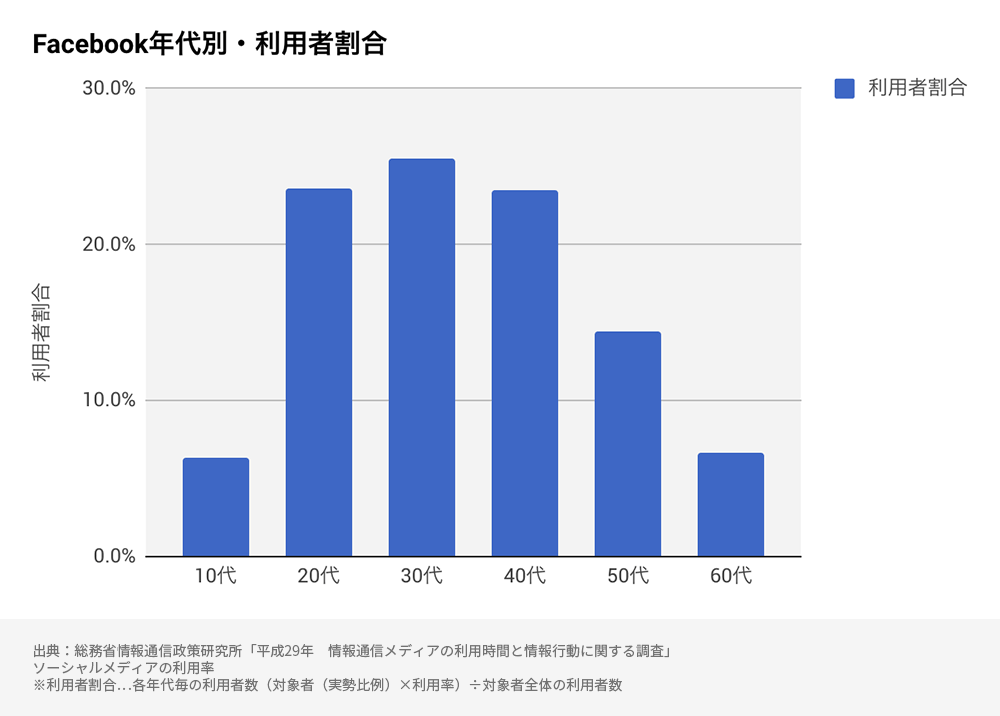雛のつるし飾りまつり
●平成31年1月20日~3月31日
1.雛の館「むかい庵」 2.文化公園雛の館 3.二ツ堀みかん園 4.なぶらとと 5.八幡神社 ※…
会場:主催:稲取温泉旅館協同組合 / 雛の館展示会場4会場(稲取温泉)
問合せ先:稲取温泉旅館協同組合 TEL:0557-95-2901
伊豆の小さな海辺町、稲取温泉に伝わる雛祭りには、古く江戸時代後期の頃より、娘の成長を願う母や祖母手作りの「つるし飾り」が飾られる風習がありました。
江戸時代においては、お雛様を購入できる裕福な家庭はまれで、せめて、お雛様の代わりに、愛する子供や孫のために手作りで、初節句を祝おうという、切ない親心から生まれたのが稲取の雛のつるし飾りです。
戦後までは盛んに行われていましたが、戦後の混乱期のさなかには、一時廃れかけておりました。
近隣の町にも、このつるし飾りを飾る風習はなく、稲取独自の美しい風習ということで、地元の稲取婦人会が、平成5年、6年度に婦人会クラブ活動の一環として復刻してくださいました。
稲取温泉旅館協同組合は、この稲取独自の美しい風習を多くの方にご覧いただきたいとの思いから、ご協力をお願いしたところ雛の会の皆様も快く応じていただき、地元の有志の方々のご協力を得て、平成10年度に稲取温泉旅館協同組合主催の春のイベントの一環として雛の館、富岡邸にて初開催され、現在に至っております。
母から娘へ、娘から孫へ、一針、一針、娘の健やかな成長を願う親心をどうぞご覧くださいませ。
 約100対(=約11,000個)展示。 |
|
 約70対展示。(=約7,700個) |
|