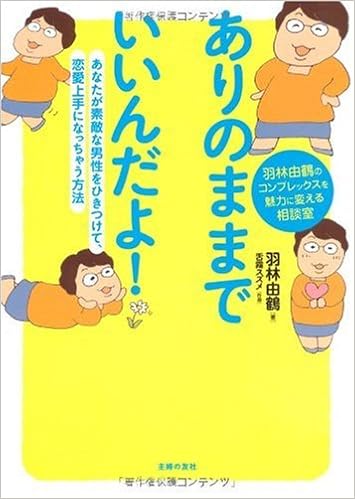内容紹介
「これは絶滅戦争なのだ」。ヒトラーがそう断言したとき、ドイツとソ連との血で血を洗う皆殺しの闘争が始まった。日本人の想像を絶する独ソ戦の惨禍。軍事作戦の進行を追うだけでは、この戦いが顕現させた生き地獄を見過ごすことになるだろう。歴史修正主義の歪曲を正し、現代の野蛮とも呼ぶべき戦争の本質をえぐり出す。
【著者からのメッセージ】
第二次世界大戦の帰趨を決したのは独ソ戦であるが、その規模の巨大さと筆紙につくしがたい惨禍ゆえに、日本人にはなかなか実感しにくい。たとえば一九四二年のドイツ軍夏季攻勢は、日本地図にあてはめれば、日本海の沖合から関東平野に至る空間に相当する広大な地域で実行された。また、独ソ戦全体での死者は、民間人も含めて数千万におよぶ。しかも、この数字には、戦死者のみならず、飢餓や虐待、ジェノサイドによって死に至った者のそれも含まれているのだ。そうした惨戦は、必ずしも狂気や不合理によって生じたものではない。人種差別、社会統合のためのフィクションであったはずのイデオロギーの暴走、占領地からの収奪に訴えてでも、より良い生活を維持したいという民衆の欲求……。さまざまな要因が複合し、史上空前の惨憺たる戦争を引き起こした。本書は、軍事的な展開の叙述に主眼を置きつつ、イデオロギー、経済、社会、ホロコーストとの関連からの説明にも多くのページを割いた。これが、独ソ戦という負の歴史を繰り返さぬための教訓を得る一助となれば、著者にとってはまたとない歓びである。
内容(「BOOK」データベースより)
「これは絶滅戦争なのだ」。ヒトラーがそう断言したとき、ドイツとソ連との血で血を洗う皆殺しの闘争が始まった。想像を絶する独ソ戦の惨禍。軍事作戦の進行を追うだけでは、この戦いが顕現させた生き地獄を見過ごすことになるだろう。歴史修正主義の歪曲を正し、現代の野蛮とも呼ぶべき戦争の本質をえぐり出す。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大木/毅
1961年生まれ。立教大学大学院博士後期課程単位取得退学(専門はドイツ現代史、国際政治史)。千葉大学ほかの非常勤講師、防衛省防衛研究所講師、陸上自衛隊幹部学校講師などを経て、現在、著述業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
この世において
「地獄」でない戦争は
存在しないのかもしれませんが
「独ソ戦」(1941-1945)は
軍事的な合理性をすら失い
「世界観戦争」(絶滅戦争)にまで
変質して行ったという点において
最高度に「地獄」的な戦争でした。
それが読了していちばんの感想であり
本書の核心と申し上げてよいかと思います。
著者は新史料(あとで述べます)に基づき
軍事的な「経緯」のみならず
独ソ戦の「性格」を正確に論じています。
一般向けの新書として白眉と思います。
上記の著者の結論は
「終章」において詳述されます。
戦争をその性格上
①通常戦争
②収奪戦争
③世界観戦争(絶滅戦争)
の3つに分類し
独ソ戦の時間的な各段階において
①、②、③がどのような
相互関係にあったのかを
「模式図」で示したものが
掲載されています(p.221)。
数学の集合論や論理学で多用される
「ヴェン図」(ベン図)を
イメージしていただけると幸いです。
要するに3つのマル(円)の相互関係です。
ちなみにジョン・ヴェン(1834-1923)は
英国の数学者・哲学者で
いわゆる「ヴェン図」を導入しました。
独ソ戦は
①通常戦争、②収奪戦争、③世界観戦争
(絶滅戦争)の3つが並行して始まり
最終的には①と②が③に完全に包含されて
しまったことが模式図から読み取れます。
そして「通常戦争」が「絶対戦争」に
変質して行っていたことが示されています。
個人的には父祖から耳で聴いた
戦争の地獄と言えばたとえば
・ノモンハン事変(1939)
・ガダルカナル島撤退(1943)
・インパール作戦(1944)
・レイテ戦(1944ー45)
・硫黄島の戦い(1945)
‥などを連想します。このように
旧日本軍の「地獄」は
例えば、敵の圧倒的火力の前に
無力感から精神的失調をきたしたり
あるいは、兵站(補給)の不足・欠損による
飢餓や餓死のイメージが強いのが
特徴と言えるかもしれません。
これらに対して独ソ戦は
ヒトラー(1989-1945)に代表される
「劣等人種」(ウンターメンシュ)を絶滅し
「東方」にドイツ民族(アーリア人)の
「生存圏」(レーベンスラウム)を獲得する
‥というナチス・ドイツ側の世界観と
スターリン(1878-1953)に代表される
「不可侵条約」を一方的に破棄した
「ファシスト」の侵略を
ソ連邦の諸国民が撃退して
「共産主義」イデオロギーの優越を示した
‥というソ連側の世界観の激突でした。
この「世界観の激突」を通奏低音として
本書は書かれていると思います。
独ソ戦の「性格」の話が長くなりましたが
軍事的な経緯やディーテイルについても
本書は「実証的に」詳述されています。
「実証的に」と強調しましたのは
これまで独ソ戦について記述された
一般向けの本の中には
誤った史料に基づいて書かれたものが
少なくなかったからです。
さらに
1989年に東欧諸国が解体し
1991年にソ連が崩壊してから
多くの新史料が見つかりましたが
それらが記述に反映されることなく
標語的に申し上げれば
「1970年代の水準で止まっている」
記述が(特に日本における)
一般向けの本では多かったことは
否定できないようです。
本書によりますと例えば
独ソ戦に直接の関係はありませんが
ヘルマン・ラウシュニングの
『永遠のヒトラー』(天声出版 1968)は
ヒトラー語録・ヒトラーとの対話
というふれこみでしたが現在では
偽書(つまり捏造)であることが
判明しています。
あるいはまた
フランス人を連想させるペンネーム
「パウル・カレル」
で多くの戦記物を書いたドイツ人
パウル・カール・シュミット
(1911-1997)につきましては
2005年
ドイツの歴史家ヴィクベルト・ベンツが
パウル・カレルの伝記を上梓し
体系的な批判を行いました。
カレルの基本的な主張は
「第二次世界大戦の惨禍に対して
ドイツが負うべき責任はなく
国防軍は劣勢にもかかわらず
勇敢かつ巧妙に戦った」(はじめに ⅷ)
でした。つまり現在の視点からみると
明らかにまちがっていたので
「歴史修正主義」(同)
です。その結果
2019年現在、母国ドイツにおいて
パウル・カレルの著作は
「すべて絶版とされている」(はじめに ⅹ)
と著者は指摘しています。
カレルの捏造(実際には存在しなかった
事象を記述すること)について
具体的な記述が「はじめに ⅸ」にあります。
新約聖書「使徒行伝」第9章18節
の表現を借りるならば
「目からうろこのようなものが落ち」る
思いを読了後にしましたのは
上記のラウシュニングやカレルに対する
現在の世界標準の評価だけではありません。
いくつか順不同で挙げてみましょう。
・ドイツ国防軍は
ナチスによる犯罪・戦争犯罪
(SSによるジェノサイドなど)
に関連して決して
無謬(むびゅう)ではなかった。
・そもそも独ソ戦は
ヒトラーの「世界観」によって
のみ起こされたのではなく
ドイツ国防軍も軍事的な観点から
「対ソ戦やむなし」と考えていた。
・ドイツ陸軍総司令部(OKH)が
立案した対ソ作戦は
1)敵を過小評価し
2)我が方の兵站能力を無視した
ずさんな計画だった。
・ドイツを含む中央ヨーロッパの
鉄道が標準軌であるのに対し
ロシアの鉄道は広軌であるから
ドイツ軍にとっては線路の
レールの幅を変える工事をしないと
鉄道による輸送はままならなかった。
(ナポレオンの侵攻を教訓に
二度と侵略されないように
ロシアはわざと鉄道の軌道の幅を
ヨーロッパと違うものにした
とする説を聞いたことがあります)
・「電撃戦」(ブリッツクリーク)
というコトバはそもそも
宣伝・啓蒙当局あるいは
ジャーナリズムが使い始めたもので
軍事用語ではなかった。
・「ドクトリン」という
軍事用語があり重要な概念である。
・史上最大の戦車戦と言えば
「クルスク会戦」(1943)
(の中の「プロホロフカ」の戦い)
という定説があったが
ソ連崩壊・冷戦終結後の新史料による
研究が進んだ結果
独ソ戦の初期において既に
大規模な戦車戦が展開されていた
ことが明らかにされた。
参加した戦車数が
クルスク(プロホロフカ)を上回る
戦車戦があったことが判明している。
ひとつの例は「センノの戦い」である。
‥上記のように私にとりまして
「目からうろこのようなもの」を
挙げて行くときりがないくらいです。
振り返ってみれば
・1989年11月 ベルリンの壁崩壊
それと並行あるいは続発する
東欧諸国の解体
・1989年12月 マルタ会談
(冷戦終結を明記)
・1990年10月 ドイツ統一
・1991年12月 ソ連邦崩壊
という歴史的事象を私は
リアルタイムで見聞きしていましたが
その結果
多くの新史料が公開され
独ソ戦を含む第二次世界大戦に関する
研究が飛躍的かつ画期的に進んだ
という事実を今、実感しています。
ヒトラーの伝記(あるいは第三帝国史)
ひとつとっても
ソ連崩壊以前に
アラン・バロック(1914-2004)
ウィリアム・シャイラ―(1904-1993)
ヴェルナー・マーザー(1922-2007)
ヨアフェム・フェスト(1926-2006)
ジョン・トーランド(1912-2004)
‥などの著者たちによる
特色ある書物が出版されていました。
それらに加え
ソ連崩壊後の新史料を踏まえた
イアン・カーショー氏(1943-)の大著
『ヒトラー(上):1889-1936 傲慢』
(白水社 2016)(原著 1998)
『ヒトラー(下):1936 -1945 天罰』
(白水社 2016)(原著 2000)
が出版されいわばヒトラー伝の
「決定版」となった観があります。
上下二段組で本文に限定しても
(上)が 611ページ
(下)が 870ページあります
(重さはどちらも軽く1キロを超えます)。
とりあえず一度目を通しましたが
なにしろ大著ゆえに細部まで
読みこなすのは時間が必要です。
独ソ戦についても的確な記述が
多々あります(特に下巻)。
カーショーの大著に比べると
逆に一冊の「新書」という
限定された舞台で独ソ戦を記述する
という行為は別種の困難さが伴なう
であろうことは容易に分かります。
材料を取捨選択し
文章の論理的構造を組み立て
かつ読者が(研究者ではなく)
(私を含む)一般人を対象とするという
配慮をする必要があります。
従って本書は
一冊の新書で独ソ戦をコンパクトに
しかも本質的に記述した労作
ということができると思います。
付録の「文献解題」は
次に読むべき本の指針となりますし
「略称、および軍事用語について」
「独ソ戦関連年表」は
よくまとまっていて使いやすいです。
当方も例に洩れずパウル・カレルをはじめとするフジ出版社などの「軍記物」や小林源文あたりからドイツ軍・武装SSについて読んでいた方だ。
この本は国防軍神話に批判的な割には意外と具体的な記述のない本だ。この著者が訳した伝記と同様、エーリヒ・フォン・マンシュタインには大甘なので、彼が第11軍司令官時代にユダヤ人虐殺の命令を出した事に触れたくないらしく、同じ南方軍集団に所属していた第6軍司令官時代にヴァルター・フォン・ライヒェナウ元帥が出したライヒェナウ指令すら出て来ない。ビーヴァーの「スターリングラード」は「ドイツ軍最高の戦略家」に手厳しいが、そんな発想がないのだろうか?
また「スターリングラード」にあるように「投降した将兵を以て『ドイツ解放軍』を結成するとの案」を出したのはヴァルター・フォン・ザイトリッツ-クルツバッハ砲兵大将なのに、パウルス元帥だと混同している。この本の著者は文献解題で犬猿の仲らしい相手の「誤訳」を批判したり、Twitterで白水社版の「ミレナへの手紙」の邦訳者がミレナ・イェセンスカーはアウシュヴィッツで「死んだ」と書いた本を酷評したりしているが、そんな事より自分の間違いに気がつくべきだ。何しろ「トレイシー」を読まないで「兵士というもの」の監修をしたり、「歴史修正主義者」というより「ナチの残党」という方が世代的にはふさわしいパウル・カレルの「砂漠のキツネ」には書かれているのにロンメル伝で他の戦死したり負傷したりした将軍達の中で後年のロードス突撃師団長ウルリヒ・クレーマンも負傷した箇所で彼だけ「削除」しているのだから。ロードス突撃師団を取り上げた「ラスト・オブ・カンプフグルッペⅢ」の著者と違って、「ヨーロッパ・ユダヤ人の絶滅」を読んでいるから、といって、こんな使い方をしていては話にならない。追記・Twitterで指摘に答える形でパウルス伝に基づいていると呟いていたが、出典を含めて本に書いてほしいものだ。
「第二次大戦の〈分岐点〉」でナルヴァの戦いを取り上げているのに「旧バルト三国」という表現を使っている。ソ連時代ですらバルト三国はソ連を「構成」する「民族共和国」なのだが、それなら「旧ウクライナ」という表現をすべきではないか?新書本だから収まりきれないだろうが、バルト三国のようなドイツとソ連との間に置かれた国家やドイツの同盟国だったハンガリー、ルーマニア、フィンランドといった国々が「絶滅戦争」では、どういう役割を果たしたのか、も触れるべきだった。また「絶滅戦争」における自由ドイツ国民委員会とドイツ将校同盟及びロシア解放軍をはじめとするドイツ側の民族部隊の位置づけも取り上げるべきだった。追記その2・「第二次大戦の〈分岐点〉」にはモスクワ戦直後の「レニングラード」解囲戦の記述で、この本での表記に従うと「第2打撃軍」がドイツ軍に包囲されてから「1942年の晩秋」に飛んでいる。つまり「第2打撃軍」がスターリンに見捨てられて壊滅して、司令官のヴラーソフ将軍がドイツ軍に投降するまでの記述がない。赤軍の「作戦術」を高く評価する為には「独ソ戦」を書くのに必要なヴラーソフの存在を抹殺したのか、それとも「ドイツ軍事史」で「予防戦争論」についてを書いた箇所で「捕虜、しかものちにウラソフ軍に走った捕虜の証言に重きを置くホフマンの主張を、『コラボ史料』が疑わしいことはいかなる歴史家にも明らかであると一蹴する」と書いたように「ウラソフ軍」の名目上の「親玉」に相当な偏見があるのか知らないが、せっかくヴォルコゴーノフ将軍が「勝利と悲劇」で一章を割いてヴラーソフを書いているという意味が理解出来ないようだ。しかし「コラボ史料」云々と評した人は「独ソ戦」の著者が忌み嫌う人が訳した「総統からの贈り物」の共著者の一人と思うが、グデーリアンの回想録を読んでいないのか、読み飛ばしたのか、あるいは邦訳とは違うテキストを使っているのか知らないけれどグデーリアンがダイペンホーフ荘園の略奪については、ある程度書いているのを知らないらしい。勿論、「誤訳」というなら話なら別ですが。「コラボ史料」という表現は例えばマルガレーテ・ブーバーーノイマンの著書や「独ソ戦」の著者がもっとも忌み嫌うパウル・カレルが「バルバロッサ作戦」でトゥハチェフスキーを書く際にシュピーゲルグラスという名前が出てくるので多分クリヴィツキーの本だと思うが、一頃だったら「反共宣伝」だの「逃亡者の捏造」だのといった「印象操作」をして「歴史のゴミ箱」に葬り去ろうとした時に使うアジプロの文句を連想する。ドイツ民主共和国国家評議会議長にしてSED書記長だったエーリヒ・ホーネッカーの「私の歩んだ道」のような本ですら「赤軍」の著者のエーリヒ・ヴォレンベルクについては「モスクワでは、レーニンの革命的教訓とレーニンの国の生活を深く理解できるよう、私を助けてくれたのであり、階級闘争の中で一〇年以上も功績をあげたのであった」とか「ボレンベルクはブションヌイと個人的な知り合いだったので、私を彼に紹介してくれたボレンベルクは、前に述べたとおり、後年、敵側に走ったが、ブションヌイとのこの一件に関して、私は今でもボレンベルクに感謝している」とかと書いているんですけれど。
独ソ戦で「ドイツ軍は占領地で徹底した破壊と殺戮を繰り広げた」
の一文の裏側で実際に何が行われていたかを知りたいと思うと、「スターリングラード攻防戦」や「クルスク戦車戦」等の個々の戦役や、アウシュビッツ等の絶滅戦争の側面を詳細に記した高価な(研究)書籍は存在する一方で、「第二次世界大戦史」のタイプの書籍では数ページしか記述がなく、価格を含めて手軽なテキストが存在せず不満でした。その中間を埋める事に成功している書籍です。
見やすい地図・図表、巻末の参考文献、略語説明、年表付きと丁寧な作り、戦争本にありがちな過度に感傷的にならない簡潔な文章・文体とテキストとして優れています。
戦局の進行(バルバロッサ作戦→スターリングラード攻防戦→ドイツ軍の退却と敗北)と呼応する形で著者が説明する所の「通常戦争」「収奪戦争」「絶滅戦争」と戦争の性質が変わっていったという記述が特に分かりやすく印象に残りました。優れたテキストですが無味乾燥な通史書ではありません。
人類史上例を見ない特異な戦争である「独ソ戦」‐その事は本書を読み進むうちに理解が進むでしょう‐に関心のある人すべてにお勧めしたいです。
個人的には「アンネの日記」や「夜と霧」、映画「スターリングラード」、アインシュタインが亡命のアメリカで原爆の実現可能性についてルーズベルト大統領に書簡を送ったという”事実”等々、本書を読んで「なるほど」と、理解が立体的に深まりました。
p.s.
いわゆる「軍事クラスタ」の読者にも刺さる内容だと思います。