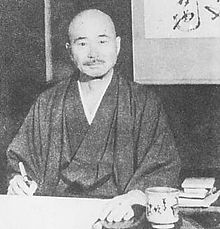眺望楽しみながら飲食
毎日新聞2019年12月17日 地方版
県庁の行政棟25階の展望ロビーに今夏、紅茶やコーヒー、軽食などを提供するカフェ「紅茶専門店花水木ティーラウンジ茨城県庁展望ロビー店」が開業した。高さ約100メートルからの眺望を楽しみながら飲食でき、若者を中心に人気を集めている。お堅い印象の県庁に登場した新名所に立ち寄った。【太田圭介】
カフェは約500平方メートルの広さで、カウンターやテーブルなど約40席。北側展望ロビーの西端にある。ディナータイム直前の夕暮れ時に訪ねると、女性客を中心ににぎわっていた。出迎えてくれたマネジャー兼店長の宮崎信子さん(46)は「開放的な雰囲気の中で紅茶や洋菓子などを味わえるすてきなお店です」と紹介した。
------------------------------------------
この夏、茨城が大きく変わる!
茨城県庁の25階・展望ロビーや水戸を代表するお祭り「水戸黄門まつり」も!
令和と共に移り変わるいばらきをご紹介します!
茨城県庁25階・展望ロビーがリニューアル!!
改修工事のためクローズしていた茨城県庁25階・展望ロビー(北側)が、満を持して、リニューアルオープンいたします。「訪れる時間によって異なるムードを楽しめる空間」をコンセプトに、来庁頂いた皆様に、より便利に、より快適に過ごしていただける空間づくりを目指しました。
「くつろぎ」「ビジネス」「打ち合わせ」「見学」と、来庁者の目的別にスペースを設置。それぞれの目的に併せた環境づくりを目的としています。
また、25階という高所から見える茨城県の広大な景色をお楽しみいただくため、昼夜の変化に対応した間接照明を導入し、よりきれいな景観をお楽しみいただけるようになりました。併設しているカフェコーナーも一新。テーブル、椅子にはモバイル対応の電源を設置するなど、快適なスペースづくりを目指しています。
開放時間を22時まで延長し、夜には、夜景を見ながら、茨城の地ビールや地酒を楽しむこともできます。

茨城県庁25階・展望ロビー「花水木ティーラウンジ」
つくば市で人気の紅茶専門店「花水木(はなみずき)」が、県庁25階・展望ロビー(北側)に登場します。
豊富な種類の紅茶はもちろん、昼の時間にはランチを、夜の時間には目の前に広がる夜景を見ながらムードある空間で茨城の地ビールや地酒も楽しめます。
今回は、「花水木ティーラウンジ」の一部をご紹介します!
|

アフターヌーンティーセット1,890円(税込)

パスタランチ(パン,サラダ,スープ,紅茶付き)1,200円(税込)

県庁オリジナルブレンドティーも販売
(ばんどう紅茶をベースに、黒糖梅酒とばらのフレーバーが香るオリジナルティー)
|
|

天気が良ければ、那須連峰まで見渡せます。

夜は、夜景を見ながら、地ビールや地酒を

イベントや宴会予約も可能
|
<リニューアルオープン(今後の開放時間について)>
7月26日(金曜日)10時オープン
リニューアルオープン後の25階展望ロビーの開放時間は、従来の20時から22時まで延長!
- 月曜~金曜日:9時30分~22時(カフェ営業10時~21時(ラストオーダー:20時),物販営業10時~20時)
- 土曜日曜祝日:10時~22時(同上)
カフェ営業については,県庁舎内店舗のご案内をご覧ください。
水戸の伝統あるお祭り「水戸黄門まつり」がリニューアル‼
昭和36(1961)年に始まり、今や水戸の夏の風物詩として愛されている「水戸黄門まつり」。
令和元年、水戸市市制施行130周年となる今年、これまでの目玉行事だった、黄門ばやしに合わせた踊りを各チームで披露する「水戸黄門カーニバル」、山車(だし)の上で繰り広げられる太鼓合戦が見物の「山車巡行」に加え、各日、目玉となる催しをご用意!熱い令和の夏を,さらに「水戸黄門まつり」が3日間にわたり盛り上げます!
第59回水戸黄門まつり
日時:7月20日(土曜日)・8月3日(土曜日)・8月4日(日曜日)
水戸に咲く日本一の花!
日本の花火師・野村花火工業が打ち上げる約7,000発の花火が湖面を彩る!
水戸偕楽園花火大会

日付:7月20日(土曜日)19時30分~21時00分
場所:千波湖(茨城県水戸市千波町3080)
初開催!日本三大提灯産地の一つ、水戸の提灯が時を超え、街を照らす!
水戸黄門提灯行列

日付:8月3日(土曜日)19時30分~20時30分
場所:国道50号(南町1丁目交差点~南町3丁目交差点間)
「水府」とは、江戸時代の水戸の異称であり、江戸時代に水戸藩の産業振興として生まれた「水府提灯」は下級武士の内職から始まったと言われています。
良質な竹からできる竹ひご一本一本を輪にして、それに糸を絡めていく「一本掛け」という独自手法に加え、水戸藩の奨励産業であった丈夫で水に強い「西ノ内和紙」を用いて作られた「水府提灯」は、まさに堅牢・質実剛健と評されました。
それにより、水戸は岐阜、福岡の八女と並び、日本三大提灯産地と称されるようになり、現在に至っています。新たな取り組みとして行われる提灯行列では「水府提灯」を使用。火の灯った提灯の行列は絶景となること間違いなし!?
日本最大級のふるさと神輿初披露!約500人で担ぐ圧巻の光景!
ふるさと神輿渡御(みこしとぎょ)

日付:8月4日(日曜日)14時00分~18時00分
場所:国道50号(南町3丁目交差点~泉町1丁目交差点間)
新しい時代の幕開けとなった令和元年、水戸市は市制施行130周年を迎えました。
その記念すべき年に、水戸神輿連合は、歴史を刻む県都水戸が新たな時代を拓くために、ふるさとに元気をふりまく絆のシンボルとして、大きな神輿を新たに作って担ぎ、伝統と和の心をつないでいきたいと強く願い、日本最大級の大神輿を製作。500名で神輿を担ぐ姿は、圧巻です!
|
水戸市出身であり、水戸大使及びいばらき大使を務める和楽器バンドのボーカル「鈴華ゆう子さん」が水戸黄門まつりのイメージソングを制作!
今回の水戸黄門まつりのために書き下ろされた新曲を、華やかなまつりの映像とともにお楽しみください。
|
 |