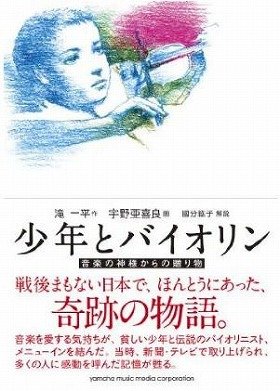島田真治が思い付いた<実験的競馬論>とは?
10万円買った馬券は、外れば紙くず同然である。
だが、紙くずのままでは、<終わらせない>と島田真治は執念を燃やす。
つまり、外れた馬券の数字の2-7に的をしぼり、<追いかけ>のである。
馬券が外れた悔しさをそのままにせずに<活かすねば>と思い入れる。
その日、女に無縁だった彼の前に、女が突然現れたのだ。
「ねえ、遊んでよ」と女が、突然、彼の進路に立ちはだかる。
府中競馬場へ向かうため、府中駅の改札口を出たとことだった。
「ダメ、これから競馬なんだ」女の懇願に戸惑う島田は正直に告げた。
「競馬なの、私ついていく」意外な女の反応だった。
女は緑のミニスカートに黒のトックリセーターで、肩までの長い黒髪であった。
彼の妹の菜穂に顔だちが似ていた。
そのために気を許したのだ。
彼は、ゲン担ぎで府中神社に立ち寄る。
女も並んで祈る。
「俺は、競馬狂だ。それでも着いてくるのか?」
「いいわ。死んだパパと同じだから。あなたは、パパに似ているので声をかけたの」
聞くと、女の父親はサラ金などで500万円の借金をし、自殺したそうだ。
「借金が500万円か? それで人は死ぬのか?!」彼は開き直る気持ちとなる。
女は自ら「ミドリ」と名乗った。
「そうか6枠だな」と競馬狂の男の反応である。
<実験的競馬論>の試みとして、「今日はミドリの6枠だな」とつぶやく。
皮肉にも6枠はでない。
「ダメか!?」と彼は弱気なる。
20万円も失っていた。
懲りずに、新たに借りたサラ金レイクの30万円が残り、10万円。
絶望的な気持ちに陥る。
これでは、ミドリと遊ぶ金も無くなると焦る。
そして、最終レース。
6枠は全くの人気薄、それでも、ミドリの6枠に賭けたのだ。
最終の4コーナー、6枠の馬は最後方のまま。
ミドリは彼の買った馬券を知って知っているので、顔が引きつる。
彼は、自らの不運を嘆く。
だが、だがである。
先行馬の人気馬はハイペースがたたったようで、ズルズル後退する。
そして、6枠の馬が1着で通過する。
二人は、<信じられない>と喜ぶより呆然とするのだ。
1万円流しの馬券が256倍。
彼はミドリに遊び代の100万円を渡す。
競馬場を後にするが、「私と、遊んでよ」ミドリは再び懇願する。
彼は、呻吟までもないので、その願いに応じてしまった。
<金で女は買わない>その頑なまでの主義を破ることに。
ミドリは彼の妹の菜穂に顔立ちがとても似ていたので、実の妹を抱いたような、言い知れぬ複雑な<近親相姦>に近い罪悪感が伴ったことは否めなかったのだ。
府中の大國魂神社は大國魂大神[おおくにたまのおおかみ]を武蔵国の守り神としてお祀りした神社です。
この大神は、出雲の大国主神と御同神で、大昔武蔵国を開かれて、人々に衣食住の道を教えられ、
又医療法やまじないの術も授けられた神様で、俗に福神又は縁結び、厄除け・厄払いの神として著名な神様です。