静岡県警による冤罪事件は4件も。
二俣事件(1958年確定)、小島事件(1959年確定)、幸浦事件(1963年確定)
そして、1966年の袴田事件である。
二俣事件――。 1950(昭和25)年1月7日早朝、二俣町(現浜松市天竜区二俣町)で一家4人が殺害されているのが見つかり、容疑者として逮捕されたのが当時18歳の少年、須藤満雄さんだった。 「自白」し、同年3月に強盗殺人罪で起訴された。
小島事件(おじまじけん)は、1950年(昭和25年)5月10日に静岡県庵原郡小島村(後の清水市、現:静岡市清水区)で発生した強盗殺人事件である。
1950年5月10日深夜、小島村で女性(当時32歳)が斧で撲殺される事件が発生した。国警静岡県本部から派遣された警部補の紅林麻雄らによる捜査の結果、同村に住む男性A(当時27歳)が被疑者として浮上した。Aはほどなく犯行を自白したが、公判の段階では自白を翻し、取調べでは拷問を受けたとして無実を訴えるようになった。また、事件には自白以外の直接証拠も乏しかったが、第一審の静岡地裁と控訴審の東京高裁はともに無罪主張を退け、被告人Aに無期懲役の有罪判決を言い渡した。
| 事件名 | 幸浦事件 | 状態 | 確定無罪 |
| 事件名(よみ) | さちうらじけん | 事件発生日 | 1948/11/29 |
| 罪名 | 強盗殺人事件 | ||
| 事件地都道府県 | 静岡県 | 事件地名 | 袋井市 |
| 事件概要 |
1948年11月29日,静岡県磐田郡幸浦村(現袋井市)で,一家4人が突然行方不明となる事件が発生した。
警察は,別件で逮捕されていた被告人2人を一家4人の殺害容疑で取り調べたところ,その内の1人が一家殺害を自白し,共犯として更に他の2人も逮捕された。 その後,被告人ら4人の自白によって,一家4人の遺体が埋められていたのが発見されたとして,起訴された。 公判では,4人とも否認し,無罪を訴えたが,1審の静岡地裁では1人を除く被告人ら3人に死刑判決が下され,2審の東京高裁まで死刑は維持された。 しかし,実際には,被告人らの自白よりも前に遺体は発見されており,自白も拷問によって採取されたものであった。 結局,最高裁は東京高裁の判断には重大な事実誤認の疑いがあるとして判決を差し戻し,差し戻された東京高裁は被告人ら4人全員について無罪判決を言い渡した。 検察はこれを上告したが,最高裁は上告を棄却し,無罪が確定した。 警察による「秘密の暴露」のねつ造と,自白偏重に由来する過酷な取調べが原因となって生じた冤罪である。 |
||
| 判決日 |
1963/7/9
|
||
| 判決裁判所 |
最高裁判所
|
||
| 書誌 |
判例時報340号17頁
|
||
| 1審 |
死刑
|
||
| 2審 |
死刑
|
||
| 最高裁 |
差戻し
|
||
| 差戻し等 |
東京高裁が無罪判決,最高裁は検察側上告を棄却
|
||
| 再審 |
|
||
| 自白/否認 |
|
||
| 備考 |
【事件関連書籍】
・上田誠吉・後藤昌次郎『誤った裁判-八つの刑事事件』(岩波書店,1960)。 |
||
紅林 麻雄(くればやし あさお、1908年〈明治41年〉 - 1963年〈昭和38年〉9月16日)は、日本の警察官。静岡県警察の元刑事。担当した事件において、数多くの冤罪被害者を生み出した。
人物
自身が担当した幸浦事件(死刑判決の後、無罪)、二俣事件(死刑判決の後、無罪)、小島事件(無期懲役判決の後、無罪)、島田事件(死刑判決の後、無罪)の各事件で無実の者から拷問で自白を引き出し、証拠を捏造して数々の冤罪を作った。その捜査手法は紅林の部下も含めて静岡県警の警察官に影響を与えることになり、紅林自身は直接捜査に関与しなかったが袴田事件(死刑判決確定後、再審第一審にて無罪判決)などの冤罪事件を生む温床ともなった[1]
あらゆる手段を用いて被疑者を拷問し、自白を強要させるなどしたことから「拷問王」、「冤罪王」と称されている[1]。
紅林はさまざまな拷問の手法を考案したが、実行には直接関与せず部下に指示を出していた。また、二俣事件における山崎兵八の書籍においては真犯人と思われる人物からの収賄の疑惑も暴露されている。
上記4事件のうち島田事件を除く3事件が一審・二審の有罪判決の後に無罪となり、島田事件も最高裁での死刑判決確定後の再審で無罪が確定した。幸浦事件・二俣事件の有罪判決破棄差し戻しの時点で御殿場警察署次席警部の地位にあった紅林は、非難を浴びた静岡県警上層部によって吉原警察署駅前派出所へ左遷された。しかも交通巡視員待遇という実質的な二階級降任だった。
紅林は世間や警察内部から非難され精神的に疲弊しきっていたが、1963年(昭和38年)7月に幸浦事件の被告人に対する無罪判決が確定したことにより、気力が尽きて警察を退職。同年9月16日に脳出血により藤枝市志太の自宅で死去。55歳没。
紅林の捜査法
前述の通り、紅林は拷問による尋問・自白の強要・自己の先入観に合致させた供述調書の捏造のような捜査方法の常習者だった。また、アリバイが出てきそうになった場合は犯行現場の止まった時計の針を動かしたトリックを自白させ、被疑者が推理マニアであることや被疑者の周辺で時計の針を動かすトリックがある探偵映画が上映されていることなどの傍証を積み重ねる手法でアリバイを否定しようとした。
これらについて二俣事件の裁判では同僚の捜査員である山崎兵八が「県警(島田事件のみ、これ以前は国警静岡県本部)の組織自体が拷問による自白強要を容認または放置する傾向があった」と証言。県警当局は山崎を偽証罪で逮捕(ただし『妄想性痴呆症(妄想型統合失調症の旧称)』として不起訴処分)したうえ懲戒免職処分にした。また幸浦事件では自分達が先に被害者の遺体が埋められている場所を探知しておきながら、被疑者に自白させた後に発見したようにして秘密の暴露を偽装した疑惑があるほか、主犯とされた男性は拷問によるためか持病(てんかん)の悪化により僅か34歳で上告中に死亡した。
紅林の捜査法に見られるような強制・拷問または脅迫によるなど任意性に疑いのある供述調書は、刑事訴訟法第322条第1項および第319条第1項により証拠とすることができない。
小島事件では実際に紅林の捜査法に最高裁の判断が下された。この最高裁判決では被告人(当時は被疑者)が取調べ中に留置場に戻ってくるたびに赤チン(局所殺菌剤)を塗るなど治療を受けていたという証言などを認定し被告人が主張する程度の過酷な拷問があったかについて疑義を呈しつつも、紅林主導の下で作成された供述調書の任意性を否定し被告人に有罪を言い渡した原判決を破棄差戻しとした(後に無罪確定)。
主な時系列
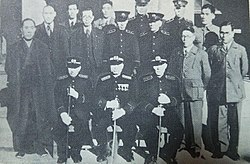
左端に当時磐田警察署所属の刑事、紅林巡査部長
- 1938年(昭和13年)8月22日、2人の女性が殺害される(浜松連続殺人事件の犯人が最初に犯した犯罪)
- 1941年(昭和16年)8月18日、1人が殺害、1人が負傷させられる(浜松連続殺人事件)
- 1941年(昭和16年)8月19日深夜、3人が殺害される。(浜松連続殺人事件)
- 1941年(昭和16年)9月27日、犯人の兄、姉、両親、兄の妻とその子供の計5人が殺害される(浜松連続殺人事件)
- 1942年(昭和17年)8月25日、4人が殺害、1人が負傷させられる(浜松連続殺人事件)
無罪の場合、戦後の4大冤罪死刑事件と数えられる、免田事件(昭和23年、熊本県、同58年無罪)、財田川事件(昭和25年、香川県、同59年無罪)、島田事件(昭和29年、静岡県、平成元年無罪)、松山事件(昭和30年、宮城県、同59年無罪)に、この袴田事件が加わり、5大冤罪死刑判決となる。









