最近、コンサートでよくするトーク。
「自分が介護する立場になって、自分がフルートを演奏する人間で本当に良かったナと実感しているんですよ」。
こんなことをよく話すようになった。
フルートを吹くことが介護とどう関係するのか。
私自身、最初からこのことに気づいていたわけではなかった。
しかし、結果として自分の職業が音楽家、しかもフルーティストであることがこれほど介護に役立つことになるとは夢にも思わなかったのだ。
どんな形の介護であれ、介護はストレスが多い。
地域で介護をする人たちが集まる「介護家族の会」の会合に出ると、時々あまりにも悲惨な話を聞かされことばを失う時がある。
みんなギリギリのところで(介護に)踏ん張っているんダ。
そんなことをいつも思い知らされる。
人の心の中をおし計ることはできないが、おそらくみんな自分たちのストレスをどこかでうまく逃がしているのだろうと思う(なかには逃がしきれずに修羅場になってしまう人もいるのかもしれないが)。
介護という「状況」で、毎日楽しく明るく笑って暮らしていける人は少ない。
理想的にはそうあるべきなのだろうが、現実は過酷だ。
私の場合も4年前に恵子が病気になり彼女の介護を24時間しなければならなくなり、しかも家事全ても一手に引き受けなければならない生活になり、自分ではそれほどたまっていないと思っていたストレスも時々「爆発しそうになる」ぐらいたまってしまうことがある。
そんな時、本気で「どうしたらこの状況から逃れられるのか?」と真剣に悩む。
ふだん伊豆の山奥に住んでいるせいか、そう簡単に友人と会ってお茶をしたりアルコールを飲んだりはできない。
そんな私がどうやってストレスを逃しているのか。
ある時気がつくと、「あ、そうか。これか」と思い当った。
それは、「楽器」の練習。
楽器の演奏が仕事の私にとって「なぜ楽器の練習が息抜きになるのか」。
私自身にもよくわからなかった。
しかし、不思議と楽器を持つとストレスは消えていく。
音楽が好きだから?
楽器をずっと長年やってきたから?
こんな私の疑問を、解剖学者の三木茂夫という方がその著書の中で明快に説明してくれていた。
三木先生の「論」はとてもユニークだ。
ユニークだけれども、とてもわかりやすい。
「ストレスがたまる」と言った時の「たまる」ということに関しての先生はこう説明する。
「植物はモノをためない。水や栄養を取り入れそれがそのまま成長につながっていく。だから、植物は自然そのもの。宇宙そのものと言える」。
しかし「動物は、飢えにそなえて身体の内部(内臓)に食べ物を栄養や血液、脂肪、筋肉に代え蓄え身体を動かしていく。だから、その内臓の働きに不都合が生じるとどんどん不必要なものがたまっていく。それが結局ガン化してしまうことになる。要は、ためないこと」。
先生に言わせると「ストレス」も「心にたまった不必要なモノがガンになってしまったモノ」ということになる。
だから、先生は「動物も、植物のように宇宙と一体化した生活をしなければならない」と説く。
解剖学者というのは、最初から「死んでいる人」を相手にしているせいか、人間の「生と死」をとても客観的に冷静に見つめる人が多い。
この三木先生もそうだし、『バカの壁』の作者の養老孟子先生もそうだし、自ら脳卒中に罹患して自分自身の右脳と左脳の機能を冷静に分析したアメリカの解剖学者のジル・テイラー女史など、解剖学の先生たちの「論」はいずれも明快だ。
普通、私たちは死んだ後のことがわからないから「生」の側から(さまざまな角度で)「死」の意味を考えようとする。
しかし、解剖学者という人たちは、最初から「死」と向き合っているのだ。
つまり、「結果(死)」から「原因(生)」を探りそこから人間(だけではなく、ありとあらゆる生物)が「生きている」ことの意味を追求する学問だからそのロジックが明快なのかもしれない。
三木先生が、人間(動物)に必然的に起きる諸悪の根源である「たまり」を解消するために一番大事だとしているのが「丹田呼吸」だ。
丹田(つまり、腹筋のこと)を外側からのマッサージで刺激することも内臓のたまりを解消するのに役に立つし(つまり便通がよくなる)、「肺にたまった汚い空気」を押し出してやることも肺の浄化に役に立つ。
せっかくなので、その辺の記述を三木先生の『生命とリズム』という本から抜粋してみる。
「植物というものは宇宙と一体をなしている。つまり、自分のからだの延長が宇宙そのものであります。ところが、動物というものは、宇宙を自分のからだの中に取り込んでいる。いわゆる小宇宙というものを抱え込んでいるため、その宇宙からある程度隔離されている。いってみれば、自然に対して自閉的になっているのです。だから、植物は宇宙と一心同体であるため、ため込む必要がない。ところが動物は自然から独立したために、やはり冬がくれば食物がなくなるから、どうしてもからだの中にため込まねばならない。そのようにため込むことを行うようになったのが人間の<業>です。
(中略)
だいたい、たまればたまるほど汚くなります。例えば、肝臓の流れが悪くなると最後には肝硬変になります。肝臓でためても、それはつねに小川のせせらぎのように流れていないといけません。
まして、夜寝る前に餓鬼のように食べる。腹いっぱい食べて寝る。胃袋の中で一晩中たまって腐っていく。こんな時はたいてい慢性胃炎になっています。この胃の粘膜の延長が舌です。舌が真っ白で、これは粘膜の新陳代謝が滞っている証拠です。
(中略)。
このたまった部分をマッサージしますと腹壁を介して腸管がハッと気づき蠕動(ぜんどう)を始めます。ですから、上腹部の丹田呼吸の運動というものは、内臓の<たまり>を解消していく理想的な方法であると思います。
(中略)。
肺といっても食道の一部が盲腸のようにふくらんだものですから、ここにもたまります。肺の中も糞づまりのようになりますから、どうしてもきれいに出さないといけない。呼気が大切なゆえんです。つまり、肺もまた空気のたまり場であります」。
そうか、自分が管楽器をやってきたことがこんな形で「身体や精神の浄化」に役に立っていたとは..。
とはいっても、丹田呼吸は別に管楽器だけに限らない。
「歌を歌う」ことでも丹田呼吸はできるし、単にゆっくりと「深呼吸」するだけでも同じ効果がある。
要は、横隔膜を使って「たまったモノ」を押し流してあげれば良いのだ。
私も、恵子に毎日のように言っている。
「良い姿勢になって肩の力を抜いて…」
「深くゆっくりと呼吸して」
「息を吐く時は思いっきりゆっくりと…」
すると、彼女のこわばり固く突っ張っていた足の指が少し開いていくのがよくわかる。
「自分が介護する立場になって、自分がフルートを演奏する人間で本当に良かったナと実感しているんですよ」。
こんなことをよく話すようになった。
フルートを吹くことが介護とどう関係するのか。
私自身、最初からこのことに気づいていたわけではなかった。
しかし、結果として自分の職業が音楽家、しかもフルーティストであることがこれほど介護に役立つことになるとは夢にも思わなかったのだ。
どんな形の介護であれ、介護はストレスが多い。
地域で介護をする人たちが集まる「介護家族の会」の会合に出ると、時々あまりにも悲惨な話を聞かされことばを失う時がある。
みんなギリギリのところで(介護に)踏ん張っているんダ。
そんなことをいつも思い知らされる。
人の心の中をおし計ることはできないが、おそらくみんな自分たちのストレスをどこかでうまく逃がしているのだろうと思う(なかには逃がしきれずに修羅場になってしまう人もいるのかもしれないが)。
介護という「状況」で、毎日楽しく明るく笑って暮らしていける人は少ない。
理想的にはそうあるべきなのだろうが、現実は過酷だ。
私の場合も4年前に恵子が病気になり彼女の介護を24時間しなければならなくなり、しかも家事全ても一手に引き受けなければならない生活になり、自分ではそれほどたまっていないと思っていたストレスも時々「爆発しそうになる」ぐらいたまってしまうことがある。
そんな時、本気で「どうしたらこの状況から逃れられるのか?」と真剣に悩む。
ふだん伊豆の山奥に住んでいるせいか、そう簡単に友人と会ってお茶をしたりアルコールを飲んだりはできない。
そんな私がどうやってストレスを逃しているのか。
ある時気がつくと、「あ、そうか。これか」と思い当った。
それは、「楽器」の練習。
楽器の演奏が仕事の私にとって「なぜ楽器の練習が息抜きになるのか」。
私自身にもよくわからなかった。
しかし、不思議と楽器を持つとストレスは消えていく。
音楽が好きだから?
楽器をずっと長年やってきたから?
こんな私の疑問を、解剖学者の三木茂夫という方がその著書の中で明快に説明してくれていた。
三木先生の「論」はとてもユニークだ。
ユニークだけれども、とてもわかりやすい。
「ストレスがたまる」と言った時の「たまる」ということに関しての先生はこう説明する。
「植物はモノをためない。水や栄養を取り入れそれがそのまま成長につながっていく。だから、植物は自然そのもの。宇宙そのものと言える」。
しかし「動物は、飢えにそなえて身体の内部(内臓)に食べ物を栄養や血液、脂肪、筋肉に代え蓄え身体を動かしていく。だから、その内臓の働きに不都合が生じるとどんどん不必要なものがたまっていく。それが結局ガン化してしまうことになる。要は、ためないこと」。
先生に言わせると「ストレス」も「心にたまった不必要なモノがガンになってしまったモノ」ということになる。
だから、先生は「動物も、植物のように宇宙と一体化した生活をしなければならない」と説く。
解剖学者というのは、最初から「死んでいる人」を相手にしているせいか、人間の「生と死」をとても客観的に冷静に見つめる人が多い。
この三木先生もそうだし、『バカの壁』の作者の養老孟子先生もそうだし、自ら脳卒中に罹患して自分自身の右脳と左脳の機能を冷静に分析したアメリカの解剖学者のジル・テイラー女史など、解剖学の先生たちの「論」はいずれも明快だ。
普通、私たちは死んだ後のことがわからないから「生」の側から(さまざまな角度で)「死」の意味を考えようとする。
しかし、解剖学者という人たちは、最初から「死」と向き合っているのだ。
つまり、「結果(死)」から「原因(生)」を探りそこから人間(だけではなく、ありとあらゆる生物)が「生きている」ことの意味を追求する学問だからそのロジックが明快なのかもしれない。
三木先生が、人間(動物)に必然的に起きる諸悪の根源である「たまり」を解消するために一番大事だとしているのが「丹田呼吸」だ。
丹田(つまり、腹筋のこと)を外側からのマッサージで刺激することも内臓のたまりを解消するのに役に立つし(つまり便通がよくなる)、「肺にたまった汚い空気」を押し出してやることも肺の浄化に役に立つ。
せっかくなので、その辺の記述を三木先生の『生命とリズム』という本から抜粋してみる。
「植物というものは宇宙と一体をなしている。つまり、自分のからだの延長が宇宙そのものであります。ところが、動物というものは、宇宙を自分のからだの中に取り込んでいる。いわゆる小宇宙というものを抱え込んでいるため、その宇宙からある程度隔離されている。いってみれば、自然に対して自閉的になっているのです。だから、植物は宇宙と一心同体であるため、ため込む必要がない。ところが動物は自然から独立したために、やはり冬がくれば食物がなくなるから、どうしてもからだの中にため込まねばならない。そのようにため込むことを行うようになったのが人間の<業>です。
(中略)
だいたい、たまればたまるほど汚くなります。例えば、肝臓の流れが悪くなると最後には肝硬変になります。肝臓でためても、それはつねに小川のせせらぎのように流れていないといけません。
まして、夜寝る前に餓鬼のように食べる。腹いっぱい食べて寝る。胃袋の中で一晩中たまって腐っていく。こんな時はたいてい慢性胃炎になっています。この胃の粘膜の延長が舌です。舌が真っ白で、これは粘膜の新陳代謝が滞っている証拠です。
(中略)。
このたまった部分をマッサージしますと腹壁を介して腸管がハッと気づき蠕動(ぜんどう)を始めます。ですから、上腹部の丹田呼吸の運動というものは、内臓の<たまり>を解消していく理想的な方法であると思います。
(中略)。
肺といっても食道の一部が盲腸のようにふくらんだものですから、ここにもたまります。肺の中も糞づまりのようになりますから、どうしてもきれいに出さないといけない。呼気が大切なゆえんです。つまり、肺もまた空気のたまり場であります」。
そうか、自分が管楽器をやってきたことがこんな形で「身体や精神の浄化」に役に立っていたとは..。
とはいっても、丹田呼吸は別に管楽器だけに限らない。
「歌を歌う」ことでも丹田呼吸はできるし、単にゆっくりと「深呼吸」するだけでも同じ効果がある。
要は、横隔膜を使って「たまったモノ」を押し流してあげれば良いのだ。
私も、恵子に毎日のように言っている。
「良い姿勢になって肩の力を抜いて…」
「深くゆっくりと呼吸して」
「息を吐く時は思いっきりゆっくりと…」
すると、彼女のこわばり固く突っ張っていた足の指が少し開いていくのがよくわかる。















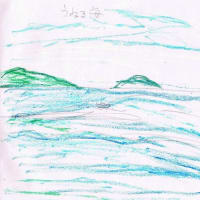


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます