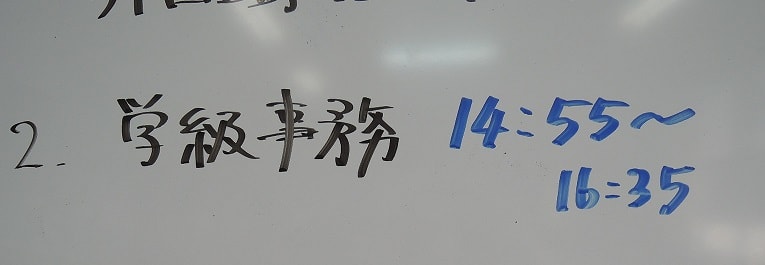現場の職員に繰り返し言っていることがある。
「問題は、一人で抱え込まないように」
である。
学年主任や校務分掌の部長に相談してほしい。
緊急を要する問題や重要な問題については、管理職に相談してほしい。
このように言っている。
相談するだけでも、心の負担はずいぶん軽くなる。
「問題は、一人で抱え込まないように」
である。
学年主任や校務分掌の部長に相談してほしい。
緊急を要する問題や重要な問題については、管理職に相談してほしい。
このように言っている。
相談するだけでも、心の負担はずいぶん軽くなる。