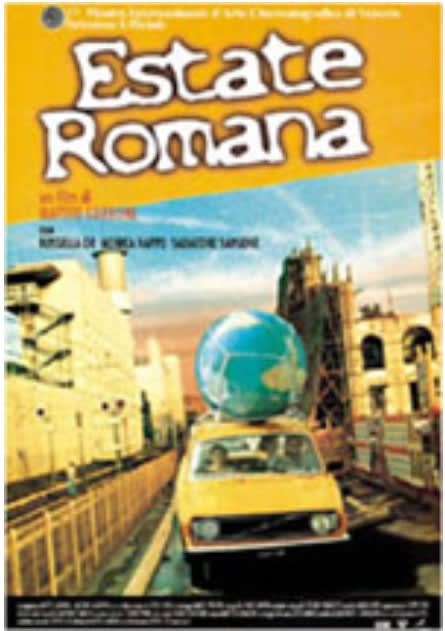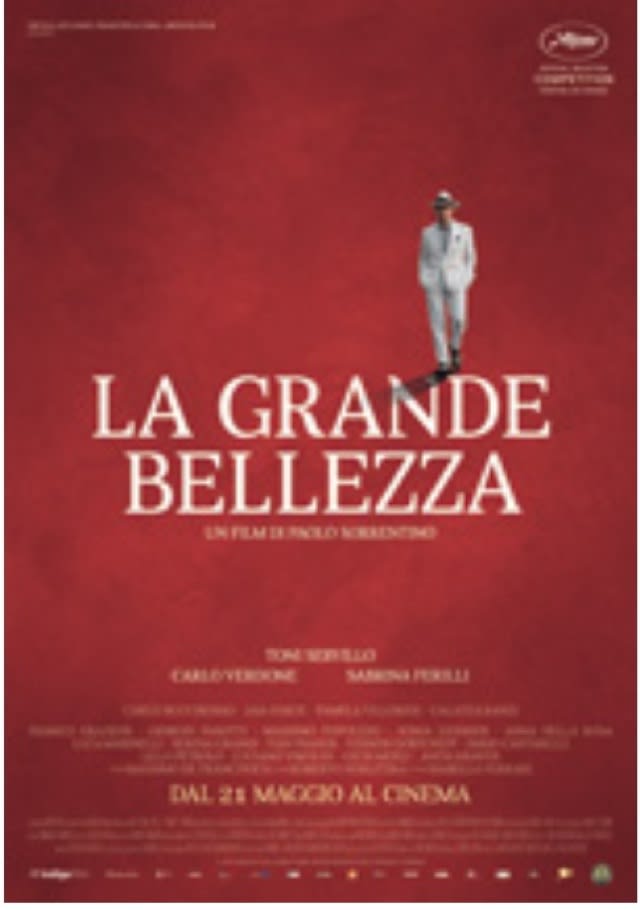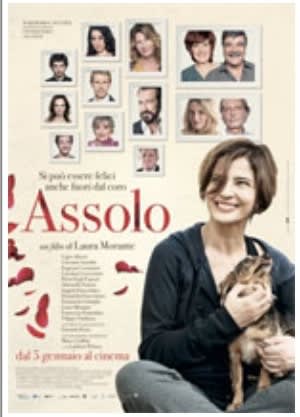Dolcetto d’Alba Piano delli Perdoni 2014 Mossio
ドルチェット・ダルバ ピアーノ・デッリ・ペルドーニ 2014 モシオ

ルカの主宰する試飲会は、試飲するワインの前にパラメーターとなるワインを出すことが多い。
これは、完全ブラインドのワインの順番をクジで決めるので、一番最初に当たったワインはたいてい部が悪い、と思っていることからある。
確かに、試飲会では一般に(ブラインドではない)、最初は軽いワイン、つまりたいていの場合安いワインでもあり(その後のに比べての意味)、品質の劣る(同じくその後より)ワインであることが多いので、そういったイメージも自然と働くのだと思う。
ただし、2本のワインをブラインドで試飲させると、1本目の方が美味しいという人が多いという逆の心理も働く。。。
だから、あってもなくても、とは私の個人的見解だが、ともかく、その試飲会のベースとなるワインを最初に出すというのが彼のやり方。
今回は、完全なブラインドで、24から32ユーロという、彼の試飲会にしては高級なワインが出るという趣向だったので(別ページを参照)それをいきなりではなく、とにかくいつもの価格帯10ユーロ程度のものを1本飲んでから、ということだった。
選んだのは、彼が年間数ケース買って自宅消費用にしているドルチェット。
(なお、これだけはブラインドではない)
ドルチェットは、昔、好きで飲んでいたのだが、ワインの勉強を始め、嫌いだったベルベーラを好きになったころから、好きだったドルチェットが好きではなくなった。そこで、今はどちらかというと避け、進んで飲むことはしないのだが、このドルチェットはドルチェットらしからぬところが美味しい。
実はこのワインは、今回はブラインドではなかったが、以前、ルカにブラインドで出され、ドルチェットだとは思わなかったドルチェットである。
チェリーがきれいで、そこにステンレス風、やや、血を思わせる香りが混じるところがドルチェットらしくない。香りがだいぶスッキリしている。しばらくして、ドルチェットらしいふくよかな感じが出てくるが、ぼってっとしてた重たさがない。そして、ほろ苦さが上がってくる。
酸がきれいに出ているのもドルチェットのイメージとは違う。重たくなく、持続性も程よく、最後にほろ苦さが残る。
いたってシンプルだが、心地よく、飲んでいて飽きないワイン。
合わせられる食事も、肉系、野菜系の料理なら大抵のものに大丈夫、というタイプ。
なお、試飲会で出たブラインドの7ワインについてはこれから。。。。
ドルチェット・ダルバ ピアーノ・デッリ・ペルドーニ 2014 モシオ

ルカの主宰する試飲会は、試飲するワインの前にパラメーターとなるワインを出すことが多い。
これは、完全ブラインドのワインの順番をクジで決めるので、一番最初に当たったワインはたいてい部が悪い、と思っていることからある。
確かに、試飲会では一般に(ブラインドではない)、最初は軽いワイン、つまりたいていの場合安いワインでもあり(その後のに比べての意味)、品質の劣る(同じくその後より)ワインであることが多いので、そういったイメージも自然と働くのだと思う。
ただし、2本のワインをブラインドで試飲させると、1本目の方が美味しいという人が多いという逆の心理も働く。。。
だから、あってもなくても、とは私の個人的見解だが、ともかく、その試飲会のベースとなるワインを最初に出すというのが彼のやり方。
今回は、完全なブラインドで、24から32ユーロという、彼の試飲会にしては高級なワインが出るという趣向だったので(別ページを参照)それをいきなりではなく、とにかくいつもの価格帯10ユーロ程度のものを1本飲んでから、ということだった。
選んだのは、彼が年間数ケース買って自宅消費用にしているドルチェット。
(なお、これだけはブラインドではない)
ドルチェットは、昔、好きで飲んでいたのだが、ワインの勉強を始め、嫌いだったベルベーラを好きになったころから、好きだったドルチェットが好きではなくなった。そこで、今はどちらかというと避け、進んで飲むことはしないのだが、このドルチェットはドルチェットらしからぬところが美味しい。
実はこのワインは、今回はブラインドではなかったが、以前、ルカにブラインドで出され、ドルチェットだとは思わなかったドルチェットである。
チェリーがきれいで、そこにステンレス風、やや、血を思わせる香りが混じるところがドルチェットらしくない。香りがだいぶスッキリしている。しばらくして、ドルチェットらしいふくよかな感じが出てくるが、ぼってっとしてた重たさがない。そして、ほろ苦さが上がってくる。
酸がきれいに出ているのもドルチェットのイメージとは違う。重たくなく、持続性も程よく、最後にほろ苦さが残る。
いたってシンプルだが、心地よく、飲んでいて飽きないワイン。
合わせられる食事も、肉系、野菜系の料理なら大抵のものに大丈夫、というタイプ。
なお、試飲会で出たブラインドの7ワインについてはこれから。。。。