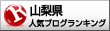市川三郷町内の道祖神巡りは今回で最後です。
最後は、我が家の近くにある道祖神を三体ご紹介します。
まず、「新町道祖神」。
新町というのは、役場前から新田橋にかけて、比較的新しくできた集落の呼び名です。
改修された道路に沿って社(祠かな?)が建てられ、その中に祀られています。

他の道祖神に比べると、恵まれた環境にあると言えるでしょうか。
残念ながら白い布に巻かれたままになっているので、どのようなものなのかはうかがい知ることができません。

祭礼などの時にしか御開帳しないのでしょうか?
中に入って近くで撮影してみても同じです。

座布団の上に鎮座ましましているという...。
二番目は地元六丁目にある福寿院というお寺の境内にある道祖神です。

福寿院はしだれ桜で有名なお寺ですが、この撮影時期は三月の半ば。
開花には二週間ほど早かったのが残念です。
写真の真ん中にある小さな祠のような形をしているのが道祖神です。

よく見ないと見落としてしまいそうな道祖神。
六丁目の道祖神は、嘉永六年(1852年)の建立だそうです。

台座に「六丁目」と彫ってあります。
さて、最後は七丁目にある道祖神です。
こちらの道祖神も、福寿院からさほど離れていない円立寺(えんりゅうじ)というお寺の入り口脇にあります。

ちょっと見ると「何でこんなところに?」というような場所に、ポツンと置かれています。

この双体道祖神は、町内では最も古く、天明七年(1787年)の建立と言われています。

最も古いという割には、掘りの深い双体神ですね。
六丁目と七丁目の道祖神は、どちらも中央通り沿いにあります。
※「甲州・市川のまちづくり読本」より
最後は、我が家の近くにある道祖神を三体ご紹介します。
まず、「新町道祖神」。
新町というのは、役場前から新田橋にかけて、比較的新しくできた集落の呼び名です。
改修された道路に沿って社(祠かな?)が建てられ、その中に祀られています。

他の道祖神に比べると、恵まれた環境にあると言えるでしょうか。
残念ながら白い布に巻かれたままになっているので、どのようなものなのかはうかがい知ることができません。

祭礼などの時にしか御開帳しないのでしょうか?
中に入って近くで撮影してみても同じです。

座布団の上に鎮座ましましているという...。
二番目は地元六丁目にある福寿院というお寺の境内にある道祖神です。

福寿院はしだれ桜で有名なお寺ですが、この撮影時期は三月の半ば。
開花には二週間ほど早かったのが残念です。
写真の真ん中にある小さな祠のような形をしているのが道祖神です。

よく見ないと見落としてしまいそうな道祖神。
六丁目の道祖神は、嘉永六年(1852年)の建立だそうです。

台座に「六丁目」と彫ってあります。
さて、最後は七丁目にある道祖神です。
こちらの道祖神も、福寿院からさほど離れていない円立寺(えんりゅうじ)というお寺の入り口脇にあります。

ちょっと見ると「何でこんなところに?」というような場所に、ポツンと置かれています。

この双体道祖神は、町内では最も古く、天明七年(1787年)の建立と言われています。

最も古いという割には、掘りの深い双体神ですね。
六丁目と七丁目の道祖神は、どちらも中央通り沿いにあります。
※「甲州・市川のまちづくり読本」より