『地図で学ぶ世界史「再入門」伊藤敏著で分かる地図と歴史』
『分かり易い「文明の発達」と地形との関係、日本と中国でのみ使われた
「世界四大文明」の発達した“超合理的な理由”に納得も!』
地図で学ぶ 世界史「再入門」
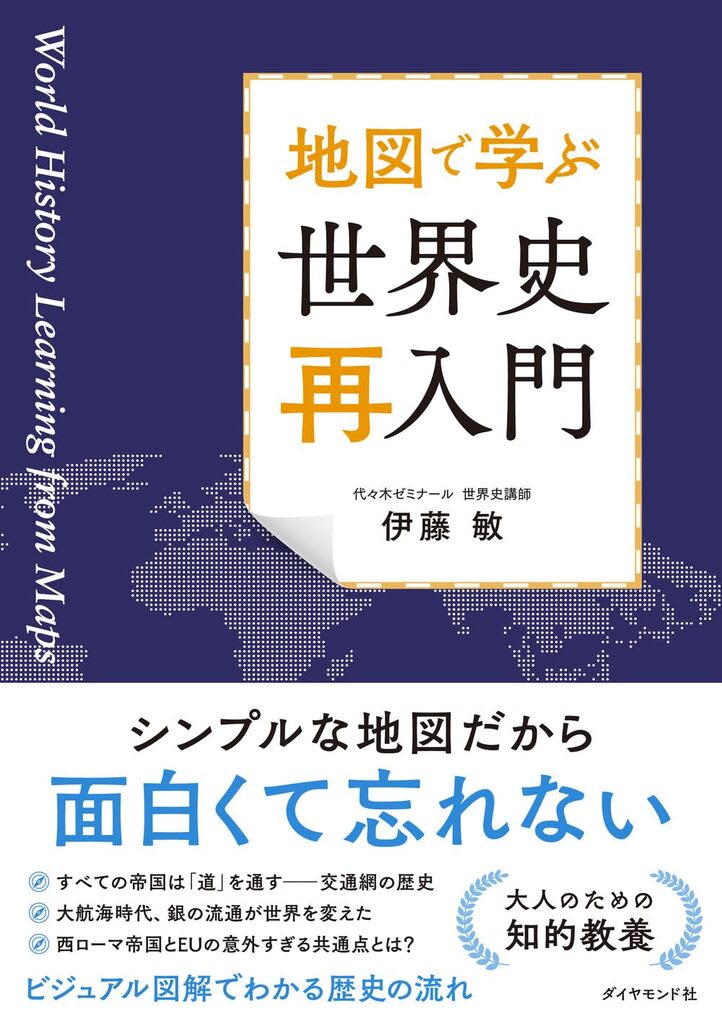
ウエブ情報から引用
先ずは、著者伊藤敏(いとう・びん)のプロフィールから、
988年、東京都に生まれる。筑波大学卒、同大学院にて修士号を取得し、
博士後期課程単位取得退学。高校非常勤講師や塾講師を経て、2019年より
代々木ゼミナール講師として首都圏や北海道などで予備校講師として活動。
世界史の「理解」を信条に、多くの受験生なかでも早慶合格者の厚い支持
を受ける。正確無比な地図の描写と、「世界史の理解」を信条とした解説に
定評がある。他の追随を許さないクオリティの地図や図解は最大の持ち味で
あり、受講生の「理解」を助ける最大のツールでもある。
授業では、言語、思想、宗教、軍事など様々な分野にわたる知識を、世界史を
楽しみながら学ぶことができる。
同氏の【大人の教養】メソポタミアで文明が発達した“超合理的な理由”「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」からの抜粋・引用、
人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。 地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。
政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。 地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。 著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。 黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。 近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。
文明と都市はどう発展するのか?
世界史上で最古の文明が生じた地域の一つがオリエントと呼ばれる地域です。さて、ここでいきなりですが、「オリエント」とはどこだか説明できますか?
Orient(英)の語源はラテン語のoriorという「上がる、昇る」を意味する動詞にあり、すなわち「太陽の昇る地(=東方)」を指します。 これは大まかにインダス川以西の地域を指し、今日では「中東(中近東)」ないし「西アジア」と呼ばれる地域にあたります。

ウエブ情報から引用
文明発達のメカニズムと合理性
さて、オリエント、すなわち中東といえば、砂漠の広がる乾燥した気候ですね。乾燥帯に属するこの地域は、年間の降水量が少ないのが特徴です。 このため水資源の豊かな地域に人口が自然と集中し、文明の形成が促されたのです。
オリエントには3本の大河があり、このうちの2本であるチグリス川とユーフラテス川は、「メソポタミア(「川に挟まれた地」の意)」を形成します。この、メソポタミア、シリア、パレスティナの一帯は「肥沃な三日月地帯」と総称されます。もう1本は「エジプト」のナイル川であり、上流のエチオピア高原で雨期に降る雨によりナイル川が増水し、氾濫を起こします。
このナイル川の氾濫は、上流の栄養に富んだ土を下流まで運ぶため、エジプトは古くから高い農業生産量を誇ります。
いずれの地域も、大河から水を引く運河など、治水による灌漑農業のための大規模な土木工事を必要とし、集村化や強力な指導者が出現します。さらに、メソポタミアとエジプトはいずれもほぼ決まった時期に氾濫が生じるため、占星術による暦の計測が発達します。
これにより、「占星術→天のメッセージを読み取る→神の意思を直接に授かる」という理屈から、占星術に長けた集団が「神官団」を形成するようになります。その頂点に立ったのが「王」だったのです。このように、神の権威により王権を正当化した政治を「神権政治」と呼びます。
人口の集中とともに近隣の部族(血縁関係を中心とした氏族が複数集まり、共通の文化的背景を有する集団)が集まることで「ムラ」を形成し、さらにそのムラが集合することで「都市」が形成されます。この都市こそ、世界史上最初の国家であり、これら最小単位の国家は「都市国家」と呼ばれます。
(『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の一部抜粋・編集を行ったものです)
『その四大文明誕生は大河川(水位変動が大きく、河床勾配が小さい)の近くで、必然的に発達』しかし、『ブラジルのアマゾン川とその流域は、その条件には合うが例外で、大文明は発祥せず』
文明 河川 長さ 水源海抜 河床勾配
エジプト ナイル 6853㎞ 1134ⅿ 0.02%
メソポタミア チグリス 2850㎞ 1150ⅿ 0.04%
ユーフラテス 2800㎞ 3520m 0.13%
インダス インダス 3200㎞ 4500ⅿ 0.14%
中国 黄河 5464㎞ 4800ⅿ 0.09%
長江 6300㎞ 5042ⅿ 0.08%
エジプト ナイル 6853㎞ 1134ⅿ 0.02%
メソポタミア チグリス 2850㎞ 1150ⅿ 0.04%
ユーフラテス 2800㎞ 3520m 0.13%
インダス インダス 3200㎞ 4500ⅿ 0.14%
中国 黄河 5464㎞ 4800ⅿ 0.09%
長江 6300㎞ 5042ⅿ 0.08%
ブラジル アマゾン川 6516㎞ 5597ⅿ 0.09%
『例外は古代アンデス文明カラル遺跡が、大河川なしでも、定住農耕・文字ありで、新大陸に古代アンデス文明カラル遺跡が存在』
ペルー カラル遺跡(写真-1)VSエジプト 大ピラミッド(写真-2)
紀元前: 3000~1800年頃 紀元前: 3000~1000年頃
総面積: 66ヘクタール 総面積: 180ヘクタール
推定人口:数万~十数万人 推定人口:数十万~百万余人
カラル遺跡(写真-1)

ウエブ情報から引用
比較するために、大ピラミッド(写真-2)

ウエブ情報から引用
カラル遺跡(パノラマ)

ウエブ情報から引用
カラル遺跡(中央部分)

ウエブ情報から引用
中南米の古代文明は大河川の畔に発祥せず
とくに、南米大陸、ペルー を中心とする 太平洋 沿岸地帯およびペルーからボリビア へつながるアンデス中央高地 に存在した古代アンデス文明。 メソポタミア文明・エジプト文明・インダス文明・黄河文明といったいわゆる世界四大文明などと異なり文字は持たない(初期の『キープ(結縄)』が数字と文字の機能を持っていた)。 今まで親しんできた、アステカ文明・マヤ文明・インカ文明(特に、古代アンデス文明)をもう少し調べてみたいと再認識しました。
(記事投稿日:2025/02/18、#988)














