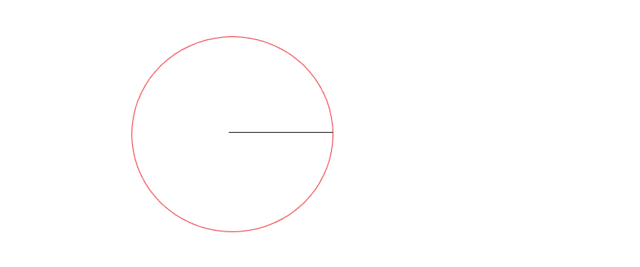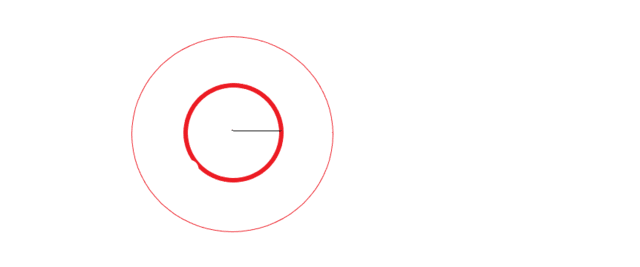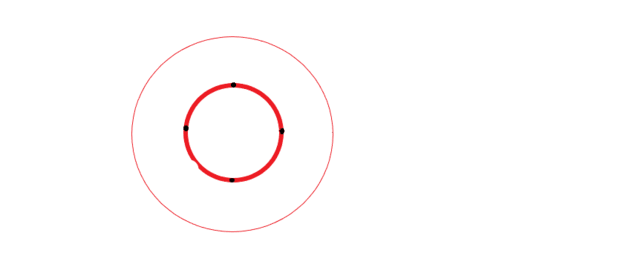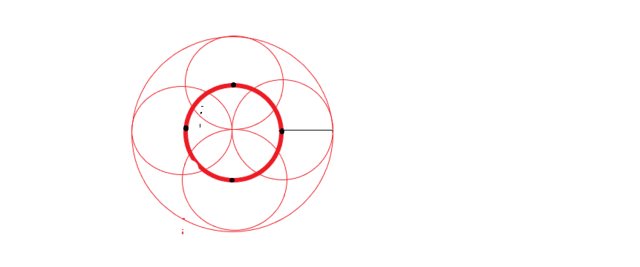稚内市にある小高い丘の上に立つと、天気の良い日はその向こうに、樺太を望むことが出来ます。
そこには、「乙女の碑」と言われる石碑が立てられています。
その碑には、今から75年前に起こった悲劇について記されているのです…。

75年前、この碑の向こうに見える樺太で、9人の電話交換手の乙女た
ちが、青酸カリによる服毒自殺を遂げました。
彼女らが最後に話した言葉。それが、この碑に書かれた「皆さん、これが最後です。さようなら
さようなら…。」
何故、そのような悲劇が起こってしまったのか…。
第二次大戦の終わり直前に、ソ連が日本に対して宣戦布告をしました。
そして、北方領土へと攻め入ってきました。
当時日本の領土だった、その土地に住んでいた日本人はそこから逃げ、また、あるものは虐殺されたり
しました。
そんな混乱の中、その情報を日本の本土に伝える仕事をしていた、電
話交換手の乙女たちは、その仕事を放棄するわけに
はいかなかったのです。
彼女たちは、最後までその業務を守ることを強制させられました。
そして、最後の時が訪れた時のために、彼女たちには青酸カリが手渡
されていました。
ここで、今の若い人たちには「電話交換手」という仕事が分からない方もいらっしゃるかもしれないので、
ここでお話しておきます。
電話交換手とは、電話の回線を取り次ぐ仕事のことです。
現在では、デジタル信号により自動で電話回線をつないでいますが、当時はその仕事を人間がしていた
のです。
電話をとると、まず、電話交換手の彼女たちが電話口に出ます。
その電話交換手の方に「何番につないで」とお願いすると、電話交換手の方が無数ともいえる差込口の
中からその番号を探して、ジャックを差し込み回線を
相手とつなげていたのです。
私が幼いころまでは、私の実家でもこの方法が使われていましたが、交換手さんがつなげているため、
今のようにいつでも電話がかけられるのではなく、深夜
などは電話をすることが出来ませんでした。
確か私の記憶では、夜の10時くらいから朝の5時くらいまでは電話できず、電話が始まる時間と終わる
時間には、電話機から音楽が流れてそれを知らせていた
と記憶しています。
そして、その電話からは、町内などの知らせ事も放送できるように、交換手さんから、直接各家庭の電話
機などに声をのせられるようにもなっていたのです。
今回お伝えする悲劇は、この機能を使って彼女たちが最後に言った
言葉だったのです。
彼女たちは、ソ連兵が電話交換所へと入ろうとしたときに、先に説明した電話機の機能を使って、「皆さ
ん、これが最後です。さようなら さようなら」と言い残
し、青酸カリによる服毒自殺を遂げたのです。
どうしてこのような悲劇が起こってしまったのか…。
国と国との政治的な争いの中で、彼女たちの様な犠牲者が出てしまったことはとても悲しいことと言わ
ざるを得ません。
この時、犠牲となったのは彼女たちだけではなく、最初にも述べましたように、多くの日本人も犠牲とな
っています。
更に、この悲劇が起こったすぐ後には、ソ連の潜水艦(Wikipediaでは「国籍不明」とありますが、小平町に
ある石碑には、はっきりと「ソ連籍」と書かれているの
で、このブログではそちらを採用します)による、樺太からの民間人引き上げ船の魚雷による撃沈、 「三
船殉難事件」も起こっています。
(上記事件については、回を改めてご紹介予定。)
これらの事件について私は思うのですが、何故人間は、戦争になると冷酷に人を殺すことが出来るので
しょうか?
そこには、時代が動く中で、政治的な都合により、人々が振り回され、あるいは、洗脳されてしまった結果
起こっているとしか思えないのです。
時代が変わってしまうと、「正義」と「悪」は簡単に入れ替わってしまいます。
これはとても怖いことだと思います。
私はロシアの人が大好きで、事実、ロシア人の友人もいます。
何故、日本とロシア、当時のソ連との間でこのような悲劇が起こってしまったのか…。
悔しいと同時に、今の平和な時代で生きていると、こんな悲劇が何故起こってしまったのか…。不思議にさ
え思えてしまいます。
私は、決して私のロシア人の友人とは戦いたくはありません…。
そこには、「乙女の碑」と言われる石碑が立てられています。
その碑には、今から75年前に起こった悲劇について記されているのです…。

75年前、この碑の向こうに見える樺太で、9人の電話交換手の乙女た
ちが、青酸カリによる服毒自殺を遂げました。
彼女らが最後に話した言葉。それが、この碑に書かれた「皆さん、これが最後です。さようなら
さようなら…。」
何故、そのような悲劇が起こってしまったのか…。
第二次大戦の終わり直前に、ソ連が日本に対して宣戦布告をしました。
そして、北方領土へと攻め入ってきました。
当時日本の領土だった、その土地に住んでいた日本人はそこから逃げ、また、あるものは虐殺されたり
しました。
そんな混乱の中、その情報を日本の本土に伝える仕事をしていた、電
話交換手の乙女たちは、その仕事を放棄するわけに
はいかなかったのです。
彼女たちは、最後までその業務を守ることを強制させられました。
そして、最後の時が訪れた時のために、彼女たちには青酸カリが手渡
されていました。
ここで、今の若い人たちには「電話交換手」という仕事が分からない方もいらっしゃるかもしれないので、
ここでお話しておきます。
電話交換手とは、電話の回線を取り次ぐ仕事のことです。
現在では、デジタル信号により自動で電話回線をつないでいますが、当時はその仕事を人間がしていた
のです。
電話をとると、まず、電話交換手の彼女たちが電話口に出ます。
その電話交換手の方に「何番につないで」とお願いすると、電話交換手の方が無数ともいえる差込口の
中からその番号を探して、ジャックを差し込み回線を
相手とつなげていたのです。
私が幼いころまでは、私の実家でもこの方法が使われていましたが、交換手さんがつなげているため、
今のようにいつでも電話がかけられるのではなく、深夜
などは電話をすることが出来ませんでした。
確か私の記憶では、夜の10時くらいから朝の5時くらいまでは電話できず、電話が始まる時間と終わる
時間には、電話機から音楽が流れてそれを知らせていた
と記憶しています。
そして、その電話からは、町内などの知らせ事も放送できるように、交換手さんから、直接各家庭の電話
機などに声をのせられるようにもなっていたのです。
今回お伝えする悲劇は、この機能を使って彼女たちが最後に言った
言葉だったのです。
彼女たちは、ソ連兵が電話交換所へと入ろうとしたときに、先に説明した電話機の機能を使って、「皆さ
ん、これが最後です。さようなら さようなら」と言い残
し、青酸カリによる服毒自殺を遂げたのです。
どうしてこのような悲劇が起こってしまったのか…。
国と国との政治的な争いの中で、彼女たちの様な犠牲者が出てしまったことはとても悲しいことと言わ
ざるを得ません。
この時、犠牲となったのは彼女たちだけではなく、最初にも述べましたように、多くの日本人も犠牲とな
っています。
更に、この悲劇が起こったすぐ後には、ソ連の潜水艦(Wikipediaでは「国籍不明」とありますが、小平町に
ある石碑には、はっきりと「ソ連籍」と書かれているの
で、このブログではそちらを採用します)による、樺太からの民間人引き上げ船の魚雷による撃沈、 「三
船殉難事件」も起こっています。
(上記事件については、回を改めてご紹介予定。)
これらの事件について私は思うのですが、何故人間は、戦争になると冷酷に人を殺すことが出来るので
しょうか?
そこには、時代が動く中で、政治的な都合により、人々が振り回され、あるいは、洗脳されてしまった結果
起こっているとしか思えないのです。
時代が変わってしまうと、「正義」と「悪」は簡単に入れ替わってしまいます。
これはとても怖いことだと思います。
私はロシアの人が大好きで、事実、ロシア人の友人もいます。
何故、日本とロシア、当時のソ連との間でこのような悲劇が起こってしまったのか…。
悔しいと同時に、今の平和な時代で生きていると、こんな悲劇が何故起こってしまったのか…。不思議にさ
え思えてしまいます。
私は、決して私のロシア人の友人とは戦いたくはありません…。