日本・ベルギー・英国 喫茶モエ営業中
Brugge Style
大阪の果物

ニューヨーク・タイムズの記事で、大阪が「今年行くべき52の場所」のひとつに選ばれている。「くいだおれ」の街として。
神戸出身のわたしは「大阪」といえば梅田しか知らない。
心斎橋も大阪出身の友達に誘われてよく遊びに行ったが、「知っている」と言えるほどの知識はない。
だから、大阪でとれる果物でできたジャムを頂いた時は心底驚いた。
イメージとしてはビルと看板の間で可憐に実をつける一本の木...
そんなはずはもちろんない。大阪でも農業は盛んだ。ジャムにできるほどの量の果物が採れるのだ。
神戸が兵庫県全体でないように、ロンドンが英国全体でないように、梅田も大阪全体ではないのだ。あたりまえだ。
しかし、ものごとに対するわたしの持つ、一瞬にして頭の中から取り出せるイメージというのは、ほんとうに限定的で短絡的なのだということが身にしみた。
英国といえば、ベネディクト・カンバーバッチのような青年紳士が「ダウントン・アビー」のような生活をしているというイメージから、わたしがどう話をしても抜けられない親友を笑えないわあ。まったく。
というわけで今回も話が長い。
この大阪の果物で作ったジャム、ほんとうーにおいしいの!
こっちでもこんな美味しいジャム、食べたことありません。
柚子もあったのだが、たまらず離乳食のようにそのままで食べてしまいました...
大阪で取れた果物、愛おしい。
「アルハンブラに降る雪(<実際降ったことがあるそう)」とか、そういう希少なイメージからどうしても抜けられないから(しつこい)かもしれない。
(「大阪府 農業」で検索すると、大阪府全域で農作物が収穫されていることが分かり、農家の求人だけでも1000件近くあった)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
giselle @ english national ballet

イングリッシュ・ナショナル・バレエで、古典の方の「ジゼル」を見た。
ジゼルは素晴らしきアリーナ・コジョカル(Alina Cojocaru)。
去年はアクラム・カーン(Akram Khan)がイングリッシュ・ナショナル・バレエのために新たに創作した、現代版「ジゼル」akram khan's giselleが、当バレエ団への一世一代の贈り物という風格で、またその作品の格に堂々と応えたバレエ団の方も凄みがあった(特に群舞が文句なく優れていた)。
そしてカーンの現代版に呼応するかのように、古典版を新年明けのスケジュールに持ってきたことにニヤっとしたのはわたしだけではあるまい。
古典の「ジゼル」、ストーリー的には素朴なこの話が語られるたびに、アダムの音楽の、あのテーマの部分がかかるだけで、胸の奥からこみ上げてくるのはなぜなのだろう。
もう数え切れないくらい鑑賞しているのに、同じ場面でぐっときて、言葉にならないものに感動するのだ。
アリーナ・コジョカルのジゼルは、2幕の精霊になったという設定で説得力を一段と発揮する。
乙女のまま死んで、男を森でとり殺す精霊になったジゼルは、生前に得意だった踊りで時間を稼いで、アルベリヒトを助けようとする。
許しと愛によって正気を保ち、夜明けの鐘とともにアルベリヒトが生き延びたことを確認した彼女は、おそらく成仏できた(天国に行った)だろう。彼女は森で毎夜さまよう必要はないのだ。
朝4時の鐘が鳴り、だんだん明るくなる森の中で、朝もやの中に次第と姿が薄れていく様の表現といったら!
アルベリヒトのアイザック・ヘルナンデス(Isaac Hernandez)もよかったし、精霊の女王ミルタ役のミカエラ・ドゥプリンス(Michaela DePrince)の峻厳さは文句無しにすばらしかった。
アルブレヒトの優柔不断さはなぜなのか、ジゼルに対する気持ちは本気だったのか...ジゼルが大人にしたアルブレヒトという男
(写真はballet.org.ukより)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
深夜のロンドン
昨夜、20時から食事をした。
レストランを出た時はすでに23時半を回っていた。
この時間帯になると、さすがのロンドンもかなり静かだ。
しかし、セヴィル・ロウまで来た車が突然全く動かなくなったので、運転手さん(Uberに乗っていたのです)に聞くと
「テムズ川で爆弾が2個発見されて、川沿いの道が封鎖されて大渋滞になっているらしい」
ということだった。
そんなニュース、全く知らなかった。
なるほど、さきほどから2人組の警官を何度も見かける。
全く動かなくなった車列を見て、こうなったら腹をくくって最終電車で帰ろうと夫が言う。
それで車を降りて、リージェント通りに出たら、クリスマスの飾り付けの大撤去中だった。
リージェント通り丸ごとと、そこに合流する道がすべて通行止にされ、クレーンや工事用のライトが何台も出ていて、まるでお祭りをしているような、その作業を見ていたいような騒ぎになっていた。
ガラガラの各駅停車で帰った。
車掌さんに「おはようございます!」と挨拶された。
(昨夜、Feraではラムに合わせてチョロギが出た。Japanese Crosnes。フレンチにはよく出てくる。美味だった!)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
マリー(クララ)の夢とモエの夢

もう一ヶ月近く前の話になるが、クリスマス直前、NYのリンカーン・センターでバランシン版「くるみ割り人形」を見たことを。
まずはチケットが高額なことに驚きを隠せず、自分が支払うでもないのに手をバタバタさせて興奮するモエ。
一番安い天井桟敷のような席でも79ドル、プラス手数料で100ドル近くだと記憶している。比べても意味はないが、ロイヤル・バレエの格安席の10倍。
娘にバタバタを抑制されたモーメントがあったことは思い出として書いておく。
実はバランシン版の「くるみ割り人形」はわたしの人生で最初に馴染んだバージョンだった。
というのはバレエの発表会でこの版を公演したからだ。
わたしは当時小学校6年生で、第一幕の男性お客様役だった。
雪のようなシルクのふんわりした袖とボウタイのブラウスに、濃い紫のベルベットの膝丈半ズボン。
母は「宝塚の男役みたいですてきじゃない」と言ったが、夢見る少女だったわたしはカラフルなロマンティック・チュチュを着たくてたまらず、女役の子のチュチュを恨めしげに優しく撫でさすったのだった。
バランシン版は子供のための子供による「くるみ割り人形」というのが一番ふさわしい。
ドロッセルマイヤーさんの役目は、
ドロッセルマイヤーさんが自分の欲望を満たすために一芝居打つロイヤル・バレエのウェイト版(クララの夢)ロイヤル・バレエのウェイト版よりも、
魔法使いのやさしいおじさんとして登場し、夢の中で人形劇をしてくれるイーリング版(クララの別の夢)よりもさらにあっさりしている。
バランシン版では、マリー(クララではなくマリー)は小さな少女で、あるクリスマスの夜、すてきな夢を見る。
クリスマス会に招待されたドロッセルマイヤーさんの、マリー自身と同い年くらいの息子に淡い恋心を抱く。その夜の夢で、くるみ割り人形にされた彼をねずみ王との戦いの最中に助け、共にお菓子の国に旅し、彼女のためにお菓子の精たちがダンスの宴を開いてくれるのである。
マリー(クララ)の役も、
ウェイト版では彼女はドロッセルマイヤーに選ばれしハイティーンで、夢の国に旅してシュガー・プラムの精に会う。
イーリング版ではより若い少女(ローティーン?)で、夢の中では憧れのお姉さんのように成長し、彼女自身がシュガープラムの精に変身する。
バランシン版はさらに小さな少女が夢の中を旅し、シュガー・プラムの精に会う。
バランシン版で、小さな少女が真っ白で綺麗なベッドに横たわり、夢の国へ旅していくシーンは最も自然で、ロイヤル・バレエのようなまどろっこしい説明がなくても、ドロッセルマイヤーさんがほんとうの魔法使いでなくても、「くるみ割り人形」のクリスマスの「夢」のエッセンスはここまで表現ができるという良い見本であるように感じた。
ただ、全体的にバレエというよりもどちらかというとお芝居色が濃い。
おそらく、普段バレエを鑑賞しないような層も鑑賞に来るのが、クリスマスの風物詩としてのアメリカの「くるみ割り人形」なのだろうと思う。すてきなことだ。
消化不良だったのは、シュガー・プラムの精のグラン・パ・ド・ドゥが短縮されていることか。あれは決して省略可能なパ・ド・ドゥではないはずだ。この世のものではない国の、光輝く美しき妖精の女王、シュガー・プラムの精の踊りで夢は最高潮を迎え、その後、クリスマスの朝の静かな目覚めにつながるのに...
さらに悪いことにわたしが見た夜のシュガー・プラム役のダンサーも、彼女のパートナーも完全に力不足だった。
オーケストラにもがっかりだった。
もし、「子供のためのショウでしょ?」という手抜きがあったなら非常に残念だ。
一方で、大勢出演している子供ダンサーの訓練された踊りと存在感には舌を巻いたが。
NYの華やかなクリスマス前の雰囲気はとことん楽しんだ。
激混みのリンカーン・センター前でキャブを拾って(<拾うのめっちゃ得意)、人を待たせていたグラマシー・タバーンに駆けつけて遅いディナーをいただいたのも雰囲気たっぷりだった。
偶然隣の席に座った家族連れが、着席するなり「あなたがた、今夜「くるみ割り人形」見に来てたわよね?」と声をかけてくれたのには驚いた。まるで小さい魔法のようだった。
(写真はThe New Yorkerより)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
picasso portraits
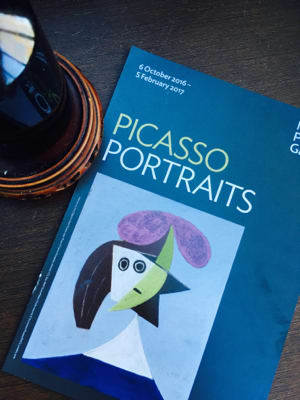 ナショナル・ポートレイト・ギャラリーのピカソ展に2回目の見学に行ってきた。
ナショナル・ポートレイト・ギャラリーのピカソ展に2回目の見学に行ってきた。前回の見学時、18時頃に夫から電話がかかって来た。
家周辺が大吹雪のため、早めに帰ってきた方がいいかもしれないと言うのだ(ちなみにこの冬初めての降雪)。
ロンドンはその時大雨だった。
ちょっとでも雪が降るとなぜか交通が麻痺するサリー州なので、展示物の最後の3枚ほどはじっくり見ずに、アタフタ帰途に着いたら雪はすでに止んでいたというオチだったのだ。
それで落ち着いて2度目の見学へ。
ナショナル・ポートレイト・ギャラリーはほんとうにいい展覧会をする。
ピカソが分からない、良さが分からない、誰にでも描けそう...と思う向きには特におすすめ。
めまぐるしく作風が変化する、しかも超多作の彼の、ティーンだったころの自画像に始まり、パリで得た友人たちのカリカチュア、バラ色の時代、なぜキュビズムを採用したか、新古典主義からシュルレアリズム...作風の変化を「人の顔」を軸にすっきり俯瞰することができる。
カリカチュアを得意とした彼の(そういえば彼は「肖像画は多かれ少なかれカリカチュア成分を含んでいる」と言ってましたね...)真骨頂。
「ピカソはまず女を犯し、それから絵を描くのです」と言った、マリー・テレーズ・ヴァルテルの含蓄や、「未知なるものへの敵意」「破壊こそが創造である」「分からないという感情に耐えることができない」といったピカソの言葉がストレートによく分かる...少なくとも分かるような気がする...
デッサンの超絶的うまさ
人たらし
ビジネスの機を読む能力
要領の良さ
自己演出力
独創性
すべて超一級ですわ
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |




