墨の料理酒 高い富士。
角倉了以朱印船貿易 高瀬川(たかせがわ)・富士川)
[ポイント]
1.角倉了以は、富士川・高瀬川を開削して舟運(しゅううん)を開いた。
[解説]
角倉了以(1554~1614)は、京都出身の初期豪商の一人で、朱印船貿易と河川土木事業に活躍した。まず幕府の許可を得て、保津川下流の大堰(おおい)川の開削に成功。これによって、丹波の山奥からの物資搬送を可能にした。続いて富士川、天竜川の通船工事に成功。もっとも著名なものは晩年の高瀬川開削。京都から細い運河高瀬川を掘って淀川へつなぎ、大坂までの水運を飛躍的に発展させた。いずれも巨額の私財を投入しているが、通船料による収益を独占することで莫大な利益を上げた。
〈2016明大・情報〉
問1 下線部ア)17世紀後半の時期の説明として、もっとも正しいものを、つぎの1~4のうちから1つ選べ。
1.幕府は、糸割符制度を設けて、貿易統制を始めた
2.上方を拠点とする井原西鶴が『好色一代男』を刊行した
3.角倉了以は西廻り航路を整備し、北前船が就航しはじめた
4.江戸の山東京伝が『仕懸文庫』を著した」
(答:2 ※1×糸割符制度(1604)、3×角倉了以→河村瑞賢、4×山東京伝(1761~1816))〉
〈2016上智大・法(地球)済(営)総人(社福)
問3 次の文章は、都市と町衆について説明したものである。文中の空欄(ア~オ)に入る適切な語句をあとの語群から1つずつ選びなさい。
都市のなかには、富裕な商工業者である町衆を中心とした自治的団体である町が生まれた。町はそれぞれ独自の町法を定め、住民の生活や営業活動を守った。京都でも、有徳人などとよばれた金融業者の( ア )や酒屋などの商人が中心になって町衆の文化が育った。町が集まって町組という組織がつくられ、さらに複数の町組が集まって、公家・武家が多い上京と商工業者の町である下京という大きな惣町が形成され、上京と下京は( イ )通りでむすばれていた。町組は、町衆のなかから選ばれた( ウ )によって自治的に運営され、応仁の乱で荒廃した京都は、これらの町衆によって復興され、御霊会として行われていた( エ )祭も、町衆たちの祭として再興された。その経済力は近世にも衰えることはなく、嵯峨の( ア )出身で、朱印船貿易に従事し、水路の開発にも貢献した( オ )や、幕府の呉服を扱い朱印船貿易でも活躍した茶屋四郎次郎などが出た。」
(答:ア土倉、イ室町、ウ月行事、エ祇園、オ角倉了以 ※原問題には30項の選択肢あり)〉
〈2015大学入試センター
問2(中略)近世の西日本の流通に関して述べた次の文X・Yと、それに該当する人名a~dとの組合せとして正しいものを、下の1~4のうちから1つ選べ。
X 大坂と東北地方とを結ぶ、西廻り航路(海運)を整備した。
Y 高瀬川の開削を行い、内陸部の河川舟運の発達に寄与した。
a河村瑞賢 b紀伊国屋文左衛門
c田中勝介 d角倉了以
1.X-a、Y-c 2.X-a、Y-d
3.X-b、Y-c 4.X-b、Y-d」
(答:2)〉
〈2014早大・国際教養
問10 下線部gの人物角倉了以について、正しい説明はどれか。すべて選べ。
ア 幕府の呉服師を務めた。
イ 朱印船を派遣した。
ウ 西廻り航路・東廻り航路を開通させた。
エ 菱垣廻船を就航させた。
オ 高瀬川・保津川などの水路を開削した。」
(答:イ・オ)〉
〈2014明大・国際日本(国際日本)
問7.農産物の全国的な流通が盛んになっていく条件として、交通網の発達は不可欠であった。江戸時代の交通網の発達について述べた以下の文章A~Cについて、その正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1~4の中から選びなさい。
A:東海道、中山道、山陽道、甲州道中、奥州道中の五街道は、重要な幹線道路として幕府の直轄下に置かれ、17世紀半ばから道中奉行によって管理された。
B:五街道や脇街道などの主要な街道には宿駅が多く置かれ、流通の要所となった。宿駅には、本陣、旅籠、問屋場などが設けられた。
C:大坂・江戸間では菱垣廻船、樽廻船が運航するようになり、17世紀後半には江戸の商人だった角倉了以によって東廻り海運・西廻り海運が整備された。
1.A〇、B×、C〇
2.A×、B× C×
3.A〇、B〇、C×
4.A×、B〇、C×」
(答:4 ※A×山陽道→日光道中、C×:角倉了以→河村瑞賢)〉
〈2014立大・現代心理(映像身体)・社会・コミュ福祉(福祉)
江戸時代には水上交通もいちじるしい発達をとげた。大量の物資を安価に運ぶには、陸路よりも海、河川、湖沼などを利用した水上交通の方が適していた。瀬戸内海は物資や旅行者に多く利用されたが、江戸~大坂間をはじめ廻船による貨物の運搬は盛んで河川・湖沼も運行の可能なかぎりは利用された。( リ )は富士川や高瀬川などを開墾し、河川舟運をひらいた。海上交通では、17世紀前半から菱垣廻船が運行を開始し、その後樽廻船の運行も始まった。」
(答:リ角倉了以)〉
〈2012立大・全学部
また、〈 く 〉による富士川や高瀬川の開削などは、内陸部の物資を舟運によって河口に運び出すことを可能とし」
(答:く角倉了以)〉
〈2012同志社大学・文経済
問キ.角倉了以が大堰川を開削して発達した、丹波より京都への輸送水路を何と呼ぶか、次の1~4の中から選べ。
1.高瀬川水運 2.淀川水運
3.保津川水運 4.富士川水運
(答:1※「た」)〉
〈2011近畿大・法済営
問5 下線部b角倉家に関連して、角倉了以についての文として適当でないものはどれか。次のうち一つを選べ。
1 朱印船貿易をおこなった初期豪商であった。
2 樽廻船の航路を整備した。
3 高瀬川の開削をおこなった。
4 富士川の開削をおこなった。
(答:2)
















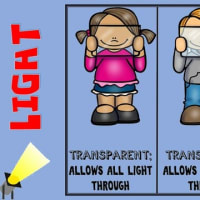


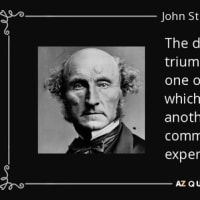






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます