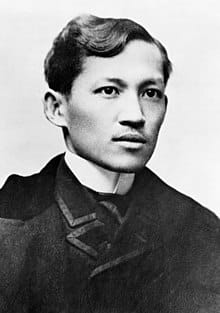2023年1月4日(火)
12月に入った頃からえらく明るいのに気づいていたが、やはり接近していたのだ。
〈2022年12月1日、約2年2か月ぶりに火星と地球が最接近します。約8100万kmまで近づきます。2022年9月から2023年3月ごろまで明るく見えます。冬の星々と競うように赤く輝く光景は見ものです。おうし座の中を動きまわる様子も楽しめます。〉
両惑星間の距離にどのくらいの振れ幅があるかと調べて驚いた。6千万km弱から3億km近くまで振れるのだ。もっとも、これは驚く方が少々まぬけである。太陽との平均距離は地球が約1億5千万km、火星が2億3千万km、太陽の同じ側にあるか反対側にあるかだけでも、そのぐらいの振れは生じるだろう。古代人にはさぞや大きな謎だったろうが、太陽系の構造を教わってしまえばあたりまえのことである。
2018年の下記のサイトがわかりやすい。地心における火星の視直径/惑星間距離は、同年1月1日に4.8"/2億9,307万kmだったが、8月1日には24.3"/5,759万kmまで拡大/接近した。8,100万kmなら16"台だろうか、明るいのも道理である。あたりまえなどと書いたが、7つの惑星(降格された冥王星は除き)の中で火星だけが目に見えて大きさを変えるのは、外惑星であってしかも地球に近いという条件を備えているからである。そのことに想到するのにしばらく時間がかかった。
冬の星空は美しいが、何しろ寒い。東京では地上の照明に妨げられて興も劣り、じっと見あげることが最近は減った。火星の大きさに気づいたのは、日没後に帰宅して東向きに歩く道で、昇ってくる満月の近くに見えたおかげである。
月を見るのはいつでも楽しい。日ごとに形と大きさを変え、形とともに太陽との相対的な位置がずれていってはぐるりと戻る、それを見あげて日を数え、満ち欠けを楽しむうちに人生はあっけなく過ぎていきそうだ。
月は太陽の光を反射して光る、そのことが多くを考えさせる。月が太陽の近くにある限り、その姿はまことに細く頼りない。光源から離れるほどに反射は強まり空に見える時間が伸びていき、ついには地球をはさんで真向かいに対面する。このとき日没と入れ違いに昇ってくる十五日の月は、女王のように煌々と地を隈なく照らす。人もまた、力を授かる源から十分離れることによってこそ、はじめて充分に輝くことができるのではないか。裏切りではない、真の応答として。
しかし満月は続かない。再び光源に近づくにつれ逆の側から細っていき、光源の中に姿を消す。姿を消してはまた現れる。その様を人工の建物と照明に妨げられることなく、晴れた空に昼も夜も追うことができるのが、田舎の暮らしの楽しさである。
ふと思い立ってブランケットを肩に巻き、夜の庭に出てみた。高く昇った十二日の月のすぐ隣で、火星が冬の大三角と肩をぶつけている。ベテルギウスの赤は大きくなった火星の前に顔色ないが、シリウスの煌めきはひるむことなく青く美しい。それより明るい木星が、西の空で火星に挑み返すようだ。土星はどこにと探そうとして、早くも体の芯が震えはじめた。
またあした。
Ω