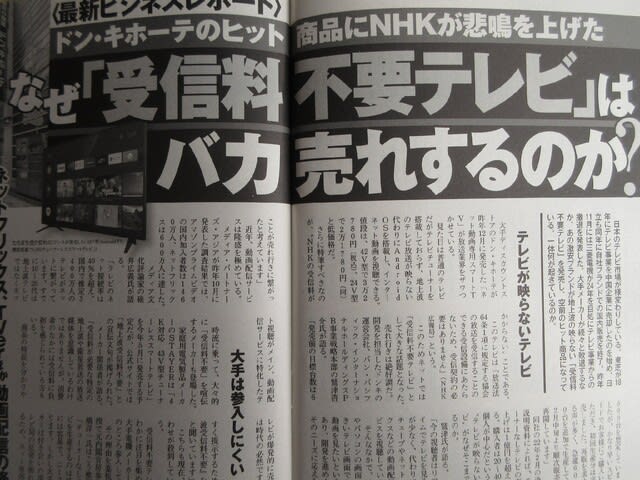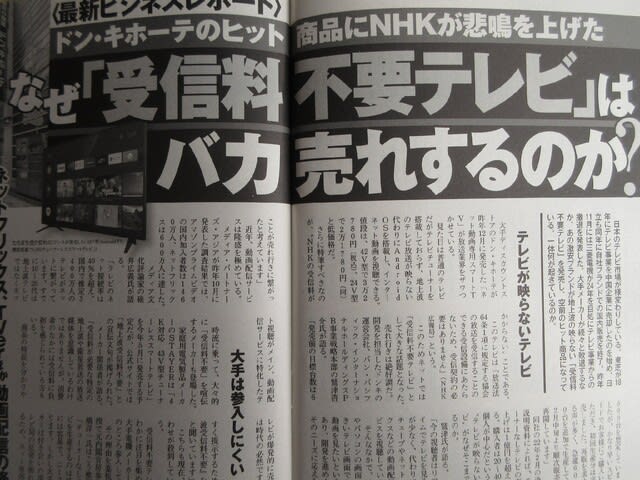
なぜ「受信料不要テレビ」は
バカ売れするのか?
大手ディスカウントストアのドン・キホーテが昨年12月に発売した「ネット動画専用スマートTV」が放送業界をザワつかせている。
見た目は普通のテレビだがテレビチューナーを搭載しておらず、地上波のテレビ放送が映らない代わりにAndroid OSを搭載し、インターネット動画を視聴できる。値段は、42V型で3万2780円(税込)、24V型で2万1780円(同)と低価格だ。
さらに特筆すべきなのが、“NHKの受信料がかからない”ことである。このテレビは「放送法64条1項に規定する協会の放送を受信することのできる受信設備にあたらないため、受信契約の必要はありません」(NHK広報局)という。
このためネットでは「受信料不要テレビ」として大きな話題となった。
売れ行きは絶好調だ。開発を担当したドンキの運営会社、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスPB事業戦略本部の鷲津啓介氏が語る。
「発売前の目標台数は6000台を想定していましたが、かなり早いスピードでお客様にご購入いただき、初回生産分は完売しました。再販を求める声が多く、急遽6000台を追加で生産して、2月中旬より順次販売を再開しています」
同社の2022年2月の決算説明資料によれば、チューナーなしテレビの売り上げは1億円を超えている。購入者は20~40代の個人が中心だというが、“テレビが映らないテレビ”がなぜそこまで売れるのか。鷲津氏が語る。
「今の視聴者はリアルタイムでテレビを見る時間が少なく、代わりにYouTueやNetflixなどの動画配信サービスを視聴しています。そんななかで、スマホやパソコンの画面より大きいテレビ画面でネット動画を見たいという声があり、開発を進めました。そのニーズに応えられたことが売れ行きに繋がったと考えています」
近年、動画配信サービスは隆盛を極めている。メディア・パートナーズ・アジアが昨年10月に発表した調査結果では、アマゾンプライムビデオの国内加入者数は1460万人、Netflixは600万人に達した。
メディア文化評論家の碓井広義氏が語る。
「テレビのネット接続率は40%を超え、国内で推定3400万人のテレビがネットに繋がっています。すでに10~20代は地上波テレビではなくネット視聴がメイン。動画配信サービスに特化したテレビが爆発的に売れるのは時代の必然です」
時流に乗って、大々的に「受信料不要」を喧伝するメーカーも登場した。
家庭用電気製品メーカーのSTAYERは「4K対応 43V型チューナーレススマートテレビ」を今年5月に発売する予定だが、公式サイトでは「地上波受信料不要」との宣伝文句が掲げられた。メーカー関係者が語る。
「受信料が必要な特定の地上波や衛星放送の放送媒体を意識しているわけではありませんが、消費者のなかには受信料に負担を感じられている方もいる。商品の特長を分かりやすく提示するため『地上波受信料不要』を謳ったと聞いています」
こちらも現在、問い合わせが殺到しているという。
受信料不要テレビがにわかに注目を集めるなか、大手電機メーカーは、今のところ参入していない。その理由を嘉悦大学教授で元内閣官房参与の高橋洋一氏はこう推測する。
「チューナーなしのテレビを生産するのは技術的には容易で、ニーズもあります。しかし大手メーカーは付き合いの深いテレビ局の反発を怖れているため、ネット専用テレビの製造に消極的なのでしょう。その間隙を縫って、ドン・キホーテが話題性のある商品を仕掛けてきたわけです」
********
このテレビは「放送法64条1項に規定する協会の放送を受信することのできる受信設備にあたらないため、受信契約の必要はありません」(NHK広報局)という。そんな「受信料不要テレビ」の台頭もあり、NHKも岐路に立たされている。
先手を打ったのがケーブルテレビや衛星放送だ。
J:COMはNetflixとケーブルテレビをセットにしたコースを2020年に開始。WOWOWやスカパーJSATは昨年から、衛星放送の加入契約がない視聴者にも動画配信サービスを提供し、番組をスマホやパソコンで視聴しやすくした。
一方で後れを取ったのが民放である。嘉悦大学教授で元内閣官房参与の高橋洋一氏が語る。
「世界各国のテレビ局がネット配信を進めるなか、日本の民放は消極的です。これはキー局がネット配信をすると、キー局の番組を放送する地方局のコンテンツ力が低下するからで、キー局と地方局の縦の関係がネット配信を阻んでいます。
逆に言えば、テレビ局がネット配信をしないのでNetflixなどの動画配信サービスがどんどん伸びていった。受信料不要テレビの台頭に拍車をかけたのは、民放の消極的な姿勢です」
ここにきて、民放もようやく重い腰を上げ始めている。
今年4月からは、見逃した番組をネットで見られる配信サービス「TVer」で、テレビ番組を放送と同時にインターネットでも見られる「同時配信」を、既に始めている日本テレビ以外の民放4局も開始すると発表した。
「NHKは同時配信に向けて積極的に動いていましたが、民放は民業圧迫として、ネット配信の足を引っ張ってきた。しかし、『この番組はネットでもやっています』が逆転して、『この番組はテレビでもやっています』という時代が来るのは明白です。最近になってネットに対応しないと生き残れないことを各局がようやく理解し、ネット配信にも目を向けるようになりましたが、まだまだスピード感に欠けます」(メディア文化評論家の碓井広義氏)
(週刊ポスト 2022年3月11日号)