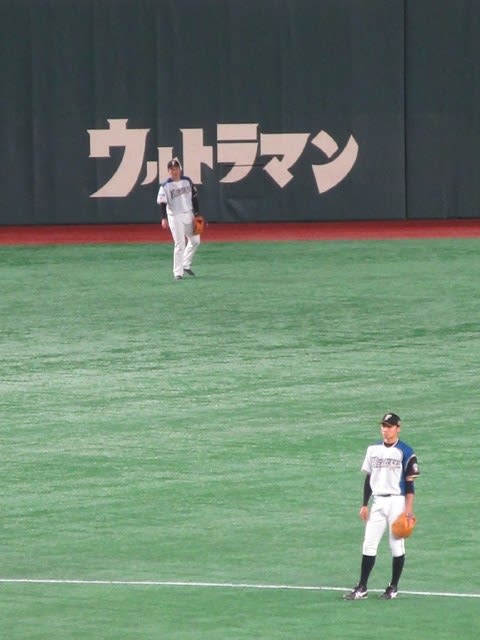他の女優では成立せず
石原さとみ「Heaven?」のハマり具合
スタートが早かったこともあり、石原さとみ主演「Heaven?~ご苦楽レストラン~」が今週、最終回を迎える。
舞台は「ロワン・ディシー(この世の果て)」という名のフレンチレストラン。オーナーの黒須仮名子(石原)が、客のためではなく、自分が食べたい時に、食べたいものを、食べたいように食べるために始めた店だ。スタッフも、上級ウエーターの伊賀(福士蒼汰)をはじめ、訳アリぞろい。わがままなオーナーに振り回されながらも、何とか店をつぶさないよう奮闘している。というか、その振り回され具合を楽しむコメディーなのだ。
何より石原のプチ女王様ぶりが笑える。しかも、ひたすら自身の欲望に忠実な一方で、時にサービスやコミュニケーションの核心に触れる言動が飛び出すから侮れない。特に「距離感」は、このドラマのキーワードだ。
佐々木倫子の原作漫画の連載開始は1999年。ドラマ化すると聞いた時、「随分古い作品を選んだなあ」と思ったが、何かしら現代性を加味するだろうと予測した。しかし始まってみれば、アッパレなほど、いつの時代のドラマか分からない。
とはいえ、20年前の石原さとみは12歳だ。彼女が黒須仮名子を演じるために、20年という歳月が必要だった! というのはオーバーだが、他の女優では成立しなかった。そんな「石原ドラマ」もついに閉店、いや大団円だ。
(日刊ゲンダイ 2019.09.11)
週刊新潮に、以下の書評を寄稿しました。
著者の運命を左右した ある雑誌との邂逅
鏡 明:著
『ずっとこの雑誌のことを書こうと思っていた』
フリースタイル 2,376円
著者がずっと書こうと思っていた「この雑誌」とは、「マンハント」のことだ。創刊は1958年。東京オリンピックがあった64年に終刊となっている。「読んだことがある人、手を挙げて!」と叫んでみても、多分そんなにはいないはずだ。当時、ハードボイルド・ミステリに特化した同名雑誌がアメリカにあり、いわばその日本版。つまり、相当マニアックな雑誌だったのだ。
すると今度は、「見たことも読んだこともない雑誌について書かれた本なんてパスだ」と考える人が出てくるだろう。当然ではあるけれど、それはもったいない。著者は「ミステリ雑誌」という観点からこの雑誌を語っているわけではないからだ。
まず、「マンハント」と出会って、自分がいかに触発されたか。次に、そのバックナンバーを集めるプロセスで、どんな活字文化を体験してきたか。そして、この雑誌を起点として玉突きのように広がっていった世界と自身の関係を振り返っている。実際、「マンハント」がなかったら、作家、翻訳家、評論家、さらに優秀な広告人でもある著者のキャリアはなかったかもしれないのだ。
本書には、「マンハント」に関連して嬉しい名前が続々と出てくる。植草甚一、片岡義男(当時はテディ片岡)、小鷹信光などだ。いずれも著者が愛読した連載コラムの執筆者たちである。小鷹へのインタビューでは、「マンハント」で展開されていた、自由過ぎる翻訳をめぐる話が興味深い。それはポジティブな“いい加減さ”であり、面白く読ませるための“型崩し”であり、後に訳者から何人もの作家が誕生したことを思うと、原文を素材とした“創作的翻訳”だったとさえ言えそうだ。
それにしても、この雑誌が今の自分のベースを作ってくれたと言える著者は、なんと幸せなことか。いや、逆かもしれない。雑誌には人の運命を左右する力がある。そのことを実感させてくれるのが本書だ。
(週刊新潮 2019年8月29日秋初月増大号)
「凪のお暇」
空気を読むことに疲れた主人公
劇作家・鴻上尚史さんの近著のタイトルは、『「空気」を読んでも従わない』だ。周囲に同調しようと息苦しい思いをしている人に、空気をわかった上で無理に従う必要はないとアドバイスしている。ドラマ「凪のお暇(いとま)」(TBS-HBC)のヒロイン、大島凪(黒木華)にも、ぜひ読んでもらいたい一冊だ。
凪は28歳の無職。会社を辞めたのは周囲の人たちとのコミュニケーションがうまくいかなかったからだ。一見普通に接しているのだが、本当は摩擦が起きないよう、仲間外れにされないよう、常に「空気」を読むことに必死だった。
職場の女子たちとのランチでも、本当は静かに一人で食べたいのに、そんなことは言えない。話題になる旅行やアクセサリーについても、その場にいるメンバーの顔色をうかがいながら無難な話を探した。
また、同僚から仕事上のミスの責任を押し付けられても、本当のことを言ってその場の「空気」を悪くするのが嫌で、文句が言えなかった。凪は、日常的に「自分でない自分」を演じることに疲れてしまったのだ。
そして、もう一つ。凪が生活を丸ごと変えようと思った理由が恋愛問題だ。同じ会社の優秀な営業マン、我聞慎二(高橋一生)とつき合っていたが、彼にとって自分が単なる「都合のいい女」であることが判明。恋人の前でも「空気」を読むことに腐心していた自分に気づいた凪は、我聞との関係も断つ。つまり、会社からも恋人からも「お暇」頂戴だ。
郊外のボロアパートに引っ越した凪。仕事も、貯金も、家財道具もないが、嬉しい出会いがあった。隣の部屋に住む、クラブDJなどをしているゴン(中村倫也)だ。一種の自由人で、誰にでも優しく、一緒にいると凪の心も晴れ晴れとしてくる。普通なら、ここから新たな恋物語が始まるところだが、そうならないところがこのドラマらしさだ。
実は、これまでゴンに夢中になった女性たちは、自分だけのものにならないゴンに苛立ち、ことごとく自壊していたのだ。しかも、そんなゴンが凪を本気で好きになる。遅すぎる初恋だ。そして、我聞の「本心」も徐々に明らかになってきた。「空気」を読む達人を自認する我聞は本当の気持ちを表すことが苦手で、凪に対しても正直になれなかったのだ。
見ている側が思い込んでいた登場人物たちのキャラクターが、物語の進展に従って大きく変容していく面白さ。ゴンと我聞と凪の奇妙な三角関係の行方と、「素の自分」で生きることを始めた28歳無職に注目だ。
(北海道新聞「碓井広義の放送時評」 2019.09.07)
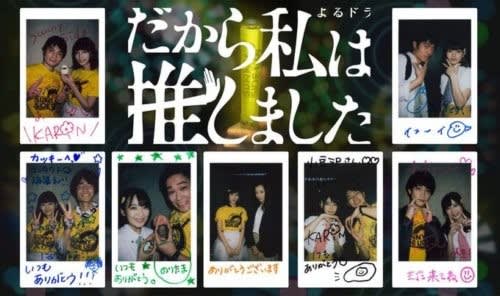
NHK『だから私は推しました』が描く
「地下アイドルのリアル」
『あまちゃん』もアイドル物語だった
よるドラマ『だから私は推しました』(NHK 全8話)が最終章に突入した。地下アイドルと、それを応援するアラサー女子の物語だが、当初の予想をいい意味で裏切る展開に目が離せない。
そもそも、「アイドル」を描くドラマ自体がそう多くはない。ましてや、“お堅い”はずのNHKが扱うテーマとしては異色だと思う人も少なくないだろう。
NHKとアイドルドラマの関係を考える時、忘れてはならない作品がある。それが『あまちゃん』だ。
アイドル物語としての名作『あまちゃん』
歴代のNHK朝ドラには、いくつかの共通点がある。まず、主人公が女性であることだ。いわゆる「一代記」の形をとったものが多い。作品によっては、その生涯を年齢の異なる複数の女優がリレー形式で演じることもある。
次に、多くの朝ドラが、女性の自立を描く「職業ドラマ」という側面をもっている。全体的には、生真面目なヒロインの「成長物語」という内容が一般的だ。
『あまちゃん』における、物語の時間設定は2008年から2012年までである。放送された2013年と地続きの4年間であり、主な舞台は2011年の震災と津波で被害を受けた東北だった。
ドラマとはいえ、現実の場所と出来事をどう取り込むか、脚本作りは難しかったと推測されるが、脚本を書いた宮藤官九郎は、結果的にこのドラマを笑いとユーモアに満ちた「アイドル物語」に仕立て上げた。それが宮藤の最大の功績だ。
過去のヒロインたちが目指した法律家(『ひまわり』1996)、看護師(『ちゅらさん』2001)、編集者(『ウエルかめ』2009)などとは明らかに異質な、朝ドラから最も遠いと思われる職業、それがアイドルである。
しかし、アイドルを「人を元気にする仕事」と定義付ければ、納得がいくのではないだろうか。主人公が、震災後、被災地となった北三陸の人々を元気づける「地元アイドル」になる、というアイデアは秀逸だった。
「人を元気にする」のがアイドルの仕事
このドラマの中では、2008年の夏に、ヒロインのアキこと天野秋(演じたのは能年玲奈、現在は「のん」)は、24年ぶりに帰郷する母・春子(小泉今日子)に連れられて、過疎地域である北三陸へとやって来た。祖母・夏(宮本信子)が住む春子の実家で、高校2年の夏休みを過ごすためだ。
この時、春子には思惑があった。一つは、地味で暗い性格であり、学校でも軽いいじめを受けていたアキを、違った環境に置いてみたかったこと。もう一つは、夫である黒川正宗(尾美としのり)の神経質な性格が我慢できず、離婚を決意していたことである。
春子の母・夏(宮本信子)は海女であり、かつて春子を跡継ぎにしようとして拒否された経緯がある。アキは偶然海に飛び込んだことで海女に興味を持ち、その見習いとなった。
北三陸の観光協会や北三陸鉄道の人たちは、過疎化対策、また地域振興を目的に、「ミス北鉄」コンテストを実施する。ミスに選ばれたのは地元で評判の美少女・ユイ(橋本愛)だ。このユイと海女のアキが、地元アイドル「潮騒のメモリーズ」を結成する。
2人が北鉄でウニ丼を売ったり、お座敷列車で歌ったりする活動はネットで流され、全国からファンが集まってくる。その人気に火がつくきっかけが、観光協会のサイトに置かれた2人の「動画」だという筋立ては、極めて現代的かつリアルなものだった。
またこのドラマでは、アキたち地元アイドルを軸に、大人たちが「町おこし」や「地域活性化」を図ろうとする展開の中で、全国各地の市町村が実際に抱えている諸問題を浮き彫りにしていた。地域の過疎化、住民の高齢化、シャッター商店街、若者の雇用問題などだ。
こうした社会的テーマや課題を、朝ドラが取り込んでいること自体が当時は珍しいことであり、挑戦的な試みだったのだ。
ドラマとして可視化された「アイドルビジネス」
アキとユイは、本格的アイドルを目指して上京することを決める。ところが直前になってユイの父親が倒れ、アキは1人で東京へ行き、アイドルユニット「GMT47」に入る。
「AKB48」のAKBが「秋葉原」の略であるように、このGMTは「地元(じもと)」の意味である。プロデューサーの荒巻太一(古田新太、怪演!)が全国の都道府県から1人ずつ地元アイドルを集め、グループアイドルとして売り出そうとしていたのだ。しかし、まだ47人は揃っておらず、現状はアキを入れて6人のユニット「GMT6」だった。
ちなにみに、このGMT6のメンバーの一人、埼玉出身の入間しおりを演じて強い印象を残したのが、松岡茉優だ。
GMT6は、すでに稼働していた「アメ横女学園(以下、アメ女)」の下位に置かれるグループだった。このアメ女の設定によって、『あまちゃん』は、いわゆる「アイドルビジネス」の仕組みを視聴者に見せていくことになる。
朝ドラはもちろん、民放のドラマでも触れられることのなかった領域だ。『あまちゃん』における“現実の取り込み”の一つである。
「グループアイドル」というシステム
アメ女のモデルは、明らかに実在の人気アイドルグループであるAKB48だ。ドラマの中で行われるアメ女に関する説明は、ほぼAKB48に準ずると考えていい。
まず、アメ女は上野に専用の劇場「東京EDOシアター」を持っている。これは秋葉原の「AKB48劇場」と同じスタイルであり、「会いに行けるアイドル」はアメ女にとっても重要なコンセプトだ。
次が階級制度である。アメ女のメンバーは、センターを頂点とする人気の順に「レギュラー」「リザーブ」「ビヨンド」「ビンテージ(卒業したOG)」と分けられていた。GMT6のメンバーはその下に位置するシャドー(代役)である。こうしたピラミッド型のヒエラルキーも、そのままAKB48にも当てはまる。
また、プロデューサーの荒巻(古田)は、このピラミッドに並ぶメンバーの入れ替えを、「国民投票」という名のファン投票によって実施する。これはAKB48における「選抜総選挙」に相当するものだ。選ばれた上位陣が新しいシングル曲に参加できるシステムもAKB48と変わらない。
注目すべきは、こうした「階級制」や「選抜制」の仕組みを『あまちゃん』の中で描くこと自体が、秋元康プロデューサーがAKBグループで展開してきたリアルな「アイドルビジネス」に対する、秀逸な「批評」となっていたことだ。これもまた、過去のドラマにはない果敢な挑戦だった。
「地下アイドル」の世界を描く『だから私は推しました』
放送中のNHKよるドラ『だから私は推しました』は、一人の地下アイドルと、彼女を推す(特定のアイドルを熱烈に応援する)ドルオタ(アイドルオタク)女子の物語だ。
主人公の遠藤愛(桜井ユキ)は一見どこにでもいそうなOLさん。最近失恋したのだが、原因のひとつは、SNSでの自己アピールに夢中で、常に「いいね!」を熱望する、その過剰な承認欲求だった。
スマホを落としたことをきっかけに、偶然入った小さなライブハウスで、初めて「地下アイドル」なるものに遭遇する。
一方の栗本ハナ(白石聖)は、地下アイドルグループ「サニーサイドアップ」のメンバー。ただし、歌もダンスも不得意な上に、コミュ障気味という困ったアイドルだ。そんなハナを見て、愛は思う。「この子、まるで私だ」と。それ以来、ハナを全力で応援する日々が始まる。
まず、このドラマで描かれる「地下アイドルの世界」が興味深い。ライブの雰囲気、終演後の物販、厄介なファンの存在、アイドルたちの経済事情などが、かなりリアルなのだ。
「地上アイドル」と「地下アイドル」
前述のAKB48やアメ横女学園が「地上」のアイドルだとすれば、「地下」の最大の特色は、アイドルとファンの「距離感」ではないだろうか。
普通、地下アイドルの公演は、武道館や東京ドームなどの大会場で行われたりしない。ほとんどは、それこそ地下にある小さなライブハウスだったりする。キャパが小さい分、アイドルとの物理的距離が近いのだ。
近いからこそ、自分の応援は「推し(応援しているアイドル)」が認識してくれるし、応援に対してアイドルからの「レス(ファン個人への反応)」が来たりもする。応援とレスの相互作用は、地下アイドルの世界ならではの醍醐味だ。
まだ楽曲も売れていないし、有名ではないし、パフォーマンスも稚拙だったりするが、そういうことさえ、地下アイドルファンには応援する動機となる。また、ファンもたくさんはいないので、「物販」と呼ばれる、ライブ後のグッズ販売やサインや握手を通じて、本人と、かなり密接なコミュニケーションが可能となる。
そんな状況が、このドラマでは細部までリアルに描写されていて、多分、本物のドルオタの皆さんが見ても、その再現度の高さに納得するのではないかと思うほどだ。
オリジナル脚本の魅力
脚本は森下佳子のオリジナル。昨年夏に放送された『義母と娘のブルース』(TBS系)同様、ヒロインの心理が丁寧に書き込まれている。また、地下アイドルについても十分な取材を行っていることがうかがえる。
加えてこのドラマには、「地下アイドル考証」として、本物の地下アイドルである「姫乃たま」の名前がクレジットされている。地下アイドルに関する著作もある姫乃が、その体験と知見でリアルを下支えしているはずだ。
女優陣も大健闘だ。徐々に自分を解放していくアラサーのドルオタ女子を、メリハリのある芝居で好演している桜井ユキ。そして、自分に自信の持てない、弱気な地下アイドルがぴったりの白石聖。2人の拮抗する熱演は特筆モノだ。
最終章に入り、それまで愛すべき地下アイドルだったはずの栗本ハナの「本当の顔」、その「本質」が見えてきた。また、警察の取調室(担当刑事はハライチの澤部佑)にいる遠藤愛の身に、本当は何が起こったのかも。
全8話のうち、残るは2話のみ。漫画や小説などの原作がない、オリジナル脚本のドラマだけに、最後までどんな展開になるのか、わからない。いや、だからこそ楽しみな「地下アイドルドラマ」なのだ。

左端がハナ(番組サイトより)

日本青年館ホールで公演中の「君の輝く夜に~FREE TIME,SHOW TIME~」を観てきました。
何しろ、脚本・演出が、ごひいきの「ラッパ屋」主宰の鈴木聡さんなので。
海に近い国道沿いにある、ホテルも兼ねた、「ダイナー」という名のダイナーが舞台です。
一人の男(稲垣吾郎)が、ふらりと入ってきます。
10年前に付き合っていた、別れた恋人との待ち合わせだと言うのです。
しかし、その女性はなかなか現れません。
待つ男は、店の女主人(北村岳子)や宿泊客(中島亜梨沙)、そして途中から加わった客の女性社長(安寿ミラ)たちと歓談。
飲んだり、しゃべったり、歌ったり、踊ったりです。
大のジャズファンである鈴木さんらしく、ジャズの生演奏があり、オリジナルの歌詞をつけた名曲が歌われ、見事なダンスが披露されます。

主演の稲垣さんはもちろん、北村さん、中島さん、いずれも達者で、曲のたびに拍手が広がります。
そんな中で、「宝塚トップ」経験者のすごさを、どどーんと再認識させてくれたのが、安寿ミラさんでした。
歌もダンスも芝居も、圧倒的な存在感で迫ってきます。
そこに立つだけで、オーラが放射されるというか、ある世界を現出させてしまう。
さすが、「ベルばら」のオスカル!
いや、ほんと、大したものです。
作品全体も、「ぜいたくな時間を過ごしたなあ」と思えるものでした。

「君の輝く夜に~FREE TIME,SHOW TIME~」は、東京・日本青年館ホールで、9月23日(月)までです。
「これは経費で落ちません!」は
多部未華子にピッタリの意欲作
ドラマ10「これは経費で落ちません!」の舞台は中堅のせっけん会社。森若沙名子(多部未華子)は経理部員だ。
毎回、沙名子が何らかの不正や疑惑に気づくことで物語が動きだす。経費で購入した高級ブランド品や撮影機材の私的流用。取引先との契約更新を利用した不正。請求書や領収書に隠された真実を見抜く力が抜群なのだ。
とはいえ同じ会社の人間がしたことであり、時には深く追及しないほうがいい場合もある。沙名子は「うさぎを追うな!」と自分に言い聞かせたりするが、やはり不正を放ってはおけない。それが「経理部の仕事」だからだ。また、そんな沙名子のおかげで、当事者が決定的なダメージを受けずに済むこともある。このあたりの“機微”の描き方も見どころのひとつだ。
沙名子が持つ生真面目さ、情に流されない正義感、そして本当の意味の優しさ。そんなキャラクターが多部未華子にピッタリで、一昨年の秀作「ツバキ文具店~鎌倉代書屋物語~」(NHK)に並ぶ適役といえる。朝ドラ「つばさ」でヒロインを務めたのが10年前。アラサーとなり、さまざまな大人の女性に挑戦する攻めの姿勢に拍手だ。
そうそう、先週の放送にベッキーが登場した。彼女が演じる小ズルイ社長秘書と、経理部の新メンバー・麻吹(江口のりこ)との、ハブとマングースのような壮絶バトル。ぜひ続きが見てみたい。
(日刊ゲンダイ 2019.09.04)
土曜午後6時のドキュメンタリー
「人生の楽園」が人気
◆セカンドライフの幸せ探る
「人生100年時代」と言われる中、充実した第二の人生の歩み方を提案するドキュメンタリー番組「人生の楽園」(テレビ朝日系、土曜後6・00)が、中高年者を中心に支持を集めている。ドラマチックなことが起こるわけではない、ごく普通の人々の人生を紹介する番組が、なぜ視聴者の心をつかんでいるのだろうか。(佐伯美保)
◆来年20周年 視聴率10%超え
番組は2000年10月に始まり、これまでの放送は900回を超え、来年には20周年を迎える。故郷にUターンした人や田舎に移住した人、50歳を過ぎてから新しい挑戦を始めた人などの様々なセカンドライフの過ごし方を紹介している。
スタートした当時は団塊の世代が50歳を超え、今後増えていく高齢者に関心が集まっていた頃だった。07年には団塊の世代の大量定年退職が始まり、現在は約4人に1人が65歳以上の高齢者だ。一方、日本人の平均寿命は延び続け、退職後の長い人生をどのように過ごすかが多くの人の関心事になっている。
そんな社会の動きに呼応するように、視聴率も伸びた。テレビ朝日によると、ビデオリサーチの視聴率(関東地区)は開始当初は4~5%程度だったが、この5年ほどは年間の平均視聴率が10%を超えている。近年は連続ドラマでも10%の視聴率を獲得する作品が少ない中、土曜日の午後6時台という時間帯では非常に高い視聴率だ。
▼人柄に焦点 地域情報も
碓井広義・上智大教授(メディア文化論)は「番組の魅力は登場する人の人柄」と指摘する。故郷や田舎などの移住先で、夫婦や親子で農業に取り組んだり、カフェや民宿を営んだり……。決して形式にとらわれたり、格好つけたりしていない。碓井教授は「やりたいことに無理せず挑戦している。身の丈にあった幸せが描かれているからこそ、人生に悩む人の背中を押す役割を果たしているのでは」と話す。
舞台となる地域の特性が紹介されている点も人気の秘密だろう。地域の美しい風景やおいしい食べものの紹介も織り交ぜ、番組最後のコーナー「楽園通信」では、登場する人たちが営む店の営業時間や連絡先などの情報をまとめている。国が地方創生を掲げて「田舎暮らし」に注目が集まる中、視聴者が足を運んでみたくなる仕掛けが満載だ。
▼頑張るシングルも紹介
番組で取り上げるのは、夫婦や親子ばかりではない。昨年12月には、離婚を経験し、移住した神奈川県二宮町で農業を始めた50代の男性を紹介した。岡本基晃プロデューサー(50)は企画を検討した時、男性の一人暮らしがさみしく映らないかと心配したというが、男性は農業セミナーで出会った30代男性ら仲間と生き生きと農作業に取り組み、汗を流していた。
岡本プロデューサーは、「今はいろいろな生き方があっていい時代。夫婦の仲が良く、子供や孫がいる幸せだけでなく、一人でも楽しく生きられることを示せたのではないか」と話す。今後も田舎に住む人や都会に住む人、子供がいない夫婦やシングルライフを送っている人など、いろいろな人たちの幸せを紹介するつもりだ。
◆中高年の生き方 他局の番組も
中高年の生き方をテーマにした番組は、他局でも放送されている。
BSテレ東は今年4月から、「カンニング竹山の新しい人生、始めます!」を放送している。移住や転職をしてセカンドライフを楽しむ人々を紹介し、年金や資産運用に関する情報も伝える。50歳が近づき、人生の後半を考えるようになったというカンニング竹山(48)が、司会を務めている。
Eテレの情報番組「あしたも晴れ!人生レシピ」は、配偶者と死別するなどして一人で暮らすようになった人の生活など、健康や住まいといった多彩なテーマを通じて50代以降の人生を豊かにするヒントを伝えている。
高齢者の人口が増加する中、今後こうした番組は増えそうだ。
(読売新聞夕刊 2019.09.02)

2019.09.02 撮影
たまには
後ろも向かなくちゃ
自分がどこにいるのか
わからなく
なっちゃいませんか
コナリミサト「凪のお暇」4
 |
凪のお暇 4 (A.L.C. DX) |
| コナリミサト | |
| 秋田書店 |