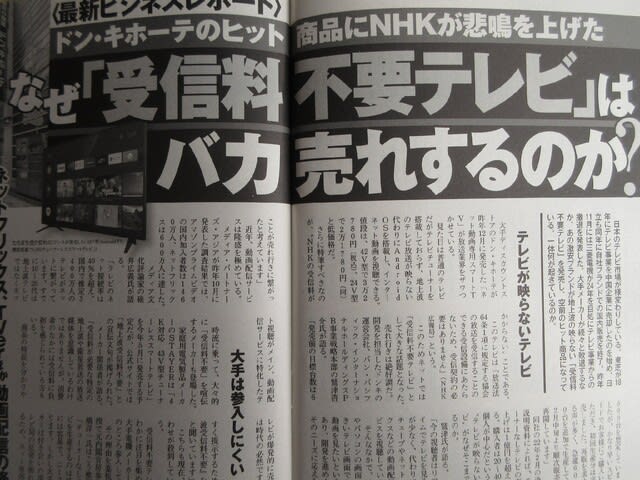日本語ロックの半世紀
日本語の歌詞によるロックミュージックが誕生しておよそ半世紀。その嚆矢(こうし)は、1971年に発表されたはっぴいえんどのアルバム「風街ろまん」といわれる。まるで洋楽のようなサウンドに日本語の歌詞を乗せ独自の世界観を表現することに成功したのである。
はっぴいえんどは、ベースに細野晴臣、ボーカルとギターが大瀧詠一、それにギターの鈴木茂、ドラムの松本隆と錚々(そうそう)たるメンバーで69年に結成され、日本ロックの黎明(れいめい)期に活躍したバンドである。ロックは英語で歌うものという固定観念を取り外した壮大な実験には、新しい音楽誕生の息吹が感じられ、一つの到達点を示しているといえよう。
はっぴいえんどとキャロルとサザンオールスターズの三つのグループが70年代以降の日本のロックを作った、と指摘するのはメディア文化評論家の碓井広義氏だ。
「僕が子どものころ、50年代にはアメリカのロックをカバーするような感じでロカビリーがあった。もしくはそこに日本語の歌詞を乗せるパターンがありました。そして、日本の音楽シーンに大きな影響があったのが、66年のビートルズ来日です。彼らが自分たちで作った歌を自分たちで演奏して歌って世界的にヒットさせていることに多くの人は驚いた」
そうした中で登場したのがグループサウンズ(G・S)だった。ただ数年経(た)つと、歌謡曲の大波にのみ込まれてしまった。
「そこへ登場したのがはっぴいえんど。アルバム『風街ろまん』に収録されている『風をあつめて』は、ロックのリズムに日本語の歌詞を高い完成度で乗せている。そして、個人の歌い手ではなく、ロックバンドであった。日本語のロックに、オリジナル曲、そしてバンド。この3要素はそれまでにありませんでした」(碓井氏)
当時の音楽的な状況は歌謡曲が全盛でフォークもあった。そこに歌謡曲でもフォークでもない全く別の音楽が現れたのである。
「しかもそれは、心象風景が歌詞になっていた。それまでにあまりないことでした。とても文学的でした。なおかつ、松本さんの歌詞に既に文体が確立していた。文体のある文学的な詩、それが歌になっている。もう一つ、聴き慣れないものを聴いた驚きがありました。言葉の音節を故意にバラバラにして、きれいに言葉が歌の流れに乗っていくのではなく、全く別物でした」(同)
◇矢沢の歌声に「破壊される快感」
それまでにない新しい感覚がサウンドとなり、徐々に浸透し認識され、日本語のロックが誕生していったのである。
「『風街ろまん』の風街とは、失われた街なんです。60年代には東京五輪で東京が改造され、70年代当時の東京に目を背けながら、かつてあった街を懐かしみながら、ある種の諦念に満ちた静謐(せいひつ)さがあった。大阪万博もあり、経済大国に向かっていく日本の明るい未来と喧伝(けんでん)されることに対し背を向け、自分たちは自分たちの世界にいたいよ、という感じが曲から表れていました」(同)
矢沢永吉が在籍したキャロルが『ファンキー・モンキー・ベイビー』を発表したのは73年。当時のロックバンドとしては異例の30万枚の売り上げを記録。作曲家で大阪音楽大講師の綿貫正顕氏はこう指摘する。
「曲全体の印象としては、当時、流行していた洋楽の影響が随所に垣間見えつつも、コード進行やメロディーに歌謡曲っぽさがちりばめられており、単なる洋楽のコピーに終始していないところに多くの人が惹(ひ)かれたのかと思われる。今の感覚で聴くと、正直、特に激しい音楽のようには感じられないが、矢沢永吉の圧倒的な歌唱力、存在感には、ロック・スピリッツを感じずにはいられない」
前出の碓井氏はこう語る。
「ロックを独特に進化させたのがキャロルです。一言で言えば、不良の登場です。いきなり不良が出てきて自分たちの音楽を主張した、そんな感覚です。日本語の発音を全てひっくり返すような矢沢さんの歌声がそこにはありました。時代性とか精神性の面で破壊力がありました。破壊される快感があった」
言葉の意味よりも響きを大切にしたのがキャロルだったのかもしれない。
75年にはダウン・タウン・ブギウギ・バンドの「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」が登場する。歌詞部分と語り口調に分かれた斬新さについて、サイト「あなたの知らない昭和ポップスの世界」を運営する「さにー」さんは、
「稀代(きたい)のヒットメーカー阿久悠さんをして“正直やられたと思った”と唸(うな)らせたといいます」
自身が単身渡米して見つけたメンバーと共にアルバムを制作、発表していたCharの「気絶するほど悩ましい」が発売されたのは77年だった。30万枚の大ヒットを記録するが、ご本人はこの曲を発表するのに「自作の曲じゃないから」と乗り気ではなかったらしい。アルバム『Char II have a wine』にはシングルとは異なるアコースティック・ヴァージョンで収録されているのも「シングル・ヴァージョンをそのまま収録するのは嫌だ」という思いからだったそうだ。
テレビを通じてお茶の間にロックを広げたのはCharのほか、原田真二、世良公則&ツイストで、ロック御三家と称されている。
◇新風吹き込んだゴダイゴ、サザン
「さらにロックを身近なモノにしたのは70年代後半にヒット曲を連発したゴダイゴではないだろうか。元々、世界を目指して結成されたバンドで、ドラマの主題歌として大ヒットした『ガンダーラ』以前は全曲英語で歌っていた。今でこそ英語で歌う日本のバンドやアーティストも珍しくなくなったが、当時、テレビで英語の歌詞を歌うゴダイゴは、非常に新鮮で、最高に格好良かった」(綿貫氏)
前出の碓井氏はこんな見方をする。
「キャロルの圧倒的だった力ずく感、不良っぽさをアートにしてしまったのが、サザンオールスターズの桑田佳祐さんでした。聴いていてぶち壊されるような快感、恍惚(こうこつ)感。歌詞は文法とか文脈と一切関係ない、というとてつもない言語感覚はそれまでにありませんでした。当時、『夜のヒットスタジオ』にサザンが登場した時、番組史上初めて歌詞がテロップで流れたほど、多くの人は聞き取れなかった(笑)」
サザンの歌詞は、スピード感と独特の歌いまわしを含めて新鮮だった。
80年代に入ると、テレビの歌番組が全盛期を迎え、ロックがより身近になった一方、「テレビという枠の中では自分たちの音楽を表現できない」と、出演を辞退するアーティストやロック・バンドがいたのも興味深い。
「もちろん、自分たちの楽曲をフル・コーラスではなく、いわゆるテレビ・サイズ(3分程度)に短くして演奏しないといけないという事情もあっただろうが、バラエティー要素の強い演出等に抵抗があったアーティストがいたのも想像に難くない。現代の若者にとっては『ロック=反体制』という感覚はピンとこないのでは、と想像するが、元々はそういう硬派な側面を持っていたのがロックという音楽だ」(綿貫氏)
商業音楽である以上、当然、そのあたりの折り合いをつけないといけないので、単純にどちらが良い悪いと片付けられる問題ではないが、そのバランスを上手(うま)く取りながら変化、発展し、131ページの表のように名曲を生み出してきたのが「日本のロック」ではないだろうか。
ここから今後、ロックがどう進化していくか、楽しみである。【ジャーナリスト・青柳雄介】
(サンデー毎日 2022.03.20号)