というわけでその苫野一徳さんの講演会に行くときの最中に読んでいた本。
山口周「世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?」
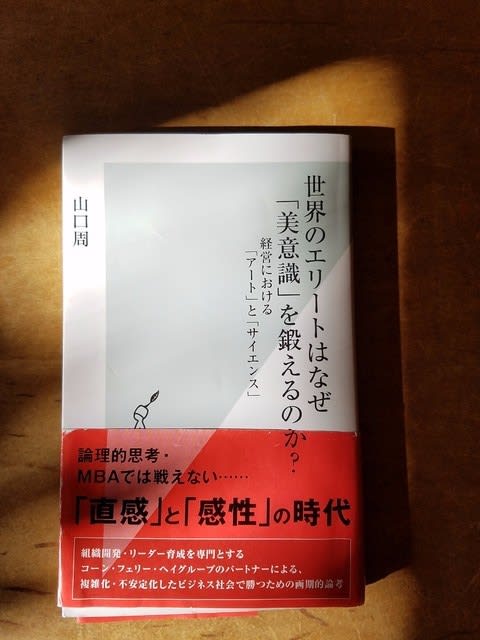
ここに美術教育の意義が熱く込められている。
美術によって学ぶことがとても重要なことであるということがわかる。
人々が美しい物を観て感じることが世界を動かすことになる。
世の中のリーダーとして、「真実、善きこと、本当に美しい物」を察知する能力が必要だということ。
そのためには美意識を鍛えなければならない。
そういうことが書いてあった。
例えば物を売るにしても、どのようなデザインが売れているかリサーチするのではなく
作り手が自信を持って美的センスの優れた物を売り出す。
作り手が自ら世の中をリードする美しさを提唱するという考え方が主流になるという。
今までのように安く、早く、たくさんの時代は終わった。
本当にいい物を価値ある物を美しい物を大切にしようという感性を養う。
そのために美意識を育てよう。鍛えようという。
そんな中で出会った教育哲学の苫野さんの本
「教育の力」

そこには、「教育は福祉だ。」という一文が。
全ての子供に良い教育をという概念が貫かれいる。
本当に意味のある教育とは、、、。
山口周「世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?」
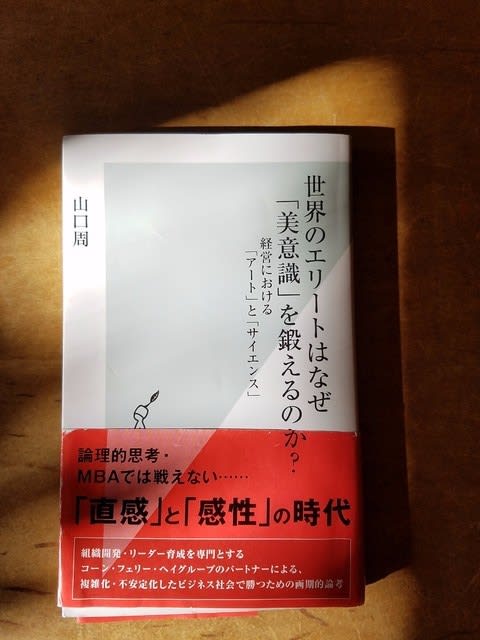
ここに美術教育の意義が熱く込められている。
美術によって学ぶことがとても重要なことであるということがわかる。
人々が美しい物を観て感じることが世界を動かすことになる。
世の中のリーダーとして、「真実、善きこと、本当に美しい物」を察知する能力が必要だということ。
そのためには美意識を鍛えなければならない。
そういうことが書いてあった。
例えば物を売るにしても、どのようなデザインが売れているかリサーチするのではなく
作り手が自信を持って美的センスの優れた物を売り出す。
作り手が自ら世の中をリードする美しさを提唱するという考え方が主流になるという。
今までのように安く、早く、たくさんの時代は終わった。
本当にいい物を価値ある物を美しい物を大切にしようという感性を養う。
そのために美意識を育てよう。鍛えようという。
そんな中で出会った教育哲学の苫野さんの本
「教育の力」

そこには、「教育は福祉だ。」という一文が。
全ての子供に良い教育をという概念が貫かれいる。
本当に意味のある教育とは、、、。












