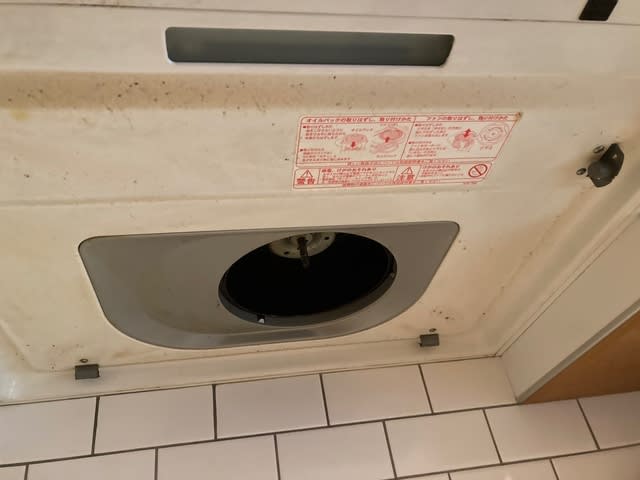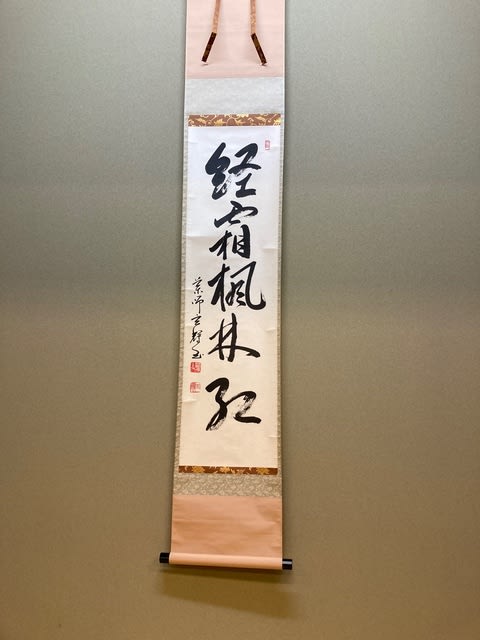図書館に予約を入れていると最近、上手い具合にいろんなジャンルの本がタイミングよく読めるようになってきた。
本当にいい制度だ。
この本は話題になっていたが、貸し出し期限が迫っている本があって、なかなか読み進められなかった。
すっと頭に入ってこなかったが、途中から俄然面白くなった。

大滝ジュンコさん。
村上市山熊田在住。
えっ?村上やん。行ったとこやん。なんと偶然。
羽越しな布と織っている方である。
本中にあるように「新潟は南北に長い。海沿いと山沿いも天気が違う。」をまるで先日の旅行で実感した。
村上城址の「熊出ます。」の看板を思いだした。
新潟の雪深い山中のマタギの嫁になり、山からの自然を生きるために取り入れ、長年脈々と受け継がれた超サスティナブルな生活。
それを絶大な好奇心で体験していく大滝さんの柔軟さとパワフルさで面白く読めた。
組合という強欲な組織に搾取されながら、ほそぼそと続いていた羽越しな布。その機織りの技術を継承しながらきちんとビジネスとして成り立たせるために柔軟に行動する姿や田んぼの田植えの方法を姑さんとバトルしながら合理的に変えて行く姿はたくましい。
マタギ軍団が山で熊を囲いながら猟をする男たちの光景もすさまじい。
日本は本来自然と上手く共存していった国なんだなとつくづく感じた。
北海道の熊と猟師の問題も悩ましい。
昨日の晩御飯はぷりぷりの鰯のフライ。キャベツの千切り。ほうれん草の胡麻和え。大根、人参、玉ねぎ、シイタケ、里芋の具沢山味噌汁。

寒くなるとまるで民宿のご飯みたいになるなー。
本当にいい制度だ。
この本は話題になっていたが、貸し出し期限が迫っている本があって、なかなか読み進められなかった。
すっと頭に入ってこなかったが、途中から俄然面白くなった。

大滝ジュンコさん。
村上市山熊田在住。
えっ?村上やん。行ったとこやん。なんと偶然。
羽越しな布と織っている方である。
本中にあるように「新潟は南北に長い。海沿いと山沿いも天気が違う。」をまるで先日の旅行で実感した。
村上城址の「熊出ます。」の看板を思いだした。
新潟の雪深い山中のマタギの嫁になり、山からの自然を生きるために取り入れ、長年脈々と受け継がれた超サスティナブルな生活。
それを絶大な好奇心で体験していく大滝さんの柔軟さとパワフルさで面白く読めた。
組合という強欲な組織に搾取されながら、ほそぼそと続いていた羽越しな布。その機織りの技術を継承しながらきちんとビジネスとして成り立たせるために柔軟に行動する姿や田んぼの田植えの方法を姑さんとバトルしながら合理的に変えて行く姿はたくましい。
マタギ軍団が山で熊を囲いながら猟をする男たちの光景もすさまじい。
日本は本来自然と上手く共存していった国なんだなとつくづく感じた。
北海道の熊と猟師の問題も悩ましい。
昨日の晩御飯はぷりぷりの鰯のフライ。キャベツの千切り。ほうれん草の胡麻和え。大根、人参、玉ねぎ、シイタケ、里芋の具沢山味噌汁。

寒くなるとまるで民宿のご飯みたいになるなー。