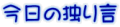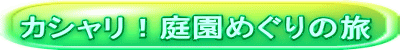【きょうの人】 1117 二宮 尊徳 歩きスマホの元祖 ■ 西有 穆山 曹洞宗の僧侶、総持寺貫首

独善的な判断で、気になる人を選んでご紹介しています。
そこに歴史や思想、人物、生き方などを感じ取って、日々の生活やビジネスに活かしてくださると幸いです。
■ 二宮 尊徳 歩きスマホの元祖
にのみや たかのり (そんとく)
天明7年7月23日(1787年9月4日)-安政3年10月20日(1856年11月17日)
江戸時代後期の経世家、農政家、思想家です。自筆文書では、金治郎(きんじろう)と署名している例が多いのですが、一般には「金次郎」と表記されることが多いです。
諱の「尊徳」は正確には「たかのり」と読みますが、「そんとく」という読みで定着しています。
経世済民を目指して報徳思想を唱え、報徳仕法と呼ばれる農村復興政策を指導しました。
四字熟語 経世済民
http://www.glomaconj.com/joho/keieijoho.htm#17
相模国足柄上郡栢山村(現在の小田原市)に、百姓二宮利右衛門の長男として生まれました。
尊徳は、まず生まれた堀之内村の中島弥三右衛門の娘・きの(キノ)を妻としますが、離縁、20歳も若い、貞淑温良ななみ(波子)と結婚しました。
文化5年(1808年)、母の実家川久保家が貧窮するとこれを資金援助し、翌年には二宮総本家伊右衛門跡の再興を宣言し、基金を立ち上げるなど、成果を出しています。
小田原藩で1,200石取の家老をしている服部十郎兵衛が、金治郎に服部家の家政の建て直しを依頼し、千両もの負債を償却し、頭角を現しました。
文政4年(1821年)には、小田原藩主大久保家の分家であります宇津家の旗本知行所が荒廃していて、再興救済を藩主より命じられました。農民の抵抗で苦労しましたが、再建しました。
晩年近く、天保4年(1833年)には、天保の大飢饉が関東を襲いましたが、金次郎の力を充分に発揮しました。
二宮金次郎といえば、戦前には、どの学校にも銅像が建っていると言えるほど、一般的でした。背中に芝を背負い、本を読む姿は、子供達へのお手本でした。今日では、歩きスマホが非難を浴びていますが、当時は、むしろ誉められる行為だったのですね。
■ 西有 穆山 曹洞宗の僧侶、総持寺独住三世貫首
にしあり ぼくざん
俗名:笹本万吉
文政4年10月23日(1821年11月17日)-明治43年(1910年)12月4日
陸奥国(青森県)八戸出身の日本の曹洞宗の僧侶で、横浜市總持寺独住3世貫首でもあります。法名は瑾英(きんえい)、直心浄国禅師で、俗名は、笹本万吉です。
天保3年(1832年)に地元の長竜寺で出家し、金栄と名乗っていました。天保10年(1839年)に、仙台に移転し、天保12年(1841年)に江戸に出て、吉祥寺旃檀林学寮に入りました。浅草本然寺の泰禅の後を継ぎ、牛込鳳林寺住職となり、小田原海蔵寺月潭全竜の下で修行しました。
瑾英に改名し、1861年、諸嶽奕堂会下の龍海院で修行中に大悟を得て、奕堂より印可を受けました。
宗参寺・鳳仙寺を経て、大教院に呼ばれて中講義・大講義、總持寺出張所監院、本山貫首代理になりました。法光寺・中央寺・可睡斎・伝心寺を経ています。
明治33年(1900年)に、信者の寄付により、横浜に西有寺を創建、翌明治34年(1901年)に總持寺貫首に選ばれます。翌明治35年(1902年)に、曹洞宗管長となりました。明治38年(1905年)に横浜で引退し、明治43年(1910年)12月4日に遷化しました。
著書に『直心浄国禅師語録』4冊、『正法眼蔵啓迪(けいてき)』3冊などがあります。

◆ 【きょうの人】 バックナンバー
歴史上で活躍したり、仏教など宗教関係の人であったり、ジャンルはいろいろですが、彼等から、学ぶところが多々ありますので、それをご紹介します。
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/b57a13cf0fc1c961c4f6eb02c2b84c9f
◆ 【今日は何の日】は、毎日発信しています。
一年365日、毎日が何かの日です。 季節を表す日もあります。 地方地方の伝統的な行事やお祭りなどもあります。 誰かの誕生日かも知れません。 歴史上の出来事もあります。
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/b980872ee9528cb93272bed4dbeb5281
◆ 【経営コンサルタントのひとり言】
経営コンサルタントのプロや準備中の人だけではなく、経営者・管理職などにも読んでいただける二兎を追うコンテンツで毎日つぶやいています。
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/a0db9e97e26ce845dec545bcc5fabd4e
【 注 】
【きょうの人】は、【Wikipedia】・当該関連サイトを参照・引用して作成しています。