19世紀にベルファストで製造され、スリランカで動き続けている。
2019年に訪れた北アイルランドを思い出した。
※タイタニック号を建造したベルファスト
※産業革命で発展したベルファスト

「シロッコ」とは、ラテン語で北アフリカから吹く熱い湿った風のこと。

収穫した茶葉を乾燥させるこの機械にも熱い風が吹いていたか?
1881年にサミュエル・デビッドソン会社が製造した。
1898年に「シロッコ」送風機の特許をとっていた。
※会社のページにリンクします

↑工場のガイドさんが自慢気に紹介する。
**
茶畑を見学してから案内された工場はそれほど大きくなかった。

19世紀からの建物なのだろう。
↓入り口でシナモンの木の皮を剥く方法を実践していた

こんなふうに

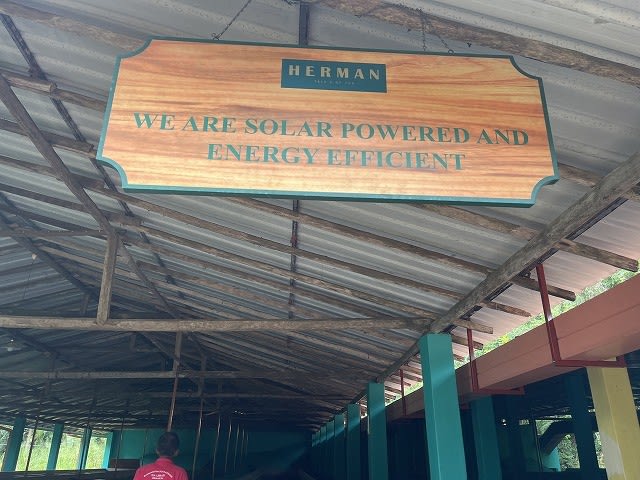
こちらが茶葉の乾燥セクション

網の下から空気が通る↓


乾燥を終えた茶葉は元の五分の一の重さになっているそうな。

乾燥した茶葉を品質によって自動選別する。

自動選別するための機械は↓

↑日本製だった↓

京都は宇治の服部製作所※ホームページに茶葉選別機の歴史が書かれています

 試飲の場所へ移動
試飲の場所へ移動


ずらっと並んだお茶をスプーンですくって味見。

冷めちゃうんじゃない?と思うかもしれないが

お茶の味わいは(感じ方によるが)、ぬるいぐらいの方がよくわかるのではないかしらん。
2019年に訪れた北アイルランドを思い出した。
※タイタニック号を建造したベルファスト
※産業革命で発展したベルファスト

「シロッコ」とは、ラテン語で北アフリカから吹く熱い湿った風のこと。

収穫した茶葉を乾燥させるこの機械にも熱い風が吹いていたか?
1881年にサミュエル・デビッドソン会社が製造した。
1898年に「シロッコ」送風機の特許をとっていた。
※会社のページにリンクします

↑工場のガイドさんが自慢気に紹介する。
**
茶畑を見学してから案内された工場はそれほど大きくなかった。

19世紀からの建物なのだろう。
↓入り口でシナモンの木の皮を剥く方法を実践していた

こんなふうに

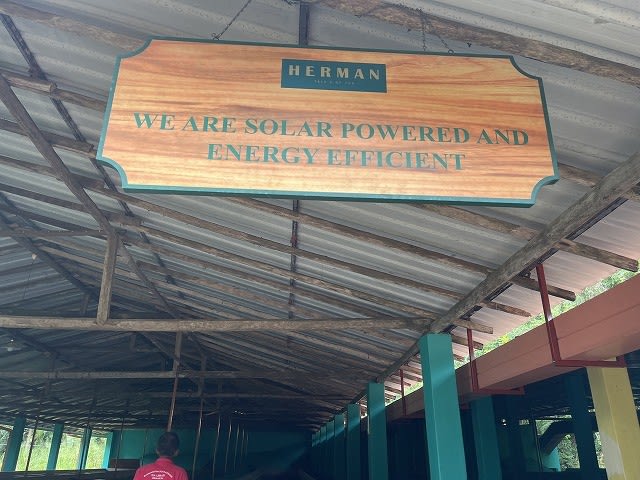
こちらが茶葉の乾燥セクション

網の下から空気が通る↓


乾燥を終えた茶葉は元の五分の一の重さになっているそうな。

乾燥した茶葉を品質によって自動選別する。

自動選別するための機械は↓

↑日本製だった↓

京都は宇治の服部製作所※ホームページに茶葉選別機の歴史が書かれています

 試飲の場所へ移動
試飲の場所へ移動

ずらっと並んだお茶をスプーンですくって味見。

冷めちゃうんじゃない?と思うかもしれないが

お茶の味わいは(感じ方によるが)、ぬるいぐらいの方がよくわかるのではないかしらん。




















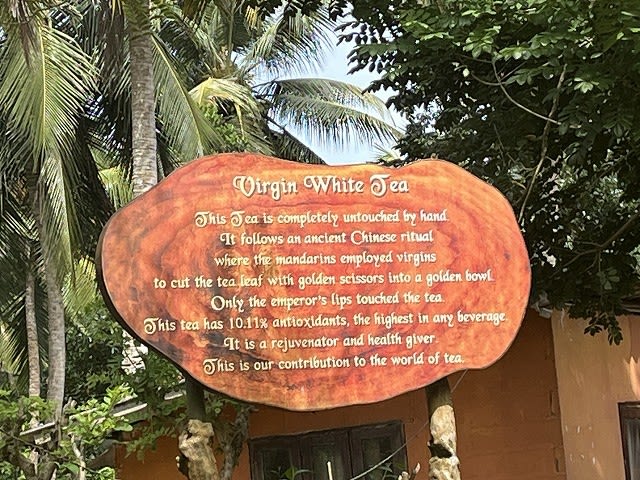
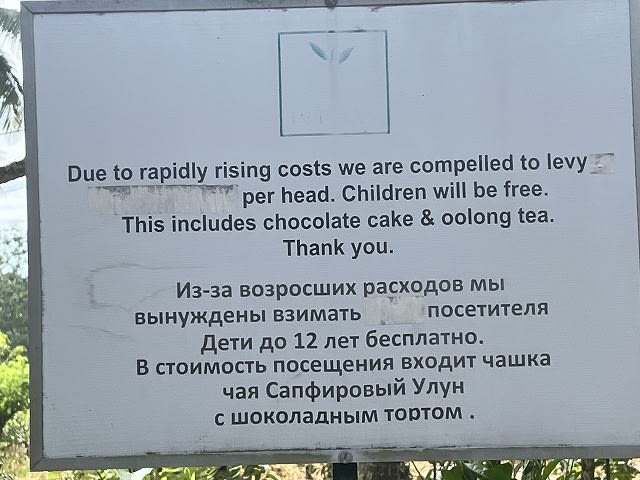





























 ひとつでこんなに大きい
ひとつでこんなに大きい








































































