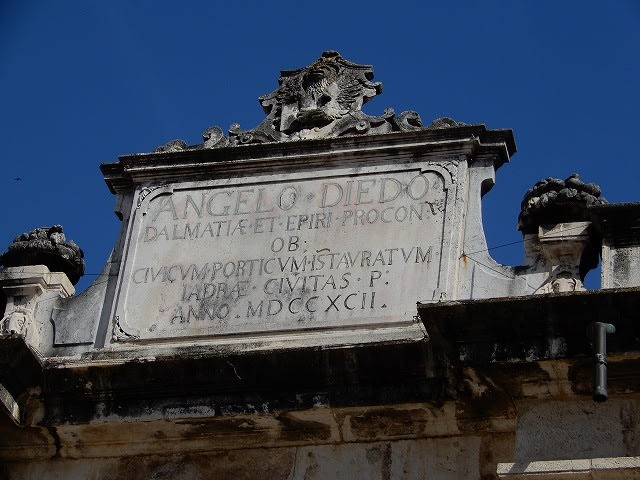ニンの小さな島から車なら五分も走らない小さな丘に、一度見たら忘れられない小さなロマネスクの聖堂がある↓

以前、道路からその姿を見てはっとしたのだがバスを止められなかった。今回は念願かなって近くに行ける(^.^)

平原の中になぜかぽこんと出た土盛り↑小松には古墳のようにみえるのだけれど、地元ガイドさんは自然のものだという。
だが、教会がつくられる以前からスラヴ民族が埋葬されていた小山だったのだそうだ。やっぱり…人工の古墳じゃないのかしらん。
 12世紀の●聖ニコラス教会という表示があるが、実際にはそれだけでは語れない歴史がある建物↓
12世紀の●聖ニコラス教会という表示があるが、実際にはそれだけでは語れない歴史がある建物↓伝説的に語られる歴史では、ニンに住んだ七人のクロアチア王が人々が見守る中、ニン島からこの小山まで馬をすすめ、丘に登り司教から冠をいただいたのだという。
古い時代のの礼拝堂は上部がこのような砦のかたちではなく、二階建てで小さなドームがあったと推察されている↓

↑ヴェネチア時代に見張り塔に改築された際に上部が砦構造に改築された。
建物の持つ魅力とは、それがオリジナルであるかどうかや大小に左右されない。
周囲の環境、見えてくるプロセスや高さ、いろいろなものが混ざり合って醸し出される。
人が設計して予定して出現させられるものではない。
こんなふうに偶然に、しかし必然に、歴史の片隅に姿を留めている。
**
ニン島の中にある●聖十字架教会も忘れられない小さなロマネスク↓

なんと9世紀からの構造をそのまま残しているという
ここはローマ時代には住居があったエリアで、現在周囲にみられる石の土台はその跡

キリスト教時代になり、この教会が出来てからは墓地となった

内部はとてもシンプル↓


かつてここにあった装飾物はすべて博物館に移された。
子供たちが自国の歴史をまなびにやってくる場所↓

**
●考古学博物館は正面の赤い建物↓

ここに島の入口につないであった黒い小舟の本物がある↓

ニンの港の入口付近の海中から発見された↓下の写真でニン島を守るように伸びている砂州の先端あたりだったそうだ↓

炭素年代測定の結果11世紀ごろ、つまり中世クロアチア王国の時代のものとわかったので
「CONDURRA CROATICA(クロアチアの船)」と名付けられた。
パッと見て、オスロ(ノルウェー)にあるヴァイキング船博物館を思い出した。
遠く離れた北欧の? と、思うなかれ。
ヴァイキングと呼ばれた彼らは木製の船ではるかな距離を南下し、シチリアにノルマン王朝をうちたてたりしていた時代である。
造船の技術というのが伝わるのは案外早かったのではないだろうか。
近づいてよく見るとオリジナルの材料を最大限使って復元してある↓

頑丈な作りで、商品輸送にもはたまた戦闘の際にも使われたと考えられている。
近くの古代ローマの旧港で見つかったより古い船がこれ↓

こちらはローマ人より前にいた先住民族の名前から「SERILIA LIBURNICA(セリーリャ・リブルニッツァ)」と名付けられた。
これら水中から見つかった船はニンの博物館でなければ見られない品である。
考古学博物館にはもちろんローマ時代の解説も多数ある↓こんな巨大神殿があったのか↓

実際の場所に復元されているのは一本の柱だけだが↓

↓中庭に展示された石造物は古代から近代まで多岐にわたる↓

小さな博物館なのでニン島で二十分よけいに時間があれば寄ってみたい。もちろんしっかりした解説付きで。