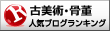18世紀に大流行した赤壁賦紋のドラ形大皿です。
蘇軾(そしょく)という詩人が詠んだ詩であり、
赤壁賦(せきへきふ)は、ご存知の方も多いと思いますが、『前赤壁賦』と『後赤壁賦』があります。
赤壁賦(せきへきふ)は、ご存知の方も多いと思いますが、『前赤壁賦』と『後赤壁賦』があります。
『前赤壁賦』
宋の元豊5年(1082)秋7月16日夜、
蘇東坡が月明に乗じて舟遊びして、
三国の英雄曹操や周瑜の風流を偲び、
自分がはかない流人の身の上であることを嘆き、
無限な生命の前では古人も我も何等選ぶところが無い、
儚いものであり、萬物同一であることを悟り、
明月と江上の清風とを楽しみ
憂いを忘れたと言う内容だそうです。
宋の元豊5年(1082)秋7月16日夜、
蘇東坡が月明に乗じて舟遊びして、
三国の英雄曹操や周瑜の風流を偲び、
自分がはかない流人の身の上であることを嘆き、
無限な生命の前では古人も我も何等選ぶところが無い、
儚いものであり、萬物同一であることを悟り、
明月と江上の清風とを楽しみ
憂いを忘れたと言う内容だそうです。
『後赤壁賦』
蘇東坡は赤壁賦を作って3ケ月後、
冬の赤壁に遊んだ際、再び詠みました。
冬の月夜、水量が少ない江石が露出し
凄惨な景色を詠じました。
月夜の美観と懐古の情感が織り成す、
叙情的な雰囲気に包まれ然も格調高く詠んであるそうです。
蘇東坡は赤壁賦を作って3ケ月後、
冬の赤壁に遊んだ際、再び詠みました。
冬の月夜、水量が少ない江石が露出し
凄惨な景色を詠じました。
月夜の美観と懐古の情感が織り成す、
叙情的な雰囲気に包まれ然も格調高く詠んであるそうです。
夏の満水期と冬の渇水期で、
12~3m水位が違う年もあると聞きますので、
あまりの情景の違いに驚いて、
詠わずにいられなかったという説があります。
12~3m水位が違う年もあると聞きますので、
あまりの情景の違いに驚いて、
詠わずにいられなかったという説があります。
前赤壁賦、後赤壁賦は、三国時代に思いを馳せていますが、
ご存知かと思いますが、蘇軾が実際に行ったのは、
赤壁ではなく、赤鼻といわれる場所だったそうですね。
ご存知かと思いますが、蘇軾が実際に行ったのは、
赤壁ではなく、赤鼻といわれる場所だったそうですね。
湖北省の蒲圻(現在は赤壁市と改名)の西にあり、
後漢末期の208年、
曹操と、孫権・劉備の連合軍が実際に闘った場所が
「武赤壁(戦いのあった赤壁)」
蘇軾が作った「赤壁の賦」は、
当時「赤鼻」と呼ばれていたといわれる、
黄州(湖北省黄岡県)赤壁「文赤壁(詩文の赤壁)」だそうです。
後漢末期の208年、
曹操と、孫権・劉備の連合軍が実際に闘った場所が
「武赤壁(戦いのあった赤壁)」
蘇軾が作った「赤壁の賦」は、
当時「赤鼻」と呼ばれていたといわれる、
黄州(湖北省黄岡県)赤壁「文赤壁(詩文の赤壁)」だそうです。
ちょっと、マンガチックな図がなんとも言えず、愛嬌があり
日本のマンガの原点を思わせるデッサンと思ってしまいます。
日本のマンガの原点を思わせるデッサンと思ってしまいます。
これは、以前のハートの窓絵の龍図と時代は、きわめて近く、宝暦~安永期はあると思われます。
ですから、これも240年くらい前の作品となりますよね。
ですから、これも240年くらい前の作品となりますよね。
この皿裏の文様が、宝暦頃に流行った独特の文様ですから、時代の目安になると思います。
大皿ばかりで、すこし飽きたかもしれませんが、ブログ主の趣味ですので、ご勘弁くださいませ。(笑)
直径約30cm高さ約3.6cm