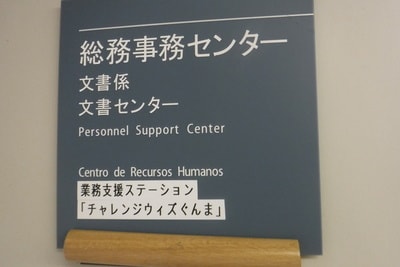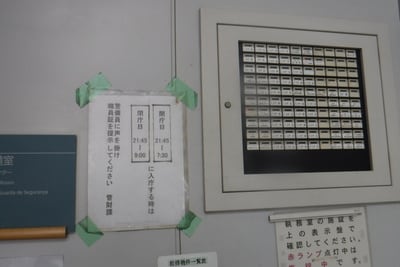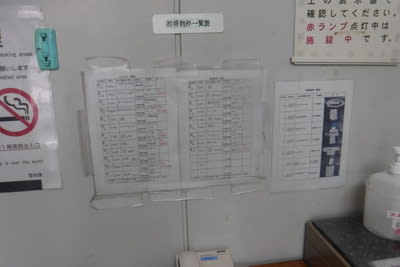■早ければ今年の10月頃から運転開始を予定しているという東電グループの関電工を主体とする前橋バイオマス発電施設ですが、放射能汚染木材を大量に集めて燃焼させることから、県民の放射能二次汚染に伴う懸念や不安をよそに、群馬県や前橋市の行政と癒着して、環境アセスメントも課せられないまま、現在燃焼設備の鉄骨組立や構成部品の現地据付など作業が進んでしまっています。こうした中、当会は地元住民団体とともに、発電施設に隣接する木質チップ製造施設に対する補助金交付の「差止」もしくは「処分の取消」を求めて訴訟を2016年7月15日に提起しました。

↑第2回弁論準備手続が行われた6月15日の消印で速達で送られてきた被告第2準備書面等が同封された封筒。これでは間に合わないので、被告は原告に裁判所で副本を渡してきた。いかにも行政目線らしいやり方といえよう。↑
その後、裁判所から補助金の一部は既に支払われていることから、支払の有無で峻別してはどうか、と訴訟指揮があり、結局、2016年12月26日に、新たな住民訴訟の訴状を裁判所に提出したところ、今度は、同じ事件で2つの訴状が出ていると被告からイチャモンがつきました。
そのため、2017年3月10日の第4回口頭弁論で、最初の訴状を取り下げる羽目になりました。
そして、2017年3月15日に、出直し裁判の第1回口頭弁論が開かれ、同5月10日に第2回口頭弁論が行われましたが、また裁判所からイチャモンがつけられてしまい、法定外の受任裁判の形で、同5月22日に第1回弁論準備が行われ、6月15日に第2回弁論準備が行われたのです。
■裁判所は、補助金の未支払い分を「処分取消」ではなく「返還」、既支払い分を「差止」としてはどうか、と、本裁判ではなく5月22日に開かれた第1回弁論準備手続きの中で、提案してきました。
その結果、6月9日付原告準備書面(2)で、「主位的請求として、今までの請求を維持する。予備的請求として,裁判所の示唆するとおり,返還請求と差し止め請求とをあわせて請求する」と訴えの方針を変更する旨伝えてありました。
この裁判の弁論準備手続きの経緯は次のブログを参照ください。
○2017年5月11日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…当会欠席で5月11日に開催された関電工の前橋バイオマス発電を巡る2件の裁判↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2311.html#readmore
○2017年5月23日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス発電補助金訴訟をよそに着々と進む発電施設建設↓ ※5月22日の第1回弁論準備の報告
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2320.html#readmore
○2017年6月11日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金訴訟6.15弁論準備に向け原告準備書面(2)を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2341.html#readmore
■2019年6月15日(木)午後3時30分~開催の第2回弁論準備手続きに先立ち、被告から、前日の6月14日に、とんでもない内容の被告第2準備書面がFAXで届いたのです。
*****被告第2準備書面*****PDF ⇒ 201706152.pdf
平成28年(行ウ)第27号 住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求事件
原 告 小川賢 外1名
被 告 群馬県知事 大澤 正明
第2準備書面
平成29年6月14日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
被告訴訟代理人弁護士 石 原 栄 一
同 関 夕 三 郎
同 織 田 直 樹
同指定代理人 板 垣 哲 夫
同 束 田 健 靖
同 織 田 知 徳
同 武 藤 淳
同 鈴 木 利 光
同 石 井 米 吉
被告より本件補助金を支出する権限につき委任を受けた渋川森林事務所長は,平成29年5月31日,本件補助金交付決定に基づいて,前橋バイオマス燃料に対し,2億4150万円を支出した(乙1)。これにより,本件補助金4億8000万円全額の支出が完了したため,本件補助金支払い差止請求について,訴えの利益が失われた。
以上
*****証拠説明書(乙1)*****
平成28年(行ウ)第27号 住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求事件
原 告 小川賢 外1名
被 告 群馬県知事 大澤 正明
証拠説明書(乙1)
平成29年6月14日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
被告訴訟代理人
弁護士 石 原 栄 一
関 夕 三 郎
織 田 直 樹
●乙号証No.:1
○標目:支出回議書
○作成年月日(原本・写しの別):平成29年5月29日(写し)
○作成者:渋川森林事務所
○立証趣旨:渋川森林事務所長が前橋バイオマス燃料㈱に対し、残額2億4150万円を支出したこと
*****乙第1号証*****
支出回議書 平成29年度
決裁日 29.5.29
詩集命令者 桑原
本書のとおり支出したい。 平成29年5月29日
発議者 渋川森林 矢島裕子 内線番号( )
支出番号 35
内訳件数 1件
関連情報
所属名 041102 渋川森林
会計 01 一般
繰越 3 事故
債務
振替番号
支出科目: 款 : 07 環境森林費
項 : 07 林業振興費
目 : 03林業・木材産業振興対策費
事業:
節 : 19 負担金補助及び交付金
細節:
相手方: コード: 0287475331-00
郵便番号: 371-0241
住所: 前橋市苗ヶ島町2550番地2
氏名: 前橋バイオマス燃料(株)
受取人区分: 0 本人
命令回数 1
特例 0 特例無し
支出負担行為決議
訂正回数 0
支払方法 3 口座振替
支払区分 0 通常払
口座振替:金融機関 ■■■■■■■■■■■■
口座種別/口座番号 ■■■■■■■■■■■■
口座名義 ■■■■■■■■■■■■
請求書番号
支出額 ¥241,500,000*
控除金額 ¥0*
支払額 ¥241,500,000*
内容 190006-00 負担金補助及び交付金(過年度)
備考 27 林業・木材産業再生緊急対策事業補助金
支払予定日 平成29年5月31日
支払日指定 無
支出負担行為年月日 平成29年4月1日
支出負担行為額 241,500,000
既支出額
今回支出額 241,500,000
支出命令残額 0
控除金の内容:科目:
控除金名:
人数:
金額:
管理番号 ■■■■■■■■■■■
会計管理者(出納員)
発議者 ?
照合年月日・印 29.5.29
支払日 29.5.31
**********
まさに行政はここまでえげつなく、よくやれるものだ、と感心した次第です。なにしろ、裁判を先延ばしにした挙句に、全額補助金をチップ工場の建設につぎ込ませた上に、裁判する意味がなくなっている、などと原告を挑発するかのような書き方だからです。
■こうして、仰天の連続の中で、第2回弁論準備手続が開かれたのでした。
これまでの法廷でのやりとりと異なり、前橋地裁3階31号法廷は、いわゆる「ラウンドテーブル」と呼ばれる配置になっていて、楕円形の机を囲んで、中央に受命裁判官が1名座り、その右手側に原告が、左手側に被告が座ります。
このため、割合リラックスした雰囲気の下で、協議が行える環境にあります。そこで、裁判官が入室するまで、被告の群馬県職員らと雑談をしました。すると職員らの発言の中で気になったことがあります。それらを列挙してみます。
(1)この補助対象は発電所ではなく、チップ工場のほうなので、工場の建設が終われば、対象工事、つまり対象となる整備工事が終わったから、全額支払った。
(2)当然、補助事業については工事の結果を確認してから支払った。
(3)トーセンが自慢する自社開発という油圧プレスの存在も確認した。
(4)こうした機材は入札ではなく、合見積で比較はしており、随契の言い値で査定しているわけではない。
(5)自然乾燥のほうがコストが安いため、木材のストック期間についても事業主体と考慮している。
(6)当初、プレス機の導入計画はなかったが、最終的に、搬入木材の全量をプレス機にかけて脱水するわけではない。
(7)チップ工場のほうは、環境アセスメントについて関知しない。また、環境アセスメントは、運用のところで定めている。
(8)フォークリストも全部随契となっているが、その理由について、いちおう事業者から聞き取りは行っている。
(9)フォークリフトは1社限定ではないと思う。1社以外の随契もあり、合見積をとっている。
(10)4.8億円の補助金だけでなく、事業者の自己負担として3.2億円もある。さらにトータル8億円以外の事業者の自己負担もある。だから、4.8億円の補助金だけでチップ工場の建設費が全部賄えるわけではない。
(11)事業者の支払いが一応完了したので、補助金を払ってやらないと債務不履行になってしまうので、支払いをしてやらないといけない。
そうこうしているうちに、午後4時が迫りました。受命裁判官の佐藤裁判官が入室する時間です。裁判官の入室前に、森山書記官から「原告に確認したいが、被告第2準備書面などをもう受け取ったのか」と聞かれました。原告は、3階のエレベーターホールで待機しているときに、副本を被告から渡されていたので「はい」と答えました。
■すると午後4時になり、裁判官が入場してきて、第2回弁論準備手続きが開始されました。
裁判官:それぞれの第2回の弁論準備。原告のほうから原告準備書面(2)が6月9日に出てきた。被告のほうからも第2準備書面ということで6月14日付に書面が出てきたが、これはきょう届いたのか?
原告:ええ、いまさっきいただきました。
裁判官:ああそうか。これはまだ、本日のところは陳述扱いとせずにもう少しちょっと聞きたいことがあったので、本日は、拝見はしているが陳述はしないという扱いにしたい。まず原告のほうだが、主位的請求として今までの請求を維持するというのは、今現状とくに訴えの変更はされていないので、4.8億円の差止を維持するという趣旨でよいのか?
原告:差止ではなくて、取消ということで、最終的にしたが、その場合は変更申立をしなければいけないのでしょうか?
裁判官:それはそうだが、取消訴訟だと前回申し上げた通り、処分性ということが問題になる。つまり、行政処分たるという、そういう行為に当たるかどうかということが問題にある、その点について別途主張してもらうことになる。それでもこれを維持するのか?結論的には結局、この処分性・・・
原告:いろいろ文献を見ました。いろいろな判例があって、処分性について認めてないというのが確かに多い。殆どがそうなっている。だけど、講学的に言ったらそうなるのかもしれないけれど、だけど、常識的に納税者の立場で言うとどうも納得できない。それを主張しても、だけど前例主義、判例主義によって取り合ってもらえないのでしょうか?時間の無駄ということになるのでしょうか?
裁判官:取消を求める意味がどこにあるのかということになる。今回、例えば差止、支払われたものの返還を求めるということ。予備的に求めるといっているが・・・。
原告:ええ。差止というのは、もとより(補助金が支払われる以前に我々は)差止で提訴した。こういった不合理な環境問題は、いろいろな関係から税金の無駄遣いでもあるし、そういうものは本来これが(県の上層部に)上程されて予算化されて、それが議会で決まって、そのあと具体的な支払いのいろいろな過程があったわけなんでしょうが、その点で我々は差し止めたいという気持ちで、ずっときました。だけど、こうやって係争しているうちに、どんどんどんどん時間が経過して、挙句の果てには「もう全部払ってしまった」という。こういうふうになった時に、最初に差し止めということを、維持していくのはどうなのでしょうか?この間の裁判所の示唆でも、なんというか、実際には既に支払われた分は差止という定義が当てはまらない、というふうにコメントをいただきましたが。
裁判官:差止にするか返還にするかというのは、また別の話であって、処分、交付決定の処分を止めるという今話になっている。その処分の取消しを求める意味があるのかという話だ。今現在は、どうやら全部、例えば支払われたということで、それを返還を求めるということだよね。そういうことになるよね。
原告:この間、そのような示唆をいただきましたので。
裁判官:だからその処分に当たるかどうかというのは、やってみなければ分からないが、それをわざわざ争う意味というのがどこにあるのかなあ、と思うわけだ。その争点を出さなくても、別途返還訴訟だけで、その、もし勝てばだが、勝てば、要するに補助金は返せという話になるわけだ。
原告:お金の部分と処分自体が、その、正規の手続きというのか、まあ環境問題だとかいろいろな部分で、それで処分自体が、まあ少し不当性があるのではないか、おカネではなくて、その罪というのかね。処分に至る・・
裁判官:その交付決定、およびその交付手続きの瑕疵、ちょっとその理由はわかるが瑕疵があるんだということで、無効だということで返せと言っているわけでだから、それは処分にせよ返還にせよ問題になるわけだ。ただ、処分の取消ということになると、まさしくこの処分が、いわゆる法律に定める処分。一定の、まあ、処分という言葉を使うが、その中でも「一定の」処分でしか対象にならないという訴訟の類型なので、その形式的な議論をしなければならないことになる。その形式的な議論をしなくても、実際的に、無効かどうかはストレートに判断できるわけなので、わざわざ形式論を挟む必要があるのかということだよね。
原告:確かに補助金の場合に、いろいろな事例があって、今回の事案は、ただで(補助金を事業者に)くれてやるんだから、いわゆる贈与みたいな感じだから処分性がどうのこうのというのが確かに判例にバンバン出てくる。そう言われれば確かにそうだが。ということは、もう返還請求一本でやったらどうかという、効率がいいというわけでしょうか?
裁判官:そのほうが争点も少なくて済むし、立証の負担も減るよね。審理も早く進むし。その、勿論、その訴訟を決めるのは原告の自由だが、ただ、このように処分の取消しという構成をとる必要があるのかと言われると裁判所には疑問符が付く。だから返還訴訟を端的に求めればよいのではないのか、というような話だ。
原告:この処分一本というのは今日初めてでてきた。ということになるので、ちょっとすぐ判断というのがあったが、これまでは半額くらい出ていて、半額残っているようなイメージだったと思っていたが。
裁判官:それはまた別の話でその次の話になる、そうしたうえで例えば、まあ、じゃあ返還にしますという話になったときに、どうやら今回被告から出てきた第2準備書面によると、もうすべて払い終えたという話なので、その差し止めを求める理由はないわけだ。だから、4億8000万円全額返せという訴訟にすれば足りるのではないかという理解で裁判所はいる。勿論、・・・・そうですね。
原告:ちょっと、第3者の意見も聞いて確認にします。早急に確認して、今の線で決め打ちでやるかどうかを決めたいと思う。ちょっと被告のほうにもあれだが、例えば、全く関係ないものだが、こう裁判例でこう言ったまあ、請求の趣旨、まあ棄却されてしまった判例であっても、まあ請求の趣旨というのはこういう立て方があるよという、全く別の関係のない裁判だが、もう(原告に)参考としてお渡ししてもよろしいかな?
被告:はい、はい。結構です、結構です。
裁判官:例えば、これ全く関係のない訴状だが、見ていただきたいのは、これ。(と言って、被告に気を使いながら原告にコピーをくれたのがこれ↓)
※宇都宮地方裁判所平成25年5月15日判決/平成23年(行ウ)第7号補助金返還履行請求事件: PDF ⇒ 20170615n.pdf
原告:補助金返還履行請求・・・23年、最近ですね、宇都宮で。
裁判長:ええ。当事者の求めた事実及び理由の求めた裁判というところがあって、1原告(1)で被告はA株式会社に対して9億7050万2380円、及びこれに対する平成23年9月14日から支払い済みまで年5分の割合になるということで、まあこれ、補助金の交付が違法だというふうに言って提起した不当利得返還請求をすることを求めた訴訟だが、こういった、立てるとすれば、こういった請求の趣旨になろうかと思う。一応参考にということでご案内させていただく。では、一度検討していただいて、、仮に今言った返還訴訟一本でなるのであれば、訴えの変更申立書を書面で提出していただくことになる。で、今現在は差止め、4億8000万円の支出をしてはならないという差止めを求める形なっているので、これを・・・。
原告:このように変更しますという申立書ですね?
裁判官:はい。ちょっとその形式論を整えたうえで、もう一度弁論に戻して、その中身の話をしたほうがよろしいかと思うので、もう一期日、すまないが入れさせていただいてよろしいか?そこで(原告の主張を)確認させていただいて、まあ弁論に戻すという進行にしたいと思うが、よろしいか?
原告:ええ、いいですすよ。
裁判官:ちょっと前回、気にされていた訴額の話ですが、あれはおそらく住民訴訟だと、返還を求める額にかかわらず、一律の金額、訴額160万なので、あまりその、差止めとか取消しにするか、今回の返還訴訟にするかで訴額の問題は、そんなに変わってくるという話ではないかと思うので、そこは、あまり気にされなくてもよろしいのではないかと思う。
原告:はい。
裁判官:それから返還、4億8000万円の返還を求める返還を求めるからと言って4億8000万円分の印紙を支払うということではないわけだ。
原告:ええ、住民訴訟のくくりだと思います。
裁判官:よろしいかね。ちょっとそれでは検討して訴えの変更申立書を出してもらうことになるが、どのくらいで?
原告:えーと、1か月以内にはやりたいと思いますけど。
裁判官:1か月以内?
原告:だから3週間で、1週間で次の、こういう期日を、1か月後に設定していただけばですね。こちらとしてはそれを希望しますけども、ちょうど夏休みとか、それはまだ7月だから関係ないか。
裁判官:書面を出してもらうのが3週間ということですね?よろしですか被告は?
被告:はい。
裁判官:それでは、1か月後ですので、まあ7月の・・・14日とかはいかがか?
原告:異存ありません。
被告:これ、書面が出る日?
原告:書面はその1週間前に出します。
被告:14日は差し支えます。
裁判官:それでは、18日(火)はいかがですか?
被告:午後の遅い時間がありがたいんです。
裁判官:同じくらいの4時がよろしいか?
被告:ええ。
原告:差し支えございません。
裁判官:では7月18日(火)火曜日の4時ということで、弁論準備もう1回やらさせていただきます。書面は(7月)7日ぐらいまでは出るということで聞いてよろしいかね?
原告:はい。
裁判官:では、そこを整えさせていただいて弁論に戻して、まあ、審理を進めるという方向で考えております。よろしいですかね?
被告:はい。
原告:まあ、あのね、(この計画は)どんどん進んでしまっているので、まあ皆さん現場に行かないでしょう。(といって、原告が用意してきた現場の現況写真を裁判官と被告に配布した)
裁判官:まあ、弁論に戻してからまた証拠としていただくから。
原告:ですから、参考資料ですよ。
裁判官:はいわかりました。
■以上のやり取りが約13分間にわたって交わされました。弁論準備手続のあと、原告は被告に「まだ、塀ができていないが、あれは補助金の対象ではないのでしょうか?8億円の補助金対象工事に入っていないのでしょうか?」と質問したところ、被告は「そうだ」と言いました。
肝心の防音壁が後回しになっていることについて、別の情報では、トーセンがお粗末な塀を計画していたので、関電工が見直しをしているらしい、という見方もあります。いずれにしても、地元説明会で「最初に防音壁を作る」といった関電工の説明が反故になっているのは確かです。
さらに原告は被告に対して「事業者の関電工らは、施設内部を全くマル秘にしているが、納税者である県民らは、補助金の納税もしているのだから、関電工ら事業者に対して、施設内部を県民に見せてやってくれ、という、そういう行政権限は行使しないのですか?」と質問しました。しかし、被告群馬県は「いや・・・」と口を濁すだけでした。
原告は「あんな不法な会社の事業に、行政はホイホイとカネを出すのに、口は出さないというのは、本当に困るんですよね。依頼があれば我々オンブズマンがきちんと査定してやるんですけどね」と被告群馬県に言ったのですが、被告訴訟代理人の石原弁護士は「裁判の中でビシビシやってください」と言う始末でした。
次回、第3回弁論準備手続は7月18日(木)午後4時から前橋地裁3階の31号法廷で開催される予定です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考情報「裁判所が原告に提示した類似事件の判例」
*****補助金をめぐる住民訴訟の判例*****
<P1>
LU/DB判例秘書
―――――――――――――――――――――
【判例番号】L06850279
補助金返還履行請求事件
【事件番号】宇都宮地方裁判所判決/平成23年(行ウ)第7号
【判決日付】平成25年5月15日
【判示事項】地方自治体等の不正不嵩な行為を監視し,是正することを目的とする権利能力なき社団である原告が,被告宇都宮市長に対し,宇都宮市がA株式会社に交付した補助金が違法な支出であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき不当利得返還の請求をすることを求めた住民訴訟で,本件補助金の交付の適法他が争われた。原告は,本件補助金の交付が地方自治法2条14項,138条の2,232条の3に反して違法であるか又は公序良俗に反し無効であると主張したが,本件補助金の交付は,いずれにも違反しておらず適法であるとして,原告の請求を棄却した事例
【掲載前】LLI/DB判例秘書登載
主 文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は厚告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
(1)被告は,A株式会社に対し,9億7050万2380円及びこれに対する平成23年9月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
主文同旨
第2 事業の概要
本件は,地方公共団体等の不正不当な行為を監視し,これを是正することを目的として結成された権利能力なき社団である原告が.宇都宮市(以下「市」という。)がA株式会社(以下「A」という。)に対し平成23年3月28日に交付した補助金が違法な支出であるとして,地方自治体242条の2第1項4号に基づき,Aに不当利利得返還の請求をすることを市長である被告に対して求めて提起した住民訴訟である。
1 前提事実(当事者閔に争いがない事実)
(1)原告は,市内に住所を有する権利能力なき社団である。
被告は.普通地方公共団体である市の市長である。
(2)市は,平成18年4月1日,企業の市内への誘致及び域内再配置を促進するため,宇都宮市企業立地補助金交付娶綱(平成20年11月1日改正齢のもの.以
下,改正の前後を通じて「本件企業立地補助金要綱」という。)を制定した。
本件企業立地補助金要綱では,市内で事業を営む者又は営もうとする者で,市税を滞納していない者に対し,補助金を交付する旨が定められた。具体的には,補助金の種類として「基本部分」と「上乗せ部分」の2種顛が設けられ,前者については「取得した土地並びに新設し,若しくは移設する建物及びそれに伴って取得した設備の投下
<P2>
固定資産の額(「投下固定資産の取得に必要な費用の総額をいう」ものと定義されている。以下同じ。)に3%を乗じて得た額以内とし,1億円を限度額と」して,補助金を交付するものとされ,後者については「取得した土地の投下固定資産の額に25%を乗じて得た額及び取得した設備の投下固定資産の額に3%を乗じて得た合計の額以内とし,1億円を限度額と」して,補助金を交付するものとされた。
市は.平成20年11月1日,市の産業のリーディングプロジェクトと位置付けられている航空宇宙関連産業,ロボット関連産業,自動車関連産業及び情報通信関連産業について戦略的に市内への誘致を実現するため,本件企業立地補助金要綱を改正し,補助金の種類として,新たに「大規模上乗せ部分(基本部分の補助限度額を超えるものを対象とする。)」を設け,これらの産業を対象業種として,「取得した土地の投下固定資産の額に25%を乗じて得た額及び取得した設備の投下固定資産の額に3%を乗じて得た合計の額以内とし,9億円を限度額」を補助金として交付するものとした。
(3)Aは,平成21年9月17日,本件企業立地補助金要綱(平成20年11月1日改正後のもの。以下同じ。)に基づき,同要綱の対象地域内の土地(以下「本件土地」という。)を取得したとして,市長に対し,補助対象事業に係る土地取得等に関する届出書を提出した。そして,平成22年12月15日,市に対し.補助金の交付を申請した。
市は,平成23年3月28日,Aに対し,本件企業立地補助金要綱に基づき,9億7050万2380円を交付した(以下「本件補助金」という。)。
(4)原告は,平成23年5月23日,市の監査委員に対し,本件補助金に係る公金の支出は違法不当な支出であるとして,当該支出によって市が被った損害を補填するために必要な措置を講ずることを求めて,住民監査請求をした(以下「本件監査請求」という。)。
市の監査委員は,同年7月19日,本件監査請求は理由がないとして棄却したため,原告は,同年8月18日,本件訴えを提起した。
2 争点(本件補助金の交付の適法性)
(原告の主張)
(1)本件補助金の交付は地方自治法2条14項,138条の2,232条の3に反して違法であるか又は公序良俗に反し無効である。
ア 地方自治法2条14項違反について
市は.税収の大幅な減少により,平成22年度には普通交付税の支給団体となるほどに財政が厳しい状況にあった。このような状況にもかかわらず,市は.国内でも有数の巨大企業であるAに対し,極めて過大な補助金を交付した。すなわち,平成18年度から平成21年度までの間に本件企業立地要綱に基づき交付された補助金の総額は6億2751万円であり,1社に対して交付された補助金の額としては5000万円が最高であった。ところが,本件補助金は,従前の補助金総額の約1.5倍,1社に対する補助金としては従前の19倍以上という高額のものであった。
したがって,本件補助金の交付は,最少の経費で最大の効果を挙げるものとはいえず,地方自治法2条14項に違反する。
イ 地方自治法138条の2違反について
本件企業立地補助金要綱が引用する宇都宮市補助金等交付規則(以下「本件補助金交付規則」という。)においては,市長は,補助金の交付の申請があったときは,法令,予算等に照らしてその内容を審査し,必要に応じて行う現地調査等により,補助金を交付すべきものと認めるときに限り,補助金の交付を決定する旨が定められている。ところが,本件補助金の交付については,その決定に至るまでの検討経過を記載した稟議書や議事録等が存在しない。また,Aの施設の新設に伴い増加する税額を試算した際には,実際には市に転入する予定のない100名が市に転入することを前提とした計算をした。
したがって,市長は,本件補助金を交付するという結論ありきで,本件企業
<P3>
立地補助金要綱を改正し,同要綱が引用する本件補助金交付規則に定められた審査を行わずに本件補助金を交付したから,その交付は地方自治法138条の2に違反する。
ウ 地方自治法232条の3違反について
Aは,本件土地を購入し,同土地上に事業所を建設したものの,実際に操業を行っているのは,別会社であるB株式会社である。Aは,本件企業立地補助金要綱が定める補助対象者には当たらない。
また,B株式会社は,従前から,Aが購入した土地と道路を隔てて隣接する土地において事業を営んでいたところ,その事業敷地の拡張のために,Aが,本件土地を購入したにすぎない。本件補助金の交付によって,本件企業立地補助金要綱の目的である産業の振興や雇用機会の拡大がもたらされることはない。
したがって,本件補助金の交付は.本件企業立地補助金要綱に反するから,地方自治法232条の3に違反する。
エ 公序良俗違反について ・
仮に.地方自治法2条14項,138条の2又は232条の3に違反する行為が直ちに私法上無効とはならないとしても,かかる行為はそれ自体行政秩序という公序良俗に反する。また,本件補助金の交付は,市のAに対する一方的行為であるから,取引の安全等を考慮する必要もない。したがって,私法上も無効となる。
(2)よって,Aは法律上の原因なく本件補助金相当額の利益を受け,そのため
に市に損失を及ぼしたから,Aに本件補助金柑当額の不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める。
(被告の主張)
(1)本件補助金の交付は適法である。
ア 地方自治法2条14項適合性について
原告は本件補助金の金額が過大である旨主張するが,本件企業立地補助金要綱は平成20年11月1日の改正により,新たに「大規模上乗せ部分」が設けられ,補助額が大幅に引き上げられたから.それ以前に交付された補助金の金額と単純に比較することはできない。本件補助金の交付は,これによりB株式会社が市内へ新たに進出し,税収の増加や市内の中小企業等に対する波及効果による受注拡大郷を期待することができるから,地方自治法2条14項に適合する。
イ 地方自治法138条の2適合性について
本件補助金の交付に当たり,市は,Aから提出された補助金等交付申請書の審査と2回の現地調査に基づき課内協議を行い,その後に部内協議を行った。その上で,市長が事務専決規定に基づき支出負担行為の決裁を行ったのであるから,十分な検討を経て本件補助企が交付されたことは明らかである。また,税額の試算についても,本件補助金の交付を決定するに当たり収集した情報の一つにすぎないのであって,実際に住民が転入した否かを確認することまでは本件企業立地補助金要綱上求められていない。したがって,本件補助金の交付について、地方自治法138条の2に違反するところはない。
ウ 地方自治法232条の3適合性について
Aが購入した本件土地上で操業を行っている会社がB株式会社である点は認める。しかし,Aを中核とする〇〇グループは,研究開発,生産製造技術,販売サービスといった機能ごとに分社化し,グループ全体で役割を分担しながら事業を展開していることから,Aは,本件土地上で生産技術研究及び開発部門を担っているB株式会社と一体約に事業を抒っていると認められる。したがって,Aは,本件企業立地補助金要綱が定める補助対象者に該当する。
また,B株式会社は,これまで市内に事業所を所有していなかった企業であって,本件企業立地補助金要綱が定める基準を満たしている。産業の振興については,国内有数の企業であるB株式会社が市内へ進出することによるモビリティ産業の振興,税収の増加,市内の中小企業等への波及効果による地域産業全体のレベルアッブ,
<P4>
本件土地周辺の産業団地の価値又は地域のブランド力の向上等の様々な効果が見込まれ,さらには、市の産業の牽引役として市のモビリティ政策との連携による様々な事業展開により,地域産業の活性化に十分寄与することを考慮した。また,雇用機会の拡大については,必ずしも即時的なものである必要はない。
したがって,本件補助金の交付について本件企業立地補助金要綱に反する点はないから,地方自治法232条の3に違反しない。
エ 本件補助金の交付が公序良俗に反するという原告の主張は独自の見解でありて,失当である。
(2)よって,原告の請求には理由がない。
第3 当裁判所の判断
1 争点(案件補助金の交付の適法性)について
(1)当事者間に争いがない事実及び掲記の証拠並びに弁論の全趣旨によれば,
以下の事実が認められる。
ア Aは,平成21年9月17日,本件企業立地補助金要綱に基づき,本件土地を取得したとして,市長に対し,補助対象事業に係る土地取得等に関する届出書を提出した(甲2)。
なお,Aは,平成20年12月16日に本件土地を取得し,平成22年3月11日に本件土地上に事業所を完成させた。そして,Aの100%子会社であるB株式会社が,同年10月1日からこの事業所においてハイプリッド車及び燃料電池車の研究開発に関する事業を開始した。B株式会社の市内での操業は.今回が初めてであった(争いがない)。
イ 市は,平成22年2月18日,本件土地上へのB株式会社の進出に伴い増加する税額を試算した。この試算では,本件土地上に事業所が完成していなかったことから,市に隣接する芳賀町にある既存の研究施設の1平方メートル当たりの評価額や市内に100名が転入するとの仮定が用いられた(甲7)。
ウ 市の議会は.平成22年3月25日,予算科目「商工振興費企業誘数推進費の負担金,補助及び交付金」に10億5005万6000円の予算額を計上した平成22年度の一敗会計予算を可決した(甲2,乙9)。
エ Aは,平成22年12月15日,本件企業立地補助金要綱に基づく補助金の交付を申請した。この申請の際に,本件土地上の事業所における人材の雇用については,配置転換により100名を雇用する計画が明らかにされた(争いがない)。
オ 市は.平成22年12月21日,Aが市税を完納していることを確認した(甲2,乙9)。
市は,同月24日,本件士地上で事業所が操業しているかどうかについての現地調査を行った。この調査で,市は,本件土地上に事業所が建設され,稼働していることを確認した。その上で,Aによる上記エの申請には,本件企業立地補助金要綱において添付することが求められている工事請負契約書の写しの一部が提出されていなかったことから,市は,この書類が提出された後に引き続き書類審査を行っていくことを確認した(乙5)。
市は,平成23年2月18日,再び現地調査を行い,Aからあらかじめ提出されていた建築工事明細を基に,本件土地上の事業所の稼働と直接関係するが否かを確認し,Aが同事業所の新設のために支出した費用のうち本件企業立地補助金要綱に基づく補助金交付の対象となる費用を算定した(乙6)。
カ 市は,平成23年3月3日.平戒22年度の一般会計予算の予算科目「商工担興費企業誘致推進費の負担金,補助及び交付金」から9億7050万2380円を,本件企業立地補助金要綱に基づく補助金としてAへ交付する旨の決集をした(甲
4)。
市は,同月15日,上記決議に基づき,9億7050万2380円の支出命令をした(甲3)。
<P5>
市は,同月28日,Aに対し,口座振替の方法により,上記金額を支払った(甲3)。
(2)以上の事実に基づき.本件補助金の交付の適法性について検討する。
ア 地方自治法2条14項違反の有無について
本件企業立地補助金要綱は平成20年11月1日に改正され,補助限度額が,従来「基本部分」と「上乗せ部分」の各限度額を合算した2億円であったところ,「基本部分」と「大規模上乗せ部分(基本部分の補助限度額を超えるものを対象とする。)」の各限度額を合算した10億円にまで引き上げられたが,本件補助金は同要綱の定める限度額の範囲内で交付された。そして,前提事実のとおり、本件企業立地補助金要綱の改正は,市の産業のリーディングプロジヱクトを位置付けられている自動車関連産業等について戦略的に市内への誘致を実現するために行われたものであり,その目的には合理性が認められる。さらに,後記ウのとおり,本件補助金の交付は公益上の必要を欠くものではない。したがって,本件補助金の交付が,従前の交付金額に比して高額であることのみをもって,地方自治法2条14項に違反して違法なものであるということはできない。
イ 地方白洽法138条の2違反の有無について
本件企業立地補助金要綱1条は,「市の交付する企業立地補助金(以下「補助金」という。)については,宇都宮市補助金等交付規則(昭和41年規則第22号)
に規定するもののほか,この要綱に定めるところによる。」と定め,本件補助金交付規則4条は,補助金の交付の申請があったときは,市長は,法令,予算等に照らしてその内容を審査し,必要に応じて行う現地掴査等により,補助金を交付すべきものと認めるときは,補助金の交付を決定する旨を定めている。前記事実関係によれば,市は,Aによる本件補助金の交付の申請があったことから,Aが市税を滞納していないことを確認した上で,Aによる申請につき書類上の不備を是正させるとともに,2回の現地調査を行い.本件企業立地補助金要綱に基づく補助金交付の対象となる費用を算定したのであるから,本件企業立地補助金要綱に照らしてその内容を審査し,本件補助金を交付すべきものと判断したものと認められる。そして,本件補助金の交付額は,平成22年度の予算の範囲内であった。したがって、市長は、本件補助金交付規則に定められた審査を行った上で,本件補助金の交付を決定したものといえるから,本件補助金の交付が地方自治法138条の2に違反して違法なものであるということはできない。
なお,原告は,本件補助金の交付の決定に至るまでの検討経過を記載した稟議書や議事録等が存在しないことを理由に本件補助金交付規則が定める審査が行われていない旨を主張するが,上記のとおりの審査が行われたことは明らかであるから,原告の主張は失当である。また,Aによる本件補助金の交付の申請に先立ち,市は.本作土地上へのB株式会社の進出に伴い増加する税額を試算したが.この試算はAから補助金の交付の申請がされる前に推計により算出されたにすぎず,ここでの仮定が結果的に誤っていたからといって、直ちに補助金の交付の決定が違法になるわけではない。この仮定の誤りが地方自治法138条の2に違反するとの原告の主張は採用することができない。
ウ 地方自治法232条の3違反の有無について
前記事実関係によれば,本件企業立地補助金要綱の目的は,補助金を交付することにより企業の市内への誘致及び域内再配置を促進することにあるところ,Aに対する本件眸助金の交付により同社の100%子会社であるB株式会社を市内へ誘致するという目的が達せられたものといえる.したがって,A自らが換業を行っていないことのみをもって,同要綱が定める補助対象者に当たらないということはできない。そして,市は,国内有数の企業であるB株式会社が市内へ進出することによるモビリティ産業の振興,税収の増加,市内の中小企業等への波及効果による地域産業全体のレベルアッブ,本件土地周辺の産業団地の価値,地域のブランド力の向上等の様々な効果を見込み,さらには,市の産業の牽引役として市のモビリティ政策との連携による様々な事
<P6>
業展開により,地域産業の活性化に十分寄与するものと判断し,本件補助金の交付を決定したというのである(乙9,証人C)から,B株式会社を市内へ誘致するために補助金を交付することには公益上の必要があるとした市の判断は,不合理なものであったとはいえない。本件補助金の交付によってB株式会社の事業所における雇用機会の拡大がもたらされるものではなかったからといって,市が見込んだ上記効果が失われるわけではない。したがって,本件補助金の交付が公益上の必要を欠くということはできない。
(3)よって,本件補助金の交付は,地方自治法2条14項,138条の2及び232条の3のいずれにも違反しておらず,適法であるから,原告のその余の主張について判断するまでもなく.市はAに対して不当利得返還請求権を有しない。
2 以上によれば,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
宇都宮地方裁判所第2民事部
裁判長裁判官 岩坪朗彦
裁判官 佐々木淑江
裁判官篠原康治は,転補のため署名押印することができない。
裁判長裁判官 岩坪明彦
**********

↑第2回弁論準備手続が行われた6月15日の消印で速達で送られてきた被告第2準備書面等が同封された封筒。これでは間に合わないので、被告は原告に裁判所で副本を渡してきた。いかにも行政目線らしいやり方といえよう。↑
その後、裁判所から補助金の一部は既に支払われていることから、支払の有無で峻別してはどうか、と訴訟指揮があり、結局、2016年12月26日に、新たな住民訴訟の訴状を裁判所に提出したところ、今度は、同じ事件で2つの訴状が出ていると被告からイチャモンがつきました。
そのため、2017年3月10日の第4回口頭弁論で、最初の訴状を取り下げる羽目になりました。
そして、2017年3月15日に、出直し裁判の第1回口頭弁論が開かれ、同5月10日に第2回口頭弁論が行われましたが、また裁判所からイチャモンがつけられてしまい、法定外の受任裁判の形で、同5月22日に第1回弁論準備が行われ、6月15日に第2回弁論準備が行われたのです。
■裁判所は、補助金の未支払い分を「処分取消」ではなく「返還」、既支払い分を「差止」としてはどうか、と、本裁判ではなく5月22日に開かれた第1回弁論準備手続きの中で、提案してきました。
その結果、6月9日付原告準備書面(2)で、「主位的請求として、今までの請求を維持する。予備的請求として,裁判所の示唆するとおり,返還請求と差し止め請求とをあわせて請求する」と訴えの方針を変更する旨伝えてありました。
この裁判の弁論準備手続きの経緯は次のブログを参照ください。
○2017年5月11日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…当会欠席で5月11日に開催された関電工の前橋バイオマス発電を巡る2件の裁判↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2311.html#readmore
○2017年5月23日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス発電補助金訴訟をよそに着々と進む発電施設建設↓ ※5月22日の第1回弁論準備の報告
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2320.html#readmore
○2017年6月11日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金訴訟6.15弁論準備に向け原告準備書面(2)を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2341.html#readmore
■2019年6月15日(木)午後3時30分~開催の第2回弁論準備手続きに先立ち、被告から、前日の6月14日に、とんでもない内容の被告第2準備書面がFAXで届いたのです。
*****被告第2準備書面*****PDF ⇒ 201706152.pdf
平成28年(行ウ)第27号 住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求事件
原 告 小川賢 外1名
被 告 群馬県知事 大澤 正明
第2準備書面
平成29年6月14日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
被告訴訟代理人弁護士 石 原 栄 一
同 関 夕 三 郎
同 織 田 直 樹
同指定代理人 板 垣 哲 夫
同 束 田 健 靖
同 織 田 知 徳
同 武 藤 淳
同 鈴 木 利 光
同 石 井 米 吉
被告より本件補助金を支出する権限につき委任を受けた渋川森林事務所長は,平成29年5月31日,本件補助金交付決定に基づいて,前橋バイオマス燃料に対し,2億4150万円を支出した(乙1)。これにより,本件補助金4億8000万円全額の支出が完了したため,本件補助金支払い差止請求について,訴えの利益が失われた。
以上
*****証拠説明書(乙1)*****
平成28年(行ウ)第27号 住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求事件
原 告 小川賢 外1名
被 告 群馬県知事 大澤 正明
証拠説明書(乙1)
平成29年6月14日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
被告訴訟代理人
弁護士 石 原 栄 一
関 夕 三 郎
織 田 直 樹
●乙号証No.:1
○標目:支出回議書
○作成年月日(原本・写しの別):平成29年5月29日(写し)
○作成者:渋川森林事務所
○立証趣旨:渋川森林事務所長が前橋バイオマス燃料㈱に対し、残額2億4150万円を支出したこと
*****乙第1号証*****
支出回議書 平成29年度
決裁日 29.5.29
詩集命令者 桑原
本書のとおり支出したい。 平成29年5月29日
発議者 渋川森林 矢島裕子 内線番号( )
支出番号 35
内訳件数 1件
関連情報
所属名 041102 渋川森林
会計 01 一般
繰越 3 事故
債務
振替番号
支出科目: 款 : 07 環境森林費
項 : 07 林業振興費
目 : 03林業・木材産業振興対策費
事業:
節 : 19 負担金補助及び交付金
細節:
相手方: コード: 0287475331-00
郵便番号: 371-0241
住所: 前橋市苗ヶ島町2550番地2
氏名: 前橋バイオマス燃料(株)
受取人区分: 0 本人
命令回数 1
特例 0 特例無し
支出負担行為決議
訂正回数 0
支払方法 3 口座振替
支払区分 0 通常払
口座振替:金融機関 ■■■■■■■■■■■■
口座種別/口座番号 ■■■■■■■■■■■■
口座名義 ■■■■■■■■■■■■
請求書番号
支出額 ¥241,500,000*
控除金額 ¥0*
支払額 ¥241,500,000*
内容 190006-00 負担金補助及び交付金(過年度)
備考 27 林業・木材産業再生緊急対策事業補助金
支払予定日 平成29年5月31日
支払日指定 無
支出負担行為年月日 平成29年4月1日
支出負担行為額 241,500,000
既支出額
今回支出額 241,500,000
支出命令残額 0
控除金の内容:科目:
控除金名:
人数:
金額:
管理番号 ■■■■■■■■■■■
会計管理者(出納員)
発議者 ?
照合年月日・印 29.5.29
支払日 29.5.31
**********
まさに行政はここまでえげつなく、よくやれるものだ、と感心した次第です。なにしろ、裁判を先延ばしにした挙句に、全額補助金をチップ工場の建設につぎ込ませた上に、裁判する意味がなくなっている、などと原告を挑発するかのような書き方だからです。
■こうして、仰天の連続の中で、第2回弁論準備手続が開かれたのでした。
これまでの法廷でのやりとりと異なり、前橋地裁3階31号法廷は、いわゆる「ラウンドテーブル」と呼ばれる配置になっていて、楕円形の机を囲んで、中央に受命裁判官が1名座り、その右手側に原告が、左手側に被告が座ります。
このため、割合リラックスした雰囲気の下で、協議が行える環境にあります。そこで、裁判官が入室するまで、被告の群馬県職員らと雑談をしました。すると職員らの発言の中で気になったことがあります。それらを列挙してみます。
(1)この補助対象は発電所ではなく、チップ工場のほうなので、工場の建設が終われば、対象工事、つまり対象となる整備工事が終わったから、全額支払った。
(2)当然、補助事業については工事の結果を確認してから支払った。
(3)トーセンが自慢する自社開発という油圧プレスの存在も確認した。
(4)こうした機材は入札ではなく、合見積で比較はしており、随契の言い値で査定しているわけではない。
(5)自然乾燥のほうがコストが安いため、木材のストック期間についても事業主体と考慮している。
(6)当初、プレス機の導入計画はなかったが、最終的に、搬入木材の全量をプレス機にかけて脱水するわけではない。
(7)チップ工場のほうは、環境アセスメントについて関知しない。また、環境アセスメントは、運用のところで定めている。
(8)フォークリストも全部随契となっているが、その理由について、いちおう事業者から聞き取りは行っている。
(9)フォークリフトは1社限定ではないと思う。1社以外の随契もあり、合見積をとっている。
(10)4.8億円の補助金だけでなく、事業者の自己負担として3.2億円もある。さらにトータル8億円以外の事業者の自己負担もある。だから、4.8億円の補助金だけでチップ工場の建設費が全部賄えるわけではない。
(11)事業者の支払いが一応完了したので、補助金を払ってやらないと債務不履行になってしまうので、支払いをしてやらないといけない。
そうこうしているうちに、午後4時が迫りました。受命裁判官の佐藤裁判官が入室する時間です。裁判官の入室前に、森山書記官から「原告に確認したいが、被告第2準備書面などをもう受け取ったのか」と聞かれました。原告は、3階のエレベーターホールで待機しているときに、副本を被告から渡されていたので「はい」と答えました。
■すると午後4時になり、裁判官が入場してきて、第2回弁論準備手続きが開始されました。
裁判官:それぞれの第2回の弁論準備。原告のほうから原告準備書面(2)が6月9日に出てきた。被告のほうからも第2準備書面ということで6月14日付に書面が出てきたが、これはきょう届いたのか?
原告:ええ、いまさっきいただきました。
裁判官:ああそうか。これはまだ、本日のところは陳述扱いとせずにもう少しちょっと聞きたいことがあったので、本日は、拝見はしているが陳述はしないという扱いにしたい。まず原告のほうだが、主位的請求として今までの請求を維持するというのは、今現状とくに訴えの変更はされていないので、4.8億円の差止を維持するという趣旨でよいのか?
原告:差止ではなくて、取消ということで、最終的にしたが、その場合は変更申立をしなければいけないのでしょうか?
裁判官:それはそうだが、取消訴訟だと前回申し上げた通り、処分性ということが問題になる。つまり、行政処分たるという、そういう行為に当たるかどうかということが問題にある、その点について別途主張してもらうことになる。それでもこれを維持するのか?結論的には結局、この処分性・・・
原告:いろいろ文献を見ました。いろいろな判例があって、処分性について認めてないというのが確かに多い。殆どがそうなっている。だけど、講学的に言ったらそうなるのかもしれないけれど、だけど、常識的に納税者の立場で言うとどうも納得できない。それを主張しても、だけど前例主義、判例主義によって取り合ってもらえないのでしょうか?時間の無駄ということになるのでしょうか?
裁判官:取消を求める意味がどこにあるのかということになる。今回、例えば差止、支払われたものの返還を求めるということ。予備的に求めるといっているが・・・。
原告:ええ。差止というのは、もとより(補助金が支払われる以前に我々は)差止で提訴した。こういった不合理な環境問題は、いろいろな関係から税金の無駄遣いでもあるし、そういうものは本来これが(県の上層部に)上程されて予算化されて、それが議会で決まって、そのあと具体的な支払いのいろいろな過程があったわけなんでしょうが、その点で我々は差し止めたいという気持ちで、ずっときました。だけど、こうやって係争しているうちに、どんどんどんどん時間が経過して、挙句の果てには「もう全部払ってしまった」という。こういうふうになった時に、最初に差し止めということを、維持していくのはどうなのでしょうか?この間の裁判所の示唆でも、なんというか、実際には既に支払われた分は差止という定義が当てはまらない、というふうにコメントをいただきましたが。
裁判官:差止にするか返還にするかというのは、また別の話であって、処分、交付決定の処分を止めるという今話になっている。その処分の取消しを求める意味があるのかという話だ。今現在は、どうやら全部、例えば支払われたということで、それを返還を求めるということだよね。そういうことになるよね。
原告:この間、そのような示唆をいただきましたので。
裁判官:だからその処分に当たるかどうかというのは、やってみなければ分からないが、それをわざわざ争う意味というのがどこにあるのかなあ、と思うわけだ。その争点を出さなくても、別途返還訴訟だけで、その、もし勝てばだが、勝てば、要するに補助金は返せという話になるわけだ。
原告:お金の部分と処分自体が、その、正規の手続きというのか、まあ環境問題だとかいろいろな部分で、それで処分自体が、まあ少し不当性があるのではないか、おカネではなくて、その罪というのかね。処分に至る・・
裁判官:その交付決定、およびその交付手続きの瑕疵、ちょっとその理由はわかるが瑕疵があるんだということで、無効だということで返せと言っているわけでだから、それは処分にせよ返還にせよ問題になるわけだ。ただ、処分の取消ということになると、まさしくこの処分が、いわゆる法律に定める処分。一定の、まあ、処分という言葉を使うが、その中でも「一定の」処分でしか対象にならないという訴訟の類型なので、その形式的な議論をしなければならないことになる。その形式的な議論をしなくても、実際的に、無効かどうかはストレートに判断できるわけなので、わざわざ形式論を挟む必要があるのかということだよね。
原告:確かに補助金の場合に、いろいろな事例があって、今回の事案は、ただで(補助金を事業者に)くれてやるんだから、いわゆる贈与みたいな感じだから処分性がどうのこうのというのが確かに判例にバンバン出てくる。そう言われれば確かにそうだが。ということは、もう返還請求一本でやったらどうかという、効率がいいというわけでしょうか?
裁判官:そのほうが争点も少なくて済むし、立証の負担も減るよね。審理も早く進むし。その、勿論、その訴訟を決めるのは原告の自由だが、ただ、このように処分の取消しという構成をとる必要があるのかと言われると裁判所には疑問符が付く。だから返還訴訟を端的に求めればよいのではないのか、というような話だ。
原告:この処分一本というのは今日初めてでてきた。ということになるので、ちょっとすぐ判断というのがあったが、これまでは半額くらい出ていて、半額残っているようなイメージだったと思っていたが。
裁判官:それはまた別の話でその次の話になる、そうしたうえで例えば、まあ、じゃあ返還にしますという話になったときに、どうやら今回被告から出てきた第2準備書面によると、もうすべて払い終えたという話なので、その差し止めを求める理由はないわけだ。だから、4億8000万円全額返せという訴訟にすれば足りるのではないかという理解で裁判所はいる。勿論、・・・・そうですね。
原告:ちょっと、第3者の意見も聞いて確認にします。早急に確認して、今の線で決め打ちでやるかどうかを決めたいと思う。ちょっと被告のほうにもあれだが、例えば、全く関係ないものだが、こう裁判例でこう言ったまあ、請求の趣旨、まあ棄却されてしまった判例であっても、まあ請求の趣旨というのはこういう立て方があるよという、全く別の関係のない裁判だが、もう(原告に)参考としてお渡ししてもよろしいかな?
被告:はい、はい。結構です、結構です。
裁判官:例えば、これ全く関係のない訴状だが、見ていただきたいのは、これ。(と言って、被告に気を使いながら原告にコピーをくれたのがこれ↓)
※宇都宮地方裁判所平成25年5月15日判決/平成23年(行ウ)第7号補助金返還履行請求事件: PDF ⇒ 20170615n.pdf
原告:補助金返還履行請求・・・23年、最近ですね、宇都宮で。
裁判長:ええ。当事者の求めた事実及び理由の求めた裁判というところがあって、1原告(1)で被告はA株式会社に対して9億7050万2380円、及びこれに対する平成23年9月14日から支払い済みまで年5分の割合になるということで、まあこれ、補助金の交付が違法だというふうに言って提起した不当利得返還請求をすることを求めた訴訟だが、こういった、立てるとすれば、こういった請求の趣旨になろうかと思う。一応参考にということでご案内させていただく。では、一度検討していただいて、、仮に今言った返還訴訟一本でなるのであれば、訴えの変更申立書を書面で提出していただくことになる。で、今現在は差止め、4億8000万円の支出をしてはならないという差止めを求める形なっているので、これを・・・。
原告:このように変更しますという申立書ですね?
裁判官:はい。ちょっとその形式論を整えたうえで、もう一度弁論に戻して、その中身の話をしたほうがよろしいかと思うので、もう一期日、すまないが入れさせていただいてよろしいか?そこで(原告の主張を)確認させていただいて、まあ弁論に戻すという進行にしたいと思うが、よろしいか?
原告:ええ、いいですすよ。
裁判官:ちょっと前回、気にされていた訴額の話ですが、あれはおそらく住民訴訟だと、返還を求める額にかかわらず、一律の金額、訴額160万なので、あまりその、差止めとか取消しにするか、今回の返還訴訟にするかで訴額の問題は、そんなに変わってくるという話ではないかと思うので、そこは、あまり気にされなくてもよろしいのではないかと思う。
原告:はい。
裁判官:それから返還、4億8000万円の返還を求める返還を求めるからと言って4億8000万円分の印紙を支払うということではないわけだ。
原告:ええ、住民訴訟のくくりだと思います。
裁判官:よろしいかね。ちょっとそれでは検討して訴えの変更申立書を出してもらうことになるが、どのくらいで?
原告:えーと、1か月以内にはやりたいと思いますけど。
裁判官:1か月以内?
原告:だから3週間で、1週間で次の、こういう期日を、1か月後に設定していただけばですね。こちらとしてはそれを希望しますけども、ちょうど夏休みとか、それはまだ7月だから関係ないか。
裁判官:書面を出してもらうのが3週間ということですね?よろしですか被告は?
被告:はい。
裁判官:それでは、1か月後ですので、まあ7月の・・・14日とかはいかがか?
原告:異存ありません。
被告:これ、書面が出る日?
原告:書面はその1週間前に出します。
被告:14日は差し支えます。
裁判官:それでは、18日(火)はいかがですか?
被告:午後の遅い時間がありがたいんです。
裁判官:同じくらいの4時がよろしいか?
被告:ええ。
原告:差し支えございません。
裁判官:では7月18日(火)火曜日の4時ということで、弁論準備もう1回やらさせていただきます。書面は(7月)7日ぐらいまでは出るということで聞いてよろしいかね?
原告:はい。
裁判官:では、そこを整えさせていただいて弁論に戻して、まあ、審理を進めるという方向で考えております。よろしいですかね?
被告:はい。
原告:まあ、あのね、(この計画は)どんどん進んでしまっているので、まあ皆さん現場に行かないでしょう。(といって、原告が用意してきた現場の現況写真を裁判官と被告に配布した)
裁判官:まあ、弁論に戻してからまた証拠としていただくから。
原告:ですから、参考資料ですよ。
裁判官:はいわかりました。
■以上のやり取りが約13分間にわたって交わされました。弁論準備手続のあと、原告は被告に「まだ、塀ができていないが、あれは補助金の対象ではないのでしょうか?8億円の補助金対象工事に入っていないのでしょうか?」と質問したところ、被告は「そうだ」と言いました。
肝心の防音壁が後回しになっていることについて、別の情報では、トーセンがお粗末な塀を計画していたので、関電工が見直しをしているらしい、という見方もあります。いずれにしても、地元説明会で「最初に防音壁を作る」といった関電工の説明が反故になっているのは確かです。
さらに原告は被告に対して「事業者の関電工らは、施設内部を全くマル秘にしているが、納税者である県民らは、補助金の納税もしているのだから、関電工ら事業者に対して、施設内部を県民に見せてやってくれ、という、そういう行政権限は行使しないのですか?」と質問しました。しかし、被告群馬県は「いや・・・」と口を濁すだけでした。
原告は「あんな不法な会社の事業に、行政はホイホイとカネを出すのに、口は出さないというのは、本当に困るんですよね。依頼があれば我々オンブズマンがきちんと査定してやるんですけどね」と被告群馬県に言ったのですが、被告訴訟代理人の石原弁護士は「裁判の中でビシビシやってください」と言う始末でした。
次回、第3回弁論準備手続は7月18日(木)午後4時から前橋地裁3階の31号法廷で開催される予定です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考情報「裁判所が原告に提示した類似事件の判例」
*****補助金をめぐる住民訴訟の判例*****
<P1>
LU/DB判例秘書
―――――――――――――――――――――
【判例番号】L06850279
補助金返還履行請求事件
【事件番号】宇都宮地方裁判所判決/平成23年(行ウ)第7号
【判決日付】平成25年5月15日
【判示事項】地方自治体等の不正不嵩な行為を監視し,是正することを目的とする権利能力なき社団である原告が,被告宇都宮市長に対し,宇都宮市がA株式会社に交付した補助金が違法な支出であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき不当利得返還の請求をすることを求めた住民訴訟で,本件補助金の交付の適法他が争われた。原告は,本件補助金の交付が地方自治法2条14項,138条の2,232条の3に反して違法であるか又は公序良俗に反し無効であると主張したが,本件補助金の交付は,いずれにも違反しておらず適法であるとして,原告の請求を棄却した事例
【掲載前】LLI/DB判例秘書登載
主 文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は厚告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
(1)被告は,A株式会社に対し,9億7050万2380円及びこれに対する平成23年9月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
主文同旨
第2 事業の概要
本件は,地方公共団体等の不正不当な行為を監視し,これを是正することを目的として結成された権利能力なき社団である原告が.宇都宮市(以下「市」という。)がA株式会社(以下「A」という。)に対し平成23年3月28日に交付した補助金が違法な支出であるとして,地方自治体242条の2第1項4号に基づき,Aに不当利利得返還の請求をすることを市長である被告に対して求めて提起した住民訴訟である。
1 前提事実(当事者閔に争いがない事実)
(1)原告は,市内に住所を有する権利能力なき社団である。
被告は.普通地方公共団体である市の市長である。
(2)市は,平成18年4月1日,企業の市内への誘致及び域内再配置を促進するため,宇都宮市企業立地補助金交付娶綱(平成20年11月1日改正齢のもの.以
下,改正の前後を通じて「本件企業立地補助金要綱」という。)を制定した。
本件企業立地補助金要綱では,市内で事業を営む者又は営もうとする者で,市税を滞納していない者に対し,補助金を交付する旨が定められた。具体的には,補助金の種類として「基本部分」と「上乗せ部分」の2種顛が設けられ,前者については「取得した土地並びに新設し,若しくは移設する建物及びそれに伴って取得した設備の投下
<P2>
固定資産の額(「投下固定資産の取得に必要な費用の総額をいう」ものと定義されている。以下同じ。)に3%を乗じて得た額以内とし,1億円を限度額と」して,補助金を交付するものとされ,後者については「取得した土地の投下固定資産の額に25%を乗じて得た額及び取得した設備の投下固定資産の額に3%を乗じて得た合計の額以内とし,1億円を限度額と」して,補助金を交付するものとされた。
市は.平成20年11月1日,市の産業のリーディングプロジェクトと位置付けられている航空宇宙関連産業,ロボット関連産業,自動車関連産業及び情報通信関連産業について戦略的に市内への誘致を実現するため,本件企業立地補助金要綱を改正し,補助金の種類として,新たに「大規模上乗せ部分(基本部分の補助限度額を超えるものを対象とする。)」を設け,これらの産業を対象業種として,「取得した土地の投下固定資産の額に25%を乗じて得た額及び取得した設備の投下固定資産の額に3%を乗じて得た合計の額以内とし,9億円を限度額」を補助金として交付するものとした。
(3)Aは,平成21年9月17日,本件企業立地補助金要綱(平成20年11月1日改正後のもの。以下同じ。)に基づき,同要綱の対象地域内の土地(以下「本件土地」という。)を取得したとして,市長に対し,補助対象事業に係る土地取得等に関する届出書を提出した。そして,平成22年12月15日,市に対し.補助金の交付を申請した。
市は,平成23年3月28日,Aに対し,本件企業立地補助金要綱に基づき,9億7050万2380円を交付した(以下「本件補助金」という。)。
(4)原告は,平成23年5月23日,市の監査委員に対し,本件補助金に係る公金の支出は違法不当な支出であるとして,当該支出によって市が被った損害を補填するために必要な措置を講ずることを求めて,住民監査請求をした(以下「本件監査請求」という。)。
市の監査委員は,同年7月19日,本件監査請求は理由がないとして棄却したため,原告は,同年8月18日,本件訴えを提起した。
2 争点(本件補助金の交付の適法性)
(原告の主張)
(1)本件補助金の交付は地方自治法2条14項,138条の2,232条の3に反して違法であるか又は公序良俗に反し無効である。
ア 地方自治法2条14項違反について
市は.税収の大幅な減少により,平成22年度には普通交付税の支給団体となるほどに財政が厳しい状況にあった。このような状況にもかかわらず,市は.国内でも有数の巨大企業であるAに対し,極めて過大な補助金を交付した。すなわち,平成18年度から平成21年度までの間に本件企業立地要綱に基づき交付された補助金の総額は6億2751万円であり,1社に対して交付された補助金の額としては5000万円が最高であった。ところが,本件補助金は,従前の補助金総額の約1.5倍,1社に対する補助金としては従前の19倍以上という高額のものであった。
したがって,本件補助金の交付は,最少の経費で最大の効果を挙げるものとはいえず,地方自治法2条14項に違反する。
イ 地方自治法138条の2違反について
本件企業立地補助金要綱が引用する宇都宮市補助金等交付規則(以下「本件補助金交付規則」という。)においては,市長は,補助金の交付の申請があったときは,法令,予算等に照らしてその内容を審査し,必要に応じて行う現地調査等により,補助金を交付すべきものと認めるときに限り,補助金の交付を決定する旨が定められている。ところが,本件補助金の交付については,その決定に至るまでの検討経過を記載した稟議書や議事録等が存在しない。また,Aの施設の新設に伴い増加する税額を試算した際には,実際には市に転入する予定のない100名が市に転入することを前提とした計算をした。
したがって,市長は,本件補助金を交付するという結論ありきで,本件企業
<P3>
立地補助金要綱を改正し,同要綱が引用する本件補助金交付規則に定められた審査を行わずに本件補助金を交付したから,その交付は地方自治法138条の2に違反する。
ウ 地方自治法232条の3違反について
Aは,本件土地を購入し,同土地上に事業所を建設したものの,実際に操業を行っているのは,別会社であるB株式会社である。Aは,本件企業立地補助金要綱が定める補助対象者には当たらない。
また,B株式会社は,従前から,Aが購入した土地と道路を隔てて隣接する土地において事業を営んでいたところ,その事業敷地の拡張のために,Aが,本件土地を購入したにすぎない。本件補助金の交付によって,本件企業立地補助金要綱の目的である産業の振興や雇用機会の拡大がもたらされることはない。
したがって,本件補助金の交付は.本件企業立地補助金要綱に反するから,地方自治法232条の3に違反する。
エ 公序良俗違反について ・
仮に.地方自治法2条14項,138条の2又は232条の3に違反する行為が直ちに私法上無効とはならないとしても,かかる行為はそれ自体行政秩序という公序良俗に反する。また,本件補助金の交付は,市のAに対する一方的行為であるから,取引の安全等を考慮する必要もない。したがって,私法上も無効となる。
(2)よって,Aは法律上の原因なく本件補助金相当額の利益を受け,そのため
に市に損失を及ぼしたから,Aに本件補助金柑当額の不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める。
(被告の主張)
(1)本件補助金の交付は適法である。
ア 地方自治法2条14項適合性について
原告は本件補助金の金額が過大である旨主張するが,本件企業立地補助金要綱は平成20年11月1日の改正により,新たに「大規模上乗せ部分」が設けられ,補助額が大幅に引き上げられたから.それ以前に交付された補助金の金額と単純に比較することはできない。本件補助金の交付は,これによりB株式会社が市内へ新たに進出し,税収の増加や市内の中小企業等に対する波及効果による受注拡大郷を期待することができるから,地方自治法2条14項に適合する。
イ 地方自治法138条の2適合性について
本件補助金の交付に当たり,市は,Aから提出された補助金等交付申請書の審査と2回の現地調査に基づき課内協議を行い,その後に部内協議を行った。その上で,市長が事務専決規定に基づき支出負担行為の決裁を行ったのであるから,十分な検討を経て本件補助企が交付されたことは明らかである。また,税額の試算についても,本件補助金の交付を決定するに当たり収集した情報の一つにすぎないのであって,実際に住民が転入した否かを確認することまでは本件企業立地補助金要綱上求められていない。したがって,本件補助金の交付について、地方自治法138条の2に違反するところはない。
ウ 地方自治法232条の3適合性について
Aが購入した本件土地上で操業を行っている会社がB株式会社である点は認める。しかし,Aを中核とする〇〇グループは,研究開発,生産製造技術,販売サービスといった機能ごとに分社化し,グループ全体で役割を分担しながら事業を展開していることから,Aは,本件土地上で生産技術研究及び開発部門を担っているB株式会社と一体約に事業を抒っていると認められる。したがって,Aは,本件企業立地補助金要綱が定める補助対象者に該当する。
また,B株式会社は,これまで市内に事業所を所有していなかった企業であって,本件企業立地補助金要綱が定める基準を満たしている。産業の振興については,国内有数の企業であるB株式会社が市内へ進出することによるモビリティ産業の振興,税収の増加,市内の中小企業等への波及効果による地域産業全体のレベルアッブ,
<P4>
本件土地周辺の産業団地の価値又は地域のブランド力の向上等の様々な効果が見込まれ,さらには、市の産業の牽引役として市のモビリティ政策との連携による様々な事業展開により,地域産業の活性化に十分寄与することを考慮した。また,雇用機会の拡大については,必ずしも即時的なものである必要はない。
したがって,本件補助金の交付について本件企業立地補助金要綱に反する点はないから,地方自治法232条の3に違反しない。
エ 本件補助金の交付が公序良俗に反するという原告の主張は独自の見解でありて,失当である。
(2)よって,原告の請求には理由がない。
第3 当裁判所の判断
1 争点(案件補助金の交付の適法性)について
(1)当事者間に争いがない事実及び掲記の証拠並びに弁論の全趣旨によれば,
以下の事実が認められる。
ア Aは,平成21年9月17日,本件企業立地補助金要綱に基づき,本件土地を取得したとして,市長に対し,補助対象事業に係る土地取得等に関する届出書を提出した(甲2)。
なお,Aは,平成20年12月16日に本件土地を取得し,平成22年3月11日に本件土地上に事業所を完成させた。そして,Aの100%子会社であるB株式会社が,同年10月1日からこの事業所においてハイプリッド車及び燃料電池車の研究開発に関する事業を開始した。B株式会社の市内での操業は.今回が初めてであった(争いがない)。
イ 市は,平成22年2月18日,本件土地上へのB株式会社の進出に伴い増加する税額を試算した。この試算では,本件土地上に事業所が完成していなかったことから,市に隣接する芳賀町にある既存の研究施設の1平方メートル当たりの評価額や市内に100名が転入するとの仮定が用いられた(甲7)。
ウ 市の議会は.平成22年3月25日,予算科目「商工振興費企業誘数推進費の負担金,補助及び交付金」に10億5005万6000円の予算額を計上した平成22年度の一敗会計予算を可決した(甲2,乙9)。
エ Aは,平成22年12月15日,本件企業立地補助金要綱に基づく補助金の交付を申請した。この申請の際に,本件土地上の事業所における人材の雇用については,配置転換により100名を雇用する計画が明らかにされた(争いがない)。
オ 市は.平成22年12月21日,Aが市税を完納していることを確認した(甲2,乙9)。
市は,同月24日,本件士地上で事業所が操業しているかどうかについての現地調査を行った。この調査で,市は,本件土地上に事業所が建設され,稼働していることを確認した。その上で,Aによる上記エの申請には,本件企業立地補助金要綱において添付することが求められている工事請負契約書の写しの一部が提出されていなかったことから,市は,この書類が提出された後に引き続き書類審査を行っていくことを確認した(乙5)。
市は,平成23年2月18日,再び現地調査を行い,Aからあらかじめ提出されていた建築工事明細を基に,本件土地上の事業所の稼働と直接関係するが否かを確認し,Aが同事業所の新設のために支出した費用のうち本件企業立地補助金要綱に基づく補助金交付の対象となる費用を算定した(乙6)。
カ 市は,平成23年3月3日.平戒22年度の一般会計予算の予算科目「商工担興費企業誘致推進費の負担金,補助及び交付金」から9億7050万2380円を,本件企業立地補助金要綱に基づく補助金としてAへ交付する旨の決集をした(甲
4)。
市は,同月15日,上記決議に基づき,9億7050万2380円の支出命令をした(甲3)。
<P5>
市は,同月28日,Aに対し,口座振替の方法により,上記金額を支払った(甲3)。
(2)以上の事実に基づき.本件補助金の交付の適法性について検討する。
ア 地方自治法2条14項違反の有無について
本件企業立地補助金要綱は平成20年11月1日に改正され,補助限度額が,従来「基本部分」と「上乗せ部分」の各限度額を合算した2億円であったところ,「基本部分」と「大規模上乗せ部分(基本部分の補助限度額を超えるものを対象とする。)」の各限度額を合算した10億円にまで引き上げられたが,本件補助金は同要綱の定める限度額の範囲内で交付された。そして,前提事実のとおり、本件企業立地補助金要綱の改正は,市の産業のリーディングプロジヱクトを位置付けられている自動車関連産業等について戦略的に市内への誘致を実現するために行われたものであり,その目的には合理性が認められる。さらに,後記ウのとおり,本件補助金の交付は公益上の必要を欠くものではない。したがって,本件補助金の交付が,従前の交付金額に比して高額であることのみをもって,地方自治法2条14項に違反して違法なものであるということはできない。
イ 地方白洽法138条の2違反の有無について
本件企業立地補助金要綱1条は,「市の交付する企業立地補助金(以下「補助金」という。)については,宇都宮市補助金等交付規則(昭和41年規則第22号)
に規定するもののほか,この要綱に定めるところによる。」と定め,本件補助金交付規則4条は,補助金の交付の申請があったときは,市長は,法令,予算等に照らしてその内容を審査し,必要に応じて行う現地掴査等により,補助金を交付すべきものと認めるときは,補助金の交付を決定する旨を定めている。前記事実関係によれば,市は,Aによる本件補助金の交付の申請があったことから,Aが市税を滞納していないことを確認した上で,Aによる申請につき書類上の不備を是正させるとともに,2回の現地調査を行い.本件企業立地補助金要綱に基づく補助金交付の対象となる費用を算定したのであるから,本件企業立地補助金要綱に照らしてその内容を審査し,本件補助金を交付すべきものと判断したものと認められる。そして,本件補助金の交付額は,平成22年度の予算の範囲内であった。したがって、市長は、本件補助金交付規則に定められた審査を行った上で,本件補助金の交付を決定したものといえるから,本件補助金の交付が地方自治法138条の2に違反して違法なものであるということはできない。
なお,原告は,本件補助金の交付の決定に至るまでの検討経過を記載した稟議書や議事録等が存在しないことを理由に本件補助金交付規則が定める審査が行われていない旨を主張するが,上記のとおりの審査が行われたことは明らかであるから,原告の主張は失当である。また,Aによる本件補助金の交付の申請に先立ち,市は.本作土地上へのB株式会社の進出に伴い増加する税額を試算したが.この試算はAから補助金の交付の申請がされる前に推計により算出されたにすぎず,ここでの仮定が結果的に誤っていたからといって、直ちに補助金の交付の決定が違法になるわけではない。この仮定の誤りが地方自治法138条の2に違反するとの原告の主張は採用することができない。
ウ 地方自治法232条の3違反の有無について
前記事実関係によれば,本件企業立地補助金要綱の目的は,補助金を交付することにより企業の市内への誘致及び域内再配置を促進することにあるところ,Aに対する本件眸助金の交付により同社の100%子会社であるB株式会社を市内へ誘致するという目的が達せられたものといえる.したがって,A自らが換業を行っていないことのみをもって,同要綱が定める補助対象者に当たらないということはできない。そして,市は,国内有数の企業であるB株式会社が市内へ進出することによるモビリティ産業の振興,税収の増加,市内の中小企業等への波及効果による地域産業全体のレベルアッブ,本件土地周辺の産業団地の価値,地域のブランド力の向上等の様々な効果を見込み,さらには,市の産業の牽引役として市のモビリティ政策との連携による様々な事
<P6>
業展開により,地域産業の活性化に十分寄与するものと判断し,本件補助金の交付を決定したというのである(乙9,証人C)から,B株式会社を市内へ誘致するために補助金を交付することには公益上の必要があるとした市の判断は,不合理なものであったとはいえない。本件補助金の交付によってB株式会社の事業所における雇用機会の拡大がもたらされるものではなかったからといって,市が見込んだ上記効果が失われるわけではない。したがって,本件補助金の交付が公益上の必要を欠くということはできない。
(3)よって,本件補助金の交付は,地方自治法2条14項,138条の2及び232条の3のいずれにも違反しておらず,適法であるから,原告のその余の主張について判断するまでもなく.市はAに対して不当利得返還請求権を有しない。
2 以上によれば,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
宇都宮地方裁判所第2民事部
裁判長裁判官 岩坪朗彦
裁判官 佐々木淑江
裁判官篠原康治は,転補のため署名押印することができない。
裁判長裁判官 岩坪明彦
**********