■(株)佐藤建設工業が、盛り土材などその販売する全て建設資材に、大同特殊鋼由来の猛毒スラグを無秩序に混ぜて群馬県内に広く不法投棄した問題で、国土交通省・群馬県県土整備部・渋川市などの工事実施主体は、「鉄鋼スラグ連絡会議」という廃棄物行政について“何の決定権限”もないのに、ほぼ“スラグを撤去せず放置”するという無責任極まりない対策方針を打ち出しました。そして、不法廃棄物に認定された有害スラグを廃棄物処理法によらず、超法規的に、強引に問題解決してしまおうとしています。(スラグ連絡会議については末尾参照)
鉄鋼スラグ連絡会議では、渋川市が国土交通省と共に、スラグを撤去せずアスファルトで蓋をすることを強力に推し進めた?ことが漏れ伝わってきています。その渋川市では、先日市長選挙が行われ、新たな市長が誕生した模様です。市長交代劇が、大同有害スラグ問題にどう影響するか、当会ならずとも関心がもたれるところです。さっそく新聞報道を見てまいりましょう。
**********2017年9月14日毎日新聞地方版
高木・市長 初登庁/群馬
渋川市長選で初当選した高木勉市長(65)が13日、初登庁した。市役所本庁舎駐車場であった式典で、高木市長は、集まった職員と支持者ら約500人に「市民に開かれ、奉仕する市役所にしたい。職員の皆さんは市民のために思い切りバットを振ってください。空振り三振は評価します。失敗したら全て私が責任を取ります」と決意を語った。
高木市長は初登庁後、記者会見で「人口減少危機突破が当面、最大の仕事。対策本部を庁内に設置して、企業誘致を中心に解決策を模索したい」との考えを述べた。公約に掲げた保育料の完全無料化については「財源を精査して来年度当初予算に向けて検討したい」とした。
このほか「市長選などを通じて身近な生活環境に対する市民の不満が強いと感じた」として、出先機関の各行政センターに権限と財源を与えて、要望に迅速に応える体制に変えていきたいとした。【吉田勝】
**********
■どうやら、渋川新市長の関心事は「人口減少」が最大の関心事のようですが、続いて「身近な生活環境に対する市民の不満が強いと感じた」と述べ、生活環境にも関心があるようです。この生活環境について新市長が正しい理解をしていることを切に願うところですが、まずは環境基本法などを読み、「生活環境」とはどのような定義であるのか、よくよく勉強して欲しいものです。
当会は、渋川市において最優先のテーマである「生活環境」の喫緊の課題としては、大同有害スラグ不法投棄問題だと考えております。大同スラグは生活環境である土壌を汚染するおそれがあり、雨水により水質汚染にまで発展するおそれがあります。すなわち、土壌と共に地下水も「生活環境」であることを特に認識しなければなりません。さすれば、大同スラグを撤去せずアスファルトで蓋をすることが、いかに間違った施策であるかが分かるはずです。
■渋川新市長の初の記者会見で「生活環境」に触れられたことで、大同有害スラグ問題に進展があるか期待したいところです。ところが、その新市長就任式で前代未聞の珍事が繰り広げられ、スラグ問題の行く先に暗雲がまたもや垂れ込めそうだ、という情報が当会にもたらされました。
市長に当選すると、初登庁する際に就任式が行われます。その模様を見ていきましょう。動画サイトYouTubeに動画がアップされていますので司会のアナウンスを紹介します。
※動画はこちら→https://youtu.be/kZHlHWYtK0A
**********
司会:渋川市長高木勉初登庁式・就任式を開式いたします。

↑司会:まず初めに、須田まさる渋川市議会議長からご祝辞をお願いいたします。↑
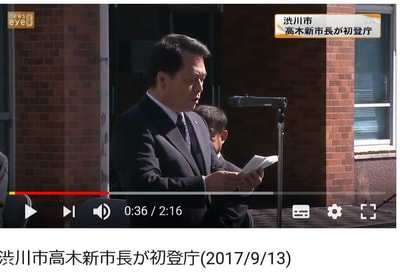
↑司会:続いて、職員を代表して田中副市長から歓迎の言葉を申し上げます。↑
当会注:次のYouTubeの動画に5:15のところで、確かに上記のように司会がアナウンスしています。
https://youtu.be/kZHlHWYtK0A?t=5m15s

↑花束贈呈の後、司会:それではここで、高木市長から就任のご挨拶をお願いいたします。↑
■このように渋川市長初登庁式・就任式が執り行われたようです。お目出たい就任式にケチをつける気持ちなど毛頭ありませんが、“あれ?”と疑問を抱く就任式となっています。それは・・・・・
〇渋川市議会を代表して → 議会議長 があいさつ
〇渋川市職員を代表して → 副市長 があいさつ
〇それを受けて → 新市長 があいさつ
となっていることです。「市長」と名がつく方が2名も挨拶しています。特に渋川市職員代表者による挨拶が問題です。地方自治法を見ていきましょう。
**********地方自治法第3条抜粋*********
(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
第三条 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3 特別職は、次に掲げる職とする。
一 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
**********
■このように、渋川市に限らず、地方公共団体の職員には一般職と特別職の二種類の公務員がいます。特別職とは、選挙で選ばれた市長や、その市長に任命され議会で承認を得られた副市長などが挙げられます。
ここで渋川市の新市長就任式を振り返ってみましょう。「職員を代表して」田中副市長が挨拶を行っていますが、大変疑問であり、問題があると言わざるを得ません。ポイントを整理してみましょう。
疑問点① 職員を代表して、特別職が挨拶していること
疑問点② 渋川市全体が、地方公務員法を読んだことがない無法者によって支配されていること
疑問点③ この副市長が、なんと選挙に落選した前市長により任命された副市長であること
ではそれぞれの疑問点について考察を加えてみましょう。
疑問点① 職員を代表して、特別職が挨拶していること
新市長就任式でのあいさつですから、最後に新市長が挨拶しています。当たり前と言えるでしょう。法律でいえば市長は選挙で選ばれた特別職です。しかしこの新市長の挨拶より前に、もう一人の特別職である副市長が挨拶しています。副市長は文字通り、市長をサポートする立場の者です。このような式典では市長の後ろに控えるのが健全な地方公共団体の特別職というものでしょう。何を勘違して副市長が渋川市職員の前にしゃしゃり出ているのでしょうか?
疑問点② 渋川市全体が、地方公務員法を読んだことがない無法者によって支配されていること
なぜ二人の特別職が挨拶するのでしょうか? 動画では司会が、「職員を代表して」と副市長を紹介しています。通常、コンプライアンス(法令順守)がしっかりした地方公共団体では、総務部長や建設部長が挨拶をするところですが、地方公務員法を読んだことのない者により、就任式が企画されたのでしょうか?特別職である副市長が挨拶しています。
渋川市の行事なのですから、「職員を代表して」挨拶するなら、やはり地方公務員法を基本に企画を進めて欲しいものです。さもないと、職員を含め、渋川市では法令を守ろうとする気構えが希薄である印象を受けてしまいます。“地方公務員法ぐらい読んだらどうだ!”と、渋川市民でなくとも失笑を買う就任式というところでしょう。
疑問点③ この副市長が、なんと!選挙に落選した前市長により任命された副市長であること
田中副市長とはどのような人物なのでしょう?新聞報道を見てみましょう。
**********2016年2月24日毎日新聞群馬版
渋川市 副市長に田中氏を起用へ 談合事件で空席 /群馬
渋川市発注の公共工事を巡り、加重収賄や官製談合防止法違反などの容疑で副市長が逮捕された問題で、市は解職で空席となっている副市長に田中猛夫企画部長(60)を起用する方針を固めた。3月1日開会の定例会で市議会の同意を得て、4月1日付で就任する見通し。
田中氏は1979年に北橘村役場に入り、市町村合併後の渋川市で法制管理課長や行政課長を務め、13年から企画部長。3月末に定年を迎える。【高橋努】
**********
渋川市では、阿久津・前渋川市長に任命された飯塚副市長が談合事件で逮捕されています。渋川市発注の公共工事を巡る談合事件での逮捕劇なので、当然疑惑の目が前渋川市長に向けられている中、その空席になった副市長に阿久津・前渋川市長により後任として任命されたのが田中猛夫副市長のようです。上記の報道によると、田中副市長は渋川市職員出身で、2017年3月に定年退職していることが分かります。
こうした状況から、次の2点を指摘したいと思います。
〇田中副市長は、前市長により任命された副市長であるので、なぜ前市長が落選し新市長が誕生した段階で、辞表を提出しないのでしょうか?新たな副市長が決まるまで職に留まりたいのなら、暫定的に渋川市の副市長であるので、なぜ「俺が俺が」でシャシャリ出て挨拶したのでしょうか?どちらにしても、自分の立場が分かっていない、つまりコンプライアンス(遵法精神)に乏しい副市長と言えるでしょう。
○この田中副市長は、既に定年を迎えた元一般職の地方公務員です。通常であれば長く渋川職員を勤め上げたわけだから、地方公務員法に精通していなければならない立場の筈です。たとえ「職員を代表して」挨拶することを強く要請されたとしても、地方公務員法に精通している人物であれば、「挨拶を辞退」するのがジョーシキでしょう。
■当会では、大同特殊鋼渋川工場が六価クロムやフッ素が環境基準を超えて含まれていることを知りながら、スラグを群馬県中に情け容赦なく投棄された大同有害スラグ不法投棄問題に取り組んでいます。中でも、大同特殊鋼渋川工場がある渋川市が廃棄物処理法を正しく理解し、住民の生活環境を保全すべく行動し、群馬県に模範となるような態度で施策を実行することが、大同スラグの排出自治体に求められていると考えています。
新渋川市長の記者会見で「生活環境」に触れられたことで、大いに大同スラグ撤去に向け、期待をもちたいところではありますが、就任式の無法ブリを見るとき暗雲が立ち込め、またしても法律が正しく履行されない悪夢が広がって見えるのです。
【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】
※参考資料:鉄鋼スラグ連絡会議について
大同特殊鋼渋川工場由来の有害スラグについては、群馬県廃棄物リサイクル課が有価物であることを否定し、廃棄物に認定しています。群馬県内の廃棄物については、群馬県廃棄物リサイクル課が監督官庁です。有価物であることを否定され廃棄物である大同有害スラグは、群馬県廃棄物リサイクル課が、廃棄物処理法に則り適正に処理するよう指導監督しなければなりません。他方、国土交通省・群馬県県土整備部・渋川市などの工事実施主体で構成される鉄鋼スラグ連絡会議は、廃棄物の適正な処理について、何の権限も有していません。
○第1回 鉄鋼スラグに関する連絡会議
http://www.pref.gunma.jp/06/h8000223.html
○第2回 鉄鋼スラグに関する連絡会議
http://www.pref.gunma.jp/06/h8000234.html
○第3回 鉄鋼スラグに関する連絡会議
http://www.pref.gunma.jp/06/h8000259.html
○2015年11月22日:大同スラグ問題を斬る!・・・第3回鉄鋼スラグ連絡会議のその後↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1809.html#readmore
○2015年11月15日:大同スラグ問題を斬れるのか!…第3回鉄鋼スラグ連絡会議の討議内容から見えてくる行政側の思惑↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1799.html#readmore
●スラグ廃棄物認定についてはこちら↓
○2015年9月13日:大同スラグ問題を斬る!…警察の強制捜査に併せて群馬県が公表した大同スラグの調査結果から見えてくるもの↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1723.html#readmore
●廃棄物スラグの適正な処理についてはこちら↓
〇2016年10月5日:大同有害スラグ問題を斬る!・・・豊洲の土壌汚染問題で都知事が所信表明!群馬県との大違いを徹底検証(2)↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2136.html#readmore
**********























