・・・私は自分でも不思議なくらいものづくりが好きです。
今日は思い立って、本を見ながら多少のアレンジを加え高さ十センチくらいの男の子の人形を作りました。

材料は紙粘土でなく細かい石粉粘土を使いました。

「仕上げた人形です」

後ろ姿は何となく雰囲気がありました。
女性の像を作ると新郎新婦になります。
そのうち、チャレンジです。
・・・私は自分でも不思議なくらいものづくりが好きです。
今日は思い立って、本を見ながら多少のアレンジを加え高さ十センチくらいの男の子の人形を作りました。

材料は紙粘土でなく細かい石粉粘土を使いました。

「仕上げた人形です」

後ろ姿は何となく雰囲気がありました。
女性の像を作ると新郎新婦になります。
そのうち、チャレンジです。
・・・時間が無くて唐津城は入場しなかったのですが、城下町の風情がとても落ち着いた城だったので、写真を撮ってきました。

昭和に再現された海に浮かぶ天守閣でとても美しく感じました。
唐津城は1608年に豊臣秀吉の側近の寺沢広高が秀吉の作った名護屋城の解体資材を使って築城したと伝えられています。
寺沢氏は息子の時代に改易にあい、その後の藩主は徳川譜代の大久保、松平、土井、水野、小笠原の諸氏が、佐賀、熊本、薩摩などの外様大名の抑えとして入城しています。


城を築城した時に新田開発の一環として暴風林、防砂林として植樹した松の林が長さ5kmに及んで広がっています。
日本三大松原の一つの「虹の松原」と言われています。
・・・先回書いたように、壱岐の島については、古代史以外の知識もなく訪れたのですが、思っていた以上に観光名所がありました。
壱岐島についての説明を聞いた中で頭に残っているのは、島の大きさは全国で21番目に大きな島で、島の平野の広さは長崎県内で二番目の面積があると聞きました。

昭和八年に日本では珍しい遠距離砲台が黒崎半島に設置され、その跡が保存されています。
写真は砲台の入り口に直径41cmの砲弾の模型が置かれてありました。

砲台の説明図を見て、現場を見学するととてつもなく大きなものであったことが理解できました。

あなほげ地蔵。この地蔵さんは海辺に立っていて、今は地元の人に大事に守られていますが、明治の廃仏毀釈運動で首を落とされ後に丸石を載せられた修理跡が痛々しいお地蔵さんです。

標高二百メーターあまりの島一番の高所に狼煙台がありました。
古代、大和朝廷が新羅・唐の連合軍と白村江の戦いで敗れ、防御のために西国一帯に防人と狼煙台を置き唐、新羅の軍の侵略に備えた跡です。
狼煙台は私が思っていた以上の大きさでした。

島一番の名所として、「猿岩」がありました。

動物に似た岩は全国各地で名所になっていますが、壱岐島の「猿岩」は、その中でも群を抜いてリアリティーがありました。
上に紹介したもの以外にも、島の名所はイルカパーク、カラカミ遺跡、元寇の古戦場、遺新羅使の墓などがあります。
今回の旅の最大テーマである「原(はる)の辻遺跡と一支国博物館」を尋ねました。
日本の成り立ちの古代史に興味を持っている私は、古代文明の通路にある「壱岐、対馬」訪れたいと思っていました。
今回は考古学的に発掘調査され、移籍を復元してある、「原の辻遺跡」と、その成果が展示されている「一支国博物館」を見学しました。

場所は島の南東の平野の中央にあります。
原の辻遺跡は弥生時代を通じて一支国の国邑(国都)として栄えた場所で「魏志人伝」にもその様子が書かれています。
「…至一支国 ・・・ 方可三百里 多竹木叢林 有三千許 差有田地 耕田猶不足食 亦南北糴 ・・・」と倭人伝に紹介されています。
私なりに意味を書くと「・・・壱岐国に至る。島は方三百里の大きさで、竹木や叢林が多く、家は三千軒くらいある。田地は少しあるが、自給するにしては足りないので、船で交易している。」とある。
前から、本で読んで頭に入っている場所なので、実際にその場所に立つと感慨深い。

遺跡の中の祭りの場所にある古代の鳥居。

田畑越しに見る、遺跡の外観と遠くに見える博物館の展望台。

博物館のパンフレット。

博物館に展示されていた弥生時代の九州や、対馬との交易に使った船。

原の辻遺跡を再現したジオラマが素晴らしく良い出来で展示されていました。

写真中央の遺跡が平野の中心の少し高くなっている丘にあることが分かる。周囲は田が耕作されている。

弥生時代に交易のために、湾から川を船で遡って、川と遺跡が近い処に船着き場の跡が、写真の中央左の青いブルーシートの場所である。
海から、川をさかのぼる順路とその位置関係が展望台から、すべて見ることができた。
現地に立って良かったのは、博物館の展望台から島のかなりの部分が見渡せて、弥生時代の生活の状態と魏志倭人伝の記載内容が想像できたことです。
・・・壱岐の遺跡を主な狙いにしたツアーの旅から帰ってきました。

旅の全工程のマップを作って上に載せています。
赤線が一日目の工程ですが、ツアーなので、色々なところに連れて行ってくれます。
福岡空港の上空で倭奴国の金印で有名な志賀島を見ることが出来ました。

飛行機の翼の斜め下に志賀島が見えます。
福岡では最初に大宰府天満宮を訪れました。
弥生時代の「奴国の遺跡」が集中する福岡市街地域の地形を都市高速の高い位置から、見下ろしながら大宰府に向かった。

大宰府政庁跡の前の道を通って天満宮に着きました。
日曜日だったので、小雨の中、たくさんの人が参拝に来ておられました。

本殿前の池のそばの牛の像

境内には受験の合格祈願の絵馬がいたるところに架けてありました。
天満宮と言えば全国にあるのですが、大宰府の天満宮は本家なので、境内の合格祈願の絵馬が多かったです。

帰りに境内で、大宰府天満宮の名物の「梅が枝餅」を買って食べました。
・・・先日、購入したモバイルパソコンは外側が傷が目立ちやすい光沢のあるフレームなので、柔らかい革で収納ケースを製作することにした。

厚みのあるケースなので、全体を柔らかい革だけで作ると腰がないので側面の革を腰のある革を使用しました。

「全体を覆う柔らかい革」

腰のある革を肩を作って側面用に成形した。

「縫い上げてモバイルパソコンを収納」

今回はフレームの疵保護用の皮ケースなので、金具類はすべてなくした。
・・・以前から興味のあった壱岐へのツアーに参加することにしました。
紀元前の弥生時代から栄えた、「魏志倭人伝に一支国」と書かれている島です。
間違いなく邪馬台国の大夫、魏の帯方郡の役人が行き来した場所です。
観光地としては大したものが無いとは思いますが、「原の辻の遺跡」に立って、弥生の時代を感じてきたいと思っています。
その時は、飛行機の中で司馬遼太郎の『街道をゆく、「壱岐・対馬の旅」』を再読して、島の思いを蘇らして、と思っています。
明日から、旅は四日間なのでブログをその間休みます。
・・・去年も行ったリンゴ農園から、誘いの便りを貰って行ってきました。
場所は天竜峡の奥にあります。

中央高速道のインターから「三遠南進道」という自動車道を走って天竜峡に行きます。
この道はアルプスを望む観光道路で平日はほとんど通行量もありませんでした。

先日、新聞に新しく開発されたリンゴとして紹介されていた「シナノ・スウィート」がちょうど食べごろでした。

外観は「富士」とよく似ていますが、味はかなり甘味が勝る品種です。
シナノ・スウィートを「シナノ・ゴールド」と「アキバエ」と食べ比べると、酸味が少なく甘味が強い印象が強かったです。

結局、家へは上記の三種類を八個づつを自家消費用に買って帰りました。
・・・日曜日の朝に松本城を訪れました。

城の公園入り口から史跡の碑と御堀に架かる橋越しに天守を見る。

堀の水面に映る天守閣


お堀のそばに立つと鯉がたくさん寄ってきて口をあけて餌を要求します。
日曜日の朝なので、観光客と地元の老人とが同じくらいの人数、城前の公園に憩っておられました。
城の前には城と同時に作られた松本神社があり、境内には樹齢五百年くらいの大きな樹がありました。

さらに城の近くの観光地として、日本でも最も古い小学校が現在も同じ名前で新しい校舎の奥に立っていました。

生徒が体操している運動場越しに見えるのが、明治六年に作られた日本でも最も古い開智小学校です。

松本城の印象は戦争をする城ではなく、お殿様が住む美しい宮殿という感想です。
同じ程度美しい姫路城ほど松本城は広くはありませんが、形の美しい城でした。
・・・NHKの朝ドラ「おひさま」は毎日楽しみに見ていたので、一度安曇野へ行きたいと思っていました。

観光わさび農園のわさび畑

自然の小川はドラマを思い出させる雰囲気でした

川の水は透明度が高く水草が茂っていました。

三時過ぎでしたが、周りをアルプスの山々に囲まれていて
陽が落ちるのが早いようでした。

季節外れなのか、そば畑は見れませんでしたが、
ドラマを思い出させる雄大な景色の広がりを感じました。
現地に行って分かったのですが、雄大なアルプスの山々ときれいな小川の水、以外はドラマの中の景色はセットで作られていたようです。
しかし、私たちが子供のころのような素朴で、のんびりした景色は安曇野にはありました。
・・・奈良井宿から中央道の塩尻ICに向かう街道にリンゴ園とブドウ畑が続く場所がある。

そこに有名な「井筒ワイン」の看板が出ていたので寄り道した。

井筒ワインの看板の出ていたワイナリーの売店によって、普通、スーパーなどで見かけないラベルのワインを数本、買ってきました。

近くには、知らない銘柄のワイナリーの売店がありました。
先を急いでいたので、今回は、そこは寄り道しませんでした。
・・・旅の目的地の松本に宿をとる予定だったので、直接、行く予定でしたが、中央道の塩尻ICから名古屋方面に旧の中山道を22kmほど戻って、木曽路十一宿の江戸から近い二番目の「奈良井宿」に行ってきました。
「馬篭」「妻籠」の江戸の町並みは名古屋からも比較的近く、何度か行ったことがありましたが、「奈良井宿」は初めて訪れました。
木曽路の宿場でも一番高所にある宿ですが、宿数は大変多かったようです。
何枚か写真を撮ってきましたので紹介します。

「500軒は軒を連ねる街道の街並み」

「旅人にとって大事な昔ながらの水飲み場が何か所かあった」

「訪れたのは日曜日だったので、人は多かったです」

街道を外れた脇道から、写真を撮ると周りが高い山々に囲まれていることが分かります。
山の木々の紅葉はこれからのようですが、少し色づいていました。
・・・いつも家に、こもっているすが、久しぶりに旅行することにしました。
目的はリンゴを買いに長野県飯田市方面に行きます、ついでにNHKの朝ドラ「おひさま」の舞台の松本城と安曇野の風景を見に行くことにしました。

「松本城とアルプス」
それから、家族も一緒に行くので、温泉にも行きたい、・・・・ と云う事で、朝から車で我が家を出発します。
・・・池上彰の解説番組は良く見ていて、特にこの現代史講義は欠かさず見ている。

今回のテーマは「中国の大躍進政策と文化大革命」でした。
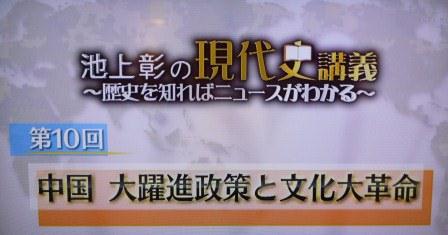
文化大革命については、過去に何度かテレビで見ていたが大躍進政策については古いことなので、私は良くは理解していなかった。
大躍進政策の中身は人民公社に代表されるマルクスの理論の実践で農業改革と鉄鋼の大増産という中身であったが、この番組を聞いていて、愚かなことをしていたと云う事が理解できるととともに、時代が変わっても組織の大きさと関係なく指導者の自戒が無くなると愚かなことをするのは、いつの時代も同じだと感じました。
国家的規模でいえば今の北朝鮮がまさしくそうで、世界には同じようなことをしている国家がアフリカ、中東にいくらもある。
又、振り返って、日本における会社の経営を見ても社長が会社全体でなく、末端作業にまで口出しした時は大抵、その会社はおかしくなっているのを何度も見てきた。
私と同じように、そんな、ことを感じながらこの番組を見ている人が多いだろうと番組を見ながら想像していました。
・・・良く食べるので、おなか周りにすぐ肉がついてしまいます。
年をとると足や腰を痛めることに気をつけなくてはいけないと日頃から考えているので、腹筋台を買ってきて鍛えることにしました。

腹筋台の手前にあるのは自作の上に載って立つと足首が曲がって、太ももをストレッチできる台です。
居間の片隅にいつでも使えるようにおいてあります。