4月18(月)~20日(水)、愛知、岐阜、長野県への小旅行に出かけた。日程に従
い、順次その行程を紹介する。
---------------------------------------
2016年4月18日(月) == 愛知県犬山市「博物館 明治村」へ ==
5時43分に自宅を出て、JR東京駅7時33分発の東海道新幹線ひかり503号に乗
る。好天の静岡県東部では、富士山がよく見えた。

9時17分に名古屋駅で下車する。
名鉄名古屋駅から犬山線で犬山駅まで行き、東口から明治村行きバスに乗る。終点の明
治村バス停には10時28分に着いた。
「博物館 明治村」は、明治建築を保存展示する野外博物館として、昭和40年(1965)
3月18日に開村したとのこと。
私は開村して間もない頃訪ねた記憶があり、帰宅後に調べてみたら、三重県鈴鹿市の社
内研修期間へ半月余り出張していたときの最初の休日、4月18日(日)と分かった。ち
ょうど開村して1か月目、そして今回の訪問はちょうど51年ぶりということになる。
開村当時の建築物は10数棟だったと思われるが、現在は国の重要文化財10棟、愛知
県指定文化財1棟を含む67の建造物が移築保存されているとか。
敷地面積は約100万㎡あり、エリアは南北約1.1㎞、東西約620m㍍に及び、南
西端に近い正門から北西端の北口まで歩くだけでも約20分になるという(入村料 シニ
ア 1,300円)。

村内地図によれば、村内は1丁目から5丁目までの五つのエリアに分かれているので、
正門に近い1丁目から順次巡ることにする。
正門は、名古屋市瑞穂区に明治42年(1909)建設の第八高等学校正門で、国登録
有形文化財である。

1丁目に入り、最初の建物が大井牛肉店。神戸市生田区元町に明治20年(1887)
頃建設され、牛肉販売と牛鍋の店を兼ねた商店で、国登録有形文化財。

村内の味どころのひとつ牛鍋大井牛肉店として、文明開化の象徴ともいえる牛鍋を味わ
うこともできる(これは展示されていた見本)。

その横は、国登録有形文化財の三重県尋常師範学校蔵持(くらもち)小学校。明治21
年(1888)に三重県名張市に建設されたもの。

建物内には古い教本や教室などが残されている。

隣接して、国登録有形文化財の近衛局(このえきよく)本部附属舎がある。東京都千代
田区に同じ明治21年に建築され、のち皇宮警察本部坂下護衛所として使用されたという。

そばに立つ赤坂離宮正門哨舎(しゅしや)も国登録有形文化財。東京・港区元赤坂の現
在の迎賓館にあったもので、当時皇太子だった大正天皇の東宮御所に明治42年(1909)
に竣工したようだ。


村内一帯は豊富な広葉樹林が残り、その間に建物が点在している。左に緩やかに上がる
と、聖ヨハネ教会の大きな建物の前に出る。

国の重要文化財で、明治40年(1907)に京都市下京区に建設された。細部はゴシ
ック調にデザインされた本格的洋風建築で、現存する明治期のキリスト教会堂の代表的な
ものだという。

周辺のモチツツジやヤエザクラ、ガマズミが見ごろになっていた。

左に上がって学習院長官舎(国登録有形文化財)へ。明治42年、東京都豊島区目白町
に建設された学習院長の公邸で、建設当時の第10代院長、陸軍大将乃木希典(のぎまれ
すけ)は赤坂の私邸から通ったとか。

公邸前のキクモモが鮮やかな彩りを見せる。

近くの、西郷従道(さいごうつぐみち)邸は国の重要文化財。東京都目黒区上目黒の通
称西郷山から移築された明治10年代(1877~)の建築物で、従道は陸海軍の大臣を
歴任していたため在日外交官の来客も多く、明治22年(1889)には明治天皇も行幸
されたとのこと。

館内に入れるので入館して各部屋を回り、調度品などを見た。


正午が近いのでそばにあった和食処碧水邸に入り、眼下の日本庭園やその向こうに広が
る入鹿池(いるかいけ)などを眺めながら昼食をした。

注文したメニューは花御膳(1,350円)である。

12時30分に碧水邸を出て、眼下の日本庭園へ。庭園の外れには、東京盲学校車寄
(くるまよせ)が移築されていた。

東京・文京区雑司ヶ谷町に明治43年(1910)に建設された、東京盲学校本館の正
面中央に設けられたもの。国登録有形文化財である。

ふり返ると、食事をした碧水邸が望まれ、入鹿池周辺の新緑などの展望が気持ちよい。

近くのウワミズザクラが、たくさんの花を見せていた。こんなに花いっぱいのウワミズ
ザクラは初めてだ。

日本庭園から南に緩く上がり、森鴎外・夏目漱石住宅に行く。東京都文京区駒込千駄木
町に明治20年(1887)頃建設されたもの。

明治の文豪 森鴎外は明治23年から1年半ほど、夏目漱石は約13年後の明治36年
(1903)から約3年住み、「吾輩は猫である」を書いて文壇でその名を高めたゆかり
の家とか。国登録有形文化財である。


林間を南に下って正門からの主要道に出て、正門に近い鉄道局新橋工場に入る。

東京都品川区大井町に明治22年(1889)に建設されたもので、やはり国登録有形
文化財。

建物内には、明治43年(1910)に新橋工場で製造された明治天皇御料車(6号御
料車)と、明治35年(1902)同工場製の昭憲皇太后(しょうけんこうたいごう)御
料車(5号御料車)(いずれも鉄道記念物)が展示されていた。下は5号御料車の内部。

鉄道局新橋工場前には、二重橋飾電燈(かざりでんとう)(国登録有形文化財)が立つ。
東京千代田区の皇居内に明治21年(1888)に建設されたもので、昭和39年
(1964)まで使用されたという。

1丁目の最後は、国重要文化財のひとつで建物も大きな三重県庁舎。明治12年
(1879)に三重県津市栄町に建設された。

間口54mに及ぶ建物で、明治9年に東京大手町に建てられた内務省庁舎にならったも
のとか。


建物内には、明治の宮廷家具が展示されていた。そばのサクラが花開く。

食事を含めて約2時間経過して、ようやく1丁目を回り終えた。すっかり曇って気温も
幾分下がり、雨も少しだけ落ちてきた。隣接する2丁目に入り、最初は第四高等学校物理
化学教室の建物へ。

金沢市仙石町に明治23年(1890)に建設され、国登録有形文化財である。
最初の部屋には、ともに第四高等学校出身でこの明治村の生みの親、名古屋鉄道の社長
や会長を歴任した土川元夫と建築家谷口吉郎の経歴や、昭和40年の草創期の明治村の様
子などが展示され、次の教室は実験もできる階段教室になっていた。
スペースとしては一番狭い2丁目の中央を直線のレンガ通りが走り、その最奥部高みに
は東山梨郡役所(ひがしやまなしぐんやくしよ)がある。

山梨県山梨市日下部(くさかべ)町に明治18年(1885)に建設され、国重要文化
財。三重県庁舎同様、内務省に代表される当時の官庁建築の特徴的建物。当時の県令(現
在の県知事)藤村紫朗は、地元山梨に「藤村式」と呼ぶ多くの洋風建築を建てさせたとい
う。
1階右手の部屋は明治村の村長室で、歴代村長の写真などが展示されている(現・4代
村長は阿川佐和子氏)。


2丁目を貫くレンガ通りの左手建物を順次回る。最初は木曽路の長野県大桑村にあった
清水医院(国登録有形文化財)で、明治30年代(1897~)の建築とか。


島崎藤村の、姉、園子をモデルにした小説「ある女の生涯」に描かれていて、実際に園
子が入院していたという。〈続く〉
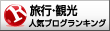 旅行・観光 ブログランキングへ
旅行・観光 ブログランキングへ
 にほんブログ村
にほんブログ村
い、順次その行程を紹介する。
---------------------------------------
2016年4月18日(月) == 愛知県犬山市「博物館 明治村」へ ==
5時43分に自宅を出て、JR東京駅7時33分発の東海道新幹線ひかり503号に乗
る。好天の静岡県東部では、富士山がよく見えた。

9時17分に名古屋駅で下車する。
名鉄名古屋駅から犬山線で犬山駅まで行き、東口から明治村行きバスに乗る。終点の明
治村バス停には10時28分に着いた。
「博物館 明治村」は、明治建築を保存展示する野外博物館として、昭和40年(1965)
3月18日に開村したとのこと。
私は開村して間もない頃訪ねた記憶があり、帰宅後に調べてみたら、三重県鈴鹿市の社
内研修期間へ半月余り出張していたときの最初の休日、4月18日(日)と分かった。ち
ょうど開村して1か月目、そして今回の訪問はちょうど51年ぶりということになる。
開村当時の建築物は10数棟だったと思われるが、現在は国の重要文化財10棟、愛知
県指定文化財1棟を含む67の建造物が移築保存されているとか。
敷地面積は約100万㎡あり、エリアは南北約1.1㎞、東西約620m㍍に及び、南
西端に近い正門から北西端の北口まで歩くだけでも約20分になるという(入村料 シニ
ア 1,300円)。

村内地図によれば、村内は1丁目から5丁目までの五つのエリアに分かれているので、
正門に近い1丁目から順次巡ることにする。
正門は、名古屋市瑞穂区に明治42年(1909)建設の第八高等学校正門で、国登録
有形文化財である。

1丁目に入り、最初の建物が大井牛肉店。神戸市生田区元町に明治20年(1887)
頃建設され、牛肉販売と牛鍋の店を兼ねた商店で、国登録有形文化財。

村内の味どころのひとつ牛鍋大井牛肉店として、文明開化の象徴ともいえる牛鍋を味わ
うこともできる(これは展示されていた見本)。

その横は、国登録有形文化財の三重県尋常師範学校蔵持(くらもち)小学校。明治21
年(1888)に三重県名張市に建設されたもの。

建物内には古い教本や教室などが残されている。

隣接して、国登録有形文化財の近衛局(このえきよく)本部附属舎がある。東京都千代
田区に同じ明治21年に建築され、のち皇宮警察本部坂下護衛所として使用されたという。

そばに立つ赤坂離宮正門哨舎(しゅしや)も国登録有形文化財。東京・港区元赤坂の現
在の迎賓館にあったもので、当時皇太子だった大正天皇の東宮御所に明治42年(1909)
に竣工したようだ。


村内一帯は豊富な広葉樹林が残り、その間に建物が点在している。左に緩やかに上がる
と、聖ヨハネ教会の大きな建物の前に出る。

国の重要文化財で、明治40年(1907)に京都市下京区に建設された。細部はゴシ
ック調にデザインされた本格的洋風建築で、現存する明治期のキリスト教会堂の代表的な
ものだという。

周辺のモチツツジやヤエザクラ、ガマズミが見ごろになっていた。

左に上がって学習院長官舎(国登録有形文化財)へ。明治42年、東京都豊島区目白町
に建設された学習院長の公邸で、建設当時の第10代院長、陸軍大将乃木希典(のぎまれ
すけ)は赤坂の私邸から通ったとか。

公邸前のキクモモが鮮やかな彩りを見せる。

近くの、西郷従道(さいごうつぐみち)邸は国の重要文化財。東京都目黒区上目黒の通
称西郷山から移築された明治10年代(1877~)の建築物で、従道は陸海軍の大臣を
歴任していたため在日外交官の来客も多く、明治22年(1889)には明治天皇も行幸
されたとのこと。

館内に入れるので入館して各部屋を回り、調度品などを見た。


正午が近いのでそばにあった和食処碧水邸に入り、眼下の日本庭園やその向こうに広が
る入鹿池(いるかいけ)などを眺めながら昼食をした。

注文したメニューは花御膳(1,350円)である。

12時30分に碧水邸を出て、眼下の日本庭園へ。庭園の外れには、東京盲学校車寄
(くるまよせ)が移築されていた。

東京・文京区雑司ヶ谷町に明治43年(1910)に建設された、東京盲学校本館の正
面中央に設けられたもの。国登録有形文化財である。

ふり返ると、食事をした碧水邸が望まれ、入鹿池周辺の新緑などの展望が気持ちよい。

近くのウワミズザクラが、たくさんの花を見せていた。こんなに花いっぱいのウワミズ
ザクラは初めてだ。

日本庭園から南に緩く上がり、森鴎外・夏目漱石住宅に行く。東京都文京区駒込千駄木
町に明治20年(1887)頃建設されたもの。

明治の文豪 森鴎外は明治23年から1年半ほど、夏目漱石は約13年後の明治36年
(1903)から約3年住み、「吾輩は猫である」を書いて文壇でその名を高めたゆかり
の家とか。国登録有形文化財である。


林間を南に下って正門からの主要道に出て、正門に近い鉄道局新橋工場に入る。

東京都品川区大井町に明治22年(1889)に建設されたもので、やはり国登録有形
文化財。

建物内には、明治43年(1910)に新橋工場で製造された明治天皇御料車(6号御
料車)と、明治35年(1902)同工場製の昭憲皇太后(しょうけんこうたいごう)御
料車(5号御料車)(いずれも鉄道記念物)が展示されていた。下は5号御料車の内部。

鉄道局新橋工場前には、二重橋飾電燈(かざりでんとう)(国登録有形文化財)が立つ。
東京千代田区の皇居内に明治21年(1888)に建設されたもので、昭和39年
(1964)まで使用されたという。

1丁目の最後は、国重要文化財のひとつで建物も大きな三重県庁舎。明治12年
(1879)に三重県津市栄町に建設された。

間口54mに及ぶ建物で、明治9年に東京大手町に建てられた内務省庁舎にならったも
のとか。


建物内には、明治の宮廷家具が展示されていた。そばのサクラが花開く。

食事を含めて約2時間経過して、ようやく1丁目を回り終えた。すっかり曇って気温も
幾分下がり、雨も少しだけ落ちてきた。隣接する2丁目に入り、最初は第四高等学校物理
化学教室の建物へ。

金沢市仙石町に明治23年(1890)に建設され、国登録有形文化財である。
最初の部屋には、ともに第四高等学校出身でこの明治村の生みの親、名古屋鉄道の社長
や会長を歴任した土川元夫と建築家谷口吉郎の経歴や、昭和40年の草創期の明治村の様
子などが展示され、次の教室は実験もできる階段教室になっていた。
スペースとしては一番狭い2丁目の中央を直線のレンガ通りが走り、その最奥部高みに
は東山梨郡役所(ひがしやまなしぐんやくしよ)がある。

山梨県山梨市日下部(くさかべ)町に明治18年(1885)に建設され、国重要文化
財。三重県庁舎同様、内務省に代表される当時の官庁建築の特徴的建物。当時の県令(現
在の県知事)藤村紫朗は、地元山梨に「藤村式」と呼ぶ多くの洋風建築を建てさせたとい
う。
1階右手の部屋は明治村の村長室で、歴代村長の写真などが展示されている(現・4代
村長は阿川佐和子氏)。


2丁目を貫くレンガ通りの左手建物を順次回る。最初は木曽路の長野県大桑村にあった
清水医院(国登録有形文化財)で、明治30年代(1897~)の建築とか。


島崎藤村の、姉、園子をモデルにした小説「ある女の生涯」に描かれていて、実際に園
子が入院していたという。〈続く〉














