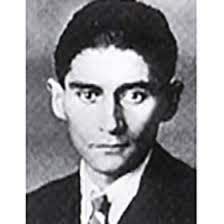いつも聴いているpodcast番組(ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」)の企画で、ジェーン・スーさんと堀井美香さんがそれぞれ書店で自分が気になった本を買って紹介していたのですが、その中で堀井さんが手に取った一冊です。
その奇抜なタイトルから私も大いに気になったので、近所の図書館で見つけてきました。(ちなみに最近、続編も含め一冊の文庫本として再出版されたようで、堀井さんが買ったのはそちらの方だと思います)
NHK〈ラジオ深夜便〉の人気コーナーを書籍化したものとのことで、期待どおり興味を惹いたところは数多くありました。その中から特に私の印象に残った部分をいくつか書き留めておきます。
まずは、冒頭、絶望名言の選者頭木弘樹さんが “絶望名言はどのようなものか” を語った一節です。
(p23より引用) ネガティブな言葉というのは、普通、かえって暗い気持ちになると思われやすいんですが、必ずしもそうではなくて、辛い時には逆にそういう言葉のほうが、自分と一緒にいてくれて、気持ちをよくわかってくれて、それが救いになることも多いと思うんです。
確かに、心底沈み込んでいるときには “将来の光を語る言葉” は眩しすぎることはあるでしょうね。
次は「ドストエフスキー」の章。
“同情” についての頭木さんの言葉です。
(p76より引用) 普通の生活じゃあ、「同情されたくない」という人も多いじゃないですか。同情というのは上から目線だみたいな感じで。でも、ぼくはけっこう同情っていうのは、すごい尊いものだと思っていますね。
本当に相手の気持ちがわかるわけではなくても、それでも同情って、やっぱりすごく素敵な心理だと思います。ドストエフスキーがこんなふうにも言っているんです。
われわれは、自分が不幸なときには、
他人の不幸をより強く感じるものなのだ。(白夜)
やっぱり辛い体験をした人ほど、他の人の辛い気持ちもわかってあげられるというところがあると思うんですね。だからそういう人が、自分が辛い体験をした人が、また他の人に同情して、親切な手を差し伸べる。これはやはり辛い体験をしたからこその、いいことのひとつかもしれないですね。
なるほど、“人の痛みを知る人” ですね。昨今しばしは「・・・に寄り添う」というフレーズを耳にしますが、その安易さとは別物の心の動きです。
そして、「太宰治」。
日本の作家で “絶望” でイメージする人といえば、やはり彼、誰もが思い浮かべるでしょう。
太宰はフランスの詩人ヴェルレーヌが好きだったとのこと。
(p153より引用) この太宰治の言葉の「あの人の弱さが、かえって私に生きて行こうという希望を与える」というのは、まさに太宰自身にも言える言葉だと思いますね。太宰治を読んで、やっぱり読者も、太宰の弱さが「かえって私に生きて行こうという希望を与える」というところがあるんじゃないでしょうか。
まさに、辛いときには “絶望名言” が救いになるという実例です。
そして、最後は「シェークスピア」。
「マクベス」に登場している「明けない夜はない」という台詞は “定番の慰めの言葉” ですが、「明けない夜もある」と考えたくなるとときもあると頭木さんは言います。
(p224より引用) 「明けない夜もある」というふうな、時間が解決しない悲しみもあるというふうなことを言うのは、なんて暗いことを言うんだと思われるかもしれませんが、現実にそういう悲しみがある以上、そういうこともあるんだよって知っておかないと、逆に、いつまでも悲しみが癒えない時に、よりこじらしてしまうわけですよね。
だから「明けない夜もある」「明ける夜もある」。両方知っておくほうが大事なんじゃないかなと思いますね。
さて、本書、とても面白い切り口の著作でしたが、ラジオ番組のコーナーはまだまだ続いています。
それらの内容を採録した第2作目も世に出ているようなので、また、時間を作って読んでみたいと思います。