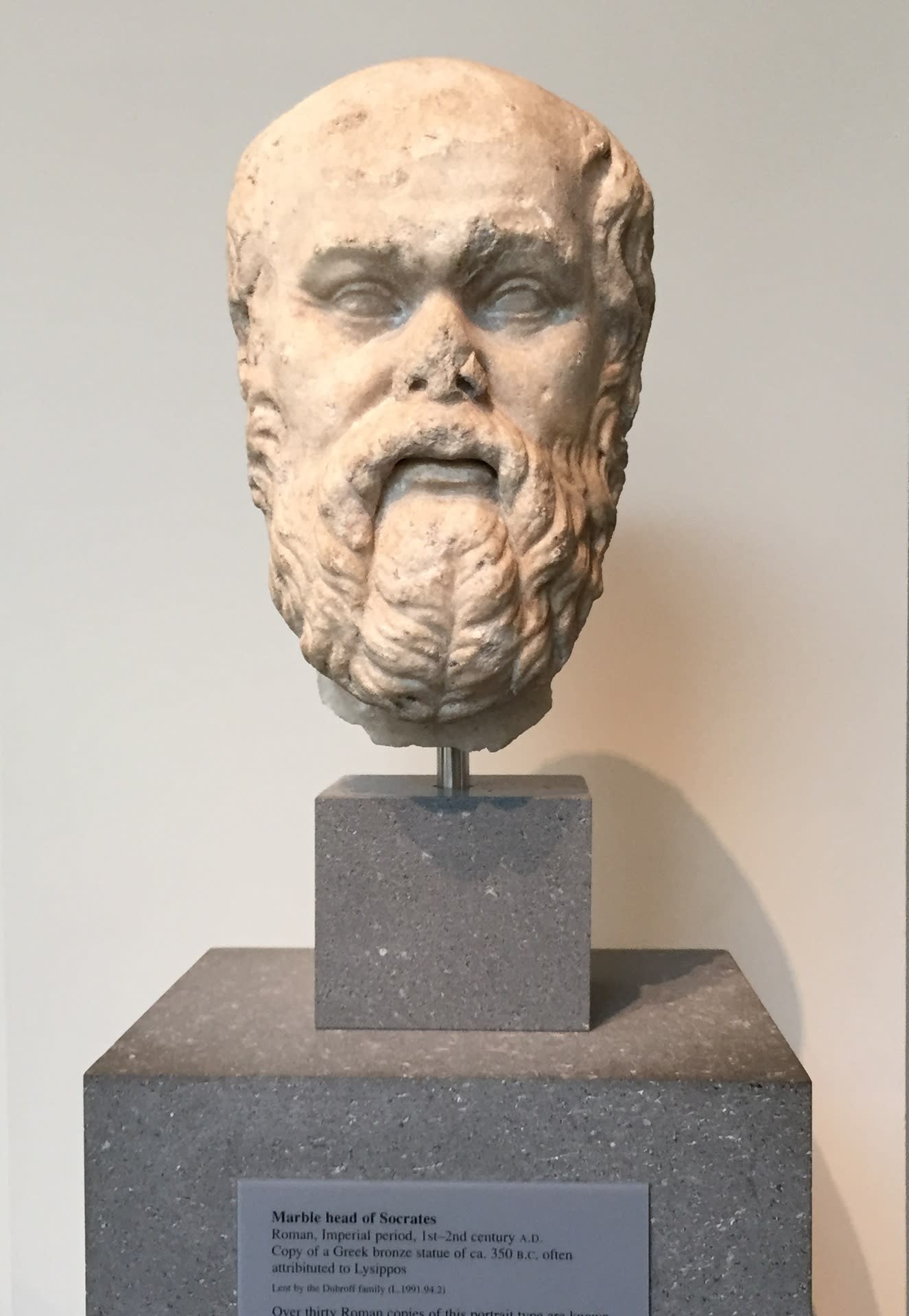ちょっと話題になっているビジネス書ですし、著者の入山章栄氏も最近かなり露出が多くなってきましたね。
そういう状況の中、従来の書籍とは違った何か新しい気づきが得られそうだとの期待を持って手にとってみました。
まずは、新進気鋭の経営学者たる著者が規定している「経営学の意味づけ」についてです。入山氏は、それを「経営学の使い方」という観点からこう語っています。
(p34より引用) 経営学は何を提供できるかというと、それは (1)理論研究から導かれた「真理に近いかもしれない経営法則」と、(2)実証分析などを通じて、その法則が一般に多くの企業・組織・人に当てはまりやすい法則かどうかの検証結果、の二つだけです。
そして、この二つを自身の思考の軸・ベンチマークとして使うことが、経営学の「使い方」だと私は考えています。
この「思考の軸・ベンチマーク」という意味から、著者は本書において経営学の理論的・実証的側面の成果を数多く紹介しています。
そういった中で、日本のビジネス書市場においてお決まりのように登場する「イノベーション」というテーマについても、やはり一章を起こして取り上げています。
(p 75より引用) イノベーションの源泉の一つは「既存の知と別の既存の知の、新しい組み合わせ」にあります。
このコメントは特に目新しいものではなく、寧ろ通常の捉え方でしょう。ただ、著者はさらに、新しい組み合わせを生み出す具体的なメソッドとして、「『知の探索』と『知の深化』について高次元でバランスを取る経営」が重要であると指摘しています。このあたりは改めて押さえておくべきポイントですね。
そして、さらに著者は、イノベーションを目指す日本企業への示唆として、以下のような面白い視点を提起しています。
(p103より引用) 日本のイノベーションに関する議論は「創造性」と「イノベーション」を混同していることも多く、結果として一辺倒な処方箋が示されがちです。しかし「創造性の欠如の問題」と「創造性から(イノベーションのための)実現への橋渡しの欠如という問題」は、まったくの別なのです。
さらに重要なのが、「創造性」に求められる要件と「創造性から実現への橋渡し」の要件が、まったく逆なことです。
たとえば、クリエイティブになるには軽いフットワークで構築された幅広い「弱い人脈」が、それを実現(製品という形)にもっていくには地道に信頼関係を積み上げて得られる社内の「強い人脈」が必要となるという主張です。
(p104より引用) 日本企業のイノベーションを考えるうえでは「創造性」と「イノベーション」の峻別が必要で、その上で自社を見つめ直すことが肝要なのです。
このあたりの解説にはなかなか興味深いものがありましたし、この視点は、従来からある研究開発から実用化に至るうえでの「キャズム」とか「死の谷(valley of death)」とかの議論とも同根のものですね。
さらに、もうひとつ、なるほどと思った「組織のパフォーマンス」に関わる議論です。
組織の学習力を高めるためには「情報の共有化」が重要と言われますが、現在の経営学の研究においては“トランザクティブ・メモリー”という概念が重要視されているのだそうです。
(p127より引用) トランザクティブ・メモリーは、組織学習研究の重要なコンセプトです。その骨子は「組織に重要なのは、組織の全員が同じことを知っていることではなく、『組織の誰が何を知っているか』を組織の全員が知っていることである」というものです。
これは、安易に語られる「情報共有」という行動を一歩掘り下げて、その重要な本質を指摘した有益なアドバイスだと思います。
そしてさらに、この“トランザクティブ・メモリー”に関して、著者はもうひとつ興味深い考察を紹介しています。
(p116より引用) では、どのようなチームがトランザクティブ・メモリーを高めているかというと、それは「直接対話によるコミュニケーションの頻度が多いチーム」に限られていたのです。それどころか結果の一部からは、「メール・電話によるコミュニケーションが多いことは、むしろ事後的なトランザクティブ・メモリーの発達を妨げる」可能性も示されました。
“トランザクティブ・メモリー”が高いチームほどプロジェクトのパフォーマンスが高いという定性的な傾向は誰でも想像がつきますが、そこに至るプロセスに着目したこういう結論は「実証研究」ならではの成果であり、大きな気付きになります。
また、最近行われたクリステンセン教授による経営者インタビューの結果も刺激的です。
数多くのスター経営者に対するインタビュー結果からクリステンセン教授は「イノベーティブ・アントレプレナーに共通する思考パターン」として4つの姿勢があると述べています。
- (1) クエスチョニング(Questioning):現状に常に疑問を投げかける態度
- (2) オブザーヴィング(Observing):興味を持ったことを徹底的にしつこく観察する思考パターン
- (3) エクスペリメンティング(Experimenting):それらの疑問・観察から、「仮説をたてて実験する」思考パターン
- (4) アイデア・ネットワーキング(Idea Networking):「他者の知恵」を活用する思考パターン
この4つですが、この中で特に私の興味を惹いたのが「Questioning」です。この姿勢について著者はさらに以下のように付言しています。
(p281より引用) 中でも重要な言葉が「What if」です。イノベーティブ・アントレプレナーたちは事業を立ち上げる前から、「もし私がこれをしたら(if)、世の中はどうなるか(what)」を考え続けるのが共通の思考パターンなのです。
こういう切り口を極く自然に自らの思考の構えとしてとることができるというのは素晴らしいですね、ここまで思考のレンジを拡げることはなかなかできるものではありません。
さて本書を読んでの感想ですが、久しぶりに面白いビジネス書に邂逅したという印象です。
すでに今までにいろいろなビジネス書を読み漁っている人にとっても、多くの興味を惹く指摘・示唆が得られることでしょう。もちろん、本書で扱っているテーマはとても広範囲なので、内容の濃度という点では紹介程度にとどまっていますが、興味をもった著者の指摘については脚注にある原典(論文)でさらに深堀りするとか、他の論考を評価するうえでの補助線として利用するとか、さまざまな活用の起点とすることができます。一読に値する良書だと思います。
 |
ビジネススクールでは学べない 世界最先端の経営学 |
| 入山 章栄 | |
| 日経BP社 |