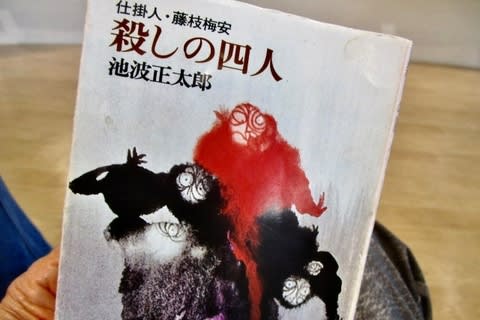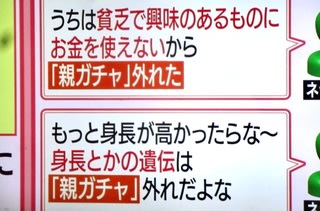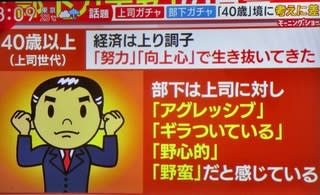今日は月に一度の篆刻サークル「石門印会」の勉強会でした。
雨の中、父ちゃん送ってもらい打瀬の公民館へ。
今日は全員集合でした。

9月の月齢競刻の講評を先生から聞く。
9月の課題は「九秋」(秋の3ヶ月、90日間をいう)
印の大きさ八分(約2、5cm)
以下、先生の講評です。

屈曲の法を取り入れて印面を十分に活用している。
「秋」字にもう少し屈曲の線を入れても可。
偏・部首の変化がうまい。
「九」字を真ん中につめて空間を生かしてもいい。

対角を境に二字を配置した構成だが「九」の右が
長いのは、この斜形に合わせたものか。巾が狭いのが
気にかかる。辺縁変化は自然で良。
「九」字を狭くしたのは「秋」を強調したかったから。とYさん。
「秋という字は「籀文(ちゅうぶん)という字形から見つけた」と
Yさんいうも、「ちゅうぶん」も「せっこぶん」も初めて聞いた私。
知らないな〜と、ネットで調べてみたら
籀文とは
漢字書体の一つ。石鼓(せっこ)文の字体によく似ており,
西周の金文から派生して戦国時代に秦で用いられたという。
これを簡略化した小篆(しょうてん)(篆書)に対し
大篆ともいわれる。石鼓文(せっこぶん)字体
「なるほど」となりましたが漢字の字形は何やら奥が深く難しい。

白文印にて大らかさがあり暖かみある印風が見受けられる。
大胆な欠けと「L」形の界線がアクセントとなり印を
引き締めていて好感。

文字に疎密の法をとり入れて、より空間の白さが極立っている。
「九」の上半を当てて斜傾させ動きがよく出た。

「九」の動きが抜群でその流動感は中々のもの。「秋」の
右半部分はどうか、異体字としてあるとしても選字には
十分気を配りたい。
「秋」字はもう一度辞典で調べてきます。Sさん。

秦漢印の風趣が辺縁を太くして力感を表す対角に文字を
配し、開いた空間が広々とゆとり感ずる。辺縁少し
軽味つけたい。



印面に十分な大きさの文字が広がり「九」の巾を狭く
「秋」を広く配分しており好印。「秋」の字形
禾・木 再考の余地あり。
「あらら、禾を木の文字にしてしまった」私の間違い。
「白文だから修正できる」という事で帰ってきて、この印を
探したら、削ってしまっていた。あちゃ〜です。
それではと修正ペンで直してみた。
本来は左の印のように刻さなければならない。
篆刻の石はヤスリで削るとまた新しく文字が刻せる。
が、削ってしまったら元に戻せない。

先ず一見して辺縁の大胆な形に驚く。文字を縦に
配置しても違和感がない。独特の風趣は見事。
文字の進展に工夫あり。
「このような場合は縦に文字を並べてもいいんだ」
「瓢箪の形で『月見で一杯』というところね」

第一に「疎密」の法が生かされて、右半の朱部が独特である。
文字回りの朱の配分も程良く印の欠けも無理なく上品といえる。

朱白同印の作である。字画を考慮しての朱白はこれで良い。
更に発展させて「九」字を中央に圧縮するのも一手か。

氏の提出された課題印影に釈文として「千秋」とあるが
「九秋」の間違いか。それは別として近年、穏やかな刻に
変わりましたね。好印。
確かに「千秋」と書いてあるけど「九」の書き間違えかもね。
以前は辺縁をダイナミックにバリバリ欠けを作っていたKさん
この頃おとなしくなった?

「九」字を中央に圧縮し、上下に朱の空間を広く取ったのは
正解なり。大胆な構成が印面にみなぎっている。
「右側の界線が九の字とくっついているので
釈文がないと九という字に読めない」とNさん、
確かにそうかもしれない。しかしながらいつものように
素晴らしい刻です。

小篆の朱文作。よく刀線がのびており好印たり。
刀線の終筆部に鋭味を入れること大切。

刀線の太さに力感がこもり疎密の文字ながら
調和がとれている。右側辺縁の真ん中の欠けは
不自然に見える。
「篆刻を勉強するのには昔の作品や今の
プロの作品を見て、先ずは真似をするのも
いい勉強法です」と先生。
今日も楽しい勉強会でした。