お休み前にいただいた質問コメント、
日常生活、少し落ち着いたので、
今頃になってアップです(汗)。
遅くなってしまいました。
ペコン。
もう解決なさっているかもしれませんが、
あつみさんからもコメントいただいたので、
アップしちゃいますね。


この記事にいただいたコメントです。
「着物初心者です。
名古屋帯等のお太鼓大きく作る。
これはどこを調節して大きくしたりするのか……
お教室で聞いたのですがよくわからず……
大きくすれば手先が上手く3点決まらないし……
謎だらけです。
先生曰く、お太鼓は垂れ先から
60センチあれば綺麗に作れる……
とのことなのですが…。
ちなみに私は151センチです。
垂れ先からどの程度あればいいのか。
決まらないお太鼓に悪戦苦闘中です。
アドバイス有りましたら教えてくださいませ!」
どのくらい応えられるかは不明ですが、
「垂れ先からどのくらいあればいいのか」
先生は60センチあればOK、とのことですね。
その場合、中に繰り込む垂れを少なく
すればいいのでは?
望みの大きさにして、
お太鼓の下線部分に
借り紐をするとスムーズにできます。
手先が足りない場合は、
横から出す手先を短くするか、
もう出さない!
その上に帯締めをします。
身長が151センチと仰ってますが、
その場合、お太鼓を大きくするより、
小さめがいいと思いますが、
あくまで私個人の意見です。
ポイント柄は少し難しい~~?
あつみさまからの質問。
「普通の長さの名古屋だと、
手か垂れのどちらかが余りませんか?
手を折ってらっしゃる?」
手が余る場合は折ります。
垂れが余る場合は、お太鼓のなかに
どんどん入れ込みます。
角出しはお太鼓がペタンコですが、
私は「ふっくらお太鼓」が好きなので、
余った垂れを入れ込むほど
中が詰まって充実。
ふっくらしてきます。
名和先生の「付け帯改造」は、
つけ帯の貧相さを
解消するものですから、
早速実行しました。

着付け本は、帯の長さも標準、
9尺2寸とか5寸(350センチから360)を
規準にして教えています。
でも、アンティークは長さマチマチですので、
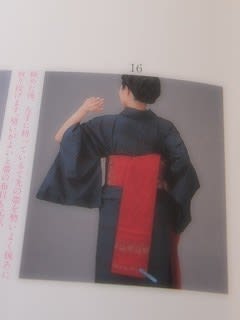
この場合手先の長さは
おおよそ53センチです。
標準帯ならこれでOKですが。
何事も教科書通りにはいきませんね。
体型も帯も着物も違うし。
その工夫が面白いのですけどね。
いつも応援ポチ
ありがとうございます。


















