先の「帯の長さとお太鼓の関係」で、
質問ならびに、
こんな愉しいコメントをいただきました。
「本もネットも探り、
諸先輩にもいろいろうかがいましたが、
とどのつまりは結局私の体型にありと。
比較的求めやすい帯は、長さゆえ、あきらめ、
お仕立てのがほとんど、、。うーーん
そんな時、
手先足りない時、出さない!!
このきっぱりしたお言葉。
目からうろこどころか、
クジラ?~~」
大笑いしたあと、
「そもそも帯の手先ってなぜ必要なの?」と
考えてしまいました。
先の記事では
お太鼓の大きさを決めれば
手先が短すぎ~~、と悩む人いれば、
「アンティークの帯では手先が出ないので
諦める人もいる~~。

思うに、手先はですね、
帯の中のぐちゃぐちゃを隠すため~~(笑)
違うかな。

これは先の帯ですが、帯結びは銀座風ですので、
手さきで、中は隠せません。
垂れをどんどんなかに繰り込んでいるので、
中がぐちゃぐちゃに。
お太鼓のなか、
もっときれいにしないと
いけないのですけどね。
なんせ、帯が長すぎて、
繰り上げる量が多い。

これは、質問もらったので、
帰宅後試行錯誤しつつ
あとから撮った写真。
で、質問いただいて、これまで
何の疑問も抱かなったけど、
「手さきの役割って何?」
考えるに~~、
ヒントはお茶。
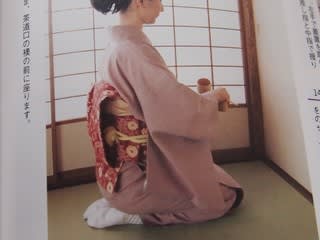
お茶をやっているとですね、
横から帯のなかがよく見える。
このとき、帯のなかがぐちゃぐちゃだと
見苦しい~~。
手先はこのためにあるのでは?と
どこにも書いてないけど、
紫苑の推測。
お茶のときにはじっと相手をみるので、
わかりやすいのです。
それゆえ、茶道では
手先は右前に持ってきて、
右からなかに入れます。
お茶のときには、客や師は右側に
いらっしゃるので。
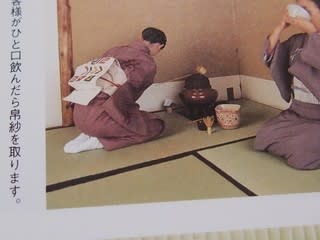
お茶のときには、苦手な
関西巻き(時計まわり)をします。
この博多も関西巻き(時計まわり)
じゃないと、
上の白でないの。
そこで、簡単な関西巻きの方法を。

手先を肩にかけずに、右上に出して、
そのまま巻き、あとで出ている手先を
後ろに回します。
右肩にかけての関西巻き、
私には難しいので~~。

これが、普通のお太鼓。
帯のなかは手先で見えません。
お太鼓の白い部分が関東巻とは
逆に右になっています。
なぜだろう??
しかし、手さきの一番の役割は、
重い帯を帯締めで支えるとき、
この手さきが帯のなかの全体
を均等に抑えて
崩れにくくするのでしょうね。
だから、垂れ先があまり短くて
帯締めに届かないと、
崩れやすくなる。
ゆえに手先が短い場合、
① 帯のなかに入れるとき、
横の部分をきれいに。
まっ、帯のなか覗く人、
そんなにいないと思うけど。
② 結ぶとき、少し気を付けて
中をきれいにする。
手さきが届かなかった左(右)の横の
部分だけでも、ね。
③帯全体が短くて中に繰り入れる垂れが短く、
またお太鼓に入れる手さきも
短い場合でも、
帯締めは中の垂れの部分を
しっかり抑えるように締めましょう。
崩れやすくなるから。

ぐちゃぐちゃ帯のなかの
紫苑を見習わないようにいたしましょう。
次は質問にいただいた
短いポイント柄の名古屋帯の
ふっくら結び方をアップしますね。
一度にやると煩雑になるので。
今回は「手さきの役割」について
推測でした。
どなたかご存知の方、
推測、憶測、忖度(そんたく、これは違うか)
でいいので、教えてくださいませ。
いつも応援ポチ
ありがとうございます。
















