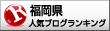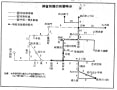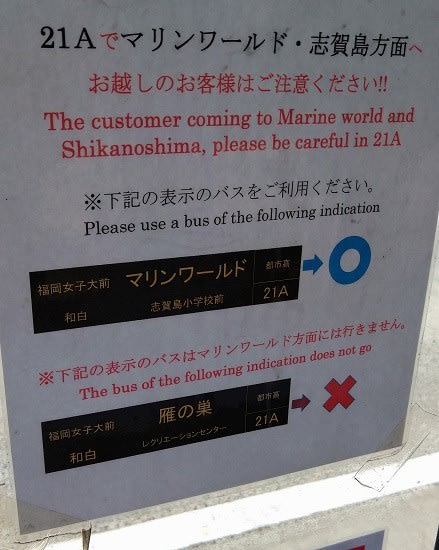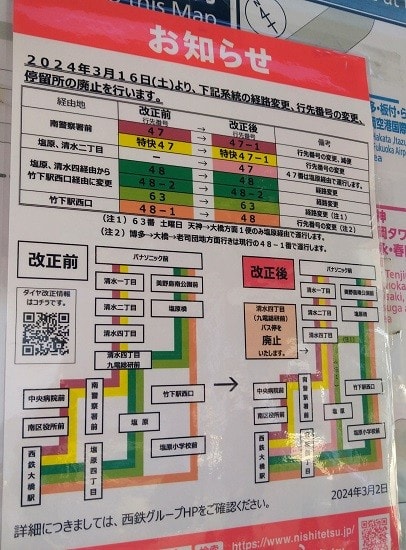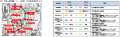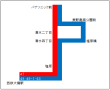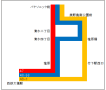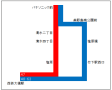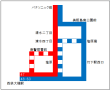(つづき)
「早良妙見西口」、英字表記は読み重視。

幼い頃、私が西鉄バスに興味を持った原点のバス停。
ただ、興味を持った直後に「野芥四丁目」「野芥三丁目」が新設されたり、「2番」に田隈新町経由ができたりしたため、最寄りのバス停であった期間は短いのですが。

その頃はまだ「早良妙見口」という名称で、業務スーパーはマルキョウで、から揚げ屋さんはたこやき屋さんでした。


信号は「早良妙見口」。
上下2車線の道路を無理やり3車線にしたため、車で走行してもなかなか窮屈です。

もともとは、現在の「早良妙見東口」の道路しかなく、新道にバスが通るようになってしばらくはどちらも「早良妙見口」だったものが、45年前くらい(おそらく)に「西口」と「東口」に名前が分かれた。
ただ、肝心の“早良妙見”は、西口と東口の間には存在せず、


東口よりもさらに遥か南東方に位置している。
ということは、「早良妙見西口」「早良妙見東口」という名称は本当は適切ではなく、「早良妙見口」の改称にあたって、「早良妙見口西」「早良妙見口東」などとしないといけなかったのだが、そうならなかったのは、「西口」「東口」のほうがリズムというか語感が良かったからだと思われる…ということは以前の記事でも何度か書きました。
「小笹南口」「神湊西口」「福岡東医療センター南門」「古賀駅南口」「下野」「上宇美入口」「レークヒルズ野多目」…などとともに、何気ない名称の中にいろんな物語や思惑が含まれていて、「鑑賞」という点ではポイントが高い。
たしかに実態は反映していないのだが、長年名前が変わってないということは、“東口と西口の間に早良妙見がないんですけど!”といった苦情なども特にないのでしょう。

郊外方面。


行先のバリエーションもここまで減ってしまいました。


ただ、地下鉄が近くを走るようになっても、まだこれだけの本数があるというのは恵まれているほうなのかも。

野芥交差点を右折する路線は、「無番」の2本だけになってしまいましたが。

「早良妙見西口」は、早良妙見の西にあるので単体で見れば一応正解ではあるのだが、


「早良妙見東口」は、早良妙見の東にはないので、「SAWARA MYOKEN EAST ENTRANCE」のように意味重視にしていないのは妥当と思われる(そういう意図で読み重視にしたわけではないかもしれませんが)。


かつては「8番」「12番」「14番」「93番」なども停車して賑やかな場所でしたが、こちらもこんなに寂しく。

水道みちなどが交差する「妙見五差路」の北側の、