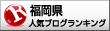(つづき)
北九州市八幡西区の「トンネル口」バス停。
北九州市には他にも、
小倉と門司の間に「手向山トンネル口」、門司の
関門海峡側と
周防灘側の間に「鹿
喰トンネル口」や「桜トンネル口」があるが(他に「関門トンネル車道口」「関門トンネル人道口」もあり)、こちらは単に「トンネル口」。
他方、
福岡地区には「トンネル」が付いたバス停はなく、
北九州と福岡の地形の違いを表す例とも言えそうだ。


トンネルの名称は「永犬丸トンネル」、トンネルを抜けると
中間市である。
北九州市のベッドタウンであり、位置関係的には八幡西区と一体化しているようにも見える中間市だが、地形的には独立性が強い。


主に八幡西区西部の住宅地と
黒崎地区を結んでいる「74番」の一部が、八幡西区から中間市に入りさらにその先、再び八幡西区の「
香月営業所」まで運行されているが、営業所からの(営業所への)出入庫を目的とした運用のようであり、運行本数も少なく時間帯も偏っている(かといって、利用者が皆無というわけではありません)。
「トンネル口」の読みは「トンネルロ」ではなく「トンネルグチ」。
当然の読み方ではあるのだが、以前、市販の道路地図で、宗像市の「
構え口」が「構之口」になっていたり、
糸島市の糸島高校の南にある「糸高南」が「縞南」になっている例を目にしたことがあり、西鉄のあずかり知らないところで伝言ゲームのように間違って伝播していく可能性がない訳ではない。
また、西鉄のあずかり知らない場面ではなく、社内の表示においても、
バス停の銘板(というのでしょうか?
バス停名が書いてある板)や
バス停掲示の路線図兼運賃表、
車内のデジタル運賃表や西鉄の公式サイトなどの間で表示が統一されていないケースは多い。
例としては、
「前」の有無、
「団地」の有無、
新字体か旧字体か、
「口」か「入口」か、
「の」か「ノ」か「之」か“そのいずれもない”か、
「ケ」か「ヶ」か“そのいずれもない”か、
「つ」か「ツ」か“そのいずれもない”か、
数字か漢数字か…などがある。

“目に見えるもの”だけでなく“耳で聞こえるもの”にまで対象を広げれば、「トンネル口」のひとつ先の「
犬王」がアナウンスでは「いのう」なのにサイトでは「いぬおう」だったり、
春日市の「須玖」がバス停の英字表記は「SUKU」なのにアナウンスは「すぐ」だったり、同じく春日市の「
放送所前」が英字表記は「HOSOSHO MAE」なのにアナウンスは「ほうそうじょまえ」だったり…と、様々な違いがある。
「一つのバス停に一つの名前がある」というのは一見当たり前のようにも思えるのだが、実は、「一つのバス停にいろんな名前がある」というケースは枚挙に暇がなく、“目に見えるもの”と“耳で聞こえるもの”の全てがすんなりと一致することのほうが珍しいのかもしれない。
バス停の数が管理しきれないほど多く、それだけ人々の生活の内部に入りこんでいるという見方もでき、このような「ゆるさ」「大らかさ」を否定するつもりはない(駅の名前とかインターチェンジなんかであれば、そのような多様性も許容されにくいのかもしれない)。
なので、「どれかひとつに早急に統一すべきだ!」などというつもりは全くないのだが、
検索に際しての弊害にだけは気を配っていただきたいものである。
(つづく)