書簡三十三がオルデンブルクHeinrich Ordenburgからスピノザに送られたのが1665年12月8日。次のオルデンブルクからスピノザへの書簡は,記録が残っているのは書簡六十一で,1675年6月8日付です。実に10年ほどの間隔で送られたものでした。遺稿集Opera Posthumaに掲載されています。
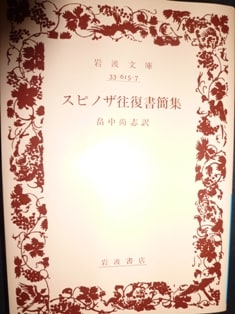
ただし,この書簡の少し前に,オルデンブルクがスピノザに書簡を送ったことが,この書簡から確定できます。その書簡の内容は,スピノザが『神学・政治論Tractatus Theologico-Politicus』を寄贈してくれたことへの礼と,『神学・政治論』へのオルデンブルクの見解だったようです。オルデンブルクはその書簡がスピノザに届いたかどうか心許なく思っていると書いていますので,たぶん届かなかったのでしょう。オルデンブルクとスピノザの間の書簡はほとんどが遺稿集に掲載されていて,届いたのならそれも掲載されたとするのが妥当だと僕は思うからです。
おそらくスピノザに届かなかった書簡の中で,オルデンブルクは『神学・政治論』について批判的な見解を記したのですが,こちらの書簡ではその見解というのは誤りであって,スピノザがキリスト教を害そうと企てていることはまったくあり得ないと考え直したという主旨のことをいっています。オルデンブルクとスピノザの間で文通が再開されたのは,何度もいっているようにチルンハウスEhrenfried Walther von Tschirnhausがオルデンブルクと面会したことが契機となっているのですが,そのときにおそらくチルンハウスが,何らかの仕方でオルデンブルクを説得し,オルデンブルクは自身の見解を改めたということでしょう。ただし実際は,オルデンブルクが最初に感じたことの方が,オルデンブルクの思想には近かったのであって,そのことはこれ以降の文通によって徐々に明らかになっていくことになります。そもそもチルンハウスとオルデンブルクの間で,キリスト教がどのような宗教であるのかということの考え方に差異があり,しかしオルデンブルクはその差異に気付かなかったために,チルンハウスにはキリスト教に反しないと思われたことについて,オルデンブルクもそれを鵜呑みにしてしまったということだったのではないでしょうか。ただその誤解があったから,文通は再開されることになったとはいえると思います。
第四部定理四七は,希望spesと不安metusに関する一般的な評価であって,それらはともに善bonumではあり得ないといわれています。各々の評価が一致するのは,スピノザが希望と不安を表裏一体の感情affectusとしてみているからで,たとえ希望はそれ自体でみれば喜びlaetitiaであり,第四部定理八により,善が意識化された喜びであったとしても,意識化された希望はそれ自体では善ではあり得ないということになるのです。ですからここではスピノザは一般的には希望も不安も善ではあり得ないといっているのですが,相対的にみれば喜びである希望を低く評価し,悲しみtristitiaである不安を高く評価しているということになるでしょう。とりわけ希望がそれ以外の喜びと比較されたとき,このことはより明瞭になるといえるでしょう。一方,不安は悲しみの一種なので,それ自体で悪malumといわれなければならないのですが,それが希望と表裏一体の感情としてみられるなら,それ自体で悪であるというより,それ自体で善ではあり得ないといういい方になるのであって,このときには不安はほかの悲しみと比較されたときには,相対的に高く評価されていることになります。
スピノザはこの後の備考Scholiumで,さらに一般的な評価を下しています。
「これに加えて,これらの感情は,認識の欠乏および精神の無能力を表示するものである。そしてこの理由から安堵,絶望,歓喜および落胆もまた無能な精神の標識である」。
希望や不安が認識cognitioの欠乏privatioを示しているということは,各々の感情の定義Definitioから明白であるといえるからここでは詳しく説明しません。ただこれは,僕たちはある確実な事柄については希望も不安も感じないということから,経験的に明白であるとだけいっておきます。実現するか実現しないか分からない事柄に対して僕たちは希望なり不安なりを感じるのですが,ここで分からないというのは確実な認識の欠乏にほかならないのであって,それは僕たちの精神mensの無能力impotentiaそのものです。他面からいえば,現実的に存在する人間は未来のことを確実に知る力potentiaをもたないのであり,その力がないという意味で無能impotentiaです。要するにこの種の無能力は,現実的に存在するすべての人間に妥当することになります。
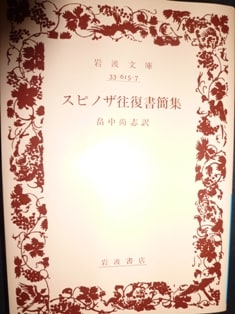
ただし,この書簡の少し前に,オルデンブルクがスピノザに書簡を送ったことが,この書簡から確定できます。その書簡の内容は,スピノザが『神学・政治論Tractatus Theologico-Politicus』を寄贈してくれたことへの礼と,『神学・政治論』へのオルデンブルクの見解だったようです。オルデンブルクはその書簡がスピノザに届いたかどうか心許なく思っていると書いていますので,たぶん届かなかったのでしょう。オルデンブルクとスピノザの間の書簡はほとんどが遺稿集に掲載されていて,届いたのならそれも掲載されたとするのが妥当だと僕は思うからです。
おそらくスピノザに届かなかった書簡の中で,オルデンブルクは『神学・政治論』について批判的な見解を記したのですが,こちらの書簡ではその見解というのは誤りであって,スピノザがキリスト教を害そうと企てていることはまったくあり得ないと考え直したという主旨のことをいっています。オルデンブルクとスピノザの間で文通が再開されたのは,何度もいっているようにチルンハウスEhrenfried Walther von Tschirnhausがオルデンブルクと面会したことが契機となっているのですが,そのときにおそらくチルンハウスが,何らかの仕方でオルデンブルクを説得し,オルデンブルクは自身の見解を改めたということでしょう。ただし実際は,オルデンブルクが最初に感じたことの方が,オルデンブルクの思想には近かったのであって,そのことはこれ以降の文通によって徐々に明らかになっていくことになります。そもそもチルンハウスとオルデンブルクの間で,キリスト教がどのような宗教であるのかということの考え方に差異があり,しかしオルデンブルクはその差異に気付かなかったために,チルンハウスにはキリスト教に反しないと思われたことについて,オルデンブルクもそれを鵜呑みにしてしまったということだったのではないでしょうか。ただその誤解があったから,文通は再開されることになったとはいえると思います。
第四部定理四七は,希望spesと不安metusに関する一般的な評価であって,それらはともに善bonumではあり得ないといわれています。各々の評価が一致するのは,スピノザが希望と不安を表裏一体の感情affectusとしてみているからで,たとえ希望はそれ自体でみれば喜びlaetitiaであり,第四部定理八により,善が意識化された喜びであったとしても,意識化された希望はそれ自体では善ではあり得ないということになるのです。ですからここではスピノザは一般的には希望も不安も善ではあり得ないといっているのですが,相対的にみれば喜びである希望を低く評価し,悲しみtristitiaである不安を高く評価しているということになるでしょう。とりわけ希望がそれ以外の喜びと比較されたとき,このことはより明瞭になるといえるでしょう。一方,不安は悲しみの一種なので,それ自体で悪malumといわれなければならないのですが,それが希望と表裏一体の感情としてみられるなら,それ自体で悪であるというより,それ自体で善ではあり得ないといういい方になるのであって,このときには不安はほかの悲しみと比較されたときには,相対的に高く評価されていることになります。
スピノザはこの後の備考Scholiumで,さらに一般的な評価を下しています。
「これに加えて,これらの感情は,認識の欠乏および精神の無能力を表示するものである。そしてこの理由から安堵,絶望,歓喜および落胆もまた無能な精神の標識である」。
希望や不安が認識cognitioの欠乏privatioを示しているということは,各々の感情の定義Definitioから明白であるといえるからここでは詳しく説明しません。ただこれは,僕たちはある確実な事柄については希望も不安も感じないということから,経験的に明白であるとだけいっておきます。実現するか実現しないか分からない事柄に対して僕たちは希望なり不安なりを感じるのですが,ここで分からないというのは確実な認識の欠乏にほかならないのであって,それは僕たちの精神mensの無能力impotentiaそのものです。他面からいえば,現実的に存在する人間は未来のことを確実に知る力potentiaをもたないのであり,その力がないという意味で無能impotentiaです。要するにこの種の無能力は,現実的に存在するすべての人間に妥当することになります。













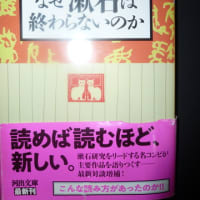








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます