㉓で示したように,天龍は全日本プロレスを退団した後も,ジャンボ・鶴田のことを気にしていました。鶴田は三沢光晴たちと戦うようになった後,1992年11月に,おそらく㉒で示した,流血戦を拒否した原因であったとされるB型肝炎を発症することによって,セミリタイアに近い状況になりました。そして1995年4月に筑波大学の大学院に入学。運動生理学を専攻して1997年に卒業。その後は大学で教鞭をとる傍ら,全日本プロレスのリングへのスポット参戦を続けました。
この間に鶴田は,両国国技館ですべての幕内力士を相手にスポーツ医学の講演を行っています。天龍はこのことを聞いて,鶴田には勝てない,鶴田は生き様としてはるか遠くに行ってしまったと感じたといっています。これは天龍らしい感じ方といえるでしょう。元々は力士で,三役まで昇進していた天龍は,相撲という競技には特別のプライドを持っていました。輪島大士に対して天龍がかなり厳しい攻撃を仕掛けたのは,輪島が横綱まで務め上げ,幕内最高優勝を何度も獲得していたからであって,横綱という地位まで務めた人間に対する,天龍のこの上ない敬意があったからだと推測されます。つまり横綱まで務めた人間は,どんな攻撃にも耐えられる,というか耐えられなければならないとか耐えてほしいといった天龍の気持ちが籠っていたのであって,それは相撲という競技に対する天龍自身のプライドであったのは間違いないと僕は思います。その横綱を含めたすべての幕内力士を相手に,教授として講義したということに,おそらく天龍は感嘆したのでしょう。それは自分には与えられることがない,中途で相撲を止めてプロレスラーになった天龍には依頼されることがあり得ない仕事であると天龍は感じたのだと思います。
天龍はそこには生き方の違いがあったといっています。天龍は明日はないその日暮らしのタイプで,鶴田は明日を見据えるタイプだったといっているのですが,このその日暮らしの生き方を教えられたのは相撲協会からだったと天龍が回顧しているのは面白いところです。
これは基本中の基本に該当しますが,スピノザの哲学では神Deusと世界の関係は,実体substantiaとその変状affectioすなわち様態modiという関係で示されます。要するに実体と実体の変状substantiae affectioすなわち様態の関係は,僕たちが通常に解するような創造主creaturaと被造物creatorの関係とは異なっているということです。

実体は第一部定義三でいわれているように,それ自身のうちにありそれ自身によって考えられるもののことをいいます。ただしこれはあくまでもスピノザの哲学における定義Definitioであって,実体という語自体は哲学においても一般的にも使われている語であり,スピノザがその哲学用語をそのように定義し直したと解するのがよいでしょう。
一般的に実体という語が用いられる場合は,その上で様ざまな変化が生じるけれども,それ自体は同一に留まるもののことを意味します。実際にはいくつもの規定がそこに付加されることになるのですが,それ自体がその規定から分けて考えることができるのであれば,そのものは実体といわれるということです。いい換えれば付加される規定というのは実体がなければ意味をなさないことになるのであって,規定自体を意味づけるものが実体といわれてきたのが歴史における実体の意味だと吉田はいっています。このことの是非はここでは問いません。
吉田の解釈を採用すると,そもそもこの世界のうちに数多くの実体があるという結論になります。たとえばネコは,白いのもいれば黒いものもいれば三毛もいるというように多種多様です。そしてネコは歩いているかもしれませんし,日向ぼっこをしているかもしれません。しかしどのような色をしていようと,またどのような行動をしていようと,それがネコであるということは否定できません。このように考えれば,ネコは実体であるということができることになります。どのような色をしているのかとか,どのような行動をしているのかといった諸々の規定は,この場合はそれがネコであるということによって意味づけられているのであって,ネコという実体がなければ諸々の規定は何の意味もなさないという関係がここでは成立しているからです。そしてこれはネコの場合だけ妥当するわけではありません。
この間に鶴田は,両国国技館ですべての幕内力士を相手にスポーツ医学の講演を行っています。天龍はこのことを聞いて,鶴田には勝てない,鶴田は生き様としてはるか遠くに行ってしまったと感じたといっています。これは天龍らしい感じ方といえるでしょう。元々は力士で,三役まで昇進していた天龍は,相撲という競技には特別のプライドを持っていました。輪島大士に対して天龍がかなり厳しい攻撃を仕掛けたのは,輪島が横綱まで務め上げ,幕内最高優勝を何度も獲得していたからであって,横綱という地位まで務めた人間に対する,天龍のこの上ない敬意があったからだと推測されます。つまり横綱まで務めた人間は,どんな攻撃にも耐えられる,というか耐えられなければならないとか耐えてほしいといった天龍の気持ちが籠っていたのであって,それは相撲という競技に対する天龍自身のプライドであったのは間違いないと僕は思います。その横綱を含めたすべての幕内力士を相手に,教授として講義したということに,おそらく天龍は感嘆したのでしょう。それは自分には与えられることがない,中途で相撲を止めてプロレスラーになった天龍には依頼されることがあり得ない仕事であると天龍は感じたのだと思います。
天龍はそこには生き方の違いがあったといっています。天龍は明日はないその日暮らしのタイプで,鶴田は明日を見据えるタイプだったといっているのですが,このその日暮らしの生き方を教えられたのは相撲協会からだったと天龍が回顧しているのは面白いところです。
これは基本中の基本に該当しますが,スピノザの哲学では神Deusと世界の関係は,実体substantiaとその変状affectioすなわち様態modiという関係で示されます。要するに実体と実体の変状substantiae affectioすなわち様態の関係は,僕たちが通常に解するような創造主creaturaと被造物creatorの関係とは異なっているということです。

実体は第一部定義三でいわれているように,それ自身のうちにありそれ自身によって考えられるもののことをいいます。ただしこれはあくまでもスピノザの哲学における定義Definitioであって,実体という語自体は哲学においても一般的にも使われている語であり,スピノザがその哲学用語をそのように定義し直したと解するのがよいでしょう。
一般的に実体という語が用いられる場合は,その上で様ざまな変化が生じるけれども,それ自体は同一に留まるもののことを意味します。実際にはいくつもの規定がそこに付加されることになるのですが,それ自体がその規定から分けて考えることができるのであれば,そのものは実体といわれるということです。いい換えれば付加される規定というのは実体がなければ意味をなさないことになるのであって,規定自体を意味づけるものが実体といわれてきたのが歴史における実体の意味だと吉田はいっています。このことの是非はここでは問いません。
吉田の解釈を採用すると,そもそもこの世界のうちに数多くの実体があるという結論になります。たとえばネコは,白いのもいれば黒いものもいれば三毛もいるというように多種多様です。そしてネコは歩いているかもしれませんし,日向ぼっこをしているかもしれません。しかしどのような色をしていようと,またどのような行動をしていようと,それがネコであるということは否定できません。このように考えれば,ネコは実体であるということができることになります。どのような色をしているのかとか,どのような行動をしているのかといった諸々の規定は,この場合はそれがネコであるということによって意味づけられているのであって,ネコという実体がなければ諸々の規定は何の意味もなさないという関係がここでは成立しているからです。そしてこれはネコの場合だけ妥当するわけではありません。










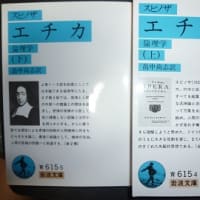



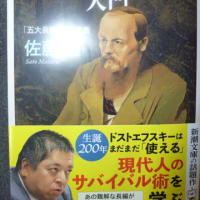






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます