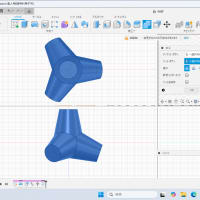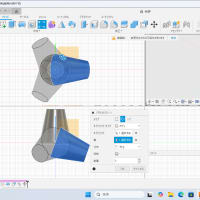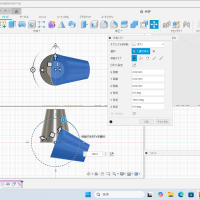ノーベル賞受賞者の多くは生徒個人の自主性を重要視するんだけど、実際の教育現場では進学率とか偏差値といった数字を追求したり恐怖権威で抑圧しようとするバカ教師が多過ぎて、なかなかノーベル賞受賞者の思うようには改革出来ない。
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
益川敏英 嫌いなことはそんなにやらなくていいから、好きなこと、得意なことを伸ばすことを考えた方が良い。
小柴昌俊 「これなら一生続けられる」、そういうものを見つけなさい。
アルバート:アインシュタイン
無知で自分勝手な教師が与える屈辱と精神的抑圧は、若者の心に荒廃をもたらす。荒廃はけっして元には戻らず、しばしば後に悪影響を及ぼす。
特定の職業にたいする生徒の性向を無視してはいけません。(なぜなら)とくに、そのような性向は早い時期に現れるからです。きっかけとなるのは、個人の才能、家族らが示す手本、他のさまざまな境遇でしょうが。
おおかたの教師は、生徒が何を知らないかを発見することを意図した質問をして時間を無駄にしています。しかし、本当の質問の技とは、生徒が何を知っているか、あるいは、知りうるかを発見することを目的としているのです。
(「アインシュタインは語る」 大月書店刊より抜粋。)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
益川理論(?)に基づけば、与えられた特定の限定的学科での成績が平均的に高くなければならない必要性はないはずで。大学入試においてペーパーテスト以外の合格基準を採用するなどのすんごい微妙な改革は進められてはいる。
何故進学率や偏差値といった数字を追求しようとするイカレた教師がいるのかと言えば。彼らは学生時代に進学率や偏差値の向上ばかりを求められて育ったからである。これは明らかに一種の「虐待の連鎖」である。
そもそもアニメファンの若者達をdisるバカ祭りにノーベル賞受賞者は出て来ることはない。
○1次元。
集団や組織の中ではどのようなメカニズムで危険性放置が発生するのかを社会心理学的手法で解明しようとする必要性があるでしょう。それは「アイヒマン実験」の追試のような形を採ることになりかねないため、コンセンサスは得られ難いかも知れないが、科学的に検証して明確にしておく必要性はあるかも知れない。
個人的には必要性は感じていないのだが。頑固な実証主義者を説得する必要性があれば、致し方あるまい。
ヒトはとかく感情的に陥ると、右か左かといった1次元的思考しか出来なくなる習性傾向がある。
たまたまバカヲヤジ達がよってたかってアニメファンをdisったからといって、社会の全てがアニメファンを排除しようとしていると勘違いすべきではない。そうした錯覚に陥らないことこそがメディアリテラシーというものでもあるからだ。
そもそも問題だと思ってすらいないヲヤヂ達はそんな番組には興味すら持っていない。(おいらもタイムラインから「何かバカ番組をやっているみたいだな。」程度。)
ですから、ヲヤヂの全ては敵といった短絡的な帰結に陥って思考停止(オッサン個人の特性を無視)して敵味方といった1次元論は、原理主義の思考パターンの基本構造と全く同じものなのです。
論理的にも統計的にもさしたる根拠のない観念的なdisりというのは、そもそもが1次元的価値観に基づくものであって。こうした1次元的原理主義者に対して気分的反感や嫌悪感だけで全面的にdisり合ってしまうと、その1次元上での議論に乗っかっちゃっているのと同じことなのです。
そもそも議論自体がトンデモなく低次元であることを認識していれば、語るに足らない変態ヲヤヂの勝手な妄想でしかないのです。
相手が提示したチンケなモノサシの上だけの議論に相手を引き込む手口は、詐欺師とか占い師の常套手段です。
乗っかってはいけません。
そこにこそ暗黒面ダークサイドが隠されているからです。
蓮@残響さんが言ってた「土俵」と例えてもいいかも知れない。相手がそそのかした土俵というものが、キチンと論理的土台がしっかり出来ているのかを確かめずに、迂闊に「売言葉に買い言葉」で乗っかってしまうと二度と出られない泥沼に陥ったり、場合によっては地雷が埋まっていることもある。
詐欺師、あ、じゃなくて。占い師が「他人の言うことを信用しないのは、心の狭い態度です。」なんて頭ごなしに決め付けたりすることがありますが。冷静に考えれば「じゃあ何かい、他人の言うことを何でも疑わずに鵜呑みにして、あんたに金を払うような、あんたにとって都合の良いカモこそが心が広いってことなのかい。」って話になるわけです。
そんなわけねぇだろ。\( ~∇~)/
脳のデフォルトモードネットワークというのは、課題を与えられている間には活性が低下します。これは街角で見知らぬ他人に道を聞かれた時に相手の服の色を全く覚えていないのと関係があるのではないかと思います。
「道を聞かれた」という「課題」によって。意識注意が「道を説明する。」ことだけに整理され、結果的に話の途中で相手の服の色が変わっても気付かないとか、それこそ相手自体が入れ替わっていても気付かないなんてことにもなるのです。
手品も、こうした意識誘導を用いてタネがわからないようにします。
「他人を騙そうとする者にとって、カモを見つけるのは簡単である。」とはマキャベリの言葉ですが。
ヒトという種の生物の脳というのは、騙すためのツボというかコツのようなものが存在していて、これを利用すると相手を意図しない錯覚状態に陥れることが簡単に出来るものなのです。この前提を忘れてその場限りの感情気分のままに無意識に流されていると、うっかり変な考えに引き込まれてしまうことがあるのです。
「自分だけは大丈夫。」そう思っている人ほど、振り込め詐欺の被害に遭うものなのです。
こういった説明をすると、もしかすると蓮@残響さんは「自分はそんなことにも気付かなかったのか」と落ち込むこともあるかも知れませんけど、こういった錯覚というのはヒトという種の生物全般に見られる普遍的性質なので、何ら落ち込んだり歎いたり、恥ずかしがったりする必要性は全くありません。
むしろハインリッヒの法則でいうところの「ヒヤリ、ハッと」事象でしかないのですから、気付いたことを教訓に騙されないよう気をつけるキッカケとなれば財産ともなるのです。
脳のデフォルトモードネットワークを働かせるためには、いちど「ぼんやり」する必要性があります。これは「脱集中」とも呼ばれ、一息ついて引きで見る客観性を働かせることで問題点に気付くことが出来るようになるコツです。
なので、感情的になってその場限りの勝ち負け論に引き込まれ、相手を攻撃することばかりに意識を奪われていると、問題の本質を見失ったまま不毛なdisり合いにしかならないのです。
感情というものは、単にそれだけでは意志ではありません。統合的に論理検証することで、本当に重要なのが何なのかを見極める客観性が伴って、初めて意志とか自己とか意識だと言えるのです。
自分の脳は自分が作ったものではありません、そもそも自分の脳というのは自分では選択不可能な遺伝要素から出来ているものであり。また、その脳に刷り込み学習された様々な価値観もまた、それだけでは自分の価値観とは言えないのです。
自分が育った社会環境というものは自分では選択していないのですから、その社会から「学習」された価値観が自分自身の価値観だと思うのは実は間違いなのです。
その場限りの勝ち負け論に執着してしまう性質というのも、ヒトの先天的習性でもあるのですが、他者との過度な競争を強いられることで強化されてしまうものでもあるのです。アインシュタインが危惧した「心の荒廃」も、無知で愚かな教師によって植え付けられた「陳腐な土俵」の弊害なのです。
もしかすると、こうした話は得体の知れない不安感を抱くこともあるかも知れませんが。それは今まで誰も触れて来なかったという「慣れ」ていないことに由来する感覚だと言えます。
慣れないことはすぐには馴染めないのは当たり前ですから、時間をかけてじっくり慣れる必要があるのでしょう。
先ずは「ぼんやり」しておきましょう。「ぼんやり」している時にしか見えないものがあるからです。
無理に急いで「最終解答」をひねり出してはいけません、それこそが原理主義の構造(暗黒面)だからです。
Ende;
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
益川敏英 嫌いなことはそんなにやらなくていいから、好きなこと、得意なことを伸ばすことを考えた方が良い。
小柴昌俊 「これなら一生続けられる」、そういうものを見つけなさい。
アルバート:アインシュタイン
無知で自分勝手な教師が与える屈辱と精神的抑圧は、若者の心に荒廃をもたらす。荒廃はけっして元には戻らず、しばしば後に悪影響を及ぼす。
特定の職業にたいする生徒の性向を無視してはいけません。(なぜなら)とくに、そのような性向は早い時期に現れるからです。きっかけとなるのは、個人の才能、家族らが示す手本、他のさまざまな境遇でしょうが。
おおかたの教師は、生徒が何を知らないかを発見することを意図した質問をして時間を無駄にしています。しかし、本当の質問の技とは、生徒が何を知っているか、あるいは、知りうるかを発見することを目的としているのです。
(「アインシュタインは語る」 大月書店刊より抜粋。)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
益川理論(?)に基づけば、与えられた特定の限定的学科での成績が平均的に高くなければならない必要性はないはずで。大学入試においてペーパーテスト以外の合格基準を採用するなどのすんごい微妙な改革は進められてはいる。
何故進学率や偏差値といった数字を追求しようとするイカレた教師がいるのかと言えば。彼らは学生時代に進学率や偏差値の向上ばかりを求められて育ったからである。これは明らかに一種の「虐待の連鎖」である。
そもそもアニメファンの若者達をdisるバカ祭りにノーベル賞受賞者は出て来ることはない。
○1次元。
集団や組織の中ではどのようなメカニズムで危険性放置が発生するのかを社会心理学的手法で解明しようとする必要性があるでしょう。それは「アイヒマン実験」の追試のような形を採ることになりかねないため、コンセンサスは得られ難いかも知れないが、科学的に検証して明確にしておく必要性はあるかも知れない。
個人的には必要性は感じていないのだが。頑固な実証主義者を説得する必要性があれば、致し方あるまい。
ヒトはとかく感情的に陥ると、右か左かといった1次元的思考しか出来なくなる習性傾向がある。
たまたまバカヲヤジ達がよってたかってアニメファンをdisったからといって、社会の全てがアニメファンを排除しようとしていると勘違いすべきではない。そうした錯覚に陥らないことこそがメディアリテラシーというものでもあるからだ。
そもそも問題だと思ってすらいないヲヤヂ達はそんな番組には興味すら持っていない。(おいらもタイムラインから「何かバカ番組をやっているみたいだな。」程度。)
ですから、ヲヤヂの全ては敵といった短絡的な帰結に陥って思考停止(オッサン個人の特性を無視)して敵味方といった1次元論は、原理主義の思考パターンの基本構造と全く同じものなのです。
論理的にも統計的にもさしたる根拠のない観念的なdisりというのは、そもそもが1次元的価値観に基づくものであって。こうした1次元的原理主義者に対して気分的反感や嫌悪感だけで全面的にdisり合ってしまうと、その1次元上での議論に乗っかっちゃっているのと同じことなのです。
そもそも議論自体がトンデモなく低次元であることを認識していれば、語るに足らない変態ヲヤヂの勝手な妄想でしかないのです。
相手が提示したチンケなモノサシの上だけの議論に相手を引き込む手口は、詐欺師とか占い師の常套手段です。
乗っかってはいけません。
そこにこそ暗黒面ダークサイドが隠されているからです。
蓮@残響さんが言ってた「土俵」と例えてもいいかも知れない。相手がそそのかした土俵というものが、キチンと論理的土台がしっかり出来ているのかを確かめずに、迂闊に「売言葉に買い言葉」で乗っかってしまうと二度と出られない泥沼に陥ったり、場合によっては地雷が埋まっていることもある。
詐欺師、あ、じゃなくて。占い師が「他人の言うことを信用しないのは、心の狭い態度です。」なんて頭ごなしに決め付けたりすることがありますが。冷静に考えれば「じゃあ何かい、他人の言うことを何でも疑わずに鵜呑みにして、あんたに金を払うような、あんたにとって都合の良いカモこそが心が広いってことなのかい。」って話になるわけです。
そんなわけねぇだろ。\( ~∇~)/
脳のデフォルトモードネットワークというのは、課題を与えられている間には活性が低下します。これは街角で見知らぬ他人に道を聞かれた時に相手の服の色を全く覚えていないのと関係があるのではないかと思います。
「道を聞かれた」という「課題」によって。意識注意が「道を説明する。」ことだけに整理され、結果的に話の途中で相手の服の色が変わっても気付かないとか、それこそ相手自体が入れ替わっていても気付かないなんてことにもなるのです。
手品も、こうした意識誘導を用いてタネがわからないようにします。
「他人を騙そうとする者にとって、カモを見つけるのは簡単である。」とはマキャベリの言葉ですが。
ヒトという種の生物の脳というのは、騙すためのツボというかコツのようなものが存在していて、これを利用すると相手を意図しない錯覚状態に陥れることが簡単に出来るものなのです。この前提を忘れてその場限りの感情気分のままに無意識に流されていると、うっかり変な考えに引き込まれてしまうことがあるのです。
「自分だけは大丈夫。」そう思っている人ほど、振り込め詐欺の被害に遭うものなのです。
こういった説明をすると、もしかすると蓮@残響さんは「自分はそんなことにも気付かなかったのか」と落ち込むこともあるかも知れませんけど、こういった錯覚というのはヒトという種の生物全般に見られる普遍的性質なので、何ら落ち込んだり歎いたり、恥ずかしがったりする必要性は全くありません。
むしろハインリッヒの法則でいうところの「ヒヤリ、ハッと」事象でしかないのですから、気付いたことを教訓に騙されないよう気をつけるキッカケとなれば財産ともなるのです。
脳のデフォルトモードネットワークを働かせるためには、いちど「ぼんやり」する必要性があります。これは「脱集中」とも呼ばれ、一息ついて引きで見る客観性を働かせることで問題点に気付くことが出来るようになるコツです。
なので、感情的になってその場限りの勝ち負け論に引き込まれ、相手を攻撃することばかりに意識を奪われていると、問題の本質を見失ったまま不毛なdisり合いにしかならないのです。
感情というものは、単にそれだけでは意志ではありません。統合的に論理検証することで、本当に重要なのが何なのかを見極める客観性が伴って、初めて意志とか自己とか意識だと言えるのです。
自分の脳は自分が作ったものではありません、そもそも自分の脳というのは自分では選択不可能な遺伝要素から出来ているものであり。また、その脳に刷り込み学習された様々な価値観もまた、それだけでは自分の価値観とは言えないのです。
自分が育った社会環境というものは自分では選択していないのですから、その社会から「学習」された価値観が自分自身の価値観だと思うのは実は間違いなのです。
その場限りの勝ち負け論に執着してしまう性質というのも、ヒトの先天的習性でもあるのですが、他者との過度な競争を強いられることで強化されてしまうものでもあるのです。アインシュタインが危惧した「心の荒廃」も、無知で愚かな教師によって植え付けられた「陳腐な土俵」の弊害なのです。
もしかすると、こうした話は得体の知れない不安感を抱くこともあるかも知れませんが。それは今まで誰も触れて来なかったという「慣れ」ていないことに由来する感覚だと言えます。
慣れないことはすぐには馴染めないのは当たり前ですから、時間をかけてじっくり慣れる必要があるのでしょう。
先ずは「ぼんやり」しておきましょう。「ぼんやり」している時にしか見えないものがあるからです。
無理に急いで「最終解答」をひねり出してはいけません、それこそが原理主義の構造(暗黒面)だからです。
Ende;