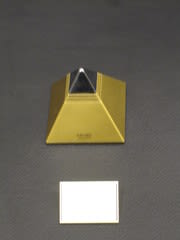タイトルといい、装丁といい、デザインといい、編集といい、本好きにはチャーミングな一冊。
読みやすく、お徳な付録まで付いているという徹底ぶり・・・恐れ入りました!
食は、あまり興味のない分野なのですが、思わず購入してしまいました。
「外食の裏側を見抜くプロの全スキル、教えます」
河岸宏和著 東洋経済新報社 900円+税
著者の河岸さんは、「食のプロや業界関係者のあいだで食品業界を知り尽くしたと言われる男」。
1958年の生まれで、帯広畜産大学を卒業後、ハム会社等を経て、商品安全教育研究所の代表をつとめられています。ま
さに、食のプロフェッショナルです。
一見、バクロ本のようにも見えますが、日本の食の堕落ぶりを嘆く著者による渾身の訴えでもあります。
添加物問題や輸入食品問題、食品偽装問題など食を巡る様々な課題が噴出している昨今。
同書は、その中でも外食についての問題指摘を行っています。
「本当は袋とじにしたい・・・」そんな覆面食べ歩きのレポートは、読み物としても、とても面白い内容です。
「汚い店にうまいものなし」
「肉がどこまでも増える植物性タンパク質の衝撃」
「そば粉が1~2割しか入っていないそばは、もはや黄色いうどん」
「コンビニのおにぎりは新米を使っている」
「お持ち帰り弁当のご飯は2年前の古古米」
「焼き鳥は、ねぎまがあるかに着目する」
「ラーメン店に入ったら大きな寸胴鍋に注目」
「回転寿司のよしあしはイカを見る」・・・・・・・・・
直球での突っ込みは、なかなか切れ味するどく、同書を読むことによって食べれなくなるものも出てきます(笑)。
それでも、これでもかと出てくる著者の指摘には感心する次第です。
外食の達人として、「まずはずさない」お店を見抜く極意も紹介されています。
外観・内装編・・・第一印象を大事にする、店内は清潔か、厨房と段ボールを覗き見る、店の臭いに注意する、席やテーブル、内装、胡蝶蘭等に注意する
客席編・・・働く人の身なりをチェック(白衣、腕時計、指輪など)、ホールの人の反応を見る、テーブルの上に箸たてがある店はそれだけでダメ・・・
なかなか厳しい突っ込みに拍手、拍手です。
巻末には、特別付録として、同書の内容を6ページでまとめたチェックリストまで付いています。
同書の続編が出れば、また読みたいと思った次第です。
今年のオモシロ本の一冊にノミネートされるのではないでしょうか。
最後に、著者お薦めの全国チェーンリストから一部を紹介させていただきます。
外食するなら、こんな店なんですね。
カレー・・・COCO壱番屋
ファミレス・・・ロイヤルホスト
牛丼・・・吉野家
中華・・・餃子の王将、バーミヤン
回転寿司・・・スシロー、がってん寿司
トンカツ・・・和幸
うどん・・・丸亀製麺
ファストフード・・・ケンタッキー、サブウェイ、ミスタードーナッツ
コーヒー・・・スタバ
ベーカリー・・・神戸屋、ドンク
やっぱりそうか・・・という裏付けをいただけるリストでした。
著者の河岸さんの続編に期待しています。