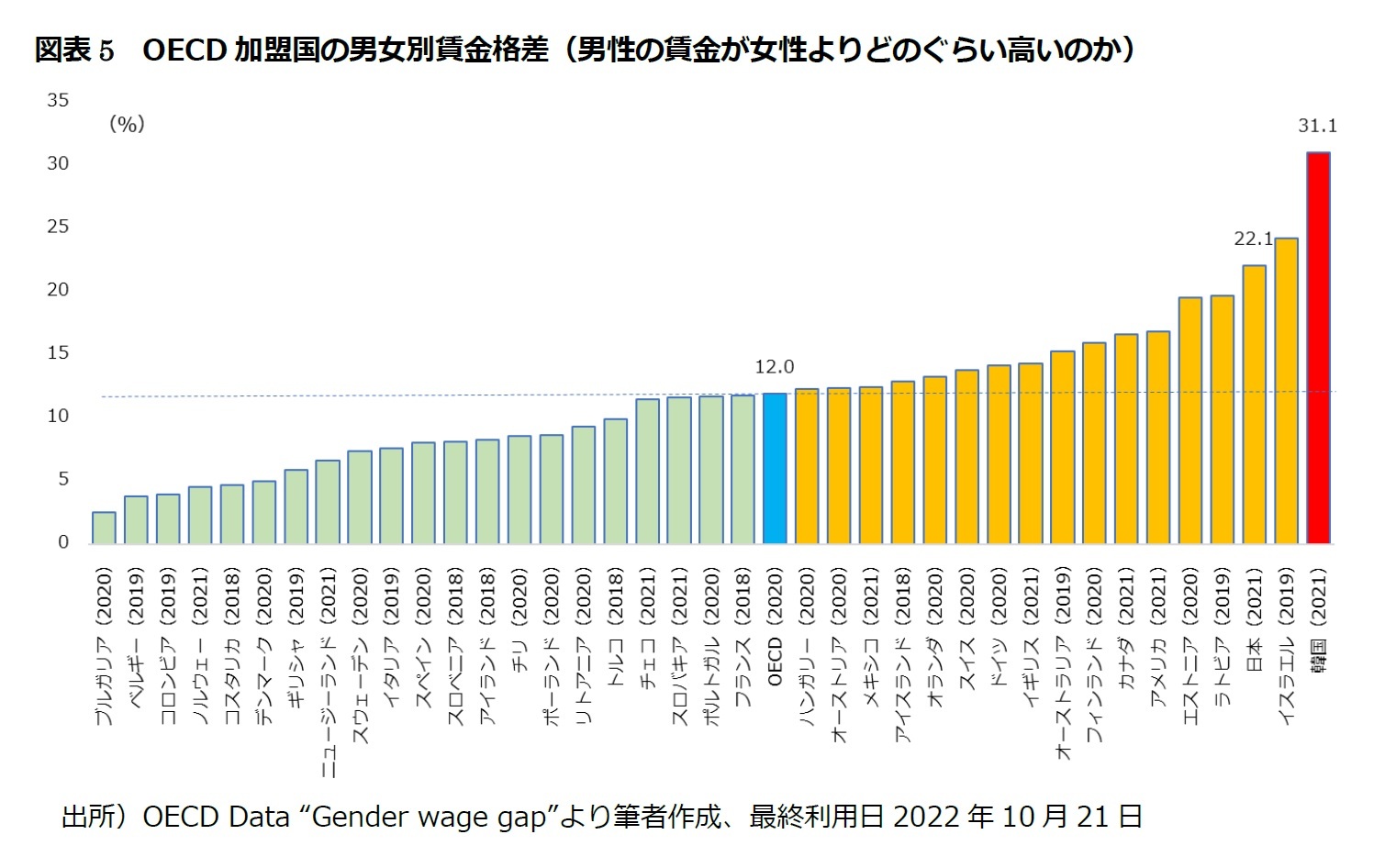茂木 久美子 (著)
車もマンションも突然、売れ始める 7つの技術!
講演年150回、全国の社長が唖然とする凄い売り方――新幹線カリスマ販売員の秘技!!
どれほど優れた技術を用いて、どれほど優れた商品を作ったとしても、ビジネスの締めくくりは「物を売る」ということにほかなりません。そして、「物を売る技術」が劣っているようでは、すべてが台無しになりかねません。価格や商品の種類といった点で、他業者とは差別化できず制約が多い新幹線のワゴン販売において、いかにして私が他の販売員の数倍の売り上げを出してきたのか――。本書では、私の仕事に対する考え方、テクニック等を通して、あらゆる業種、職種のビジネスパーソンが活用できる、物を売るための「七つの技術」をご紹介しています。そして、それを理解していただくことで、皆さんのビジネスの成績が向上すると確信しています。
●お客さまをあえて「悩ませる」と
●「いかがですか?」の言葉の重圧
●買う意思がない人の注意を引く技
●言葉は少し足りない程度が効果的
●声の出し方「三つのポイント」
●「欲しいとき」を逃さないコツ
●サービス重視かスピード重視か
●「なじみ」の販売員になる技術
●常連客に「買わせない」気遣いを
●山本五十六的発想で指導すると
講演年150回、全国の社長が唖然とする凄い売り方――新幹線カリスマ販売員の秘技!!
どれほど優れた技術を用いて、どれほど優れた商品を作ったとしても、ビジネスの締めくくりは「物を売る」ということにほかなりません。そして、「物を売る技術」が劣っているようでは、すべてが台無しになりかねません。価格や商品の種類といった点で、他業者とは差別化できず制約が多い新幹線のワゴン販売において、いかにして私が他の販売員の数倍の売り上げを出してきたのか――。本書では、私の仕事に対する考え方、テクニック等を通して、あらゆる業種、職種のビジネスパーソンが活用できる、物を売るための「七つの技術」をご紹介しています。そして、それを理解していただくことで、皆さんのビジネスの成績が向上すると確信しています。
●お客さまをあえて「悩ませる」と
●「いかがですか?」の言葉の重圧
●買う意思がない人の注意を引く技
●言葉は少し足りない程度が効果的
●声の出し方「三つのポイント」
●「欲しいとき」を逃さないコツ
●サービス重視かスピード重視か
●「なじみ」の販売員になる技術
●常連客に「買わせない」気遣いを
●山本五十六的発想で指導すると
茂木/久美子
1980年、山形県に生まれる。日本レストランエンタプライズ・チーフインストラクター。
1980年、山形県に生まれる。日本レストランエンタプライズ・チーフインストラクター。
山形城北高校卒業。1998年からJR東日本の車内販売会社、日本レストランエンタプライズ山形営業支店で山形新幹線車内販売員として勤務。
ダントツの売上成績を挙げ、2005年10月にインストラクター、2006年10月に最年少でチーフインストラクターに抜擢される(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
後ろ向きでワゴンを引き、注文したい人を見逃さない。
自分からも声を掛け、山形弁で会話するなど多くの工夫。
何より一人一人の客への「オーダーメード」のサービスを心掛けた。
当初、効率良く売ることに腐心していた茂木さんだが、客を<買う人>としか見ていない自分み気付く。
口では「お客さま第一」と言いながら、<売るため>の接客だった。
以来、客が「どうされたら、うれしいか」に心を砕いた。
出会いを大切に「お客さまに喜んでいただく」という姿勢が、結果として売り上げにつながった。
接客の面でも、人としても、とても勉強になりました✨
アンテナを立てていることって大切ですね☺
アンテナを立てていることって大切ですね☺
人の5倍売る人は、やっぱり普通のことはしないんですね。何度も読みたい本です。
売る技術というか、気づきのヒント満載、新入社員研修で紹介しました。
著者作品は初めて。
昔は、商店街の魚屋さん、八百屋さん、酒屋さんの量り売り、タバコ屋さん、毎朝訪ねてくる行商人等、
人から買うことが当たり前だったが、今では、スーパーマーケット、コンビニ、自販機、通販など、
お店や機械、ネットなど、人以外から買うばかりになった。
人から買う意味を考えさせられた。
本書では、会話が伴う販売が
客同士の『口コミ』効果をもたらす等、
言われてみれば確かにそうだよなー、という紹介もあり、
『売る技術』を超えている感もある。
他にも、
・「如何ですか?」でYes/Noを迫らない
・商品のお勧めポイントだけを伝える
・客との関係が切れない会話
紹介しているので、
販売に携わる人に於いては一読して、
今迄の自分の販売行為を見直されると いいかもね。
内容には、
客の本をのぞき見するとか、
ちょっとくさい所や冗長な部分もあるが、
大筋は外してはいない。