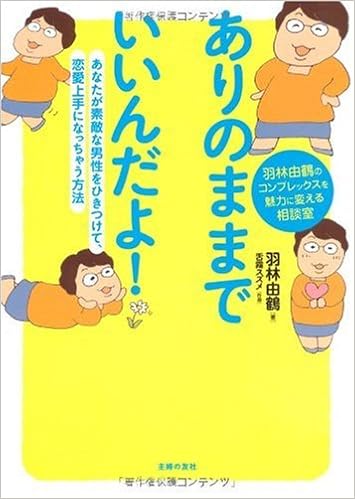内容紹介
28か国で翻訳、世界的ベストセラー!会話のできない自閉症者の心の声。
「僕が跳びはねている時、気持ちは空に向かっています。空に吸い込まれてしまいたい思いが、僕の心を揺さぶるのです」(本文より)
人との会話が困難で気持ちを伝えることができない自閉症者の心の声を、著者が13歳の時に記した本書。障害を個性に変えて生きる純粋でひたむきな言葉
は、当事者や家族だけでなく、海をも越えて人々に希望と感動をもたらした。世界的ベストセラーとなり、NHKドキュメンタリー「君が僕の息子について教えてくれたこと」でも放映された話題作、待望の文庫化!
デイヴィッド・ミッチェル(英語版翻訳者)による寄稿を収録。
内容(「BOOK」データベースより)
僕は跳びはねている時、気持ちは空に向かっています。空に吸い込まれてしまいたい思いが、僕の心を揺さぶるのです―。人との会話が困難で、気持ちを伝えることができない自閉症者の心の声を、著者が13歳の時に記した本書。障害を個性に変えて生きる純粋でひたむきな言葉は、当事者や家族だけでなく、海をも越えて人々に希望と感動をもたらした。世界的ベストセラーとなった話題作、待望の文庫化!
著者について
●東田 直樹:1992年8月千葉生まれ。作家。重度の自閉症。パソコンおよび文字盤ポインティングにより援助なしでのコミュニケーションが可能。理解されにくかった自閉症者の内面を綴った作品『自閉症の僕が跳びはねる理由』(エスコアール)が話題になり、2013年には英語版がデイヴィッド・ミッチェルの翻訳で刊行。その後20か国以上で翻訳され世界的なベストセラーに。エッセイに『跳びはねる思考』『自閉症の僕の七転び八起き』、詩集『ありがとうは僕の耳にこだまする』等。全国各地で講演会を開催している。
最後まで、心を動かされたまま読みきった。障害者が書いたから評価される…そんな作品では全くない。もちろん、自閉症である著者でなければ書けない本だが、哀れみや「福祉」の観点で評価されているわけではないことが読めばわかる。本の虫を自負しているが、本を読んで初めて、心に突き刺さった。全く自分の知らない世界を、これほどリアルに突きつけられた気持ちをどう表現すべきなのかわからない。感動、驚き、共感といった言葉では追いつかない気がする。自閉症に関心のある人だけでなく、多くの人に手にとってほしい。
8月中旬、突然主人がこの本を予約していました。
実際に届いたのは9月の中旬で、1か月近く経ってようやく手元に届いたのでした。
しかしながら、私はさっぱり主人の気持ちが分かりませんでした。
届いた本の表紙を見て「病気を持つ方が自費出版したものなのかな?」と思った程度で、
その本を手に取ろうとすら思いませんでした。
しかしながら、その数日後、たまたまNHKでこの本を取り上げた番組をみました。
気づけば、番組をみながら、ずっと泣いている自分がいました。
わが家には4歳になる息子がおり、生後半年まで健康体だったのですが、
ある病気にかかり、その治療中薬の副作用で脳死状態となりました。
命はとりとめましたが、脳に酸素が行かず、
歩くことも、喋る事も将来は不可能だと言われました。
今は歩くことは出来ていますが、発語はできません。
奇声も上げますし、飛び跳ねますし、かみつく事もしょっちゅうです。
正直、こういった状況に疲れ果てておりました。
命は助かったものの、死んでくれたほうが楽かもしれない と
何度も思う事もありました。そして、そんな自分を責めていました。
朝夕、沢山の親御さんの前を通って、息子を施設の保育園に送っていますが、
健常なお子さんを見る事の辛さ(息子も病気にならなければ、普通に
喋っていたのに。。。歩いていたのに・・という思い)と、
他の親御さんが息子に対して向ける「変な子」という視線に耐えられない日々でした
そんな中、東田さんの番組を見て、自分の息子と重なるものがありました
(自閉症ではないものの)
障害を背負った息子の、母親になった自分だけが辛いのだ と思っていましたが、
それは大きな間違いだった という事に気づかされました。
あの番組を見て、著書を拝読して以来、息子に対しての態度も
変わりました。
親である私が、息子に対して、1個人として接していなかったこと、
腫れ物に触るような気持ちでいたこと、
そんな自分を、とても恥ずかしく思いました。
今後、喋る事の出来ない、自己表現の出来ない息子と歩む人生で、
東田さんの本が大きな影響を与えてくれたことは、間違いありません。
テレビで東田さんが話していた事で、一番印象的だった言葉は
「周りの人の刺すような視線が辛い」
というものでした。
飛び跳ねたり、大声をあげたり、奇声をあげる我が息子ですが、
周りからの冷たい視線はよく感じます。
それが嫌で、私は引きこもっていました。
でも、その視線が当人にとっても辛い物である とは考えもしませんでした。
勿論、東田さんの心情と、息子の心情が同一であるとは思いませんが、
周囲の冷たい視線が辛いのは、私の息子もそうなのかもしれない・・・と一瞬思いました。
自分だけが辛いなんて、何を馬鹿な事思っていたんだろう
と思わされた一言でした。
A横道にそれる内容ばかりで申し訳ありません。
AMAZONのレビューに書く内容ではない と思いましたが、
率直な気持ちを書かせて頂きたいと思い、
恥ずかしながら載せさせていただきました。
ここに一人、東田さんの存在で、出された本によって、それが普及することで、
救われた気持ちを抱いた人間が存在する事をお知らせしたかったのです。
この方の著書が日本内で、世界中で、障害のあるなしに問わず
多くの方に読んでもらえる事を心の底から望んでいます。
最初にテレビで作者のことを知りました。自閉症としては重たいほうかなと感じました。症状の重さと知的感覚・能力は比例しないことはなんとなく理解はしていました。私たちにとって理解しようのない行動パターンや意味不明な言語は、好んで表現しているとは限らないと知っただけでも意義がありました。この本を読んで疑問に思う人がいても、反発があったとしてもそれはその人にとっては正しいと思います。人はみな同じ考えを持っているわけでも、同じ能力を備えているわけでもありません。
だからこそ他人を理解しようと努力し、他人の意見を聞き、理解を深めていくのだと思います。
日ごろの作者の思いを理解できたことがこの本を読んだ大きな収穫です。そのことをどのようにとらえ、何を目標に置いて前に進むかは十人十色なのでしょう
知り合いの幼児が自閉症と分かり、勧められて読みました。話せなくても、ちゃんと考えていること、私たちより、より平和で優しい心を持っていると分かり胸が熱くなりました。彼らの平和な世界を造っていきたいと影ながら考えています。みんな違っているのが、当たり前だし、当然なのだと考えさせられました。私達が枠に拘り未熟なのだと、ハッとさせられました。
家族の事をもっとわかることができ、今後の助けになりました。
愛しい存在が、ますます愛しく感じられました。
様々な自閉症の本を読み、不安になってしまったご家族などにもお勧めです。
しかし、何より私自身の心が洗われ、涙が沢山流れました。
何気なく生きている世界の、真の美しさ、やさしさ、有難さを見せていただいたような、
まるでデトックスされた気持ちです。
そして直樹さんがここまでの文章を書けるよう支え続けている、お母様やご家族様、周りの方々の、
その愛と忍耐にも感動、敬服しております。
感動がうまく言葉にならず恐縮なのですが、人生で1番、人に薦めたい本です!!
英語版”The reason I jump"を読んだ英国人の友人が、「自閉症の人が、こんなに素晴らしい能力を持っているなんて、想像したこともなかった」と言って、紹介してくれました。私は日本語版を読みました。自閉症の人の心と体内で起きていること、それによって本人がどれだけ苦しんでいるのか、そして同時に周囲の人にどれだけ心を配っているのかを、初めて知りました。ショートストーリーにはウィットとユーモアを感じました。「自閉症についてどう思ういますか?」には胸がつまされました。とても良い本です。自閉症の人、障害に苦しむ人が、少しでも楽な気持ちで生きていける世界を作りたいものです。
10年以上前から、駅のホームで、突然にダーと駆け出す子供がいて、どこか傷害がある方だと大くくりで見ていました。しかし、本書を読み、障害には様々あるということ、心の中で感じたり考えたりしていることに、健常者と全く違いはないということを知りました。こちらの理解しようとする努力が足りず申し訳なく思います。
読んで感じたことです。一人の自閉症者ではあるものの、そうした方々の考えの一端に触れることができたのはありがたかった。
素直な言葉で綴られてるので場所によっては、そんなこと言われてもなとかそれは我儘なのではと思ったところもあった。ただ、心も感覚もそれら全てを自由に適切に制御できないとしたら自分はどう感じるだろう、いやそもそも彼らの素直な思いが特殊なのか大多数の一般的見解や感情が実は特殊なのか考えさせられた。
何が正常で何が異常なのか、そもそも正常って何のなのか見つめ直す良いきっかけになった。