小説家、劇作家。1944年、『花ざかりの森』刊行。代表作に『仮面の告白』『禁色』『潮騒』『金閣寺』『鏡子の家』『憂国』『豊饒の海』、戯曲『鹿鳴館』『サド侯爵夫人』など。写真は市ケ谷の陸上自衛隊東部方面総監部に乱入して、「憲法改正に決起せよ」などと演説する三島由紀夫。
三島由紀夫が戦後の日本文学を代表する作家であることは論を俟たない。1970年に陸上自衛隊市谷駐屯地で割腹自殺するまで、実に多くの作品をこの世に残した。その比類なき才能の源泉は、多々あった“コンプレックス”だともいわれる。
劇作家の平田オリザさんは、三島の代表作『金閣寺』の根底には、三島特有のコンプレックスがあったと説く。(朝日新書『名著入門』から一部を抜粋、再編集)
「三島作品は、日本と日本人が西洋文学に追いつき追い越せと努力を重ねた、その結晶のような作品だ。題材や内容は日本的なものが多いが、その論理構成は極めて西洋的で、翻訳をしてもそれが崩れることはなく、すなわち皆さんに読みやすいものとなっている。私の作品は内容は極めてグローバルで、多言語の舞台も扱っているが、表現形式が日本的なのだと思う。私の多くの戯曲は、皆さんになじみのある題材を、日本人の思考様式に乗せて発話させている」
三島由紀夫はすぐれた小説を多く残したと同時に、劇作家としてもめざましい活躍を遂げた。ただここでは、やはりその代表作である『金閣寺』を取り上げたいと思う。
日本海沿いの辺鄙(へんぴ)な貧しい寺に生まれた主人公溝口は、僧侶である父から、「金閣ほど美しいものは此世(このよ)にない」と聞かされて育った。身体が弱く重度の吃音(きつおん)でもあった溝口は強いコンプレックスの中で成長していく。やがて父の勧めもあって、彼は金閣寺に修行に入ることとなる。
当初、心の中で思い描いていたほどには、金閣を美しく感じなかった溝口だが、戦況が激しくなり、金閣も自分も共に空襲で焼け死ぬかもしれないという同じ運命に思いを馳せると、金閣はもはや実在以上の永遠に儚(はかな)い美の象徴として感じられるようになった。
私を焼き亡ぼす火は金閣をも焼き亡ぼすだろうという考えは、私をほとんど酔わせたのである。同じ禍(わざわ)い、同じ不吉な火の運命の下で、金閣と私の住む世界は同一の次元に属することになった。私の脆(もろ)い醜い肉体と同じく、金閣は硬いながら、燃えやすい炭素の肉体を持っていた。
ところが敗戦後は、金閣の周りに進駐軍や娼婦などが訪れるようになり、またある種の幻影は崩れていく。大学に進学した溝口は、内反足(ないはんそく)の障害を持つ柏木と友人になる。この柏木は障害をある種の道具にして、女たちを籠絡(ろうらく)していた。溝口も柏木から下宿屋の娘を紹介してもらうが、性交の寸前になって目の前に金閣の幻影が立ち現れ、失敗に終わる。
そのとき金閣が現われたのである。
威厳にみちた、憂鬱な繊細な建築。剥(は)げた金箔(きんぱく)をそこかしこに残した豪奢(ごうしゃ)の亡骸(なきがら)のような建築。近いと思えば遠く、親しくもあり隔たってもいる不可解な距離に、いつも澄明に浮んでいるあの金閣が現われたのである。
(中略)
下宿の娘は遠く小さく、塵(ちり)のように飛び去った。娘が金閣から拒まれた以上、私の人生も拒まれていた。隈(くま)なく美に包まれながら、人生へ手を延ばすことがどうしてできよう。美の立場からしても、私に断念を要求する権利があったであろう。
さらにもう一度、溝口は同じことを繰り返す。女性の乳房を前にして、またしても金閣が出現し、溝口は不能に終わる。やがて溝口は金閣に対し憎しみを抱くようになる。
ほとんど呪詛(じゅそ)に近い調子で、私は金閣にむかって、生れてはじめて次のように荒々しく呼びかけた。
「いつかきっとお前を支配してやる。二度と私の邪魔をしに来ないように、いつかは必ずお前をわがものにしてやるぞ」










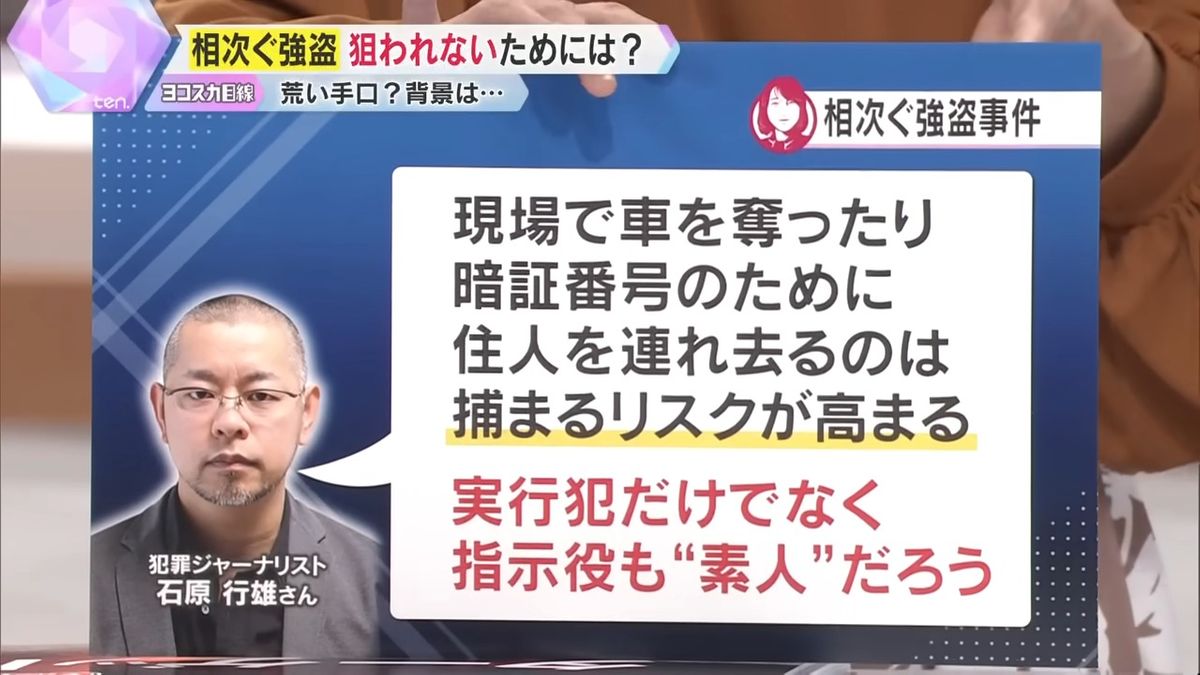
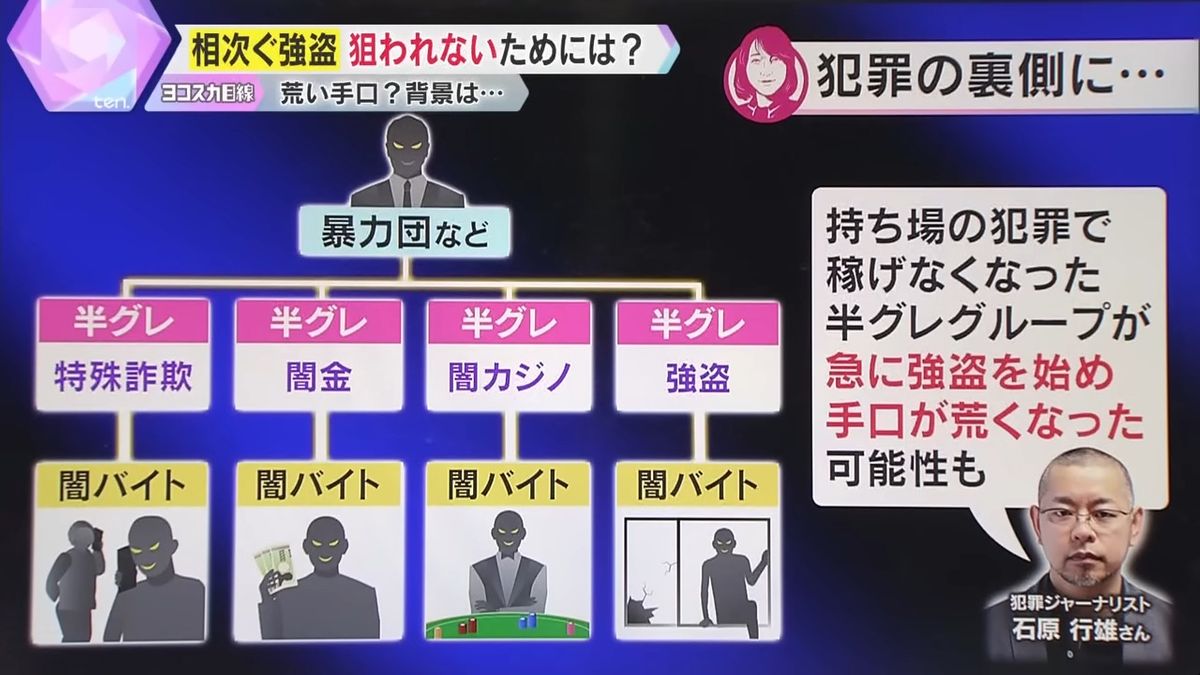
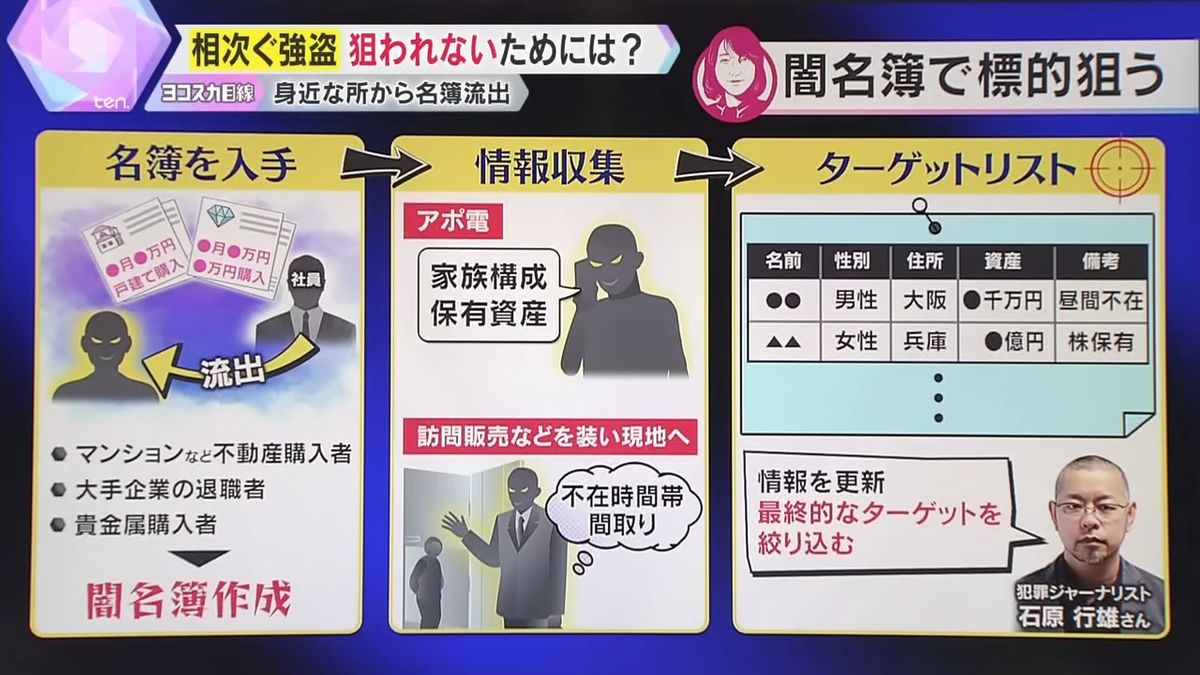

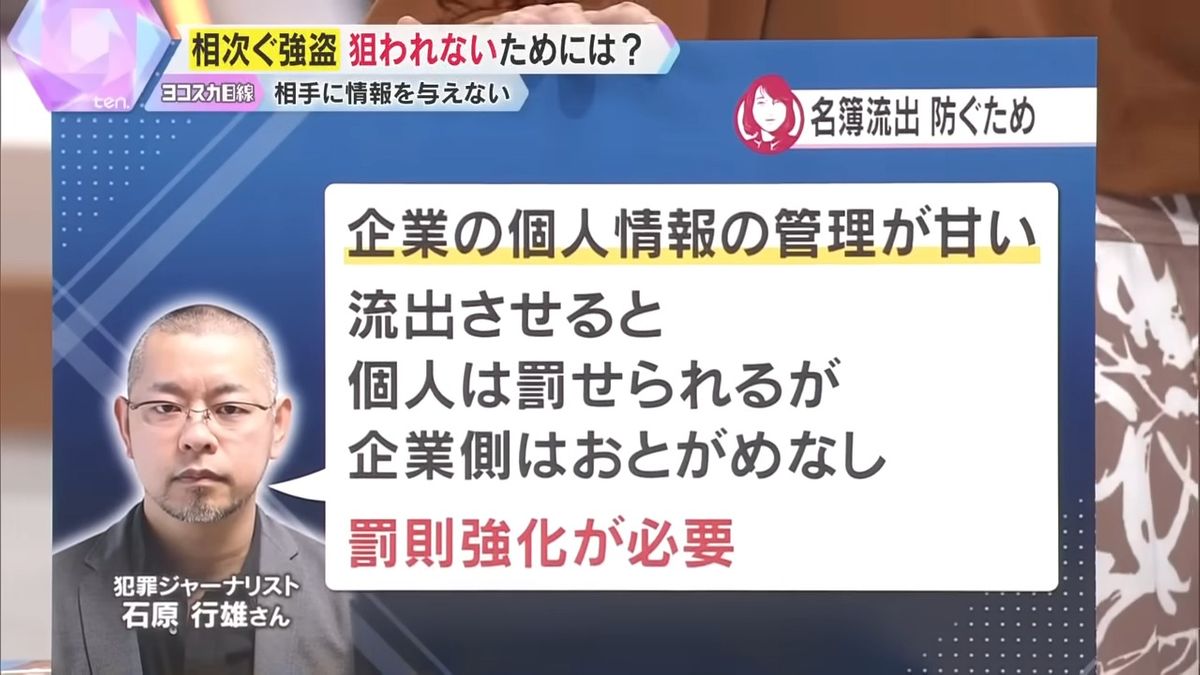






















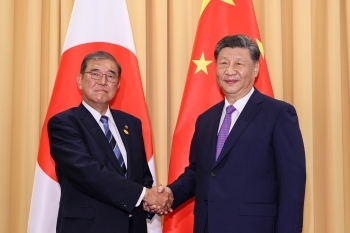
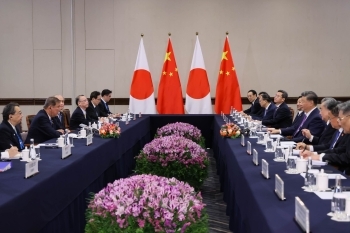














先に掲げた背が低かったこと、身体的なコンプレックスがのちに三島をボディビルなどの肉体改造にのめり込ませる。それはよく知られた話だが、私は何よりも、三島の戦争経験の欠落の方が、後年の行動の起点としては大きかったのではないかと思う。戦後派と呼ばれる作家群の中で、ほぼ三島由紀夫だけが戦場も外地(植民地)での経験もない。