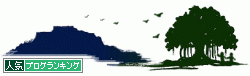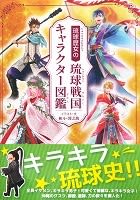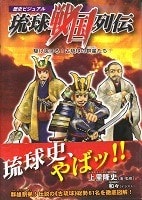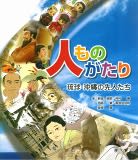抹茶の入った新・伊右衛門。
お供はうちな~てんぷら(1個40円♪)
伊右衛門、思ってたよりはスッキリ味でした。
もうちょっと抹茶味が濃いほうが好みだな~。
うちなーてんぷらは衣にもほのかに味がついているので
本当においしいです♪
時々無性に食べたくなる沖縄のソウルフードです

さて、お茶つながりで今日は
「お茶と鬼大城と百十踏揚」の話。
沖縄では、来客にお茶を2杯飲んでいただく
という風習があるそうです。
あるそうです、と書いたのは
ワタシ自身は馴染みのない風習で最近知ったので(^^;
(地域とか世代にもよるのかな~?)
で、この「お茶二杯」の風習の由来は、
実は鬼大城と百十踏揚にあったというのです。
1458年、護佐丸を討伐した阿麻和利は、
いよいよ次は首里に攻めのぼろうとしていた。
しかし、そのたくらみを事前に察知した鬼大城(大城賢雄)は
百十踏揚と共に勝連グスクを脱出。
二人の脱出を知った阿麻和利は
急いで追手を差し向かわせた。
首里までの逃亡の途中、暗くなったので
二人は灯りのともっていた百姓の家に入れてもらい
お茶を一杯飲んだ。
お礼を言って立ち去ろうとした時、
主人に「もう一杯どうぞ」とすすめられた。
追われている身であるため
すぐに立ち去りたいと気が急いたが
心を落ち着かせて二杯飲んだ。
すると、まさにその時、
追手の蹄の音が家の前をかけていった。
つまり、お茶を二杯飲むため家にとどまっていたため
命拾いした、という話。
お茶を二杯飲むくらいの心の余裕をもてば事故に遭わない、
という戒めによるもののようです。
でもこの話、実は同じストーリーで主人公を変えて
色々あるんですけどね。
別の本によると
勝連が王軍に攻められたときに脱出した阿麻和利が
同じく逃避行の途中、茶を2杯飲んで助かった、
という説を紹介しています。
参/「真説 阿麻和利考」高宮城宏著(2000)
参/「ほんとうの琉球の歴史」渡久地十美子著(2011)
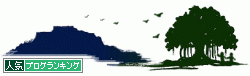
1日1回、クリックしてくれると嬉しいです!↑