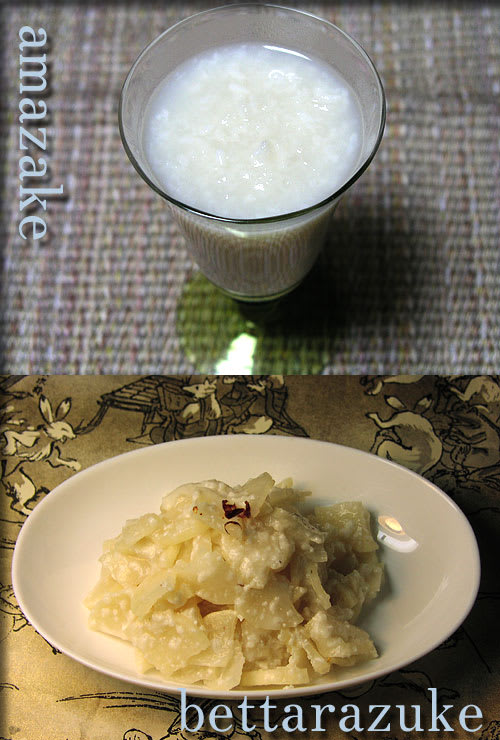快晴、気温は4度。山歩きには調度よい日曜日、早めに昼食を食べて用事の帰りに妻女山へ寄りました。蝶の越冬幼虫を撮影するためでしたが、食樹は見つかるのですが肝心の幼虫がなかなか見つからず落胆していました。
斎場山古墳の上で熱い緑茶を飲んで休憩、気を取り直して薬師山の方面へ下りました。ここで御陵願平から岩野駅方面へ下る今は廃道となった古い山道を発見。途中まで下りてみました。ひょっとしたら昔あった正源寺から土口将軍塚古墳へ登る、
江戸時代後期の榎田良長『川中島謙信陳捕ノ圖』にある山道ではないかと思いました(頁下部の絵図・中央山麓の小さな寺から右上のひょうたん形の古墳へにょろにょろと登る山道)。だとすると凄い発見です。帰宅して父に聞いても知らないというのですから。正源寺の山号は「荘厳山」といいます。荘厳山とは、国指定史蹟・土口将軍塚古墳のことで、岩野では「荘厳塚」といいます。古代科野の国の重要な史蹟です。
これは後の宿題にして、陽射しの麗らかな尾根を古墳へ。古墳の左手に回るとバラにひっかりました。剪定ばさみで切り落として刺を外していると、前方で枯葉を踏みしめる音が。だれか来たのかなと見上げるとクヌギの木の向こうにグレーの動物。ニホンカモシカです。
いつもは、視線を感じて見るとニホンカモシカがこちらをジッと見ているというパターンで、相手にいつも先に見つけられていましたが、今回は初めて私の方が先に気付きました。クヌギの幹に隠れてしばらく観察することにしました。距離は10mほど。相手は全く私に気付いていません。
カモシカは、クヌギの根元で盛んに枯葉を押しのけてはなにかを食べています。枯葉の下には、春を待ちかねて既に草が新芽を出しているので、それを食べているのだろうと思いました。すると突然カモシカが顔を上げて匂いを嗅いでいます。風向きが一瞬南風から東風に変わり、私の匂いに気付いたのでしょう。警戒して逃げられてはまずいので、木の陰から姿をゆくりと現しました。
今までの経験から、カモシカは黙っていると逃げてしまうことを知っているので、話しかけてみました。思った通り逃げません。ジッとこちらを見ています。話しかけながら撮影し、少しずつ間合いを詰めます。それでも5mを切ろうかろいうときに振り向いて逃げ出しました。そこですぐに声をかけました。「あ~ちょっと待って!」と。するとカモシカはちゃんと止まるんですね。振り向いて「何?」という表情をするんです。
暫くすると古墳の北側に下りていきました。後を付いていきまた声をかけると止まってくれました。そしてまた写真を撮らせてくれた後、ゆくりと雪の残る北側の斜面を下りていきました。写真で分かるように、すぐ下には人間の街があり、車も行きかっています。こんな近くに普通にニホンカモシカがいるなんて、おそらく麓の人はほとんどが知らないでしょう。ニホンカモシカは、そんな下界をどんな思いで毎日見つめているのでしょうか。それにしても、いつも思うのですが、ニホンカモシカとの出合いは、冷え切った心を優しく温めてくれます。
ニホンカモシカ。日本に分布する野生では唯一のウシ科動物。せきつい動物亜門哺乳類(哺乳綱)偶蹄目ウシ科ニホンカモシカ(日本羚羊)。定着性の動物でなわばりを持ち、普通単独で生活します。複数のときは、繁殖期か子供と一緒の時です。秋に交尾をして7ヵ月の妊娠期間の後、春から初夏に一頭出産します。母親は子供と2~3年は一緒に行動するようです。角を木の幹にこすりつけマーキングをします。眼下腺や蹄腺から酸っぱい臭いのある分泌液をつけてなわばりを主張します。イネ科の笹や草木の葉、樹皮や新芽を食べます。
角は雄雌ともにありますが、骨が発達したものなので鹿のように毎年生え替わることはありません。なので角の大きさで大雑把な年齢を判断することはできます。また、角研ぎをするので、大きな個体は角の前部がすり減っています。
縄張りは食性の豊かさや雄雌により違うようですが、直径1キロから2キロということです。溜糞をする習性があり、糞場は決まっています。また、縄張りには必ず岩場やガレ場があり、避難や休息の場所とします。平均寿命は5年前後ということです。非常にデリケートな動物で、ストレスに弱く飼育が困難でしたが、関係者の長年の飼育研究で人工的な繁殖もできるようになりました。
古来ニホンカモシカは、重要なタンパク源として狩猟の対象でしたが、乱獲によって絶滅しそうになり天然記念物に指定されて保護され増えました。逆に今度は増えすぎて林業などに重大な損害を与えるようになり、捕獲や射殺が行われています。野生動物の人工的な保護管理は、非常に困難な命題で、ニホンジカやニホンザル、月の輪熊などと同様に色々な意味で危機的な状況にあることには変わりないのです。
ネイチャーフォトは、【
MORI MORI KIDS Nature Photograph Gallery】をご覧ください。キノコ、変形菌(粘菌)、コケ、花、昆虫などのスーパーマクロ写真。滝、巨樹、森の写真、特殊な技法で作るパノラマ写真など。